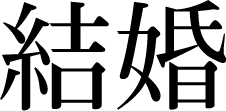
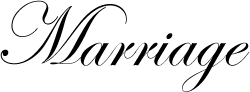
僕には離婚の経験が1回あります。同棲してから29年、結婚してからだと26年間一緒に暮らした妻と、19年前に別れました。別れたというより、一方的に僕が家を飛び出して、そのまま別居して1年後に離婚しました。
原因は僕に好きな人ができたことです。
相手は写真家の神藏美子でした。以前から写真家の荒木経惟さんのパーティーでよく見かけていましたが、いつも人が多くてざわざわしているので、長く話したことはありません。
あるパーティーで、たまたま長く話す機会があって、そのとき「女装してみませんか?」と彼女に言われました。あとで聞いたところによると、その頃『QUEEN』という女装専門雑誌で表紙の写真を撮っていて、そこで知り合った女装者を自分の作品として撮っていたそうですが、女装者でない人を女装させて撮るプロジェクトも考えていて、その第1号として僕に声をかけたそうです。
「女装してみませんか?」と言われたとき、7年前に女装したときのことを思い出しました。
僕が勤めていた出版社で出していた『元気マガジン』という風俗雑誌の廃刊が決まったとき、何でそんなことをしないといけないのかわかりませんが、編集長の山崎邦紀さん(いまはピンク映画の監督をしています)が「廃刊記念にみんなで女装しよう!」と突然言い出し、編集者やライターやデザイナーや発行人である僕も呼ばれて、エリザベス会館という女装クラブに行って集団女装したのです。
女装するのはみんな初めてでした。僕の顔はニキビ跡だらけで、人から毒ミカンと言われていたことがあるし、しかも顔デカで鼻は低いし目は細いし額は狭いし、顔に関してまったくいいところがなく、そんな僕が女装なんかしたら目も当てられない姿になるはずで、それが嫌で何となく気が進みませんでした。でも、みんなで写真を撮って最後のページに載せたいと山崎編集長は強く言うので、仕方なく参加することになったのでした。
神田のエリザベス会館に行くと、まず自分が着る衣装を選ばされました。みんなはワンピースのドレスとかツーピースとかを選んでいましたが、僕はどうせならと派手でセクシーなチャイナドレスにしました。
次に個室に入り、女性用の下着を付け(ここが肝心)、ドレスを着ます。そして、メイクルームでメイクしてもらい、カツラを被り、ふと目を上げて正面の鏡を見たとき、「あら? 何? この人キレイじゃない?」と思ったのでした。
みんなは、お互いの顔を見合ってゲラゲラ笑っています。ヒゲを生やした人は、剃らないでそのままメイクしているので、何かお笑い芸人のようです。おそらく、僕だけがマジになったというか、自分の中に女の人が降りてきたような気持ちになって、煙草の吸い方から歩き方まで、自然と女の人のようになってしまうのでした。
エリザベス会館の2階は、女装した人がお茶を飲んだり、写真撮影したりするサロンになっていました。僕らがドカドカ階段を上がっていくと、ソファで静かに煙草を吸っていた女装の人が、一瞬ギョッとしたような表情になりましたが、僕と視線が合うとニッコリ微笑んでくれました。マニア同士が交わす目線の挨拶を僕だけに送ってくれたように思って、内心ちょっと得意な気持ちになっていました。
女装の話がだいぶ長くなりましたが、以上のようなことがあったので、神藏さんから「女装してみませんか?」と言われたとき、自分でもびっくりするぐらい簡単に「あ、いいですよ」と引き受けたのでした。
運命ってそういった偶然の積み重ねで成り立っているものなんですね。僕が7年前に女装していなかったら、おそらく女装の話は断っていただろうし、断ったら神藏美子と付き合うこともなかったわけですから。
7年振りにする女装で、僕は女子高生になりました。『QUEEN』はエリザベス会館が出している雑誌だったので、撮影はエリザベス会館(その頃は神田から亀戸に移っていました)のスタジオを使いました。
エンジのリボンが付いたセーラー服(夏用)を着て、メイクをしてもらい、三つ編みのカツラを付けてスタジオに入ると、『QUEEN』の女性編集長から「名前は何にします?」と聞かれたので、咄嗟に「アキコ」と言うと、「アキコちゃん可愛いわよ~」と、みんなで声援してくれました。「アキコちゃん」「アキコちゃん」と言われて、自分がだんだん女子高生アキコになっていくような気がして、気持ちがどんどん解放されていくようでした。撮影していた神藏美子も突然セーラー服になって、アキコの友達のヨシコになって僕と一緒に写真を撮ったり、僕は調子に乗ってエッチなポーズを取ったりして2人で盛り上がりました。
女装するということはセクシュアルなことだし、写真を撮ったり撮られたりすることは、セックスみたいに人と人を親密にするようで、この撮影のあと神藏美子とどんどん仲良くなっていくのでした。
僕が結婚をしたのは21歳のときでした。
前にも書いたように、僕は自分の顔に失望していたし、仕事も給料の安い工員だったし、結婚ということを考えたことがありませんでした。その前に、自分に恋人ができるということが夢のまた夢で、そういう僕がどうやって結婚相手を見付けたかというと、電気ストーブのおかげでした。
岡山の高校を出て、大阪の工場で3ヵ月間働き、そのあと川崎の工場で働くことになったとき、以前から出稼ぎで川崎に来ていた父親のアパートに同居したのですが、毎日グチを言いながら溜息ばかりついている父親と一緒にいるのが嫌になり、近くの安い下宿に移ったのでした。
その平屋建ての家にはお婆さんが一人で住んでいて、空いている部屋を人に貸していました。僕が借りた部屋は窓のない3畳間でしたが、僕が入る前から、窓のある玄関横の4畳半に住んでいる女の人がいました。
僕はそれまで女の人と付き合ったことは1回もなく、高校は男子ばかりだったので、女の人を近くに感じたのも中学以来でした。僕の部屋からすればリッチな部屋に住んでいるその人はどんな人なのか、下宿に帰るたびに気になっていました。
季節は真冬でした。僕は工場が終わったあと、渋谷の青山デザイン専門学校に通っていたので、帰るのが遅くなります。部屋が寒いので、初めて使う小さな電気ストーブのスイッチを入れると、バチンとヒューズが飛びました。しばらくして、お婆さんが懐中電灯を持って僕の部屋にきて、「電気ストーブは電気を食いますからねぇ」と恨めしそうに言います。まるで僕が悪いことをしたように言うのですが、みんなが暖房器を使っているので、電気の容量が目一杯になっていて、僕が使う分がなかったんじゃないかと思います。
それで、お婆さんが懐中電灯を照らし、僕がヒューズを取り替えていたら、4畳半の女の人が出てきて「コタツがあるからこっちに来ませんか?」と言ってくれたのでした。
それからときどき彼女の部屋へお邪魔するようになったのですが、電気ゴタツはお互いの足が触れ合ったりするもので、抱き合ったりするのも時間の問題でした。
彼女は僕より1つ年上のきれいな人で、僕と同じように南武線沿線にある工場に勤めていました。
日曜日は彼女と川崎のスケートリンクなんかに行くようになり、彼女のことがどんどん好きになっていきました。何しろ生まれて初めての恋人ですから、彼女を独占したい気持ちが強くなります。
ところが彼女には彼氏がいて、そいつがときどき訪ねてきていました。それから、すったもんだのあげく(詳しくは、webアックス「放電横丁」に連載中の「流れる雲のように」6話、7話参照)2人で逃げるようにその下宿を出て、アパートで暮らすようになったのでした。
これも偶然なんですね。電気ストーブを買わないで寒さを我慢していたら、コンプレックスが強く内気だった僕は、彼女と仲良くなることなんてなかったかもしれません。500ワットぐらいの小さな電気ストーブでしたが、よくぞヒューズを飛ばしてくれたと感謝してます。
僕たちは祐天寺のアパートで暮らすようになり、しばらくして籍を入れました。僕は工員からディスプレイの会社を経てキャバレーの宣伝課に勤め、そこを辞めてフリーの看板屋になり、それからフリーで出版関係のデザインやイラストレーションの仕事をするようになった頃、経堂のマンションに移りました。そして会社に勤めるようになって生田に小さな建て売り住宅を買い、その10年後、向ヶ丘遊園に家を建て、そのまた10年後に、僕がその家を飛び出すことになります。
すぐ飛び出せた要因の1つとして、僕たちに子供がいなかったことがあります。妻の体が弱かったので、子供をつくることは無理だったのですが、子供が欲しいと思ったこともありませんでした。僕はメチャクチャな家庭で育ったので、ファミリーというものを嫌悪していました。それに、自分が父親に似ているということもものすごく嫌で、自分に似ている子供ができるということもさらに嫌でした。
父親は食欲と性欲だけで生きている下等動物のような人間でした。まだ川崎の下宿で半同棲していた頃、僕がいないときに父親が下宿にやってきて、彼女に襲いかかろうとしたことがありました。彼女が、「(僕に)言いつけてやるから!」と言うとやめたそうですが、父親の性欲は見境がありません。それ以来、彼女は「お父さん、気持ち悪~い」と言って、父親と会いたがりませんでした。
僕はそういう父親が大嫌いで、父親みたいな人間にだけはなりたくないと思っていたのですが、編集者になった頃、知り合った女の人に襲いかかったわけではありませんが、その人を強引にホテルに連れ込みました。妻以外の人とセックスするのは初めてのことでした。
妻とするセックスに飽きてきた頃だったので、彼女とセックスばかりしていたのですが、しばらくして、彼女が郊外の実家から僕たち夫婦が住んでいた経堂のすぐ近くに越してきて、僕は自宅と彼女のアパートを自転車で行ったり来たりするようになりました。
彼女は「これ、母から引っ越し祝いにもらったの」と言って、夫婦茶碗を見せてくれたことがあるので、僕と結婚したいと思っていたようですが、僕にそういう気がまったくないことがわかって、やんわり僕を批判する長い手紙がきたあと連絡が取れなくなりました。
僕はだんだん図々しくなり、その後も何人かの女の人と付き合うようになったのですが、離婚してその人と結婚しようと思ったことは一度もありませんでした。
妻は僕を信頼してくれていました。編集の仕事は徹夜することが多いので、女の人と朝までいたときも、仕事だと嘘をついていました。女の人とホテルにいて朝方帰ると、妻は「あまり無理しないでね」と言ってくれました。そういうとき、結構心が痛みます。
付き合っている女の人から自宅に電話があって、浮気しているのがバレバレなときも、僕は「絶対そういうことはしてない!」と嘘をつき通しました。本当のことを言わないことが愛情だと思っていたし、本当のことを言ったあとのことが恐かったのでした。妻は「わかった」とひとこと言い、それからはその話は一切しませんでした。そういうきっぱりしたところがある人でした。
妻は動物が好きで、捨て猫を見付けるたびに拾ってくるので、猫がどんどん増えました。餌がもらえない隣の犬にこっそり餌をあげていたら、その犬は飼い主を見ないでいつも妻のほうばかり見るようになったそうで、その一家が引っ越しするとき犬を押し付けられ、その犬も飼うようになりました。そのうちどこからか来た犬が住みついたり、子犬をもらってきたりで、犬も3匹になりました。
動物が増えることは、妻が寂しい気持ちでいるからではないかと思うのですが、僕は相変わらず家に帰ったり帰らなかったりで、家庭というものが築けないままズルズル同じ生活を続けていました。
朝方帰ると、妻が「犬の散歩に行ってくれる?」と言うので、3匹の犬を連れて散歩に出るのですが、あまりにも眠いので、近くの公園に行って犬をつないでベンチで眠っていました。不満そうな犬たちに申し訳ないと思いながらも、妻から「ありがとう」と言われると、朝帰りの罪悪感が少し薄らぐのでした。
神藏美子と親密になった頃は、僕にとってそれまでで一番マズい時期でした。
女の人との付き合いも、別れたいのに別れようと言えないままズルズル続いていたし、バブルの頃に商品先物取引や不動産投資でできた借金が3億円以上あったし、それを返済するために毎週競馬をやるようになって、逆に何百万かマイナスになっていたし、管理職の仕事はつまらないので身が入らず、その分ギャンブルに身が入り過ぎて、毎晩のように麻雀をやったり地下カジノに行ったりしていました。ボロボロに負けたりすると、自分でも何がやりたいのか、何をやっているのかわからなくなってきて、自分が父親以下の人間になっているように思ったりするのでした(父親もお金にルーズで、人から借金ばかりしていました)。
神藏美子とデートするとき、行くところがないのでいつも行っている地下カジノに連れて行くと、帰りがけに「あんなもの、お金を取ったり取られたりして、いったい何が楽しいの? 末井さんはほかにやることがあるでしょう」と怒られました。
この頃の僕のことを、神藏美子は著書『たまもの』の中で次のように書いています。
古くてガランと広い、その渋谷のラブホテルの部屋で、末井さんの後姿の向こうには大きく窓が開いていて、建ち並んだビルの向こうには夜空が見えた。私はその後姿とネオンの反射するビルや空を見ながら「神様この人を幸せにして下さい。」という気持ちになった。だからその古いホテルの窓のあたりは、私には神聖な場所に思える。「いっしょに暮らしたら楽しいと思うよ。」と言ってみた。わたしはその時「家族」になりたいと思っていた。「家族」という言葉の実感は人によっていろいろ違うものだ。その頃末井さんはギャンブル漬けのせいばかりでなく、どこか空虚な感じがした。あてどなく夜の街をひとりトットットッとさまよい歩いているはぐれ犬のような感じだった。(神藏美子『たまもの』)
神藏美子は嘘のない人でした。思ったことは何でも言うし、お世辞など一切言わないし、相手のためになると思えば真剣にとことん話します。僕は、そういう女の人と初めて出会ったような気がしました。この人と一緒に暮らしたい、一緒に暮らせば自分も変わるかもしれないと思うようになりました。
しかし、何も知らない妻にいきなり別れようとは言えません。それに、29年も一緒に暮らしていると情がからんで、離婚する決意も揺らいでしまいます。
ある朝、出かける前に些細なことで妻と喧嘩になりました。そのとき、僕のほうから「別れよう」という言葉が思わず出てしまいました。喧嘩のときに言うのは卑怯だと思いましたが、そういうときでないとたぶん言えなかったと思います。
僕はもう一度「別れよう」と言いました。妻は驚いたような表情になり「ほんと?」と言って僕の顔をジッと見ていました。「ほんとだよ」「好きな人がいるの?」「いる」「誰?」と聞かれましたが、僕は答えないで玄関で靴を履きました。妻が「ねぇ、どうしたの? 何があったの?」と言うのを尻目に、玄関のドアをバタンと閉めました。「嫌だあ~!!」という妻の叫び声がドアの向こうから聞こえてきました。その声で胸がギュッと締めつけられるようになり、歩いていると涙が出てきました。(末井昭『自殺』)
そして3日間家に帰らず、4日目に一度家に帰り、紙袋2つに衣類と現金300万円を入れて本格的に家出しました。僕が49歳のときでした。
----------- この続きは書籍『結婚』でお楽しみください。-----------