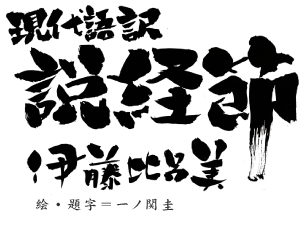第7回 小栗判官 その7 照手に車を引かれ、山伏に背負われ、餓鬼阿弥は湯の峯へ
あらあらいたわしくてなりません。
照手姫さまが、お茶の清水を汲みに出て、餓鬼阿弥に目を止めました。
「夫の小栗どのがあのような姿になっても、それでも、生きてこの世にいてくれさえすれば、どんなに苦労をしても、苦労とは思わないのに」と思わず語る心のうちこそ、あらあらあわれでなりません。そばに近寄って、その胸札を見てみましたら、『この者を一引き引けば、千人の僧を供養することになる。この者を二引き引けば、万人の僧を供養することになる』と書いてある。
照手姫さまはこれを見て、「たった一日でいい。夫の小栗のために、これを引きたい。たった一日でいい。十人のご家来衆のために、これを引きたい。二日引いた車道(くるまみち)は、かならず一日で戻るから、三日の暇をもらいたい。長(ちょう)どののご機嫌のいいときにおねがいしてみよう」と思いました。君の長のところに行こうとしたそのときに、「いやいけない、この御奉公をはじめるときに、あたくしは、たしか夫がないと言ったはず、今、夫のためと言ったところで暇はもらえない」と思い直し、「父上も母上もまだ生きておいでだが、親のためといいつくろって、おねがいしてみよう」と考えながら、長どのの前へ出ていきまして、
「おねがいがございます、長どのさま。門のところにいる餓鬼阿弥の、その胸札を見てみれば、『この者を一引き引けば、千人の僧を供養することになる。この者を二引き引けば、万人の僧を供養することになる』と書いてございます。どうか、ただ一日でよろしゅうございます、父のために、これを引きたいのです。そして、もう一日、母のために、これを引きたいのです。二日車を引きましたら、かならず一日で戻りますから、お情けでございます、三日の暇をくださりませ」と言いました。
君の長はこれを聞き、
「おまえはなんとも憎たらしいことをいう子だね。前に、流れの姫になれとおれが言った。そのときに流れの姫になっていたなら、三日どころか十日だって暇をやる。でも今はちがう。からすの頭が白くなり、馬に角が生えたとしても、おまえに暇なんぞやるものかい、常陸小萩よ」と言いました。
照手姫さまはこれを聞き、
「おねがいでございます、長どのさま。これはたとえでございますが、費長房(ひちょうぼう)や丁令威(ちょうれい)は鶴のつばさにお宿を召して、達磨尊者(だるまそんじゃ)は芦の葉にお宿を召して、張博望(ちょうはくぼう)は浮木(うきぎ)にお宿を召したといいます。旅は心、世は情け、回船は浦につながれます、捨て子は村に育てられます。木があれば、鳥も棲みます、港があれば、舟も入ります。一時雨(ひとしぐれ)に、一村雨(ひとむらさめ)に、雨やどりをいたしますのも、百ぺんくり返すいのちのご縁でございましょう。三日の暇をいただけたなら、まんがいち、君の長ご夫婦の身の上に大事がありますそのときには、わたくしが身替りになって立ちましょう。ご夫婦をおまもりしましょう。ですからどうか、お情けでございます、三日の暇をくださいませ」と言いました。
君の長はこれを聞きまして、
「おまえはなんともやさしいことをいう子だね。暇なんかやるかと思ったが、まんがいち、おれたち夫婦の身の上に大事があろうそのときには、自分が身替りになって立とうと、おれたち夫婦をまもろうと。その一言に動かされた。慈悲に情けをあい添えて、五日の暇をやる。五日が六日になろうものなら、そのときは、いいか、おまえの死んだ両親も、地獄の底に、阿鼻無間劫(あびむげんごう)に堕としてやる。車を引け」と言いました。
照手姫さまはこれを聞き、
あまりのうれしさに裸足で外に走り出て車の手縄にすがりつき。
一引き引いて、これで千の僧の供養になる。
これは夫の小栗のため。
二引き引いて、これで万の僧の供養になる。
これは十人のご家来衆のため。
すでに善行を為しまして、その善行を死者たちにふりむけまして。
でもそのときに考えたのでありました。
「聞けば、あたくしはなりとかたちがよいという。そんなことで、町や宿場や関所でいやな目にあったらかなわない」と考えまして、また、長どのの内にかけ戻り、古い烏帽子(えぼし)をもらいうけ、髪にくくりつけ、背丈と同じ長さの黒髪をふりほどき、顔には油煙のすみをぬりたくり、着ている小袖の裾を肩までからげ、笹の葉に幤(しで)をつけ、心はもの狂いではありません、でもなりとかたちはそう見せかけて、「引けよ、引けよ、子どもらよ、もの狂いがとおるよ」と声をかけ。
姫の涙はしたたる、垂井。
美濃と近江の境には、長競(たけくらべ)、二本杉、寝物語。
在所在所を引き過ぎて、高宮川原に鳴く雲雀(ひばり)。
姫にうたってくれるのか。
けなげな小鳥だ、やさしい声だ。
み代は治まる、武佐(むさ)の宿、鏡の宿に車は着きました。
照手はこれを聞きまして。
鏡のようにあかるいと人は言う。
でも姫の心はこの日々は、あのことやこのことに。
そしてあの餓鬼阿弥に、心の闇がかき曇り。
鏡の宿もあかるくないまま通り過ぎ。
姫のすそには露はつかないが、露おく草は、草津の宿、
それから野路(のじ)、篠原を引き過ぎて。
三国一の瀬田の唐橋をえいさらえいと引き渡し。
石山寺の夜の鐘が、耳に聞こえる、おごそかになりひびく。
馬場、松本を引き過ぎて。
道をいそいで行きましたので、ほどもなく。
西近江に名の高い、上り大津の関寺の玉屋(たまや)の門(かど)に、車は着きました。
照手姫さまは、餓鬼阿弥のそばにいられるのも今夜きりだと思いまして、別のところに宿をとることもせず、餓鬼阿弥の車のわだちを枕に、夜すがら泣いて、夜を明かしました。明け方に鳴くという八声(やこえ)の鳥のようでありました。東の空が白む頃、玉屋の内へ行きまして、料紙と硯を借りまして、餓鬼阿弥の胸札に、こう書きつけたのでありました。
「東海道七か国、車を引いた人は多くとも、その中で、美濃の国、青墓の宿、万屋の、君の長どのの下女、常陸小萩という姫が、青墓の宿から上り大津の関寺まで車を引きました。熊野の本宮の湯の峯にお入りになり、病が本復したならば、お帰りのさいかならず青墓の万屋にお寄りください。かえすがえすも、お名残りおしゅうございます」
どんな因果のご縁やら。
蓬莱の山のお座敷で夫の小栗に離れたときも。
この餓鬼阿弥と別れる今も。
思いは同じでありました。
ああ、この身が二つあったなら。
一つのその身は、君の長どのに戻したい。
もう一つの身は、餓鬼阿弥の車を引いて行きたい。
心は二つ、身は一つ。
見送り、たたずんでいたのでありますが。
いそぎの帰り道を、いそいで行きましたので、ほどもなく、君の長どのに戻りついたということ、ここにこそ、ものごとのあわれをとどめたのでございます。
さてまた、車を引こうという人が出てきまして。
上り大津を引き出して、逢坂の関、山科に、車は着きました。
もの憂き旅に、逢わないままの粟田口(あわたぐち)、都の城(じょう)に車は着きました。
東寺、三社、四つの塚、鳥羽に、恋塚、秋の山。
月かげは川面にやどらなくとも、月がうつると評判の、桂の川をえいさらえいと引き渡し。
山崎の千軒の町並みを引き過ぎて。
これほど狭いこの宿をだれが広瀬とつけたのか。
塵(ちり)かき流す芥川、太田の宿を、えいさらえいと引き過ぎて。
中島の三宝寺の渡りを引き渡し。
道をいそいで行きましたので、ほどもなく、天王寺に車は着きました。
天王寺の七不思議のありさまを、餓鬼阿弥にも拝ませてやりたいと、引く人は思いましたが、耳も聞こえず、目も見えず、ものもいわない餓鬼阿弥でありました。帰りには心静かに拝みなさいよと、阿倍野五十町を引き過ぎて。
住吉四社の大明神、堺の浜に車は着きました。
松は植えてなくとも小松原、わたなべ、南部(みなべ)を引き過ぎて。
四十八坂、長井坂、糸我峠や、蕪坂、鹿瀬(ししがせ)を引き過ぎて。
心を尽くして仏坂、こんか坂に車は着きました。
こんか坂までたどり着いたのでありますが、これから湯の峯へは、道が険しくて車を引いては行かれない。しかたがない、引く人は、ここで餓鬼阿弥を捨てて行きました。そこへ、大峯山に入る山伏たちが百人ばかり、ざんざめいて通りかかりまして、この餓鬼阿弥を見て、「いざ、この者を熊野本宮の湯の峯に入れてやろう」と言いまして、土車を捨てて籠を組み、餓鬼阿弥を入れて、若い山伏の背中にむんずとおぶわせ、さらにのぼっていきました。
お上人に引かれて上野が原を立ってから、日にちをかぞえてみれば、四百四十四日めに、とうとう熊野本宮の湯の峯に入りました。たいそう効き目のある薬湯でありました。
一七(いちしち)、七日間、入ったあとには両眼が明き、二七(にしち)、十四日間、入ったあとには耳が聞こえ、三七(さんしち)、二十一日間、入ったあとには早くもものが言えました。七七(しちしち)、四十九日めになりますと、六尺二分の、どうどうと豊かな、元の小栗どのに戻ったのでありました。
小栗どのは、夢から覚めた心持ちで、熊野三山、本宮、新宮、那智のそれぞれの湯に入っておりました。それを熊野の権現さまがごらんになりまして、
「あのような大剛の者にこそ金剛杖を買わせたい。あの者が買わなければ、末世の衆生に買う者はあるまい」と、山人(やまびと)に変化(へんげ)して、金剛杖を二本お持ちになりまして、
「ああ、そこの修行者さんや、熊野へ詣った記念はいらんかね。どうだな、この金剛杖をお買いなされ」とおっしゃいました。
小栗どのは、むかしの傲慢さがまだなくなっておりませんから、
「おれは東海道七か国を、餓鬼阿弥などと呼ばれながら、車に乗って引かれて歩いたことが無念でならないのだ。そのおれに金剛杖を買えとはなんだ。おれを呪いたおそうとしているのか」と言いました。
権現さまはこれをお聞きになりまして、
「いやいや、そうではない。この金剛杖というのは、そなたが天下に出たときに、そなたの弓とも楯ともなり、運を開く杖なのだ。金がなければ、ただでやろう。一本の杖を川に捨てればたちまち舟となる。また一本は帆柱となる。舟の名前を『浄土の舟』という。この舟に乗るならば、どこへでもそなたの行きたいところへ行くぞ」とおっしゃいまして、かき消すようにいなくなりました。
小栗どのはこれを見て、
「そこらの山人と思ったが、権現さまだ。おすがたをあらわしてくださった権現さまを、手に取るように拝み申したのだ、なんとありがたい」と、熊野三所を伏し拝み、二本の杖をいただいて、ふもとを指して降りていきました。教えられたとおり、一本を川に流してみましたら、浄土の舟として川の面に浮かびました。もう一本を帆柱として立てて、船に乗りこみましたら、まことに権現さまのおはからいか、漕ぎ手も押し手もいないのに、するすると舟は向かいまして、小栗どのは都に戻ったのでありました。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。