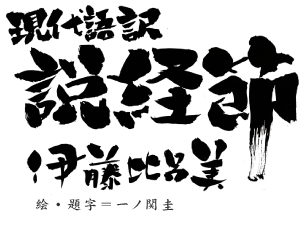第10回 しんとく丸 その2 しんとく丸が生まれ育ち、そして恋をする
仏のお誓いはあらたかでありました。長者の妻は月水がとまり、七月間のわずらい、九月間の苦しみ、とうとう十月めにお産がはじまりました。そば近くに仕える女房たちが取り上げて、男か女かと見ましたら、石をみがいてまっ青な瑠璃(るり)の玉があらわれ出たような若君でありました。長者夫婦の喜びは何にとも譬えようがありませんでした。
屋形に長く仕える翁が参りまして言いました。
「若君に名をつけてさしあげます、何とおつけいたしましょう」
信吉どのはこれを聞きまして言いました。
「この子は清水観音さまの申し子であるから、どうぞよい名前をつけておくれ」
そこで翁は、「富にめぐまれた福徳はお父上にあやかりたまえ、身命(しんめい)の長さはこの翁にあやかりたまえ」と、「しん」と「とく」とを一字ずつ取りまして、しんとく丸とつけました。
若君には、乳を飲ませる者が六人、世話をする者が六人、十二人の乳を飲ませる者や世話をする者が産湯をつかわせ、かわいがってそだてたのでありました。二歳三歳もたちまちすぎて、あっという間に九歳になりまして、何もかも昨日今日のできごとのようで、長者夫婦の喜びはかぎりがありませんでした。
信吉どのが妻を呼びまして言いました。
「妻や、しんとく丸を信貴(しぎ)の寺へ上げようと思うのだが」
それがよろしゅうございますと妻も言い、さて信吉どのは、家来の仲光(なかみつ)を呼んで言いました。
「よくきけ、仲光や、しんとく丸を信貴のお寺に三年の間預けようと思っておる。よく学問させるように」
承知いたしましたと、仲光が若君のお供をして、お寺入りになりました。道をいそいで行きましたので、ほどもなく信貴のお寺に着きました。そこで仲光は、お寺の偉い阿闍梨(あじゃり)さまに会いまして、「この若君は河内高安、信吉長者のお子でございます。三年の間、お預けいたします」と申しましたら、阿闍梨さまからは「ご安心なさい、しっかりとお預かりしますよ」というおことばをいただいて、仲光はしんとく丸の許に行き、「若君、よく学問なさるんですよ、三年が過きましたらお迎えに参ります」と言い置いて、河内の国へと帰っていきました。
しんとく丸の賢いことは、他の少年たちをはるかに抜きん出て、お師匠さまから一字を聞けば二字悟り、十字を聞けば百字を悟り、千字を悟る。ほどもなく、寺で一番の学者と言われるようになりました。
さて、お話は変わります。
和泉、河内、摂津の国、三か国の金持ちが一つ所に集まりまして、なにか豪勢な遊びをいたそうと、それなら二月二十二日の精霊会(しようりょうえ)、天王寺の蓮池の上に石の舞台を張らせ、四方に花をささせ、稚児に舞を舞わせて楽しむのはどうかということになりまして、それはいい提案だということになりまして、今年は信吉どのが当番にと指名されたのでありました。
信吉どのは家に帰り、仲光を呼びまして、「信貴のお寺へ行って、しんとく丸を連れてまいれ」と言いつけました。承知いたしましたと仲光は信貴の寺へ出かけていきました。道をいそいで行きましたので、ほどもなく信貴のお寺に着きまして、お寺の阿闍梨さまに事情を申しあげますと、阿闍梨さまからは「ご安心なさい、すぐにお返ししますよ」というおことばをいただいて、そうしてひさしぶりの父母との対面を果たしたしんとく丸でありました。
信吉どのは言いました、
「よくもどった、しんとく丸よ。呼びもどしたのは他のことではない。こんど天王寺で催す稚児の舞、今年はおれが当番の役をつとめることに相成った。それで、よそから稚児をやとって舞わせるか、おまえに舞わせるか、どうしようか考えておったのだ」
しんとくは聞きまして「よその稚児に舞わせるより、わたくしが舞いましょう」
二月二十二日になりますと、他の稚児たちも寄り集まり、それぞれの役を決め、稚児の舞が行われたのでありました。しんとく丸の稚児は、それはそれはあでやかで美しく、扇の手ぶりはなめらかですばらしく、人々はいうに及ばず、もろもろの諸菩薩も、そして川の魚さえ、その舞見たさに川の面に浮かびあがってきまして、見物の群衆は、貴いも賤(いや)しいも満ち満ちて、ほめないものはありませんでした。
七日間の舞が三日間つづき、四日目のことでありました。しんとく丸は、踊る扇の手の隙間から、北西の座敷に、その姫を一目見たのでありました。
ああこの世が思うようになるならば、あの姫君とちぎりをむすびたい、むすべるものならば、今生(こんじょう)に思い残すことは何もない。
これが恋路となりまして、しんとく丸はその日の舞を中途で舞いやめ、仲光を供に、高安さして帰りまして、部屋に引き籠り、籐(とう)の枕を引き寄せ、床についてしまったのでありました。仲光はおろおろとして、しんとく丸の閉じこもる部屋に行きまして、
「どうなさいました、若君。どうしてそんなに伏せっていらっしゃいます。大事なおからだでございます。お手をこちらにお出しください。仲光めが、お脈を取ってご病気を直してさしあげます」。
しんとく丸が両手を仲光にあずけましたら、仲光はたんねんにその脈を取りまして、
「上のお脈はおだやかだが、底のお脈は乱れておられる。これは四百四病の病じゃございませぬ。恋路の脈ではございませんか。どなたかに恋していらっしゃいますね。若君、隠さずにおっしゃいませ。あちらのお気持ちをなびかせてさしあげます」
若君はこれを聞き、重い頭を軽やかに上げまして、
「思いが内にあれば、色が外にあらわれる。恥ずかしいことだが、今はもう隠すつもりもない。舞を舞っていたとき、北西の座敷に輿が三丁あるのを見た。中の輿の姫君は、どちらの姫だったろう、仲光よ」
仲光はこれを聞いて言いました。
「恋していらっしゃるのはそのかたでございましたか。それなら、和泉の国、近木(こぎ)の庄、蔭山長者の乙の姫さま。蔭山長者と信吉長者、位も氏も劣ってはいませんよ。決まったお相手のおられぬ姫さまです。一筆おかきなさいませ。恋をなびかせてさしあげます」
しんとく丸は舞い上がる心持ちで、硯、料紙を運ばせまして、墨をすりながし筆をとっぷりと染めまして、思いのたけ、心にあることを、ねんごろに書きとどめ、山形様におし畳み、松がわ結びに結びまして、「頼んだよ」と仲光に手渡しました。
仲光は受け取って、「それでは行ってまいります」と高安を立ち出て、堺の浜に行きました。そこで数々の薬を買い求め、十二種の身のまわり品やら雑貨やらも買い求め、さて自分は商人に様を変え、道をいそぎましたので、ほどもなく、和泉の国、近木の庄に着きました。
蔭山長者の堀の船橋をうち渡り、平地(へいじ)の門からつっと入り、大広庭にずっと立ち、なんと仲光は、そこで商いを始めたのでありました。
「紅や、白粉(おしろい)、畳紙(たとうがみ)。御たしなみの道具には、沈(じん)、麝香(じゃこう)。お入り用ではございませんか」と行ったり来たりしておりましたら、女房たちが聞きつけて、「あら、めずらしい、商人だわ、なにか持ってきましたか」と出てきました。
仲光は応えて、かついだ連尺(れんじゃく)を広縁におろし、自分は落ち間に腰を掛け、唐の薬や日本の薬、十二種の身のまわり品や雑貨類、つづらの懸子(かけご)にいろいろと包みわけてある品々を取り出しますと、あれやこれやと女房たちが品定めしはじめました。よい頃合いと見定めた仲光は、例の手紙を取り出しまして、
「聞いてください、女房たちよ。わたくしはこの三日前、河内の国高安、信吉長者のお屋敷で商いをしていたんでございます。そのおりに、信吉長者の裏辻で、実に美しくしたためられた文を拾ったのでございますが、拾った場所に好奇心がそそられまして、今まで捨てられずに持っておりました。どうぞみなさん、一目ごらんになりまして、お気に召したら、お手本にでもなさいませ。おいやなら、この場の笑いぐさになさいませ」と女房たちに手渡しました。
女房たちは受け取って、謀(たばか)る文とはつゆ知らず、さっと広げて読み始めました。
「なになに、『上なるは月や星、中は春の花、下は雨霰(あめあられ)』と書いてある。
狂人がわけのわからないことを書き散らして、そこらにひょいと捨てたんだわよ」と一字も読みとけずに、みんなで笑いたてたのでありました。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。