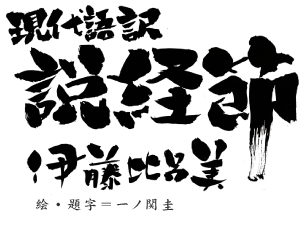第12回 しんとく丸 その4 継母の呪いでしんとく丸は...
信吉どのの新しい妻は、前世の報いに、よい報いがあったのでありましょう、まもなく若君ができました。信吉どのは、この子に乙二郎と名づけたのでありました。妻はこれを聞きまして、心に思ったのでありました。
「あたしはこうして子をひとり生んだ。それなのに、その子は総領の扱いもされず、人に乙二郎と呼ばせなければならなくなった。腹立たしくてたまらない。たとえ無理だとわかっていても、しんとく丸を呪い倒して、乙二郎を総領にしてやりたい」
これが悪い心の素となりました。妻は信吉どのに近づいて、こう言いました。
「あなた、お話がございます。あたくしは都の生まれですから、清水のご本尊に立てた願(がん)がございますの。清水詣でをいたしとうございます」
信吉どのはこれを聞きまして、「いいとも、行っておいで。輿(こし)で行くかね、馬で行くかね」
妻はこれを聞きまして、「馬だの輿だので行きましたら、大事(おおごと)になりますから、いろんなうわさを立てられてうるさくてたまりませんわ。乙二郎は女房たちに抱かせて忍んで参ります」と言いました。そして旅の用意をし、高安を立ち出でまして、旅の巡礼の通る道すじをじゅんじゅんに通っていったのでありました。
通っていったのはどこどこでしょう。植付畷(うえつけなわて)、讃良郡(さくらごおり)、洞が峠をうち過ぎて、伏見の里もはや過ぎて、道を急ぎましたので程もなく、清水坂に着きました。
着きますと、妻は宿を取り、鍛冶屋を頼み、夜の間に六寸釘をあつらえまして、夜が明けますと、すぐに清水の観音さまにお詣りして、鰐口を、じゃん! とうち鳴らして祈りました。
「心から帰依いたします。大きなお慈悲をお持ちの観世音菩薩さま。わたくしがここまで参りましたのは、他のことではございません。しんとくはご本尊さまの氏子だそうでございますが、今日からは、わたくしの乙二郎を氏子にさしあげます。ですから、どうぞ、しんとくの命をお取りくださいませ。それがご無理なら、どうぞ、しんとくに、人の嫌う病をお授けくださいませ」と深く呪いをこめまして、「これは、しんとくの四本の足の関節に打ち込みますのです」と言いながら、おん前の立ち木に、観音さまのご縁日の数だけ、十八本の釘を打ち込みました。
それが済みますと、今度は南に行きまして、祇園の八坂神社に詣りまして、毎月七の日が縁日でありますから、おん前の格子に七本の釘を打ち込みました。
それから八柱の神々を祀る御霊(ごりょう)神社に詣りまして、八本を打ち込みました。
それから櫟谷七野(いちいだにななの)神社に詣りまして、七本を打ち込みました。
それから今宮神社に詣りまして、十四本を打ち込みました。
それから北野天満宮に詣りまして、二十五本の釘を打ち込みました。
それが済みますと、今度は南に行きまして、東寺の夜叉神(やしゃじん)さまに詣りまして、二十一本を打ち込みました。
それから因幡堂に詣りまして、「これはしんとくの両眼に打ち込むのです」と言いながら、十二本を打ち込みました。
余った釘を、鴨川と桂川に、「荒れよ、水神」と打ち込みました。
妻が都の神社のお社に打ち込んだ釘の数を数えてみれば、打ちも打ったり百三十六本になりました。
それから清水に戻ってまた観音さまにお詣りし、おん前に三度、伏し拝みまして、「どうか、わたくしが家に帰りつく、その前に、あの憎いしんとくめに、病を、お授けくださいませ」と深く呪いをこめまして、高安へ帰ったのでありました。
(ああ、いたわしい!)しんとく丸は、持仏堂で、亡き母のためにお経を読んでおりました。すると呪いのしるしが現れてきました。呪いは強うございました。百三十六本の釘の打ち込んだところから、人の嫌う病がとりつきまして、あっという間に両眼がつぶれ、しんとく丸は、病者になり果てたのでありました。
(ああ、いたわしい!)しんとく丸は、情けないことになったとうちひしがれ、萎(しお)れ果て、沈み込んで、自分の部屋に閉じこもり、籐の枕をひきよせて横たわりました。しんとく丸の心の内をあわれと言うのはたやすいのですが、何かにたとえることなど到底できることではありませんでした。
それはそれ。こちらは信吉どのの妻でございます。
妻は高安に帰りつき、間仕切りの障子のすきまから、しんとく丸のようすをのぞいてみましたら、望んだとおりのことになっていました。妻は都の方を伏し拝み、かぎりない喜びに充ち満ちました。そして、信吉どののところに行って、こう言いました。
「あなた、お話がございます。都の辻々で人がうわさしてますのよ。武士の身内に病者が出たということは、七代もの間、神仏のご加護がなくなってしまうのではないかといってますのよ。なんでもしんとくは、人の嫌う病になり果てたそうじゃございませんか。かわいそうではございますけど、どこへなりとも、人の待つ松の木の根本にでも、お捨てなさいましな。そうしてくださらないようでしたら、あたくしは、ええ、お名残り惜しゅうございますけど、お暇を取らせていただきます」
信吉はこれを聞いて、言いました。
「おれは長者だ。病者が五人十人いたからといって養えないことはない。一つの家に住むのがいやなら、別に家を建てさせて、そこでしんとくを養おう」
妻はこれを聞いて、さらに言いました。
「もうよろしゅうございます。とにかく、乙二郎とあたくしはお暇を取らせていただきます。ええ、お名残り惜しゅうはございますけども」
信吉どのはこれを聞いて、とうとう思い切ったのでありました。あの妻を追い出して、別の妻を迎えたとしても、姿は違うだろうが、邪慳な心は変わるまい。そんならいっそしんとく丸を捨ててしまおう。それで家来の仲光を近くに呼んで、言いました。
「仲光、話がある。なんでもしんとく丸がいやな病になったそうじゃないか。かわいそうだが、どこへでもいい、どこかへ捨ててきてくれ」
仲光はこれを聞いて、言いました。
「仰せではございますが、お殿さま。この仲光、産みのお母上のご遺言に、仲光頼むと申しつけられてございます。どうか、ほかの者にお命じになりまして、仲光に仰せつけられることだけはお許しくださいませ」
信吉はこれを聞いて、言いました。
「死んだ先の妻がおまえの主人で、まだ生きている信吉は主人じゃないのか。捨ててこいというのに捨ててこないのなら、しんとく丸だけでない、仲光も同じことだ。おれは、おまえに、金輪際会わないぞ」
それで仲光はしかたなく承知をいたしまして、信吉の前からさがって誰もいない部屋に入り、そこでひとり嘆くようすがあわれでなりませんでした。
「今のおれは、なんだか藻塩草をかきあつめたみたいだよ。もつれにもつれて、にっちもさっちもいかなくなった。何がよくて何が悪いのかもわからなくなった。血を分けた親が、心変わりをして、子を捨てろというのだ。ましてやおれは他人だ。思い切るのにためらいはあるまい」
それからしんとく丸のところに行きまして、間仕切りの障子のこちらから言いました。
「若君、どんなぐあいでいらっしゃいますか。若君、ご病気はいかがでございますか」
しんとく丸はこれを聞いて、言いました。
「仲光かい、めずらしいなあ。おれはどんな因果でこんな病気になったのか。目が見えないというのは、いつも長夜のようだね。病気になってからは誰も見舞いに来てくれないよ。仲光、よく来てくれた、うれしいよ」
仲光は涙にくれながら、しんとく丸に言いました。
「あのですね、若君、実はですね、なんでもいつぞやの稚児の舞をおやりになったあの天王寺に、都から貴いお坊様がいらっして、七日間のご説法をなさるそうですよ。お詣りにおいでになりませんか」
しんとく丸はこれを聞いて、言いました。
「忌日(きにち)や命日はいろいろあるが、中でも明日は乳房の母が亡くなって三年目の命日だ。お詣りしよう」
それで仲光は「おともいたします」と、駄馬の背に鞍を置き、さて、乗せるのは何と何か。金桶に、小御器(こごき)に、細杖、円座に、蓑。それから笠をくくりつけ、しんとく丸を抱き乗せて、表門は人目があるからと、裏門から引き出したのでありました。
(ああ、いたわしい!)信吉どのも、これが別れと思えばこそ、門まで出てきて言いました。
「おお、出かけるのか、しんとく丸、天王寺へお詣りか。早く帰って来るんだよ」
しんとく丸はこれを聞いて、言いました。
「父上ですか。馬の上からのお返事、お許しください。なるべく早く帰ってまいります」
信吉どのはこれを見て、「和泉、河内、津の国の三か国で、美しい少年と評判だったのに、病にかかった今となっては、馬に乗る姿も見苦しい」と普段はその勇猛さで名の高い信吉どのですが、はらはらと落ちる涙が抑えられなかったのでありました。
しんとく丸が言いました。
「仲光よ、目が見えないというのはいつも長夜のようなのだ。道のようすを語っておくれ」
仲光は引き受けまして、
「若君、ここは高安馬場の先でございますよ。向かいに見えるのは恋の松でございますよ」と語りながら、玉串(たまこし)、みし、上(かみ)の島、さいべの橋を引き渡したのでありました。
そのとき、しんとく丸がこう詠じました。
「衣摺(きする)を出で。蛇草(はくさ)の露に、裾濡れて、いかが渡らん、中川の橋」
そして小橋(おばせ)、小野村(このむら)、つかわし山、西寺をうち過ぎて、天王寺の南の門に着きました。
仲光が言いました。
「さあ、着きました。若君、今日のお説法はもう終わってしまったようでございます。今晩のお宿は、町家に取りましょうか、それともお寺の宿坊に取りましょうか、若君、どちらがよろしゅうございますか」
しんとく丸はこれを聞いて言いました。
「世が世であれば、宿坊に泊まりたい。町家の宿じゃ人に笑われて恥ずかしい。今夜は念仏堂で夜明かしをしよう」
「承知いたしました」と仲光は言いましたが、実はそれこそ願うところでありました。念仏堂の縁まで馬を引き寄せて、そこにしんとく丸をどうと下ろしますと、(ああ、なんていたわしい!)しんとく丸は、こんな苦しい旅は初めてした。馬に揺られて、疲れ果て、前後不覚に、ばったり倒れてしまいました。
(ああ、いたわしくてたまらない!)仲光は、宵の間こそ話し相手をしていましたが、はや夜も更けました。若君を捨てると思えば、まんじりともできませんでした。仲光は、しんとく丸の枕元に行きまして、後れ髪をかき撫でて、若君をお起こしして暇乞いをしようか。いやお起こししてはお気の毒だ、心の中で暇乞いをすればいいのだと、消え入るように嘆いていたのでありました。そしてとうとう「これでおいとまいたします、さようなら」と立ち去ろうとしましたが、あまりにつらくて悲しくて、また戻ってきて、眠るしんとく丸にすがりつき、しかしとうとう「これが別れか、悲しいなあ」と心強くも仲光は、名残りの袖を振り切って、馬の手綱に手を掛けて立ち去ろうとしましたが、馬にも心がありました。手綱を引いても動きません。そして仲光も、涙にむせるばかりで、涙は五月雨(さつきあめ)のように滴るばかりで、なかなか立ち去ることができません。
(ああ、いたわしくてたまらない!)仲光の嘆くようすがあわれでなりませんでした。
「昔から今にいたるまで、おれは、主のない馬の口を引くなんて、他人の話だと思っていたのだ。でもそれが、今のおれなんだ。悲しい、とても悲しい」と嘆くようすが、ほんとにあわれでなりませんでした。
(ああ、いたわしくてたまらない!)仲光は心が引かれてならないように、しんとく丸をしばらくじっと見守ってから、身をひるがえし、河内の国の高安をさして帰っていきました。道を急ぎましたので程もなく、高安に着きまして、信吉どのに対面し、しんとく丸を捨てたということをしっかりきっぱりと告げたのでありました。その仲光の心の内をあわれというのはたやすいのですが、何かにたとえることなど到底できることではありませんでした。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。