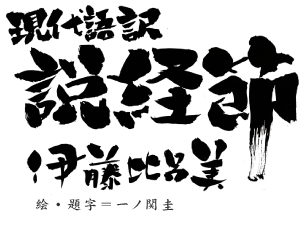第16回 山椒太夫 その2 「ああ、いたわしい」、きょうだいは山椒太夫に売られていく
ああ、いたわしくてなりません。
四人は売られるとも買われるとも知らずに、太夫の家をしのび出て、人の家の軒端(のきば)をつたって、浜に向かって行きました。
浜に着きますと、太夫は一行を夜舟(よぶね)に乗せまして、もやい綱をほどくのももどかしく、腰の刀をするりと抜いて、ざっくりと綱を切り放ち、やったやった、久しぶりにいい商(あきな)いになると心の中でほくほくしながら、「えいやっ」と声をあげ、櫓拍子(ろびょうし)を踏んで押し、夜の波間に、三里ほどこぎ出していきました。
沖をじっと眺めれば、霞の中に、舟が二艘、見えました。
「そこの舟、商い舟か、漁の舟か」と太夫が問いますと、一艘は「えどの二郎の舟」と答え、一艘は「宮崎の三郎の舟」と答えました。
「おまえの舟はどこの舟だ」と向こうも聞きまして、「これは山岡の太夫の舟だ」と。
「めずらしいな、商い物はあるのか」と聞きますので、山岡太夫が「これだけある」と片手を差し上げて親指を一人折ったのは、四人あるとの合図でありました。
「四人あるなら五貫で買おう」と二郎が早速値をつけました。
「そっちが五貫なら、おれは前々からの取引だ。一貫あげて六貫で買う」と三郎が言いました。
おれが買う、いやおれだと口論になり、けんかになりかけましたので、太夫は向こうの舟に飛び移り、
「音を立てるな、鳥が立つ。こっちの鳥は若鳥だ。末に繁盛するように、両方に分けてやる。まずえどの二郎どのは奥方二人買ってゆけ。また宮崎の三郎どのはきょうだい二人買ってゆけ。五貫に負けよう」
そしてまた自分の舟に飛び移り、
「お聞きください、旅の奥さま。今の口論は誰のためとお思いか。奥さまのためでございますよ。二艘の舟の船頭はおれの甥ども、伯父思いの甥どもが、伯父の舟の客人を自分が送ろう、いや自分が送ろうと口論しております。二人の気の済むようにしてやってくださいませんか。行く先も一つ、港も一つ、舟の足を軽くすると思って二つの舟で行ってください。まず奥さまがたはこちら、あの舟にお乗りなさい。きょうだいはこちらの舟にお乗りなさい」と太夫は四人を五貫にうち売って、直井の浦に戻っていったのでありました。
なによりも哀れでならないのはこの舟二艘。ここに哀れも極まったのでありました。
五町ばかりは並んで行きましたが、十町も行きますと、舟は、北と南へ別れていきました。奥方はそれを見て、「ちょっと船頭どの、舟と舟の間が開きすぎてはいませんか。同じ港へ行くようには見えません。舟をこぎ戻して、そうっと進めてくださいませよ、船頭どの」と言いますと、船頭は「なにをいうか、今朝の商いでもうけそこなって、腹が立ってたまらねえのだ。奥方二人はおれの者だ。舟底に乗れ」と言うばかりでありました。
奥方はこれを聞いて言いました。
「まあなんということ、聞きましたか、うわたき。あたしたちは売られたのよ、買われてしまったのよ。太夫どの、なんて情けない。船頭どの、なんて恨めしい。売るなり買うなりするにしても、親と子を二つに売り分けるなんて、なんて酷(ひど)い。悲しゅうございます」
そして宮崎の三郎の方をうち眺めて言いました。
「子どもたち、きょうだいたち。あなたたちは売られたのよ、買われてしまったのよ。命を大切にするのですよ、きょうだいたち。また世に出ることだってあるかもしれない。姉のはだに掛けたのは地蔵菩薩さま、もし二人の身の上に何か大事が起こったときには、身代わりにも立ってくださる地蔵菩薩さまですよ。よく信心して掛けておきなさいよ。弟のはだに掛けたのは、信太玉造(しだたまつくり)の系図です。死んで冥土に行くときも、閻魔(えんま)さまへのいいみやげになりますからね。落としたらいけませんよ。厨子王丸」と声の届くかぎり呼びかけていたのでありました。
次第に帆影は遠くなりました。声が届かなくなりました。奥方は腰の扇を取り出して、ひらりひらりと招きましたが、舟は近寄るどころか、今朝、越後の国の直井の浦に立つ白波が、妨げる雲のようにさえぎるばかり。
「わが子が見えない、見えない、ああ悲しい。善知鳥(うとう)というあの鳥でさえ、子が取られれば嘆き悲しむという。どうか、おねがいです、船頭どの、舟をこぎ戻して、もう一目、生きているうちにもう一目、わが子に会わせてくださいませ」
船頭はそれを聞いても、「なにをいうか、舟を一度出したらもう戻らない。それが掟だ。船底に乗れ」と言うばかりでありました。
うわたきはそれを聞き、「わかりました」と呟(つぶや)いて、「賢臣は二君に仕えず、貞女は両夫にまみえずと申します。あたくしは、二張(にちょう)の弓は引きません」と言いまして、船梁(ふなばり)に立ち上がり、数珠(じゅず)を取り出し、西に向かって手を合わせ、声たからかに念仏十遍となえ、身を投げて、直井の浦の、浦の底の藻屑(もくず)となりました。
奥方はこれを見て、「親とも子ともきょうだいとも思って頼りにしてきたうわたきがこんなことになってしまった。どうしたらいいの」と身も世もなく泣きじゃくりました。やがてこぼれる涙をおしとどめ、ちきり紋様の村濃(むらごう)染めの小袖を一重ね取り出しまして、
「船頭どの、少ないのですけれど、これは今朝のお代金としてお収めください。わたくしもこれでおいとまして身を投げます、船頭どの」
船頭はこれを聞き、「なにをいうか、一人は損してしまったが、二人めまで損をするものか」と言いまして、手にした櫂(かい)で奥方を打ち伏せて、船梁にしばりつけ、蝦夷の島に売り飛ばしたのでありました。蝦夷の島の人買いは、能がない職がないと言い、奥方の足の筋と手の筋を断ち切りまして、奥方は日に一合の穀物を食べて生きのびながら、粟にたかる鳥どもを追うことになりました。
これは奥方の物語。
それはそれとして、とくに哀れでならないのは、あの宮崎の三郎が、きょうだい二人を二貫五百で買い取った後、二人があちらに売られ、こちらに売られ、とうとう丹後の国、由良の港の山椒太夫に、十三貫に値をつけられて買い取られていったこと。世の中には哀れなことがさまざまありますけれども、これこそ哀れでたまらないことでございました。
太夫は買い取った二人を見て、「これはよい下人(げにん)を買い取った。うれしいぞ。孫や曾孫(ひまご)の代まで、この者どもを、譜代(ふだい)の下人と呼んで使えるとはうれしいことだ」と喜ぶことはかぎりがありませんでした。
ある日のことでありました。太夫はきょうだいを前に呼び、
「うちでは名のない者は使わないのだが、おまえたちの名はなんという」と聞きました。
姉はこれを聞いて言いました。
「はい、わたしたちは奥州の山深くの者ですから、姉は姉、弟は弟と呼ぶばかりで、名を持ちません。よい名をつけてください」
太夫はこれを聞いて言いました。
「よし、そういうことなら、生まれた国はどこだ。国の名で呼ぶ」
姉はこれを聞いて言いました。
「はい、わたしたちは伊達の郡、信夫の荘の者ですが、三月十七日にほんのかりそめに国を出たところ、越後の国、直井の浦から売られ売られて、あんまり辛くて、そっと数えておりましたら、ここの太夫どのまでに七十五回売られました。どこでも商いのしなもの扱いされるだけで、きまった名前もありません。どうかよい名をつけてお使いください、太夫どの」
太夫はこれを聞いて言いました。
「よし、そういうことなら、伊達の郡、信夫の荘から取っておまえを『しのぶ』と名づけよう。忍ぶ草には忘れ草がつきものだ。今までのことは忘れて太夫によく仕えるように、弟を『忘れ草』と名づけよう。明日になったら、姉のしのぶは浜に行って潮を汲め。弟の忘れ草は日に三荷(さんか)の柴を刈れ。太夫のためによく働け」
夜明けになりまして、きょうだいは鎌と天秤棒(てんびんぼう)、桶と柄杓(ひしゃく)を渡されました。
いたわしいことにきょうだいは、鎌と天秤棒、桶と柄杓を受け取って山と浜に出て行きました。いたわしくてなりません。姉上は、浜のとある所で立ちつくし、桶と柄杓をからりと捨てて、山の方をうち眺めて泣いておりました。
「目の前にこんなに潮がある。それなのにあたしにはうまく汲めない。ましてや弟は、鎌なんて持ったこともない。手元が狂って手を切ったりしてないか。山では峰を渡る風が激しくて、さぞ寒かろう。悲しい」
弟の厨子王どのも、岩鼻に腰を掛け、浜の方をうち眺め、
「ここにはこんなに柴があるが、おれにはちっとも刈りとれない。浜に立つ白波には女波男波(めなみおなみ)があるという。男波の潮を打つ間に、女波の潮を汲むという。波のことなんか何にも知らない姉さまは、桶や柄杓を波に取られてないか。浜では浜の風が激しくて、さぞ寒かろう。悲しい」
そのように山と浜とで泣き暮らしておりました。そこに里の山人(やまうど)たちが柴を刈って帰りがけに通りかかりました。
「この童(わっぱ)は山椒太夫のところに来たばかりの童だ。山へ出て柴を刈らずに戻ったら、邪慳(じゃけん)な太夫や三郎がいじめ殺すことは間違いない。人助けは菩薩の行(ぎょう)ではないか。おい、みなの衆、この童のために柴を集めてやらないか」と柴を少しずつ刈りまして三荷分の柴を刈りあつめ、「さあ、荷を作って背負いな」と言いました。
厨子王どのが「刈ったことも背負ったこともありません」と言いますと、それはそうだろうと山人たちも思いまして、それぞれの荷の先にくくりつけ、あすみが小浜まで運んでくれたのでありました。
昔から申します、「重荷に小付け」ということわざは、この時代からこうして言われるようになったんでございます。
なんといたわしい厨子王どの、三荷の柴を運んでいきましたら、三郎が見て、厨子王どのを片手に、柴を片手にひっつかみ、太夫どののところへ引っ立てて行きました。
「はなしがございます、太夫どの。童の刈った柴をごらんください」
太夫はこれを見て言いました。
「おまえは柴を刈ったこともないと言ったが、ほんとに刈れないのなら、根元をそろえることも知らず、束ねたってばらばらになるはず。ところがこれはどうだ。土地の山人がやったようにうまくできておる。こんなにできるのなら、三荷じゃ足りない。七荷増やして十荷刈れ。十荷刈ってこなければ、おまえたちの命はないよ」と厨子王丸を責めたのでありました。
いたわしくてなりません。
厨子王どのは、門の外に出て、姉の帰りを待ちました。
いたわしくてなりません。
姉上は、すそは潮風に、そでは涙にしょぼぬれて、桶をかついで戻ってきました。厨子王どのは姉のたもとにすがりついて言いました。
「ねえ、聞いておくれ、姉さま。おれが今日の柴を刈れずにいたら、山人のおじさんたちが情けで刈ってくれた。そしたらきれいに刈ってあったのを見とがめられて、七荷増やして十荷刈れと言われたよ、姉さま。どうか太夫どのに頼んで、三荷にゆるしてもらって」
姉はこれを聞いて言いました。
「そんなに泣いちゃだめ、厨子王丸。あたしもそう。今日の潮を汲めなくて、波に桶と柄杓を取られていたら、海人(あまびと)が情けで汲んでくれたのよ。今日はこれで助かったけど、明日はどうなるかわからない。ねえ、厨子王丸。なんでも太夫どのの五人ある息子の中で、二番目の二郎さまは慈悲第一の人らしい。三荷にしてくださいとお願いしてみよう。ほら、そんなに泣かないの、厨子王丸。あたしまで悲しくなってくるから」
そして、きょうだい連れ立って戻っていったのでありました。
姉は柴を三荷にしてくれるように頼んでみました。邪慳な三郎がこれを聞きつけまして、
「はなしがございます、太夫どの。昨日の柴は、あの童の刈ったものと思い込んでおりましたが、あれは里の山人たちが気まぐれに助けたんだそうですよ。由良の千軒に触れを出します」
邪慳な三郎が由良の家々千軒に触れを出してまわりました。
「山椒太夫の身内では、来たばかりの姫と童を使っている。山で柴を刈ってやる者、また浜で潮を汲んでやる者、隣三軒と両向かいまで、罪に問われることになる」
こう触れてまわった三郎を鬼と言わない者はありませんでした。
なんといたわしい厨子王どのは、三郎が触れてまわったのも知らずに、また昨日のところへ行き、助けてもらおうと思って佇(たたず)んでおりました。山人たちはこれを見て、「おまえにやる柴が惜しいわけじゃないのだ。邪慳な太夫から触れがあった。だから助けてやりたいと思っても、柴を刈ってやる者はいないだろうよ。こう持ってこう刈るのだよ」と鎌を持って教えて、通りすぎていったのでありました。
いたわしいことに厨子王どのは、泣いてばかりじゃだめだと思い切り、腰の鎌を取り直して、何という木か、木を一本切ったのでありますが、やり方を知らずに根元を持って引きました。引いた木も、茨(いばら)、葎(むぐら)にからみ取られて、どうにも動かなくなったのでありました。
「この身の上では、柴さえ思いどおりにならないのだな」と泣きながら呟くことばも道理でありました。
「人の寿命は、八十、九十、百まで続くという。おれはまだ年若いけど、十三年が一生だったと思えばそれまでだ」
そう言うと、守り刀のひもを解いて自害しようと思いましたが、
「ちょっと待て、わが心。ここでおれが自害したら、浜にいる姉さまが何とする。姉さまにもう一度会いたい」
浜に行って姉に暇乞(いとまご)いをしてからと考えて、守り刀をおさめて、鎌と天秤棒を肩に掛け、浜辺を指して下っていきました。
いたわしくてなりません。
姉上は、すそは潮風に、そでは涙にしょぼぬれて、潮を汲んでおりました。厨子王どのは姉の衣のすそにすがりつき、
「ねえ、聞いておくれ、姉さま。おれは自害しようと思ったけど、姉さまにもう一度会いたくて、ここまで来た。この世からさっさと離れて、自害しよう、姉さま」
姉はこれを聞いて言いました。
「なにをいうの、あんたは年下だけど男だわ。それが自害しようというのね。あたしも身を投げようと思ってたのよ。待って、待つことができて、ほんとによかった。あんたがそのつもりなら、いっしょにおいで。身を投げよう」
そしてたもとに小石を拾い入れ、岩鼻に上って言いました。
「ねえ、厨子王丸。あんたは越後の直井の浦でお別れしたお母さまを拝むと思って、あたしの姿を拝みなさいよ。あたしは筑紫の安楽寺に流されておいでのお父さまを拝むと思って、あんたを拝むわ」
今、まさに身を投げようとしたそのときに、同じところで働く伊勢の小萩が、これを見て言いました。
「ちょっと待ちなさいよ、二人とも。命を捨てるつもりなの。命さえあれば、しあわせにめぐり会えることもある。また世に出ることだってきっとある。あんたたちが命をむだにしないなら、あたしが自分の話をしてあげる。あたしだってあの太夫に代々使われてきた下人じゃない。国をいうなら大和の国、宇陀(うだ)というところから来たの。継母(けいぼ)にいじめられて、とうとう伊勢の国の二見が浦から売られたの。あんまり辛くて、持っていた杖に刻みをつけて数えてみたら、この太夫のところまでに四十二回売られたの。今年で三年になるけど、初めから慣れるものじゃない、でもいつか慣れる。柴を刈れないなら、あたしが刈ってあげる。潮が汲めないなら、あたしが汲んであげる。だから命をむだにしちゃだめ」
姉はこれを聞いて言いました。
「ああ、そうよ。それができなくて命を捨てようとした。それさえできれば、命をむだになんかしたくない」
伊勢の小萩が言いました。
「それなら今日からは、太夫の家の中で、自分には姉がいるんだと思っていてね」
姉と弟が言いました。
「妹と弟がいると思っていてくださいね」
こうして浜辺できょうだいの契りを交わし、きょうだい連れ立って、太夫の家に戻っていったのでありました。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。