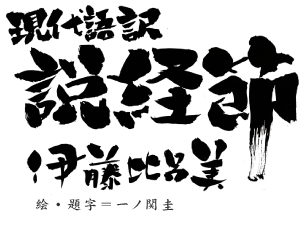第17回 山椒太夫 その3 三郎はきょうだいの顔に焼きごてを当てました
中
時はすぎていきました。昨日今日のことと思っているうちにもう師走の大晦日(おおつごもり)になりました。太夫は三郎を呼び出して言いました。
「おい、三郎よ。あのきょうだいは、奥州の山奥の者だから、正月ということも知らない。ああいつも泣き顔をみせているんじゃ、一年の運もおかしくなるわい。三の木戸の脇に柴がけの小屋を作って、あいつらをそこで年越しをさせろ、三郎、どうだい」
「承知しました」と三郎は言いまして、三の木戸の脇に柴がけの小屋を作り、きょうだいをそこで年越しさせました。
二人は嘆き語りました。それがいたわしくてなりませんでした。
「去年の正月までは浪人の身ではあったけど、伊達の郡の信夫のお屋敷で、身分の高いおとのさまやおひめさまたちの間で、破魔弓(はまゆみ)や羽子板のお相手をして、かわいがってもらったわね。今年の年越しはこのみすぼらしい柴の小屋。あたしたちの国の習わしでは、けがれがある人たちをきらって、こんな別小屋にやるんだそうよ。でも、あたしたちはけがれてなんかない。けがれていると誰に言われるすじあいもない。これは丹後の風習なのかしら。
寒くない? 厨子王丸、
おなかすいてない? 厨子王丸。
ねえ、厨子王丸。
こんなところで一生こき使われるなんてたまらない。ここでは新年に初めて山に入るのは一月十六日だって聞いたのよ。あんたもそのときそこに行く。そしたら、あたしにお別れなんて言わなくていいから、そのまま山から逃げなさい。逃げて世に出てみせて。そしてあたしを迎えに来て」
厨子王どのはそれを聞いて、姉の口に手を当てて言いました。
「だめだよ、姉さま。岩に耳あり、壁が物言うっていうよ、太夫たちがこのことを聞いたらどうなるか。逃げたいなら姉さまひとりで逃げればいい。おれは逃げない」
姉はこれを聞いて言いました。
「ひとりで逃げるのはかんたんだけど、女のあたしには家柄がないの。あんたは家に伝わった系図の巻物を持ってるんだから、一度は世に出なくちゃいけないのよ」
姉に逃げろ、いや、弟に逃げろ、逃げろ逃げないというやりとりを、心の邪険な三郎が、藪の中で小鳥をねらっておりました。そして立ち聞きしてしまいました。三郎は太夫のところに行って告げ口をいたしました。
「聞いてください、太夫どの。あのきょうだいが、姉に逃げろ、弟に逃げろ、と話しておりますよ。こうするうちにも、逃げたかもしれません」
太夫はこれを聞きまして、「連れて来い」と言いつけました。それで三郎は、三の木戸の脇の柴がけの小屋にやってきたのでありました。
いたわしいことでございます、姉上は言いました。
「ああ、やっぱり。正月三日のお祝いを今、くださるんだ。今は太夫どのに譜代の下人と呼ばれて使われていても、もともとあたしたちが、伊達の郡、信夫の荘で、おとのさまやおひめさまに混じってやっていた年賀のご挨拶や式のやりかたを忘れないようにね」
そうして、きょうだい連れ立って太夫どののところに出て行ったのでありました。太夫は怒りに目をひん剥(む)いて、ふたりをにらみつけて言いました。
「やい、おまえらは、十七貫で買いとられて、まだ十七文相当の働きもないくせに逃げるだなんだと企(たくら)んでおったそうだな。逃げたいと言ったって逃がすものか。どこの浦まで逃げたってすぐ太夫の下人とわかるように、印をつけてやる。おい三郎」と言いました。
心の邪慳な三郎は「どんな印をつけてやろうか」と言いながら、天井から炭を取り出して、土間のまんなかにどんと置き、矢籠(やかご)から丸根の矢じりを取り出して、大うちわであおいで熱したて、それから、いたわしいこと、姉姫さまの、背の丈ほどもある美しい黒髪を手にくるくると巻きつけて、姉姫さまを抱え込んだのでありました。
いたわしいこと、厨子王どのは言いました。
「ああ、どうか、三郎さま。ご本気ですか、おたわむれか。おどしのためか。焼きごてを当てられたら、姉の命はありません。よし命が助かったといたします。そしたらいつか、太夫どのの五人のご子息がたの奥様たちが月見や花見の宴を催されるとき、そのお供として、姉はお役に立つでしょう。そのときに、あんな美しい娘がどうして焼きごてをと、人はいぶかしく思うでしょう。そして、本人の過ちだとはだれも思わず、主人のせいと思うでしょう。姉に当てるその焼きごてを、二つとも私に当ててください。そして姉は、お許しください」
三郎はこれを聞きまして、「なんの、一人一人に当てるから、印になるのだ」と焼きごてを真っ赤に焼きたてまして、姉の額に、十文字に当てました。厨子王丸はその瞬間、いつもはあんなにしっかりした子ではありましたが、姉に当てられた焼きごてを目の前に見て、ちりりちりりと逃げました。三郎はそれを見て、「へっ、口ほどにもない臆病者だ。逃げようとしても逃がさない」と、髪の毛をつかんで引き戻し、膝の下に抱え込みました。
いたわしいことでございます、姉は焦(こ)げた額を手で押さえながら、
「ああどうかどうか、どうか三郎どの。神仏の罰があたります。今お助けくださったら、後生のご利益もございます。弟に逃げろとそそのかしたのはこの姉です。しかし弟は太夫どののためにはよいことを申しておりました。男の顔の傷は買ってでも持てとは言いますが、それも傷によります。これは恥辱の傷でございます。二つでも三つでも、わたしにお当てください。そして弟は許してください」
三郎はこれを聞いて言いました。
「なんの、一人一人に当てるから、印になるのだ」
そして弟の額に、じりりじっと焼きごてを当てました。太夫はこれを見て、「よけいなことを言うから痛い目に遭うのだ」と笑い声をあげて言いました。
「ああいう口のたっしゃなやつらは、命が果てることになったとしても、正直には吐かないものだ。浜に連れていけ。八十五人がかりで持ち上げられるような、松の木の湯船のその下で年越しをさせろ。食事もやるな。ただ干し殺せ、飢え死にさせろ」と申しました。三郎は「承知しました」と言い、きょうだいを浜辺へ連れて行き、松の木の湯船のその下で年越しになりました。
きょうだいが二人で語り合ったその悲しみも苦しみも道理でありました。いたわしいことでございます、姉は厨子王どのにすがりつき、「ねえ、厨子王丸。あたしたちの国の習わしでは、六月の晦日に夏越(なごし)の祓(はら)いの輪に入るそうよ。これは丹後の習わしかしら。食事ももらえず、このまま干し殺されるの。なんて悲しい」と、姉は弟にすがりつき、弟は姉に抱きついて、涙を流し、焦がれるように身をよじり、嘆き悲しんだのでありました。
太夫どのの五人いる息子たちの中でも、二番目の二郎どの、これは慈悲の心にあつい人で、自分の食べ物を少しずつ取り分けて、そっとたもとに入れまして、父、母、兄弟の目をぬすんで、毎晩、浜へ降りてきては、松の木の湯船の底をくり抜いて、だまって二人に差し入れてくれました。この恩はいつかきっと返したいと、二人は心に思ったのでありました。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。