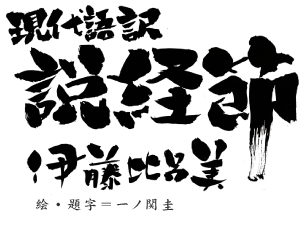第18回 山椒太夫 その4 厨子王丸を逃がして、姉は三郎に責め殺される
昨日今日のことと思っておりましたら、もう正月の十六日になりました。太夫は三郎を呼びつけまして、
「おい、三郎よ。人の命というのは、もろいようでけっこう強いもんだ。浜に追いやったきょうだいの命がまだあるかどうか、見て来い」と言いつけました。
「承知しました」と三郎はさっそく浜へ降りていきまして、松の木の湯船のところに行きまして、その湯船を取りのけてみましたら、あらあらいたわしいことでございます。きょうだいは、生きてはいましたが、すっかり土気(つちけ)色になっておりました。三郎が二人を太夫どのの元へ引っ立てていきますと、太夫は言いました。
「命拾いしたのだな。どの神仏のおかげやら。もうよい、さあ山へ行け。浜へも行け」
姉は、これを聞いて必死で頼みました。
「そのとおりにいたします。でも、どうか、山か浜か、どちらかにいっしょに行かせてください」
太夫はそれを聞いて言いました。
「ふむ、人がおおぜいいれば、一人くらいはもの笑いになるやつがいなくちゃいけないと思っていたのだ。おい、三郎よ、姉が山へ行きたいと言っている。ざんばら髪にして行かせてやれ」
「承知しました」と三郎は答え、あらあらいたわしくてなりません。姉の背丈ほどもある黒髪を、手にくるくると巻きとりまして、結いぎわからばっさりと切り落とし、ざんばら髪に仕立てて、山へ行かせたのでありました。きょうだいの嘆きよう、それは哀れでありました。
あらあらいたわしいことでございます。厨子王どのは姉を先に立て、その後ろ姿をつくづくと眺めながら歩いていきました。
「ねえ、姉さま、人の姿は三十二相と言うでしょう。でも、姉さまの姿はそんなものじゃない、四十二相だ、とても美しい。その四十二相の中でも、その長い髪がなにより大事なものだった。今はその髪がなくなってしまった。おれがこうして後ろから見ても、今までみたいな頼れる力がなくなったのがわかる。おれが感じるくらいだから、姉さまはどんなに頼りなく感じているだろう。悲しいな」
姉はこれを聞いて言いました。
「世が世であれば、髪だって役に立つけど、こういう身の上になっちゃったんだから、髪も何もいらないの。あんたといっしょに山へ行けるっていうだけでうれしいのよ」
二人はけもの道のような小道をのぼっていきました。やがて、雪のまだらに消えかかる岩の洞(ほら)の前で立ち止まり、姉は肌身はなさず持っているお守りの地蔵菩薩を取り出して、岩鼻にそっと掛けました。
「母さまは、あたしたちの身の上に何か大事のあるときは、身代わりにもなってくださる地蔵菩薩さまだとおっしゃったけど、こうなってしまったら、神や仏の力も尽き果てて、だれにも守ってもらえないのね、悲しいわ」
厨子王どのはこれを聞いて、姉の顔を見て、言いました。
「姉さま、姉さま、姉さまの顔に、焼きごての痕がない」
姉はそれを聞いて、弟の顔を見て、
「ほんとだ、あんたの顔にも、焼きごての痕がない」
地蔵菩薩の白毫(びゃくごう)のあたりを見ると、そこに、きょうだいの焼きごてを受け取られたしるしがくっきりと刻まれてありました。身代わりにお立ちになったのでありました。
「焼きごてをお取りになってしまわれたら、邪慳な太夫や三郎が、また当てるにちがいありません。痛くも熱くもないように、どうか元どおりに戻してくださいませ」
そう姉は祈りましたけど、何しろ一度身代わりになってくださったものはもう元に戻りません。
「もしかしたら、これでいいのよ。この折をのがさずに逃げろということなのかもしれない。厨子王丸、逃げなさい。逃げて、世に出て、あとであたしを迎えに来て」
厨子王どのはそれを聞いて言いました。
「一度で懲りない者は二度目は死ぬことになると、姉さまは言ってたじゃないか。逃げたいなら、姉さまが逃げなよ。おれは逃げないよ」
姉はそれを聞いて言いました。
「あの焼きごては、あたしの言ったことのために当てられたと思ってるの。あたしがお逃げと言ったときに、あんたがちゃんと言うことを聞いてたら、こんな焼きごてなんか当てられなかったのよ。あんたがそういう了簡なら、今日からはもう、太夫のところに姉がいるなんて思わないで。あたしも弟がいることは忘れるから」
そして鎌を鎌にちょうちょうと打ち合わせ、それがさむらいの子としての決意でありました、姉はひとりで谷底へ降りていきました。
厨子王どのはあわてて言いました。
「まったく、なんて怒りっぽい姉さまだ。怒らないで。逃げろというなら逃げるから、戻ってきて」
姉はそれを聞いて言いました、
「逃げるというのね、そんならいいわ。そのつもりなら、別れの杯をちゃんと交わしましょう」
でもここに、酒もさかな肴(さかな)も、あるわけがありません。そこで谷の清水を酒ということにして、柏の葉を杯にして、まず一つ姉が飲み、それから弟に杯を差して言いました。
「今日は、お守りの地蔵菩薩もあんたにあげる。逃げるときにも、短気はだめよ。短気はかえって未練になるから。
逃げていったところに里があったら、まずお寺を探して、そこにお行き。そしてお坊さまに頼りなさい。お坊さまならきっと助けてくださる。
さあ、もう行きなさい、早く行きなさいってば。あんたを見てるとあたしの心が乱れるわ。
ねえ、よく聞くのよ、厨子王丸。こんなふうに薄雪が降ってるときは足の草鞋(わらじ)を、後と先とを逆にして、しっかり履くの。右についてる杖を左でつくと、上りの場合でも下りに見える。下りの場合は上りに見える。さあ、行って、早く行って」
それじゃ姉さま、それじゃ厨子王丸と、くり返しくり返す暇(いとま)乞い、ほんのかりそめの別れと思っていましたが、そのまま、永(なが)の別れとなりました。
いたわしいことでございます。姉は「何もかも流れていく、あしたからはだれを弟と思って話をしよう」と、そこでしばらく泣いておりましたけど、やがて、こぼれる涙を押しぬぐって立ち上がり、人の刈り落とした木の枝をたんねんに拾い集め、小さな柴に束ねて、頭の上に乗せまして、太夫のもとへ戻りました。
正月十六日のことでありました。太夫は表の櫓(やぐら)に上がり、遠くを見張っておりましたが、帰ってきた姉の柴を見て言いました。
「おまえは弟よりもいい柴を刈ってきた。どれ、弟は」
姉はこれを聞きまして、涙を流しながら言いました。
「それがわかりません。今朝わたしが、浜へではなく、山へ行くと言いましたら、弟は、髪を切られた愚かな姉といっしょに行くのはいやだと言って、里の山人たちと連れ立って行ってしまいました。もしかしたら道に迷って、まだ戻らないのかもしれません。行って探してまいります」
太夫はこれを聞いて言いました。
「そうさな、涙にもいろんな涙があるものだ。表面だけの面涙(めんるい)、怨みだらけの怨涙(おんるい)、心が動いた感涙(かんるい)に、愁いのこもる愁涙(しゅうるい)。おまえの涙のこぼし方は、弟を山からそのまま逃がしたという、表面だけの喜び泣きに見えるのだがな。おい、三郎、どこにいる。この女を責め上げて問いただせ」
邪慳な三郎は「承知しました」と言いまして、姉を梯子(はしご)にくくりつけ、湯責め水責めに責め上げて問いただしました。それでも姉は言いません。それで今度は三つ目錐(ぎり)を取り出して、姉の膝の皿骨に、からりからりと揉み入れて問いただしました。もう弟を逃がしたと言ってしまおうか、いやだめだ、言ってはいけない、言うものかと姉はもだえておりましたが、とうとう口を開いて、こう言いました。
「どうか、少しものを言わせてください」
それで太夫は言いました。
「ものを言わせるために、こうして責めているのだ。言うというなら言わせてやる」
すると姉は言いました。
「今に弟が山から戻りましたら伝えてください、姉は弟のせいで責め殺されたのだと。そして弟をどうかよろしく、目をかけて使ってやってくださいね」
太夫はこれを聞き、かんかんに怒って言いました。
「聞いたことには答えぬくせに、聞いてもないことをぺらぺらと語る女だ、ものも言えなくなるほど責め上げてやれ、三郎」
邪慳な三郎は、天井から炭を取り出して土間に移し、うちわを振ってあおぎたてました。いたわしいことでございます。姉の髪の結び目をにぎって引きずりまわし、「熱いなら話せ、話せ、話せ」と責め立てました。責め手は強く、身は弱く、耐えられるものではありません。正月十六日のまっぴるま、朝四つ時の終わり頃、十六歳の一生でありました。姉をそこに責め殺したのでありました。
(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。