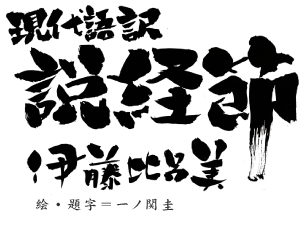第20回 山椒太夫 その6 京へたどり着いた厨子王丸はみかどに名乗り出る
下
太夫はこれを聞いて言いました。
「よくやった、お聖(ひじり)よ。明日からおまえの寺の檀家になってやる。寄進してやるぞ」
三郎はそれを聞きまして
「父上、お待ちください。あやしいところがございます。あそこに吊ってあるあの皮籠(かわご)、皮籠は古いのに、掛けた縄は新しい。風も吹かぬのに、一揺るぎ二揺るぎ、ゆっすゆっすと動いたが、これがどうもあやしくてなりません。調べずに帰りましたら、一年ずっと、不審の思いが心の中に炎のようにくすぶりつづけておりましょう。父上、お戻りください」
兄の太郎はこれを聞きまして、
「何を言うか、三郎よ。父は老いぼれても、おまえまで老いぼれるな。こういう古寺には、古経(ふるきょう)やら、古仏(ふるぼとけ)やら、破れ反古(ほご)やら、要らなくなったものをああして吊ってあるものよ。昨日吊ることもあろうし、今日吊ることもあるだろう。外には風が吹かなくても、家鳴(やな)りがする。その上に木霊(こだま)が響いて、家の中が風に揺れるのだ。たとえあの皮籠の中のものがわっぱであっても、今、このお聖の誓文を聴いたからには、もういいじゃないか。あのわっぱがいなけりゃ、他にだれも使う者がいないとでも言うのかよ。なあ、今回は、おれに免じてまず戻れ」
三郎はこれを聞きまして、
「兄者(あにじゃ)の意見は、聞くこともあるが、聞かないこともある。何を情け心を起こしているものやら。兄者、そこをどいてくれ」と言いざま、刀の鞘をはずして、吊った縄を切り、降ろす間にも縄の結び目をひっぱって、おお、わっぱがいるぞと喜んで、下へ降ろす間ももどかしく、縦縄横縄をむんずと切って、皮籠のふたを開けてみれば、身につけていたお守りの地蔵菩薩から、金色(こんじき)の光がぱあっと放たれ、三郎の両眼がくらんで、縁(えん)から下へころげ落ちたのでありました。
太郎はこれを見て言いました。
「ほら言ったじゃないか、今、命を取られなかったのは仏のご慈悲だよ、元のように吊っておけ」
そして皮籠に縦縄横縄をむんずと掛けて、元のように吊っておき、三郎は兄弟の肩にかつがれて、由良の港へ戻ったのでありました。面目のないことでございました。
いたわしいことでございます。お聖は、今にも皮籠が降ろされようとしているのを見ておりました。皮籠が降ろされれば、わっぱは連れていかれる、わっぱを連れていくなら、やつらはこの聖にも縄を掛けるだろうと覚悟していましたが、皮籠の中は、ありがたい、神の方便、仏の神通(じんつう)。
お聖は皮籠の下に行って聞きました。
「わっぱはいるか」
厨子王どのは弱々しい声で答えました。
「はい、ここにおります。太夫の一行は行きましたか」
お聖はこれを聞きまして「安心おし」と皮籠を降ろし、ふたを開けてみれば、ああ、ありがたいことでございます。地蔵菩薩が金色の光を放って、そこにおいでになりました。厨子王どのは皮籠の中から飛び出して、お聖にすがりついて言いました。
「ああ、聞いてください、お聖さま。名乗るまいとは思いましたが、今は名乗らずにはいられません。わたしをだれとお思いか。奥州五十四郡の主、岩城の判官政氏(まさうじ)の総領(そうりょう)、厨子王丸でございます。思いがけない訴えがありまして、都に上って、みかどからお許しのご判を受けようとしておりました。途中で、越後の国の直井の浦から売られました。それから、あちらこちらへ売られました。とうとうあの太夫に買い取られ、刈ることなんて習いもしなかったのに柴を刈り、汲むことなんて習いもしなかったのに潮を汲み、苦労をたんといたしました。わたしは逃げ出してきましたが、まだ太夫の家に姉が残っております。もし都への道をご存じならば、教えてください。お聖さま、わたしは都へ逃げていきたいのです」
お聖はこれを聞いて言いました。
「何も知らないのだな、厨子王は。今ごろは太夫が家人をおおぜい、五里も三里も先へ、追っ手に差し向けているだろうよ。そんなに逃げたいのなら、いっそのこと、わしが送りとどけるとしよう」
厨子王どのを元の皮籠へどうと入れ、縦縄横縄むんずと掛けて、お聖の背中にどうと背負って、上には古い衣をひき着せて、
「町屋や関所のそこここで、聖の背中に背負ったものはなんだと人々が聞いてきたら、これは丹後の国、国分寺の金焼(かなやき)地蔵だが、あんまり古びたので、都へ上って仏師に彩色してもらうのだと言えば、とがめる者もあるまいよ」と丹後の国を立ち出でました。
菟原(うばら)、細見(ほそみ)はここですか。鎌谷(かまだに)、井尻をうち過ぎて、船井、桑田はここですか。口郡(くちごおり)にも聞こえたる花に浮き木の亀山や、年は寄らねど老の坂、沓掛峠をうち過ぎて、桂の川をうち渡り、川勝寺(せんしょうじ)、八町畷(なわて)をうち過ぎて、先を急いで行きましたので、ほどもなく、都の西に名の聞こえた、西の七条朱雀(すざく)の権現堂(ごんげんどう)に着きました。
権現堂に着きまして、皮籠を降ろし、ふたを開けて見てみましたら、皮籠の中が狭かったか、凍傷にでもかかったか、厨子王どのの腰が立たなくなっておりました。
お聖はこれを見て言いました。
「わしが都に上って、おゆるしのご判を申し受けてやりたいが、出家の身ではできないことだ。ここで別れよう」
ああ、いたわしいことでございます。厨子王どのは言いました。
「命の親のお聖さまは、丹後の国にお戻りになるのですね。わたしはうらやましゅうございます。つらい思い出があるのも丹後の国。姉がおりますから、恋しいのも丹後の国。命の親のお聖さまに、わたしのことを思い出す何かをさしあげたい。地蔵菩薩がいいでしょうか。守り刀がいいでしょうか」
お聖はこれを聞いて言いました。
「なんだね、おまえさまは、この聖が命を助けたと思っているのかね。肌身離さず持っている地蔵菩薩さまがお助けくださったのだよ。よく信じて掛けておくのだよ。さむらいという者は、守り刀を七歳の頃から差すそうじゃないか。出家には、刃物なんてかみそりの他にはいらないのだ。ほんとに何かくれるつもりなら、おまえさまの鬢(びん)の髪をおくれ。わしからは、衣の片袖をあげよう」
そして、厨子王どのが鬢の髪を一房切り取り、お聖も衣の片袖を切り取りまして、交わしあいますと、お聖は、涙ぐみながら丹後の国に戻っていったのでありました。
ああ、いたわしいことでございます。朱雀の権現堂では、朱雀七村の乞食の子らが集まって、厨子王どのを養ってやろうとしましたが、一日二日は食べ物をめぐんでもらえても、その後はだれもめぐんでくれなくなりました。そんなら土車を作って、そこに乗せて、都のにぎやかなところへ引いていけばどうかと考えて、にぎやかなところへ引いていきました。都は広いとはいえ、五日十日は食べ物をめぐんでもらえても、その後はだれもめぐんでくれなくなりました。それなら、ここより四天王寺の方がいいだろうと、宿から宿へ送り、村から村へ送り、四天王寺へ引いていきました。
ああ、いたわしいことでございます。厨子王どのが、四天王寺の石の鳥居にとりすがり、「えいやっ」と声をかけて立ちましたら、四天王寺を建立なさった聖徳太子のおはからいか、あるいは厨子王どののご果報か、腰がすっくと立ったのでありました。
折も折、四天王寺で聖徳太子さまをお守りする阿闍梨大師(あじゃりだいし)のお通りでありました。阿闍梨大師は、厨子王どのを見て聞きました。
「この若侍は、遁世(とんせい)を望むか、奉公を望むか」
厨子王どのはそれを聞いて答えました。
「奉公が望みでございます」
阿闍梨大師はそれを聞いて言いました。
「わたしのところには、百人の稚児、若衆が住んでおるのだが、おまえも、古袴(ふるばかま)をはいて、お茶の給仕でもするかね」
「はい、いたします」と厨子王どのは言いまして、阿闍梨大師のお供に加わり、稚児たちの古袴を身につけて、茶坊主として働くことになりました。厨子王どの、東国の生まれ育ちで訛(なま)りがありました。そこで、あちらで「声訛りの茶坊主よ」、こちらでも「声訛りの茶坊主よ」と、人々に可愛がられたのでありました。
これは厨子王どのの物語でございます。それはそれといたしまして、花の都におられる三十六人の大臣たちの中に梅津の院という方がおられました。この方は、男にしても女にしても、末の跡取りがなかったので、清水の観音へお参りして申し子をしていましたが、あるとき清水の観音さまが内陣から揺るぎ出でておいでになりまして、枕上にお立ちになりました。「梅津の院の養子の件なら、四天王寺へ参れ」との仰せでありました。
ああ、ありがたいおことばだと、梅津の院は屋敷に帰り、かぎりないお喜びでありました。そして三日後に、四天王寺参りをすることにいたしました。阿闍梨大師はそれを聞き、「都の梅津の院がお参りに来られるそうだ。座敷を飾ってお迎えせよ」と、天井を綾錦金襴(あやにしききんらん)で飾りつけました。柱を豹や虎の皮で包ませました。高麗縁(こうらいべり)の畳を千畳ばかり敷かせました。座敷のご本尊は、その頃、都で流行りの牧谿(もっけい)の、墨絵の観音像、釈迦像、達磨(だるま)像を、三幅一対(さんぷくいっつい)に掛けさせました。花瓶の花は、右の枝で天をさし、左の枝で地をさすという、天上天下唯我独尊の様式に立てさせました。そして、百人の稚児、若衆をも花のように飾り立て、梅津の院のおいでを今か今かと待っておりました。
早くも三日が経ちまして、梅津の院は四天王寺へお参りに来られました。「おお、これはすばらしい花の景色だ」と言いながら座敷に入り、百人の稚児、若衆を上から下へ三遍くり返してじっくりと眺めましたが、養子にするべき稚児はみつかりません。でもさらに見ていきますと、はるか末席におりました厨子王どのの額に、米(よね)という字が三行(くだ)り坐り、両眼には瞳が二体あるのを、梅津の院はたしかに認めて、「あのお茶の給仕をわたくしの養子に迎えよう」と言いました。
百人の稚児、若衆はこれを見て、「なんとまあ、都の梅津の院は目の利かない方なのだな。昨日や今日、土車に乗って乞食をしていた卑しい茶坊主を養子にするなどと」と一斉に笑いました。
梅津の院はこれを聞いて、「わが家の養子をお笑いになるか」と、厨子王どのを湯殿に連れて行かせ、風呂に入れさせ、身を清めさせ、肌には青地の錦を着せ、絞り染めの直垂(ひたたれ)に、刈安(かりやす)色の水干(すいかん)を着せて、玉の冠を被せ、一段高い、梅津の院の左の座敷に坐らせましたところ、百人の稚児だれ一人として、それより美しい稚児はいなかったのでありました。
梅津の院は、自分の屋敷に厨子王どのを連れ帰り、遠くの珍味に近くで穫れたての産物を山と積みあげ、宴をひらいて祝いまして、かぎりないお喜びでありました。そして、ご自分の代理として、みかどの護衛の大役に、厨子王どのを送り出しました。三十六人の大臣たちはこれを見て、「梅津の院の養子だろうとかまわぬ。卑しい者がわれらと同じ座に着くのを許すわけにはいかない」と言いまして、その座敷から追い払おうとしました。
ああ、いたわしいことでございます。厨子王どのは、今は名乗り出ようか、今名乗り出れば、父岩城どのの面目にかかわる、また名乗り出なければ、養親(やしないおや)の面目にかかわる、父の面目はまたいずれ考えよう、まず養親の面目をたてねばと思いまして、肌身離さず持っていた信太玉造(しだたまつくり)の系図の巻物を取り出して、扇の上にのせ、上座へ持って行きました。自分の身は白州(しらす)へ飛んで降り、玉の冠を地にひたとつけて、みかどに向かって、平伏したのでありました。すると二条の大納言が、この巻物を取り上げて、高らかに読みあげました。
「そもそも奥州の国、日の本の将軍、岩城の判官正氏の惣領、厨子王判」
みかどはごらんになりまして、
「今まではどこの者かと思っていたが、岩城の判官正氏の惣領厨子王か。
長々の浪人、苦労であった。奥州五十四郡は元の領地として返してやるぞ。日向(ひゅうが)の国は馬の飼料代につけてやる」
と、みかどのしるしの薄墨の御綸旨(ごりんじ)を下されたのでありました。厨子王どのはこれを聞いて、みかどに向かって申しあげました。
「今申し上げてよいものか、申し上げるのはよすべきか、申し上げずにおこうとは思いましたが、今申しあげずにおりましたら、いつの世に申しあげられるかわかりませんので、ここに申し上げることにいたします。奥州五十四郡も、日向の国も、望みではございません。これには事情がございます。どうか丹後五郡に相換えてくださりますよう」
みかどはこれをお聞きになり、
「なに、大国に小国を換えてくれというか。それなりの事情があるのだろう」とおっしゃいまして、「丹後の国も馬の飼料につけてやる」と重ねてご判を下さったのでありました。
三十六人の大臣はこれを見て、「今まではどこの者かと思っていたが、厨子王どのでありましたか。それならわれらは同じ座にはおられまい」と座敷を下がっていきました。厨子王どのは梅津の院の屋敷に帰り、かぎりないお喜びでありました。(続く)

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。