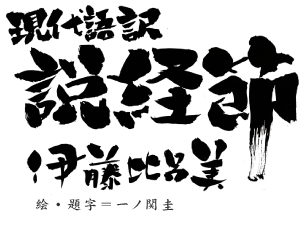第21回 山椒太夫 その7 金焼地蔵のお力によるふしぎなお話でございます
ああ、いたわしいこと、厨子王どのの嘆くようすが哀れでなりませんでした。
「おれは、今、鳥になりたい、羽が欲しい、丹後の国へ飛んで行き、潮を汲む姉さまの衣のたもとにすがりついて、世に出たこと、出るまでのことを、すっかり語りたい。
蝦夷の島へも飛んで行き、そして母上さまを尋ねあて、世に出たことを語りたい。筑紫(つくし)安楽寺へも飛んで行き、父の岩城どのを尋ねあて、世に出たことを語りたい」
いつまで待つようなことでもなし、みかどへこの事情を申し上げ、おゆるしのご判を申し受け、筑紫安楽寺へも迎えの輿(こし)を差し向けました。さてその後に、まず丹後の国へお国入りということのお触れが出回りました。三日後の宿は、丹後の国、国分寺ということになりまして、寺の門のまん前に、宿泊予定の宿札(やどふだ)を打たせたのでありました。
お聖(ひじり)はこれを見て、考えました。
「丹後は、ほんのちっぽけな国ではあるが、広い堂だの寺だのは他にもある。こんな古ぼけた寺に、わざわざ都から来る国司が泊まるという。これはきっとこの身があぶない。なに、出家と書いて、家を出ると読むんだわい」
そして、傘を一本かついで、どこともなく逃げていきました。
はや三日がたちました。厨子王どのの一行は、丹後の国分寺に着きました。厨子王どのは里人を呼びまして、「尋ねるが、この寺に堂守(どうもり)どのはおられないのか」と問いますと、里人は答えて言いました。
「おられますとも。この間まで、尊い僧が一人おられました。国司の宿札をお打ちになったのはわが身の危険と思われたようで、どこへともなく逃げていかれました」
「探してこい」との言いつけに、「承知いたしました」と家来の者たちが、丹波の穴太(あなお)より探し出し、高手小手(たかてこて)に縛り上げて、国分寺へと引いてきたのでありました。
厨子王どのはこれを見て言いました。
「命の親のお聖になぜ縄を掛ける。放してさしあげろ」
お聖はこれを聞いて言いました。
「今まで都の国司の命を助けたことはないぞ。そんなふうに出家を嬲(なぶ)るものではない。さあ、さあ、早く命を取りなされ」
厨子王どのはこれを聞いて言いました。
「なるほど道理でございます。わたしをだれとお思いか。皮籠(かわご)の中のわっぱでございます。都の七条朱雀(すざく)まで送ってくださったそのときに、交わした品もございます。これがお聖さまのくださった衣の片袖、お聖さまのお持ちなのは、わたしの鬢(びん)の髪」
お聖はこれを聞いて言いました。
「まだ百日もたたぬ間に世に出られたか、なんとめでたい。さむらいと黄金は朽ちて朽ちせぬと言うけれど、こういうことなのだなあ」とかぎりないお喜びでありました。
厨子王どのは言いました。
「由良の港に残していった姉さまは、この世におられますか」
お聖はこれを聞いて言いました。
「そのことだが......。姉上さまは弟を逃がした咎(とが)を負って、邪慳な三郎に責め殺されてしまわれたのだよ。捨てられた遺骸を引き取って、この僧が火葬にいたした。その死骨と遺髪が、ここに」
そして涙ぐみながら、取り出した骨と髪を、厨子王どのに手渡しました。
「これは夢か、それとも現(うつつ)か。姉さま、こんなことになるなら、おれが世に出た甲斐もない」
厨子王どのは骨と髪とを顔に当て、声をあげ涙を流してむせび泣いたのでありました。
いつまでもこうしてはいられない、山椒太夫を召し寄せて重罪に処してやろうと、由良の港へお使いが立ちました。太夫はこれを聞き、五人の息子を呼んで言いました。
「よく聞けや、息子たち。わしはこの国に長く住んでおるから、国司閣下からは、きっと名所旧跡についてお尋ねがあるんだろう。そしたら、わしが前に出て、一つ一つの名所旧跡について詳しくお話し申そう。そしたらきっと所知(しょち)をいただける。
おい、三郎。所知をいただくときにはな、小国を望むなよ。『太夫は子も孫もたくさんおります、末広がりの者でございますから、大国をくださりませ』と言うのだよ。けっして、けっして、忘れるな」
そして、五人の息子に手を引かれて国分寺へやって来ました。厨子王どのはそれを見て聞きました。
「太夫には、早々と、ようこそお越しになられた。このわたしを見知っておられるか」
「存じております。都の国司とあがめております」
厨子王どのは言いました。
「そなたのところには、よい下女がいると聞いた。その女をわたしの妻にして、そなたはわたしの主筋(しゅうすじ)となって、富貴の家として栄えるのはどうだね」
太夫は三郎の方をにらみつけて、
「伊達(だて)の郡(こおり)、信夫(しのぶ)の荘(しょう)の者とかで、姉にしのぶ、弟に忘れ草というきょうだいがいたが、姉のしのぶは見目も形もよい女だった。こんなことなら、殺さないでおけば、都の国司の妻にして、わしは国司の主筋となって、富貴の家と栄えたものを」と悔やんだのでありました。
厨子王どのはこれを聞き、隠そうとした心をもはや隠せなくなりました。太夫の前に顔をぐいと差し出して言いました。
「やい、おまえたち、姉のしのぶを何の罪咎(つみとが)があって責め殺した? おれをだれと思うか、おまえのところにいた忘れ草とはおれのことだ。姉さまを返せ。太夫よ、三郎よ。死んだ姉を返せと言うのは、無理なことであるか。あのとき、おれが三荷(さんか)の柴を刈れなくて、山人(やまうど)たちが憐れみで刈ってくれた柴を、よく刈れたのが罪だといって、三荷の柴に七荷増やして、十荷刈れと責めたのは、これは無理なことではないのか」
そして調子を変えてこうつづけました。
「いやいや、おれは何をつまらないことを言っておるのだろう。仇を仇で返すのは、燃える火に薪を入れるようなものだ。仇を慈悲で返すのが、み仏のわざだと聞く。どうだ、太夫。大国がほしいか。小国がほしいか。望み次第に取らせるぞ。太夫、望みを言え」
太夫はにっこり笑って、三郎の方をちらと見ますと、三郎が答えて言いました。
「ありがとうございます。太夫は、子や孫も大人数、末広がりの者でございます。小国ではとうてい足りませぬ。どうぞ大国を取らせてくださいませ」
厨子王どのはこれを聞いて言いました。
「抜け目のない答えであった、三郎よ。太夫が小国をほしがっても、おれは無理にでも大国を取らせようと思っていたのだ。それ、太夫には、望みどおりに、広い黄泉(よみ)の国を取らせよ」
「承知いたしました」と家来たちは、太夫を引っ立てて、国分寺の広庭に、五尺の深さに穴を掘り、肩から下を堀り埋めました。そして竹鋸(たけのこぎり)をこしらえました。
「他人に引かせてはいけない。息子に引かせて、つらい目に遭わせるのだ」と厨子王どのが言いますと、「承知いたしました」と家来はうなずいて、まず兄の太郎に、鋸が渡りました。するとそのとき、厨子王どのが言いました。
「太郎には思うところがある。鋸許せ」
次に二郎に鋸が渡りました。二郎は鋸を受け取って、後の方へいきまして、そこでひとり嘆くようすが哀れでなりませんでした。
「昔から今に至るまで、子どもが親の首を引くなんていうことは、聞いたこともない。おれの言うことは間違ってなかった。『大波を超えて遠くから来たような者でも情けをかけて使え』とつねづね言っていたのはこういうことなのだ。それができなかったおれたち一家だ、引かせられるのも当然だ」と言いつつも、涙にむせて引くことができませんでした。するとそのとき、厨子王どのが言いました。
「実は、二郎にも、思うところがある。鋸許せ」
三郎に鋸が渡りました。邪慳な三郎は鋸を奪い取って、
「卑怯ではないか、兄者、国司どの。自分の咎はさておいておれたちの咎だというのか。父上、もういいでしょう。これまで唱えてきた念仏はいつ役に立てるんですか。今ここで用にお立てなさい。死出(しで)三途の大河を、この三郎が負ぶって渡してさしあげます。一引き、引いては、千僧供養。二引き、引いては、万僧供養。えい、さら、えい」と引くうちに、百六回目で、首は前に引き落ちました。
それから、厨子王どのの家来たちは三郎を浜に連れて行きまして、通りかかる山人たちに、七日七夜の間、首を引かせたのでありました。
厨子王どのは、二郎と太郎を呼んで言いました。
「昔から『苦い蔓(つる)には苦い実が成る、甘い蔓には甘い実が成る』という。おまえたち兄弟は、苦い蔓に甘い実が成ったようだ。兄の太郎に鋸を許したのは、ほかでもない、『あのわっぱがいなければ、他にだれも使う者がいないとでも言うのか。おれに免じてまず戻れ』と言ったそのことば一言によって、鋸を許す。また、二郎に鋸を許すのは、ほかでもない。松の木の湯船のその下でみじめに年越しをさせられたあのときに、夜ごとに浜へ降りてきて食べ物を差し入れてくれた。二郎どのへの恩は、湯の底水の底までも、返しがたく感じている。丹後八百八町、四百四町を分けて、兄の太郎にやろう」
太郎は髪を剃り落とし、国分寺に住みついて、姉上の菩提(ぼだい)を弔い、また太夫の菩提も弔うことになりました。
「そして残り四百四町は、二郎どのを、一色(いっしき)に統括する総政所(そうまんどころ)に任じて任せよう」
そこで昔から、丹後の国の地頭を一色どのと呼ぶのであります。
それから、お聖さまを命の親と定め、同じ家で使われていた伊勢の小萩を姉と定め、網代(あじろ)の輿に乗せて、都へ呼びよせました。それから、厨子王どのは蝦夷の島へ渡っていきまして、母上の行方を尋ねたのでございます。
いたわしいことに母上は、明ければ「厨子王恋しやな」、暮れれば「安寿の姫が恋しや」と泣き暮らし、とうとう両眼を泣きつぶしていたのでございます。広い千丈の粟畑へ出ては、鳥を追う日々でありました。鳥威(とりおど)しの鳴子(なるこ)の手縄に取りついて、「厨子王恋しや、ほうやれ。安寿の姫恋しやな。うわたき恋しや。ほうやれ」と言っては、どうと身を投げるのでありました。
厨子王どのはこれを見て言いました。
「なんとふしぎな鳥の追い方をする人だ。もう一度追ってごらんなさい。領地を与えてあげますよ」
母上はこれを聞いて言いました。
「領地なんか何になります。わたしの仕事はこれでございます。また追えとおっしゃるなら追いますよ」
そして鳴子の手縄に取りついて、「厨子王恋しや、ほうやれ。うわたき恋しや、ほうやれ。安寿の姫が恋しや」と言って、どうと身を投げました。
厨子王どのはこれを見て、母にまちがいないと、思わず抱きついて言いました。
「母さま。厨子王丸でございます。世に出て、ここまでやってまいりました」
母は払いのけて言いました。
「たしかにわたしは、姉に安寿の姫、弟に厨子王丸という、二人の子を持っておりましたが、遠くへ売られていって行方もわからなくなったと聞きました。眼の見えぬ者をおからかいになってはいけません。盲人の打つ杖には咎もないと申しますよ」
厨子王どのはこれを聞き、
「たしかにそうだ、でも思い出した、これがあった」と身につけていたお守りの地蔵菩薩を取り出して、母上の両眼に当てて唱えました。
「善哉(ぜんざい)なれや、明らかに。平癒(へいゆう)したまえ、明らかに」
三度撫でますと、つぶれて久しい両眼がはっしと開いて、鈴を張ったようにぱっちりとした眼になりました。母は見て言いました。
「あなたは厨子王丸か。安寿の姫は」
厨子王どのはこれを聞いて言いました。
「聞いてください、母さま。直井の浦から別れ別れに売られていったわたしたちです。あちらこちらと売られた後に、丹後の国の由良の港の山椒太夫に買い取られ、汲むことなんて習いもしなかったのに潮を汲み、刈ることなんて習いもしなかったのに柴を刈り、苦労をたんといたしました。わたしがそこを逃げ出した後、姉さまは責め殺されました。母さま、わたしは世に出て、姉さまの敵(かたき)を取り、そして、ここまで尋ねてきたのです」
母はこれを聞いて言いました。
「あなたは世に出たのね、なんてめでたいこと。でも安寿は死んだのね。わたしは若木を先に立てて残ってしまった老蔓(おいづる)なのね。悲しくてたまりません。ああ、しかたのないことなんでしょう」
そして玉の輿に乗って、国へ帰ることになりました。
さてその後、厨子王どのは、越後の国、直井の浦へ行きまして、最初に売った山岡太夫を、簀巻(すま)きにして海に沈める刑に処しました。助けようとしてくれた女房の行方を尋ねましたが、死んだということでした。しかたがないこととあきらめて、柏崎に渡り、なかの道場という寺を建てて、女房のうわたきの菩提を弔わせたのでありました。
そしてそれから厨子王どのは、母上のお供をしながら、都に上っていきました。梅津の屋敷に帰りつきますと、梅津の院も出て来て、母上に対面し、まことにまことに、すべてうまくいった、めでたい、とてもめでたいと、かぎりないお喜びでありました。
話は変わりまして、岩城どのでございます。
厨子王どのが世に出たことで、みかどのおとがめも許されて、岩城どのも都に上っていきました。お屋敷にやって来ますと、奥方さまも、厨子王どのも出てきまして、思わず抱きつき、これはこれはと言うばかりでありました。嬉しいときも、悲しいときも、先立つものは涙でございます、安寿の姫がもしこの世に生きていたならばどうかしらと、さめざめと泣いたのでありました。
梅津の院も、お聖も、伊勢の小萩も、言いました。
「お嘆きはよくわかります。でも、どんなに嘆いても、しかたのないこともございます。おあきらめなさいませ」
そして蓬萊山のように飾り立てた宴席をしつらえて、喜びの酒盛りは夜昼三日つづいたそうでございます。
杯も納まったころ、厨子王どのは、姉上の菩提のためにと、肌の守りの地蔵菩薩を丹後の国に安置して一宇(いちう)のお堂を建立しました。それが、今の世に至るまで、金焼地蔵菩薩と呼ばれて、人々に崇め奉られておられます。
それから厨子王どのはお国入りを果たしたのでございます。父上母上を網代の輿に乗せ、命の親のお聖も、伊勢の小萩も、それぞれに輿や牛車に乗せまして、自分は馬にまたがって、十万余騎を引き連れて、奥州を指して下っていきました。その地に着きますと、昔お屋敷のあったその跡に、多くの屋敷を建てまして、昔の郎等(ろうとう)どもが我も我もとふたたび仕えるためにやって来まして、富貴の家と栄えたのでありました。大昔にも、今も、これからも、めったにない、ふしぎなお話でございました。(「山椒太夫」終わり)
※伊藤比呂美「現代語訳
説経節」はここで一区切りといたします。ご愛読ありがとうございました。加筆のうえ、来春に小社より単行本として刊行いたします。ご期待ください。

1955年東京都生まれ。詩人。
1978年現代詩手帖賞を受賞。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で高見順賞、07年『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、08年紫式部賞を受賞。
エッセイ集に『良いおっぱい 悪いおっぱい(完全版)』『閉経記』、古典の現代語訳に『日本ノ霊異(フシギ)ナ話』『読み解き「般若心経」』『たどたどしく声に出して読む歎異抄』、対談集に石牟礼道子との『死を想う』などがある。著作の一方、自分の詩の朗読活動も行っている。