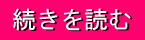第1回 ゲッゲッゲッ、外道か? 男色は香りの中に −アリラン・プレスリーの朧げな告白(1)
そもそもの始まり
「負けた、自覚なきごっこに負けた」
アリラン・プレスリーが総武線に乗り込むや、ドアを入ってすぐ左の席。60がらみの身なりに清潔感のある男が、悔しそうに、そう腕組みして呟いた。
意味するところはよく解らないが、何か相当悔しいことがあったのであろうことは、アリラン・プレスリーにも充分に察せられた。
悔しいことなど、アリラン・プレスリーにだって幾らでもあり負けてはいない。
大韓民国ソウル特別市の下町でそもそも生まれ育ち、「稼ぎ」とあわよくば「名誉」のため日本へ渡り、今、キャバレー歌手として「ワダクシ、シガー(Singer)頑張テマスネ」といった日々の明け暮れのアリラン・プレスリーの記憶は、渡日前後へと飛んだ。
何をやっても、まあ何というか、渥美清の「泣いてたまるか」の様な展開となり、働く意志はあるものの、あらゆる職業に就こうと間の悪いミスを重ね、アマチュア野球の審判を生業とすれば、繰り返し、明らかなアウトをセーフと判定し、たちまち悪い評判が広がり、球場に姿を見せるや、「あいつか!」「退場!!」と野次が飛び交い、カップ麺やビビンバや焼酎の瓶をぶっつけられたりと散々だった。結果、職を転々とするのを余儀なくしていた。
そんな彼の唯一の特技は"カラオケ自慢"だったが、まさかあくまで街のポンチャック歌手にすぎなかったそれ、が職業になるとは思いもしなかった。
10余年前の晩、当時勤めていた警備会社の控え室で、テレビの「人間時代(インガンシディ)」というドキュメント番組で〈ポンチャック・ディスコの星〉として注目を集める、李容昃(イ・ヨンソク)こと李博士(イ・パクサ)の姿を初めて見た。李容昃は江原道(カンウォンド)を代表する大衆キャバレー・マンモス・グループの会長にレパートリィの膨大な数を感心され、「博士」の称号を頂戴し、以降「李博士」の名前で売り出したのだった。
キャバレーで歌う傍ら、観光バスに乗り込み、中高年の女性たちの間で既にスターであった李博士はツアーバスが観光ホテルに到着する迄、花鳥風月に没しながらその内部は俗にして余りあるバスの中で、知る限りの歌をうたい、年のややいった、それでいて「まだまだ現役よ、ねえ、オトーちゃん」といった熟年女性たちを熱狂させていた。
観光ホテルに着くや夕食もそこそこに、ラジオカセットのボタンを押すと、たちまち李博士を囲んで、ホテルのオンドル部屋はフロアと化し、李博士から次々と繰り出される歌謡ディスコ・メドレーは女性ファンを最高潮まで狂喜させ、テレビカメラは博士の胸元から全身のポケットへと、沢山のオヒネリが力尽くで捩じ込まれる姿を映していた。
深夜、宴も終わり、静まったホテルの小部屋で、律儀にも籠一杯のオヒネリをバスの運転手、ガイドと三人で公平に分配する李博士の姿を時々チカチカと歪むブラウン管の中に見た。
場面はかわり、今にも朽ち果てそうな住居が映し出された。晩舞台(パンムデ)、つまりキャバレーの歌謡ショーの仕事にそなえ、仮眠をとろうと、押入れの上、つまり天袋というのか、そこへ敷いた蒲団に横たわる李博士は「ただいま」という声を耳に寝床から起き上がり、帰宅した小学生の息子に向けて天袋からピョコンと首を出した。そして「お帰り」とひと声かけ、再び、首を引っ込め床に就くシーンが続いた。居間兼台所では年上と思しき博士の女房が米を研いでいる。
「亀......にしては首が細いな」
カップラーメンを食べながら、男はそう思った。
転機(但し、本人思い込み)
それから、数年して、転機は訪れた。
両手、両足の指二人分でも最早数えられぬ程の職を転々とし、大衆キャバレーで板前をしていた時のことだ。その晩のステージを、このところの絶不調のまま終えた、「アリラン・プレスリー」の名で歌っている年老いた歌手が、閉店前に、まだ板前であった男に伝令を遣わした。
丁場で片付けをしていたところ、以前から独特の強烈な何というのか、とにかくあの、ある種の嗅いでいるとどうにもむず痒さを覚える香水の香りをプンプンさせた一番若いボーイの、通称・洪吉童(ホンキルドン)ことミスター金が、「アリラン・プレスリーのハラボジ(お爺さん)が呼んでおりマッスムニダ」と言うので、男は楽屋に赴いた。ぴんからなカツラも、義足(本人、曰く「朝鮮戦争で右足を失った」)もはずし、しかもメイクも拭ったアリラン・プレスリーはかつて〈キャバレー青春スター〉のキャッチフレーズで晩舞台と称される夜のステージを風靡した時代とは程遠い、すっかり只の老人だった。それが、以下の様な話を持ちかけてきた。
「もう俺もアレ......そのう、歳だから、この仕事も年貢の納め時だとハッキリ決意した」
「ハァ......」
「そこで、お前に良い話がある」
「良い話って?」
「大丈夫、大丈夫だ。高いことはいわない。まあ払えるだけ払ってくれ」
「えっ、払う?......何をですか」
「俺の芸名、アリラン・プレスリー。これはこの晩舞台てえか、要は韓国中の大衆キャバレーでは実に知られた由緒ある名前だ!」
「え、ハア、それで?」
「でなァ、ヘヘン、特別に、この名前とプレスリーみてえな白いひらひらの付いた衣装とブーツ、皆、特注のな。あと得意先のウリナラ(我が国)中の名門キャバレー......、ああ、そのな、大衆キャバレーったって、永登浦(ヨンドゥンポ)の"銀馬車"だとか、どこも有名な高級店ばかりだ。勿論、紹介状込みで、芸名、衣装、リストを書いた手帳、そのみっつを一式として、アンタに特別に買い取りってえか、二代目襲名も全部の権利をやるから、是非、明日からでもアリラン・プレスリーにアンタが成ってみる気は、なぁ、あるよなぁ、この俺がここまでヨロシクお願い申しますてえば、なあ?」
「いや、そもそも歌で喰っていく程、この俺は、そんな喉は持っちゃいねえです。せいぜいカラオケのど自慢でちょいとばかり......」
「んなことね! 何ヶ月か前、いつだったか、インフルエンザだったか、百日咳だったか赤痢か何かで、とにかくよォ、歌手がのきなみ休んだ日があっただろ、なあ!?」
「ぁ......」
「あの時、お前がよォ、ひと晩だけ、楽屋にあった誰だかの銀色のスーツを着て、ドドメ色のシルクハットを被ってよ、ショーの合間、何回かステージに上がって歌ったろ? "ノムハムニダ"、"大田ブルース"、"ナオトケ"......ありゃ、歌声も貫禄も立派な歌手だった。感心したね、実に。なァ、この俺だって、あの時にアンタの才能を見届けなきゃあ、こっちにもそりゃ、こんな老いぼれちまっても、プライドっつうもんがある。幾ら金積まれようが、それが100万ウォン(10万円)だろうが1億ウォン(1000万円)だろうと、おめえ、誰カレ構わず、栄えあるアリラン・プレスリーを名乗らせるワケにゃあいかねえってんだ、なあ? ......で、アンタ幾ら出せる?」
「え! ああっ、いや、ちょっと待ってくださいよ、先生様(ソンセンニム)」
と、初め強く拒んだが、その時まだキャバレーの板前だった男は、結局、高いのか安いのか峻別出来かねる有り金で「アリラン・プレスリー」一式を丸ごと購入することとなり、キャバレー回りとはいえ、歌手への道を歩むことと行き掛かり上、なってしまったのだった。
「まあ、包丁抱えた板前よりは、アリラン・プレスリーでマイク握った方が金になるべ」―そう、軽々しい気持ちから、板前より、今、正に、歌手に転職しようという男は思った。話がさしたる抵抗もなくほぼ押しきる様に決まった時、初代アリラン・プレスリーは、こう言った。
「アンタから金が入ったら、今よォ」と辺りを見まわし、唇をほやほやの二代目の耳元に近付け、「実は別のところから、今、傷痍軍人のシマ、道具、権利一式、俺のもんにって話があって、まあ俺も歳だし、いつまでも義足で舞台にひと晩何度も立つのもキツイし、これからはしばらく傷痍軍人で喰ってく。だがなぁ、時代ももう21世紀、その仕事だって通じるのはあと5年、6年がせいぜいだと思っとる」
「はあ......」
「でも、その世界も色々あってな、俺の譲り受けるシマ、要するに座る場所は、あっちの世界でいう一等地だ。そこらの二等兵みたいな同業者とはワケが違う。いわば将軍が傷痍軍人をやる様なものだ。ヒーコラ言って歌うのと比べ物にならない程、今ならまだ稼げるって話だ。しかも、日がな座ったまま楽チンによ。なあ?」
「え、そうすか......」
「まあ、とにかく、気持ちで、俺ァ気持ちで構わねえんだ、アンタの。とはいえ、そこはまあ、払えるだけ払って貰うとしてだな、とにかく、アンタは栄えある二代目アリラン・プレスリーを引き継ぐんだから、ケチなことはお互い言いっこなしだ。うん。こりゃあもう、この世界じゃあ大したもんだから」
「しかし、プレスリーの歌なんか、トロット(韓国歌謡の俗称のひとつ)専門の俺にはひとっつも歌えねえよ」
「あーん、んなもん名前だけでええ。あと衣装。この俺だって、お茶濁しに"ラヴ・ミー・テンダー"がワンコーラスだけ歌えるだけで、あとはもっぱら懐メロだ。あんな気取った歌にゃあ俺だって性が合うワケじゃあねえ」
「あ、ハァ......」
「でも、おめえなぁ、ンッ、グアア、ペッ」と痰を切り唾を吐き、初代アリラン・プレスリーは続けた。
「プレス、リー......李エルヴィス......? ああ、エルヴィス・プレスリー! そう、プレスリーったらもうそれだけで世界的な価値のある大看板で、アメリカ国だニューヨーク国だ、どこの国に行こうと未だ大人気だ。我が大韓民国では、俺が辞めたらお前しか名乗れねえ。そりゃ、まあ、大したもんだ」
結果的に、その様に、つまり以上の様に、「俺の話を聞け」、そしてそれに従うのが当然と決めるも同然の、初代アリラン・プレスリー(まあ、この初代そのものが怪しいがここでは問うまい。又、どうでもよい問題だ)に有無を言わされぬまま、二代目として包丁をマイクに持ち替えて、アリラン・プレスリーとしての歌手生活は始まるのだった。
 ※ この写真はイメージです。
※ この写真はイメージです。