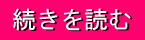二代目〈アリラン・プレスリー〉ドサ周りの日々
そんな訳で心機一転、アリラン・プレスリーとなった男は、東は38度線沿いの東豆川(トンズチョン)という基地の街―ここでは客の殆どが米兵で、芸名と衣装ばかりでいつまでもプレスリー・ナムバーを歌わぬその男に罵声とともにビール瓶が飛び交い、ステージを途中で降りた―で歌ったり、西は犬でも有名な珍島のNO.1キャバレーCHINDO STARで唯一知る日本のヒット曲「珍島物語」で大喝采を浴びることもあった。
だが、「この手帳にある店ならば、どこのキャバレーもアンタによくしてくれる」はずが、大方の店でアリラン・プレスリーは冷遇された。
全羅北道(チョルラプクド)の首府、全州(チョンジュ)郊外のひなびたというより半壊したかの様なキャバレーは、入場時に、汚れた手で「サービス!」とばかりに鷲掴みしたアンパンを一人ひとりに配るモギリ兼副支配人が有名?だったが、そのサービスマンをして、アリラン・プレスリーを蔑みながら、「奴に何て言われたか知らねえが、アンタみたいなのを"オルグロプスヌン・カス"(顔のない歌手)というんだ。名前は立派なもんだがな、しかしそれだけのもんだ」と言った。
「あ、う......」と、僅かな1万ウォン札を数えながら、アリラン・プレスリーは、それ以上言葉が出なかった。
が、モギリ兼副支配人の男の口から次に意外な話が飛び出した。
「そういやあ、以前、"シンパラム! 李博士"っていたろ? お前らの同業でよ」
「ん、ああ......」
「アイツは大したもんだ」
「と、言いますと?」
「おめ、知らねえのか? ああ、まあ、大方、こっちじゃそんなもんだろうけどよ。オレ、その、ワタクシは12、3年前、大阪にオリマシタカラ理解がある。あ、でな、アイツはこっちとは違ってイルボン(日本)に渡って大成功をしたんだなア。ソレも不思議なもんで、こっちみてえに大学なんて縁も所縁もない連中や老人中年、バスやタクシーの運転やってる奴じゃなくって、良家のガキや坊ちゃん嬢ちゃん共の間で売れっ子になってな、武道館って知ってるな? アレに出りゃあ日本一だってえ、アソコにも♪パラッパッパン、パラッパラーのスーダラダッタって舞台に立つわ、終まいにゃあホーレ、キンチョール、あの日本の有名なキンチョール、ダニとかシュファッと一発で殺っちまうヤツ、あるべ? アレのアレ、コマーシャルまでやって、テレビにはバンバン出て来るは、あげく、ソウルのホーレ何ってったっけ、アップだかアックジョン区だか一等地に家を建てたんだから、ありゃあ大したもんだ」
「えっ、本当ですか!?」
「ああ、本当だ。しかも、女房まで、新しいのにトッカエタッてえ話だ。ん、まあ、人間、何処にチャンスがあるか解りゃしねえよ」
と、ここまで言うと、さっきから横でボリボリと蚤を探して掻いている猫の方に顔を向け、「なあ?」と同意を求めた。
アリラン・プレスリーを巡る人間模様(出自やら差別やら)
何が猫に「なあ?」かはともかく、この時耳にした話が、遡れば、アリラン・プレスリー渡日のほのかな芽を生む発端となったといってもまあよいだろう。テレビのCM、それも「キンチョール」ってありゃー有名だもんなあ......。
その頃、國民学校(小学校)5年の長男を頭に、5歳と2歳、3人の息子と折り合いの近年ままならぬ妻を抱えていたアリラン・プレスリーは、全州で李博士の成功譚を聞いた直後、ソウル市内の中堅大衆キャバレー「キプソンソ(悦び組)」の専属となったのだが、同歌手の先輩にあたり、自称旧ソビエト出身で、ペレストロイカ期のモスクワ、旧ソ崩壊後は上海、香港、タイ、モロッコのキャバレーを転々として、去年ソウルにやって来たと、そう本人は語る流暢な韓国語を駆使するハンサムなロシア人ポンチャッカーは、「釜山港へ帰れ」や「大田ブルース」などのお馴染みの曲から「雨降る京釜線」や「帰らざる三角地」などもレパートリィに入れているほどだった。その名もトラジ・ヴィソツキーと、やや抜けの悪い芸名ながら、歌唱力はもとより、ステージング、韓国は元より世界のヒット曲も何でもござれな広いレパートリィ、ルックス、そしてロシア人ポンチャッカーという意外性からくるその人気を含め、アリラン・プレスリーにあらゆる面で大きな差をつけ、当初はこみ上げる笑いをこらえフレンドリーを装っていたが、やがてあからさまに見下す様になり、楽屋でも何かにつけ、侮辱的な態度をいちいち示した。
便所の個室に籠もり、独り、悔し涙を流すその時によくアリラン・プレスリーは父(アボジ)の顔を浮かべ、浮かんだアボジがこう語るのを思い出してみるのだった。
「もともと、儂らの金家は、歴代の大統領を次々と生み出した慶尚北道(キョンサンポクド)だって言うが、辿れば金海金氏(キメキムシ)へ辿り着く由緒ある家系だ... まあ証明する旅譜(チョクポ)は先の戦争で焼けちまったが。でも、間違いあるまい」
そう、幼少時よりことある毎に聞かされた出自に根付く誇りを、打ちひしがれた時々で持ち出して生きてきたアリラン・プレスリーだったが、その店の支配人からボーイに至るまで、全羅南道(チョルラナムドウ)、済州島(チェジュド)の出身者が多くを占め、とりわけ、高(コ)という年かさのボーイが、トラジ・ヴィソツキーの一番の子分で、出演直前にブーツを隠したりなど、日常的に他愛ないことではあるが、ヴィソツキーの差し金で、アリラン・プレスリーへの嫌がらせは絶えなかった。その度に、唯、ひとり、慶尚南道(キョンサンナムド)出身の細面の尹(ユン)という青年が、そういった状況をいつも距離を少しばかり置いて眺めており、ブーツの隠し場所など教えてくれるのだが、アリラン・プレスリーは、その度に尹青年から、板前時代にボーイをしていたあの金青年の発した香水と似た類の香りを覚え、言葉にしがたいあの官能的ともいえる情感が一瞬腰から脇腹をよぎるのだ。が、即座に香りに気を取られぬ様、たまたま通り掛かった、一見、モルモットみたいな犬などへ気持ちを向けたりと、ほんのちょっと努力をした。
やがて、一触即発、いつ何かコトが起ころうとおかしくない緊張感がトラジVSアリランの間に漂ったが、それでも扶養家族4人を抱え、しかも近頃益々、自分に冷たい妻を思い浮かべ、アリラン・プレスリーは少しでも家庭の安定を守ろうと堅い煎餅を齧る自慢の前歯の強ささながら、歯を喰いしばり、日々の屈辱に耐えていた。
無責任男の一大決心+ハッテンしない韓流エピソードその1
そんな生活の中、家に帰る度、自分のことを一から百まで何かとこきおろす女房にグッタリして、李博士に続くこの道(イ・キル)の成功を夢みるというより、現実的な問題として活動の場を単身日本に移すことを、これ以上、脳内に止めることなく、その外側へ向け、行動として進める方向を取ろうと試みることにした。すると、あたかも赤いプラスチック製の、豚さんの貯金箱に1ウォン玉、10ウォン玉、100ウォン玉をビッシリと貯めるように、アリラン・プレスリーの頭の中はまだ手にせぬ金で一杯になっていった。同じ不景気とはいえ、それでも日本のレートで稼げば、女房の機嫌も元へ戻るかもしれない。それも大きかった。連日、店では、ヴィソツキーとの確執からくたくたになって、帰宅すれば、今度は妻に倒れるまで罵倒、侮辱、愚痴られては気の休まる時がない。
その秘かな計画の背景はどうあれ、当人にとって無限の大事業である以上、実行に移す前、アリラン・プレスリーは誰かにその事を公明正大に宣言しようと思い立ち、真っ先に脳裏に浮かんだのは、今頃、傷痍軍人の世界でさぞやひと旗揚げているはずの、初代アリラン・プレスリーだった。そこで初めの第一歩にと、初代のもとをその一等地と呼ばれるソウル駅近くの歩道橋へ訪ねた。
が、初代の姿はなく、サングラスをかけた別の傷痍軍人がそこで何故か正座をしながら、ポンコツのラジカセで、〈シンパラム! 李博士〉のノビノビのよれたテープを大音響でかけて、小声で全ての通行人に詫びていた。「戦争に勝てなかったのは当時天下の第五師団、伍長だった私の踏ん張りが足りなかったからでございます」といった意味のことを呪文、或いは念仏を唱える様に、切れ目なく繰り返し、そして、伍長の前に敷かれたゴザにはバラの煙草(米軍基地から流れたマールボロ)、ゴムヒモ、中国製のトランクスが並べてあり、長方形に切った段ボールにマジックインキで大きく「みっつで、五百元でございます」と記されていた。が、「五百元」の下に小さく、震える字で「但し、子供のみ。大人は五千元以上」とよく見ると書いてある。
「あ、あのう......」とアリラン・プレスリーが2、3度声を掛けると、かつての伍長殿はサングラスを右手でずらし、アリラン・プレスリーの方をジッと見た。
左目は潰れていた。が、それは戦場でというより、比較的最近の事故か喧嘩の傷跡に思えた。
そして伍長殿はもじもじするアリラン・プレスリーに、しゃがれた声で「ヌギンガヨ?(アンタ、誰や?)」と尋ね、次にその時たまたま普段着さながらに着用していたステージ衣装をしげしげと眺め、「ギャグマンか?」と訝しげに問うた。
そこで、アリラン・プレスリーが、ことの次第を説明すると、そんな奴(初代)のことなど全く知らないし、心当たりもなく、自分は10年前からここで、こうしてこの仕事をしていると、何らの澱みのない返答には説得力があった。
行きがかり上、アリラン・プレスリーは5000ウォン差し出し、伍長殿がトランクス他みっつを掴み、アリラン・プレスリーに差し出したが、「結構です、伍長殿」と言って、掌で制した。
「ああ、ほんじゃあ、また、次にな」
伍長殿はそう答えるや、すぐに当初の体勢に戻り、また同じ呪文とも念仏ともつかぬアレを繰り返した。
そして踵を返してその場を去ろうというアリラン・プレスリーの白い背中が、「モッチン・アジョシ(いかしたオッサン)」との声を聞いた様な気がした。振り返ると伍長殿は右手の親指を立て造作なく突き出した。伍長殿なりの自分への励ましだろうと感じたアリラン・プレスリーは「ワン・ツー・スリー!」とスキップでもする様な気分で家路へ就いた。
尚、「初代」の所在やその後はともかく、事情やらあの伍長やら総てひっくるめ、〈よくある話〉として、このエピソードは終わった。
 ※ この写真はイメージです。
※ この写真はイメージです。