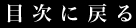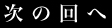第1回
なぜ、いま、土光敏夫なのか
土光敏夫(1896~1988)は、「昭和」を代表するリーダーだった。戦前から戦後復興、高度成長、石油危機、バブル前夜にかけて、技術者、経営者、財界人として日本経済を牽引した。石川島播磨重工(現IHI)、東芝の社長を経て経団連会長を務め、80歳を過ぎて第二次臨時行政調査会の会長に就く。鈴木善幸内閣の「増税なき財政再建」を受けて、専売公社、国鉄、電電公社の民営化などを提言した。第二臨調は「土光臨調」と呼ばれている。
とにかく現場が好きな人だった。石川島重工の社長に就任した当時、土光は、一升瓶をぶら下げて工場の労働組合事務所を訪ね、労使交渉に臨んだ。徹夜で組合員と交渉し、同じ話がぐるぐるくり返されるので「山手線」のニックネームをつけられる。戦後の動乱期とはいえ、大会社の社長がわざわざ工場に出向いて、朝まで労使交渉をするのは珍しかった。その真意はどこにあったのか。
 土光の長男で、石川島重工で航空機エンジン工場の工場長などを務めた陽一郎(86歳)は、「現場には夜勤の人がいるでしょう」と指摘する。陽一郎も、父と同じく機関設計で実用新案などを取って重電メーカーの屋台骨を支え、のちに関連会社・石川島コーリングの重役を務めた。工場での徹夜の労使交渉を経験している。
土光の長男で、石川島重工で航空機エンジン工場の工場長などを務めた陽一郎(86歳)は、「現場には夜勤の人がいるでしょう」と指摘する。陽一郎も、父と同じく機関設計で実用新案などを取って重電メーカーの屋台骨を支え、のちに関連会社・石川島コーリングの重役を務めた。工場での徹夜の労使交渉を経験している。
「僕は、常務として、ひと晩じゅうやりました。長く交渉すれば議論も尽きて、へとへとになる。でも、やり続けるのが組合の立場でしょ。だから、経営側は、それを分かったうえで、耐えなきゃいかん。夜勤の人が油と汗にまみれて働きながら、事務所の灯りを、期待をこめて見上げていますからね。自分がやってみて分かった。親父は山手線なんて言われても、持久戦をやった。現場を大事にしてたんじゃないかな。やっぱり最後は人ですよ」
公害問題が喧(かまびす)しかったころ、東芝の工場を視察した土光は、現場に着くと儀礼的な挨拶を抜きに排水処理施設へ直行。汚れた水に指をつけてペロリと舐めて「これなら大丈夫」と破顔一笑した。石油ショックの渦中で経団連を担うと、福田赳夫副総理(以下肩書は当時)を相手に拳で机を叩きながら「景気回復」を訴える。福田は、土光のあまりの剣幕に「怒号さん」と呼んだ。土光は現場の最前線に立って「背なか」で人を引っぱる男だった。
もっとも、完璧な人間はいない。土光の超積極主義経営は、財務無視と非難されたこともある。原子力開発への猛進は、福島第一原発事故が起きたいまとなっては批判の矛先も向けられよう。東芝の再建は頓挫した、行政改革の筋道を示した「土光臨調」は政権に利用された、との見方も残っている。毀誉褒貶は世の常である。
だが、同時代の経済人の誰も及ばない国民的な「人望」が土光にあったことは、紛れもない事実だ。あだ名の多さにも、それは表れている。「山手線」「怒号さん」のほかに「財界の荒法師」「ミスター合理化」「メザシの土光さん」と愛称はいくつもある。石川島時代には「オヤジ」「オヤジ」と社員に慕われた。積極財政派で、当初は行革に反対していた田中角栄元首相でさえ、土光の清廉な暮らしぶりを見て「あの人がやるのなら仕方ない」と脱帽したという。庶民から政治家、経済人まで幅広い層の人望を集めていた。
いま、われわれの周囲を見まわして、人望と地位が一致する人物が何人いるだろうか。IT化が進んだ高度情報社会の特性なのか、一時的な人気は燃え上がっても、人望にまで昇華しにくい。あるいは人望はそれなりにあるのに、不可解な権力闘争でリーダーシップを握れない人もいる。社会全体の焦点がボケたまま、手段が目的化して「前へ、前へ」と人も組織もつんのめっているようだ。
そんな時代に生きているからこそ、いま一度、私は土光敏夫の精神的な背骨を確かめたいと思い、「昭和」へのささやかな旅に出ることにした。
昭和の時代に土光が遺した言葉は、現在も多くの人びとに愛され、支持されている。
・組織はピラミッドでなく、宇宙系であれ
・「資本金」ではなく「資本人」である
・エネルギー政策で縄張り争いするな
・女性を適材に配置し、能力開発を
・創造性を高める「重荷主義」
・社員をクビにしない
・社員は三倍、重役は十倍働け、俺はそれ以上働く
・経営者の人事権は独裁権ではない
・身辺を飾りたがる者に本物はいない
・苦労を体験して「地力」をつける
・「観の眼」つよく「見の眼」よわし
・全従業員と話すのが楽しみだ
......と、あげていけばキリがないのだが、土光の言葉はリーダーの身の処し方であれ、若者へのメッセージであれ、大きく分けて二つの光源から放たれている。ひとつは技術者らしい合理主義で「改革」を徹底的に追求しようとするバイタリティだ。それは、中国は殷時代の湯王に由来する座右の銘「日に新たに、日々に新たなり(今日の行いは昨日より新しくよくなり、明日の行いは今日よりもさらに新しくよくなるように修養を心がける)」に集約される。
土光は日蓮宗を信仰する両親の影響で、朝晩30分の法華経の読経を欠かさなかった。「日々に新た」であるために読経を日常のけじめとしていた。では、日々に新たに不断の改革を続けて経営を刷新する、その先にあるビジョンとは何か。
そこで浮上するのが、もうひとつの光源「共生」である。端的にいえば「人」を大切にして、ともに救われようとする大乗的な共生観だ。男女雇用機会均等法(1986年施行)のはるか以前から、土光は女子社員をお茶くみから解放し、「社長室は誰にでもオープン」と扉を開け放った。固定化した上下関係を嫌い、「上司を役職で呼ぶな」とも言っている。組織は宇宙系であれと唱え、マネジメント・ボードという「太陽」の周りを「事業部」という惑星がくっつかないで回っている事業部制を、早い段階で採り入れた。
土光の共生観が凝縮された、最も彼らしいフレーズは「個人は質素に、社会は豊かに」だと私は思う。この言葉はもともと母・登美が常々口にしていたらしいが、土光はそれを実践した。とても大企業の社長宅とは思えない古びた木造家屋に住み、つましい生活を送る。ひと月の生活費は土光と妻で「10万円でお釣りがくるくらい」だったという。
そんな生活の上面だけを見て、「あなたのような暮らしをする人が増えると、世のなか、不景気になるのではないか」と訊く者もいたが、まったく、お門違いの質問であった。土光が質素な暮らしを続けたのは、そもそも贅沢を望まず、稼いだお金を「橘学苑」という戦中に母が創設した女子校の教育事業に投じていたからだった。土光は語っている。
「僕らには学校経営という大命題がある。私学をやっていくのは大変です。あれもしたい、これもしたい、と思えば金はいくらあっても足りない。僕の収入の大半は『橘学苑』に吸い取られるが、といって授業料を上げるのはいやだし、いつも青息吐息の状態だ。
要は、得た収入を何に使うかなんです。教育に投資するのも、ささやかではあるが、経済活動の一助とはなると思う。しょせん金は天下の廻りもの、タンス預金では困るが、銀行に預けても、それは産業資本として転用されるわけだし、それなりの意義がある」
母の口癖だった「個人は質素に、社会は豊かに」へ土光はこうつけ加える。
「『思想(おもい)は高く、暮らしは低く』と言っているんです。だが、その価値観を人に押しつける気は毛頭ない。人それぞれに人生の楽しみ方はあるわけで、そのおかげで東芝の商品も買っていただけるのだから、そんなこと、経営者の端クレであれば誰だって分かることですよ。
ガキのころから、僕はずっと法華経を信奉してきた。が、残念ながらこの年になっても未だ『安心立命』の境地には至らない。『不自惜身命』の教えは、なんとか実践してきたつもりだけれども」(『土光敏夫大事典』池田政次郎監修、産業労働出版協会、カッコ内筆者)。
経済人の学校経営といえば、古くは商法講習所(一橋大学の母体)や日本女子大学、国士舘などの設立に携わった渋沢栄一、大倉商業学校(東京経済大学の前身)を創設した大倉喜八郎、成蹊学園のために用地を提供した三菱財閥の岩崎小弥太、戦後では流通科学大学をつくったダイエーの中内功らの顔が思い浮かぶ。皆、オーナー経営者だ。土光のようなサラリーマン経営者で、私財を教育事業に投じた例は寡聞にして知らない。
しかも、土光はそのことをずっと伏せていた。経団連の職員がたまたま私学助成金の関連資料を調べていて、会長の土光が給料のほとんどを教育事業に注ぎ込んでいることが判明したのである。土光は「公」と「私」をきっぱりと峻別する人でもあった。表の公の場では妥協を許さず、大声で怒鳴りもしたが、一歩会社を出て私の領域に戻れば仕事を持ち込まず、穏やかに過ごした。長女の和田禮子(83歳)は「父が家で大声を上げたのは聞いたことがない」と言う。「子ども心に一番覚えているのは、よく御礼を言われたことですね。ちょっとしたこと、たとえば新聞受けから新聞を取ってきただけでも、ありがとう、ご苦労さん、と声をかけられました」とふり返る。
改革と共生、公と私、動と静。土光敏夫の精神的な背骨は、対照的な価値観を貫いて、まっすぐに伸びている。
おりしも、野田佳彦政権は「平成版土光臨調」のふれこみで「行政改革懇談会」を発足させたところだ。行革懇は、稲盛和夫京セラ名誉会長をトップに政府の行政刷新会議の民間議員ら10人で構成されている。その顔触れを見ると......、即断はやめておこう。ただ、平成版土光臨調が増税の「アリバイ工作」に使われないよう祈るばかりである。
土光は、阿修羅のごとく経営の改革に取り組む一方で、一切衆生が救われる共生を志向した。その精神の背骨に触れる旅は、彼が私財を投じ続けた、もうひとつの現場、橘学苑が創設されるところから出発しよう。