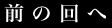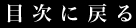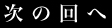第2回
母・登美と日蓮の遺産
土光敏夫は、母親の登美の「生きざま」を糧として、自らの心の置きどころを練ったとみられる。母の影響を受けた精神的痕跡はいくつも見出せる。
たとえば「日輪」への崇敬だ。
登美は、明治天皇御製の和歌を好んで口にしていた。
さしのぼる朝日のごとくさわやかに もたまほしきは心なりけり
敏夫の長女、和田禮子によれば、登美は「心に太陽をもて」としきりに孫たちに教え聞かせたという(『たちばなのかおり――土光登美先生の追憶』橘学苑・山本丑之助編)。すがすがしい朝日の輝きを心に持とうと登美は呼びかけた。その教えは、この時代の庶民に常識的なものだったかもしれないが、経済人の道を歩む息子のなかで座右の銘へと深められる。
日に新たに、日々に新たにして、また日に新たなり
今日という日は、天地開闢(かいびゃく)以来、初めて訪れる日だ。貧しい者にも富む者にも、遍(あまね)く平等にやってくる。だからこそ、この一日を大切に精いっぱい生きよう......。もとは儒教の経書『大学』にある言葉なのだが、土光は80歳を超えて、「増税なき財政再建」の最前線に立ったときも「日に新たに」の生き方を崩さなかった。
アグレッシブな情熱と、人がともに生きるための包容力を、土光は母から受け継いだ。母を「ふつうの農家の主婦」と呼ぶ一方で、「実に強い意志をもっていた」「子供に対しては実に寛大」と評している。
その土光登美は、70歳を過ぎて、徒手空拳、ゼロから学校創設に挑んだ。いったい、どのような女性だったのか。現代からは、暗黒時代のように語られがちな明治、大正、昭和前半期に登美は庶民のなかに生き、自分の信念を学校という形にした。農家の主婦が建学の祖へと変容していくところに「近代」のダイナミズムが垣間見える。登美の信念を支えたのは、法華経への強烈な信仰であった。法華経こそが釈迦の本懐だと唱えた日蓮(1222~82)の教義に登美は引きつけられた。
信仰心とは、たとえていえば「火」のようなものだろう。生きていくためのエネルギーであり、暮らしを穏やかに温めもするが、ひとたび勢いづけばすべてを焼き尽くす業火へと変わる。1931(昭和6)年の満州事変から、翌年の国家主義者による政財界人の暗殺(血盟団事件)、青年将校の反乱(五・一五事件、二・二六事件)......と、戦争への扉が押し開かれる思想的背景には日蓮宗への信仰があった。満州事変を先導した陸軍の石原莞爾、血盟団事件を指揮した井上日召、「昭和維新」を掲げ、二・二六事件の首謀者として処刑された北一輝らは、いずれも日蓮の熱烈な信者でもあった。日蓮宗は、革命への渇望を内包していた。
一方で、晩年にさしかかった登美はというと、「国が滅びるのは悪ではなく、愚によってです」と唱え、女子教育の学校づくりに没頭する。同じ火でも燃え方がまるで違っているのである。登美の半生には「近代」を大衆の視点で読み解く鍵が潜んでいる。「土光敏夫の母」という形容を外して眺めると、女傑と呼ぶにふさわしい存在感が漂ってくる。
*
 土光登美は、1871(明治4)年8月8日(戸籍上は翌年1月25日)、岡山県御野郡当新田村(現岡山市)の瀬戸内海に面した児島湾に近い開拓地の地主、伏見家に生まれた。明治4年生まれの幸徳秋水、明治5年生まれの島崎藤村、樋口一葉、英国の哲学者バートランド・ラッセルなどが同時代人だ。(写真:『たちばなのかおり』より)
土光登美は、1871(明治4)年8月8日(戸籍上は翌年1月25日)、岡山県御野郡当新田村(現岡山市)の瀬戸内海に面した児島湾に近い開拓地の地主、伏見家に生まれた。明治4年生まれの幸徳秋水、明治5年生まれの島崎藤村、樋口一葉、英国の哲学者バートランド・ラッセルなどが同時代人だ。(写真:『たちばなのかおり』より)
伏見家は、池田藩士だったが、明治に入って戸長を務めるようになった。地方政治を動かす地主層といえるだろう。岡山は「備前法華」と呼びならわされる、法華経信者の多い地方である。登美の父・義三郎も熱心な信者でお寺や宝塔を建てたという。登美は、もの心つくころから、法華経に向き合った。
備前法華には、日蓮の革命思想の片鱗が埋め込まれている。その源流をさかのぼると、京都の公家の名門に生まれた大覚大僧正妙実にいきくつ。若くして出家した大覚は、当初、真言宗に籍を置いていたが、1313(正和2)年、16歳のときに日蓮の弟子だった日像の説法を聞いて共感し、その弟子となった。大覚は、朝廷と日蓮宗の仲立ち、備前地方への布教を二大使命と期して日像に仕える。
この大覚の活躍こそ、日蓮が遺した革命への布石でもあった。日蓮は鎌倉幕府を牛耳る北条氏とたびたび衝突し、焼き打ちや流罪に処せられても終生、節を曲げなかった。反権力、倒幕の志を抱き続けた日蓮は、臨終の間際に日像に京都布教を命じる。京都に行って天皇に近づけば、鎌倉幕府に代わる親政への道がひらけるかもしれない......。日像は比叡山延暦寺や他宗の圧迫を受け、三度も京都を追放されながら、そのつど赦されて妙顕寺を開く。弟子の大覚の奮闘もあって、妙顕寺は信徒を獲得し、後醍醐天皇から勅願寺のお墨付きをもらった。日蓮の読みは、後醍醐天皇の「建武の新政」で的中する。
つまり備前法華には、日蓮から日像を経て、大覚に受け継がれた意思が脈打っているというわけだ。幼い登美は備前法華の末席に連なった。
登美は10歳で小学校を卒業し、裁縫塾に通いながら娘時代を過ごした。いずれ東京で学問を修めたいと願っていたようだが、19歳の誕生日を迎える前に、御野郡大野村で農業と米穀肥料の仲買を営む土光菊次郎に嫁した。大柄で、男勝り、農作業も平気でこなす登美と、温和でやや女性的一面もあった菊次郎は、ある意味、似合いの夫婦であった。登美は、長男の英太を一歳で亡くしたが、次男の敏夫、実父の名をつけた三男の義三郎、長女の満寿子、次女節子、三女美子(はるこ)と子どもを産む。登美は「農家の主婦」をこなしつつ、政治演説を聞きに行き、国粋主義の評論家といわれた三宅雪嶺の『日本及日本人』を読みふけった。学問への飢えをずっと感じていた。
子育てを終え、中年の域に入ってから、登美はいよいよ個性を発揮する。次男の敏夫は東京高等工業学校(現東京工業大学)、三男の義三郎は京都帝国大学に進んだ。義三郎が京大在学中、マルクス主義経済学者の河上肇教授が、夏休みを利用して学生だけでなく、その家族も対象にした講習会を開くと聞くと、登美は、いそいそと京都まで出かけて行き、耳をそばだてて講義を聞いた。登美は、次のように感想を語り残している。
「私も母として、講義を聞いたが、日蓮上人の立正安国論と余りにも反する趣意に驚ろき、その何れが正しいかと、みずから、南無妙法蓮華経の本尊と対坐して一週間、黙考した。しかるに一週間目の満願の日に豁然として目の前が明るくなり『日本は古来、天皇を中心とした国である。今日これを無視するごとき、マルクス主義などを信ずべきではない』と覚り、お題目を唱えた」(「故土光刀自の思い出」『たちばなのかおり』所収)
敏夫が所帯を持って間もない1925(大正14)年ごろ、登美と菊次郎は、岡山を引き払って上京した。敏夫が赤坂区青山高樹町(現港区南青山)に建てた新居に同居するようになった。そこには次女の節子と三女の美子(はるこ)も転がり込んでくる。敏夫にすれば新婚気分も何もあったものではなかっただろう。
登美は、青山に住み始めて半年ばかり経つと、日蓮主義を標榜する在家の団体「国柱会」に入った。娘の節子、美子もそれに続いた。
*
国柱会は、元日蓮宗僧侶の田中智学が日蓮の三大請願のひとつ「我日本の柱とならん」に由来してつくった組織である。田中の思想は、単純化していえば、「近代天皇制を日蓮仏教によって意味づけ、日本国体の仏教的意義を国民に啓蒙するところ」(『日蓮仏教の社会思想的展開』松岡幹夫、東京大学出版会)に特徴がある。国柱会は日蓮主義の政治観と日本による世界統一を唱えるなど、超国家主義的な色彩を帯びていた。
もともと法華経には、革命的に解釈できる素地があった。たとえば「娑婆即寂光」という教えである。娑婆、すなわちこの現実世界は理想的な寂光土へ変革していけると説く考え方だ。法華経は釈迦入滅の数百年後に成立したとされる。法華経以前の経典では、仏は現実を離れた別の国土に住んでおり、仏に救いを求めるのなら、煩悩が巣くう現実を離れて仏の国へ行くしかない、とされていた。
しかし、28章節(28品)で構成される法華経のなかの第16如来寿量品(じゅりょうほん)で、遥か昔から娑婆世界に仏は現れ、衆生を救いつづけてきたと示される。これによって、この世を理想の国に変革する考え方が成り立つようになった。
国柱会の会員で関東軍参謀だった石原莞爾は、満蒙領有計画を立案し、1931(昭和6)年に満州事変を敢行。関東軍は満州を占領した。石原は、翌年の満州国建国に向けて「王道楽土」「五族協和」を大義名分に掲げる。王道楽土には、アジア的な理想国家(楽土)を、西洋の武力による統治(覇道)ではなく、東洋の徳による統治(王道)で実現させるという意図が込められている。まさに「娑婆即寂光」の転用である。
五族協和には、満州人、日本人、蒙古人、漢人、朝鮮人の五つの民族が協力して平和国家をつくる趣旨が託されていた。満州には革命後のロシアを脱してきた白系ロシア人、ウイグル人などのイスラム教徒も暮らしていた。そこに内戦で疲れた漢人、日本の国策で新天地をめざす満蒙開拓団、一旗揚げようと野望を抱いた大陸浪人が流れ込む。ドイツのナチス政権の迫害から逃げてきたユダヤ人も加わり、満州の人口は急増した。
ところが、満州事変の仕掛け人、石原莞爾は、満州国の建国間もなく、一転して満蒙領有論をあっさり捨てた。満州国は日本と中国を父母とした独立国をめざし、日本人も国籍を捨てて満州人になろうと説いた。石原独特の世界最終戦争論の日米決戦への備え、という構想が根底にあったにせよ、満州を共和国に、とまで語っている。帝国主義の海外進出から平和的な共和主義路線への転向に石原の内面の大変化が読み取れる。
なぜ、石原は自らまいた種から吹いた芽を摘みとるような転向をしたのか。推測するに、
石原は信仰心や愛国心という狂熱の「火」が御しがたいことに気づいたのではないだろうか。このままでは業火になってしまう、と......。陸軍内で、石原は東條英機ら戦線拡大派に正面からぶつかっていく。
登美は、田中智学の指導で設立された立正婦人会の役員に就き、青山高樹町の自宅には日蓮宗関係者がしばしば集まった。娘の節子と美子は、海軍主計軍人の妻で文筆家でもあった白土(小泉)菊枝とともに法華経を信ずる若い世代の研究会をつくった。会員のほとんどは主婦だった。田中は、この会を「まこと会」と命名した。節子と美子は、「まこと会」で活動する傍ら、クリスチャンの羽仁もと子が主宰する「生活改善運動」にも加わっている。若い二人は好奇心旺盛で、活発だった。娘たちにとって法華経信仰は、政治を動かす観念論などではなく、生活に直結した行動原理に近かった。
登美は、婦人会やまこと会の人びとの動きを、じっと凝視していた。女性ばかりでなく、軍人や政治家、実業家のふるまいを見つめている。
1937(昭和12)年に日中戦争が始まると、石原は軍部にあって戦線を拡大してはならぬ、と主張した。強行派の部下に「石原閣下が満州事変当時にされた行動を見習っている」と反論されても、石原は早期和平にこだわり、その工作にも関わった。だが関東軍参謀長の東條英機らと対立し、陸軍中枢から外され、予備役に編入される。日本はずるずると日中戦争の泥沼へと入っていった。登美は憂いを深めた。
1939(昭和14)年、まこと会の機関誌に、海軍主計の夫とともに大陸に渡った白土菊枝の文章が載った。登美は、娘の節子や美子から白土のことを聞いている。白土は、新京(現長春)で参謀副長官だった石原と初めて会ったときのようすを、まこと会の機関誌「まこと」に寄稿した。登美は、その文章を読んで満州と軍部の実態を知ったと想われる。
白土の石原への第一印象は、それまで将軍に対して描いていたイメージとは似ても似つかぬものだった。窮屈な軍服の袖はほころびかけていて、石原は向き合ったとたん、丸くなってピョコンとお辞儀をした。眉は薄く、黒いひげもなく、頭は禿げかかっている。もっさりとした田舎侍のような男であった。
だが、その冴えない中年男が口を開くと、白土はたちまち魅了されていく。
「私(白土)は満州国建国のいきさつや、民族協和の理想については(略)一通り心得ているつもりでしたが、建国精神の根底にあるという『王道』ということの意味が、どうもしっくりと胸におちつかないので、その説明をしていただきたいと願ったのです。
『王道か』
と閣下は言って、右手で後頭部をぴしゃりとたたき、そのまま上を見るような形で、頭をひとまわりさせ、そして私をまっすぐに見て言われました。
『王道の正反対をやっているのが今の満州国なのですよ』
私はびっくりしました。満州建国の重要な責任者であり、理想実現に確信をもっているはずの閣下のこの否定的な言葉は意外だった。閣下はいささか皮肉な笑みをうかべて言葉をつづけられました。
『まずごらんなさい。司令官が、あんな眼と鼻のところにある司令部に出勤するのに、毎朝堅固な護衛つきで、自動車をとばして行く。日系官吏は満州人の高官に向かっていばっている。満州人の大臣は部下の満人にたいしてふんぞり返っている。部下の官吏は下役にいばっている。むしゃくしゃした下役たちは、自宅に帰って奥さんにどなりちらす。奥さんは女中や下男に当たってしまう。雇人は茶碗でも割ってうっぷんを晴らす。これが王道の正反対の情景ですよ』
私は言われる通りの情景を一々心に思い浮かべながら、黙って聞いていました」(『将軍石原莞爾――その人と信仰に触れて』白土菊枝著、まこと会)
石原は、日蓮がいたころの立正安国は日本一国の問題だったが、いまや東亜の範囲で理解しなくてはいけない、法華信者の信仰実践の場はこれ以外にない、と断言する。白土は「名人の画いた襖絵の虎」が襖から脱して動きだしたような衝撃を受けた、と記している。
白土の記事を読んだ登美の心のなかでも、同じく何かが動きだした。
そのころ、登美は体調がすぐれない夫の菊次郎と一緒に隠居をする「終(つい)の住処」を探して、小田急線沿線の成城や玉川学園、東海道沿いの神奈川県内各地を歩き回っていた。土地選びには、一番年長の孫、陽一郎を伴った。陽一郎は語る。
「祖母は、夏になると孫たちを引き連れてよく海水浴に出かけたものですが、その場所を決めるために首から海軍将校が使うような双眼鏡をぶら下げて探査するような人でね。隠居場所を探して、小学校高学年か、中学生だった僕もあちこち一緒に行きました。横浜鶴見の獅子ヶ谷の坂の上に来て、よしっ、ここにしようと決めたのは昭和13~14年だったと思うなぁ。広々とした眺望で、直感で決めたんじゃないかな。親父の職場も近いしね」
登美が土地相をみたかどうかは定かでないが、谷を挟んで西に霊峰富士がそびえる風景は一幅の屏風絵のようであった。登美は富士山をこよなく愛した。「子や孫にいたわられつつ登り来て 長尾峠に富士を見るかも」など、富士を詠み込んだ短歌をいくつも残している。富士山を真正面に望む、広い高台は魅力的だっただろう。
獅子ヶ谷は、敏夫が取締役を務める石川島芝浦タービンにも近かった。会社は鶴見駅を挟んだ臨海地にあった。敏夫は青山高樹町の自宅から、市電と山手線、京浜線を乗り継いで会社に通っていた。息子の会社が近いことは、老いた親にとっては心強い。残念ながら菊次郎は建物の完成を待たずに逝去したが、登美がこの地を選んだのは隠居所をつくるためだけではない。背景には、女学校を建てるという秘めた大望があった。
だが、一家の大黒柱である敏夫は、母の学校創設の提案に真っ向から反対する。