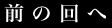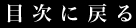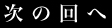第3回
国が滅びるのは悪ではなくて、国民の愚によるのです
高齢の母親から「学校をつくりたい」と打ち明けられたら、あなたはどう応えるだろうか。土地もなければ、建物もない。教師も生徒もゼロから集めると言われたら、冗談でしょ? とんでもない、無理だよ、と返事をするのがおちだろう。
日に日に世のなかは戦時色に染まっていた。土光敏夫もまた母・登美の法華精神に基づいた学校創設の発案を拒絶するしかなかった。いくら土光が重役の覚えめでたいエリート社員とはいえ、本人いわく、まだ一介の「腰弁(日々弁当を携えて勤務する月給取り)」である。学校創設など途方もない事業であった。
土光は、東京高等工業学校(現東京工業大学)を卒業し、1920(大正9)年、伝統ある石川島造船所(現IHI)に入社した。幕末のペリー来航に抗して水戸藩主徳川斉昭が創設した造船所に由来する石川島に入った土光は、社運がかかる「タービン」の設計技術者としてメキメキ頭角を現した。タービンとは流体の運動エネルギーを機械の回転運動のエネルギーへ変換する、複雑な風車のような原動機だ。当時、日本は欧米の技術に頼り切っていた。石川島が狙ったのは、スイスのエッシャー・ウィス社が開発したツェリー式船舶用蒸気タービンだった。この技術の導入・改良と開発による国産化の先兵役に土光は選ばれた。「海外留学」を入社の条件にしていた土光は、入社翌年、スイスへ留学し、2年半かけてエッシャー社の技術を修得した。
間もなく石川島は駆逐艦「菫(すみれ)」を皮切りに、国産タービンを次々と戦艦に搭載していく。土光は、23年に帰国すると社業を取り仕切る常務・栗田金太郎の娘、直子を娶った。父が佐賀藩士だった栗田は、大声で誰にでも直截にものを言う一方で、他人の面倒をよくみた。親分肌である。東京・原宿の栗田家には、佐賀出身の苦学生や生活に困った若者たちが身を寄せていた。人にもまれて育った直子は、控え目ではあるが腹の据わった女性だった。
新婚の土光夫妻は、原宿の栗田家から目と鼻の先の青山高樹町(現港区南青山)に新居を構える。敷地は栗田家が所有していた。直子は、新婚当初のことをこう語っている。
「いっしょになって、東京・青山の高樹町に所帯を持ちました。古い家をサトの方で買っていて、同じ敷地の別棟には、おじたちが住んでいました。甘い新婚生活なんてありませんよ。まさかねえ......」(『無私の人 土光敏夫』上竹瑞夫著、講談社)
直子が言葉をのみ込んだ「......」を勝手に補うなら、「まさかねえ、結婚1年足らずで、あちらのご両親(菊次郎と登美)と妹(節子と美子)さんが岡山を引き払ってきて、同居するとは思ってもみませんでした」となるだろうか。
登美と節子、美子は、新婚家庭に「不受不施義(法華信者以外の布施を受けず、供養も施さない)」の先鋭的な「備前法華」の空気を持ち込み、間もなく「国柱会」に入る。俗に「小姑一人は鬼千匹に向かう」という。長男の陽一郎を頭に禮子、紀子、哲夫、立子と、5人の子どもを産み育てる直子の苦労が偲ばれる。土光家は、子どもの笑い、泣く声と「南妙法蓮華経」の唱題が入り交じり、とても賑やかだった。
会社人の土光は、「気働き」と「剛腕」を兼ね備えていた。少年工の技量を向上させようと、「うどん」を奢って、工場内で「土光塾」を開くかと思えば、陸上の大型発電機用タービンの売り込みでは、大赤字と背中合わせの「独断専行」で受注にこぎつけている。
そのころ、発電機は未開拓の分野だった。市場はゼネラル・エレクトリック(GE)などの外国製品で占められていた。秩父セメントが発電機を導入すると知った土光主任は、時機を逸したら純国産製発電機の道が閉ざされると奮い立ち、先方の常務に直談判をした。
「石川島は技術には絶対の自信があります。使ってもみないで外国製品に劣ると言えますか。発電機の国産化は日本の将来に不可欠です」と熱っぽく語った。
秩父セメントの常務は、冗談まじりに言う。
「それほど、きみの会社のタービンが優れているというなら、どうだね、万一故障をしたり、欠陥が見つかったときには引き取ってくれるかね」
「......承知しました。引き取りましょう」と土光は啖呵をきる。
常務は、まさか30過ぎの若造が「引き取り」を明言するとは思ってもいなかった。なかなか度胸はある。だが会社に戻って上司に反対されて、「あの話はなかったことに」と泣きを入れてくるだろうと侮っていた。案の定、石川島の社内は上を下への大騒ぎとなる。「頭を下げて話を白紙に戻せ」と反対論が強まる。最後は、専務の「土光くんにかけてみよう」の一声で売り込みは決まった。土光は、不眠不休で秩父セメントの現場に泊まり込み、数カ月かけて徹底的に細部を手直しして発電機用タービンをすえつける。
1929(昭和4)年5月、関係者が緊張の面持ちで見守るなか、タービンのスイッチが入った。乾いた機械音とともに最大出力7500kWのタービンが稼動する。結果は大成功だった。次々と注文が舞い込んでくる。ここから、火力、水力、戦後の原子力へと続く石川島の発電機部門が発進したのである。土光は課長に昇進した。
満州事変を機に、軍需が景気を押し上げた。石川島は船舶用タービンも好調で、32年には極東最大の5万3000kWタービン1号機を尼崎発電所に送り込む。上層部はGEの技術を導入している芝浦製作所との共同出資でタービン会社の新設を企画する。世界最高峰のGEのノウハウを吸収すれば鬼に金棒というわけだ。
当初、土光は新会社の設立に大反対だった。海軍中将出身の松村菊勇社長を相手に、「世界の巨大メーカーがひしめいているなかで、別会社で斬り込むのは無謀です。早い話、一つの受注が、100万円を越すような大仕事を、わずか資本金75万円程度の子会社で、なにができるというんです」と辞表を叩きつけそうな勢いでまくしたてた。芝浦と組めば、エッシャー社路線で進めてきた石川島の純国産路線を変更しなくてはならない。土光は、それが許せなかった。しかし土光の反発も大勢を変えられず、36年4月、新会社「石川島芝浦タービン」が資本金300万円で横浜市鶴見区の海に突き出た造成地(現海芝浦駅がある東芝敷地)に設立された。土光は技術部長で赴任し、岳父の栗田も取締役に名を連ねる。
新会社の発足直後、土光はアメリカのGE本社に特別派遣され、5カ月間の研修を受けた。GEの軍需、民需の両面にまたがる広大な産業の森を目の当たりにする。帰国後、土光は石川島芝浦タービンの取締役に任じられる。日中戦争が始まると、鶴見の工場は関西共同火力発電所向けに7万5000kW、日本発送電の発電用には5万3000kWと巨大タービンを完成させる。さらに海軍と連携して航空機のジェットエンジンの開発にも加わった。
土光は、仕事の鬼となってがむしゃらに働いた。法華経の世界に意識を向ける余裕などなかった。そんなころ、母の登美は、菊次郎と余生を過ごす「隠居所」を鶴見の工場から京浜線の駅をはさんで山を一つ、二つ越えた獅子ヶ谷の高台に建てる決心をした。子どもの成長につれて青山高樹町の家は手狭になっている。老いた両親が隠居するのは自然の成り行きでもあった。
1940(昭和15)年9月20日、父・菊次郎は隠居所の完成を見ることなく、永眠した。翌年3月末、鶴見区獅子ヶ谷(現鶴見区北寺尾)に戦時下の30坪制限を受けた木造住宅が出来上がり、登美は青山から移った。時勢は日米開戦に向けて風雲急を告げていた。
大陸では満州国が「王道楽土」「五族協和」の夢と、侵略への反抗という現実の間で激しくきしんでいる。日中戦争は和平の糸口さえ見出せず、長期化していた。にもかかわらず、日本軍は危険な二正面作戦に打って出る。東南アジアの資源、なかでも蘭印(現インドネシア)の石油を狙って41年7月、南部仏印(ベトナム)に進駐した。
この時点で、日米の経済力を比較すると、石油でアメリカは日本の721倍、鋼材17.7倍、国民総生産で12.7倍の開きがあった。戦争には資源が不可欠なのだが、日本は石油の90%をアメリカに依存するありさまだ。アメリカは在米日本資産を凍結し、石油の対日輸出を禁じた。天皇の御前会議で「帝国国策遂行要領」が採択され、10月下旬を期して、アメリカ、イギリス、オランダとの開戦準備に入ることが決まる。東京では、大人一日2合5勺の米の配給が始まっており、戦時統制経済での「国家総動員」体制が強化されていた。
土光敏夫の家は、青山高樹町の市電が走る表通りから、開館したばかりの根津美術館に向かう路地の右手にあった。間取りは、1階が8畳の食堂と4畳半の和室が二つ、8畳洋間の書斎に3畳和室、2階は8畳と6畳の和室。ここで、45歳の敏夫は、2男3女の子どもたちと暮らしていた。一番下の娘は、まだ3歳だ。長男の陽一郎は麻布中学から岡山の第六高等学校に進学して親元を離れていたが、家のなかは相変わらず、大賑わいだった。
9月19日、菊次郎の一周忌法要が土光家で営まれた。登美は、久しぶりに鶴見の隠居所から青山に来ていた。どことなく登美は吹っ切れたようだった。法要が終わり、家族がやれやれと2階の和室でくつろいでいると、おもむろに登美が親族に言った。
「学校を建てたい。国が滅びるのは悪ではなくて、国民の愚によるのです。とくに女性の教育はしっかりしなくてはならん。正しい信念を持った女を育てる学校を建てたい」
すでに登美は70歳を超えていた。日本人の平均寿命が50歳に届くかどうかの時代である。十分に老いている。女学校の創設など荷が重すぎる。家族は口をそろえて反対した。長男の敏夫は、「とてもそんな余裕はありません。体のことも考えてください」と強く諌めた。内心、「とうとうお袋は大っぴらに言いだしちまったか」と舌打ちした。
土光関係の書籍の多くは菊次郎の一周忌の席で、登美がいきなり学校創設を言いだしたように記している。けれども親族の証言や資料を突き合わせると、登美は、かなり早い段階で、遅くとも獅子ヶ谷を終の住処と決めたときには女学校開校を思い描いていたふしがある。土光敏夫は登美の追悼集『たちばなのかおり』に「母を思う」と題して、こう記す。
「母が女学校を創設したいと決心したのは、何年頃か私にははっきりしないが、母が東京で暮らす日が多くなった昭和十二、十三年頃からかと思う。当時の信仰のない女子教育に不満をもつようになって、それを口にすることが多くなった。そしてだんだん女学校を創める決心に移って行ったようである。そして私に協力を求めるようになった。当時、私は自分の専門の仕事に熱中して、夜昼なくそれに没頭していて、時間的にも気分的にもまったく余裕がなかったので、強くこれに反対していた。
私に協力をすすめることが無駄であると考えてから、母は独力でこれをやろうと決心したようである。やがて獅子ヶ谷の丘に居を構えて、ここを学校の位置に選定してからの母の動きは実に激しいものであった」
菊次郎の一周忌よりも前に、敏夫は母から内々に学校創設の相談を受け、拒絶していたものと考えられる。登美は、娘の節子と美子を通して「まこと会」にも十周年の記念事業で学校創設を持ちかけている。こちらも話は進まなかった。登美は夫の一周忌の席で、突然、思いついたわけではなく、ずっと胸の奥に抱いていた悲願を吐露したのであろう。
敏夫の賛同を得られなかった登美は、独力で獅子ヶ谷周辺の地主と交渉し、女学校用地の借地を広げる。「そなた(あなた)は天皇陛下に次ぐご身分だ」と地主を持ち上げ、「世のため人のため」「わたしが亡くなって香典をくださるなら、学校のために必要ですからいまください」と早朝から地主を口説いて回った。その気魄は凄まじく、鬼気迫るものがあった。地主が了解しても小作人が承諾しなければ借地契約を結べない。登美は小作人の作料は一切値切らず、気前よく払った。あまりに調子がいいので、あの婆さんは「女山師ではないか」と噂が立った。ただし相手が地主の場合は精いっぱい値切ったので、この噂は消えた。
 登美は、8人の地主から1万320坪もの土地を借りた。ひと月の賃借料は坪当たり7銭。つごう722円になる。ちなみに東京の長屋形式(6畳、4畳半、3畳、台所、洗面所)の借家の賃料は月13円だった(『値段の明治大正昭和風俗史』下、週刊朝日編集部編)。毎月、長屋56軒分の家賃を負担する計算だ。さらに建物を用意し、教師を雇わねばならない。誰の目にも無謀な挑戦と映った。(写真:橘学苑の最初の校舎〈昭和18年〉)
登美は、8人の地主から1万320坪もの土地を借りた。ひと月の賃借料は坪当たり7銭。つごう722円になる。ちなみに東京の長屋形式(6畳、4畳半、3畳、台所、洗面所)の借家の賃料は月13円だった(『値段の明治大正昭和風俗史』下、週刊朝日編集部編)。毎月、長屋56軒分の家賃を負担する計算だ。さらに建物を用意し、教師を雇わねばならない。誰の目にも無謀な挑戦と映った。(写真:橘学苑の最初の校舎〈昭和18年〉)
何が70歳の登美を突き動かしたのか。戦争にのめり込む日本の「愚」に底知れぬ危うさを感じ、子を産む女性が目覚めれば「愚」の根が絶てる、と一大決心をした。一見遠回りでも女子をしっかり育てれば社会は変えられると判断した、ととらえるのは常識的だ。登美の原動力はそれだけではない。もっと具体的な反骨の素があったと私は思う。
それは、軍と政財官が結託した「国家主義」への嫌悪である。登美が明確な反戦思想を持っていたかどうかは定かではないが、国家がすべてに優先する集団主義には批判的なまなざしを向けていたと思われる。教師の人選にそれがうかがえる。登美は、女学校の初代校長に、日蓮宗の名刹、池上林昌寺の住職で立正大学の哲学教授だった加藤文輝を招いた。
加藤文輝は、日蓮宗教団内で、天皇本尊論を唱え、国家主義へと突き進むグループ「皇道仏教行道会」に敢然と反旗を翻す良識派だった。仏教界の戦争協力を分析する上で、敗戦直後に、戦場に若者を駆り立てた責任をとって自決する加藤の軌跡は重要な意味を帯びている。
12月8日未明、日本軍はハワイの真珠湾を攻撃し、アメリカとの戦争に突入した。先制攻撃の成功で、街は歓びにあふれているようだった。開戦布告とともに電車や公共施設など至るところに国威発揚の広告文が張りだされる。
が、しかし、作家の永井荷風は『断腸亭日乗』に12月12日付で、こう記した。
「......広告文を見るに、屠れ英米われらの敵だ、進め一億火の玉だ、とあり。▼ある人戯れにこれをもじり、むかし米英我らの師、困る億兆火の車、とかきて路傍の共同便処に貼りしという」(原文旧仮名、句読点なし)
民衆は「これはおかしい」と陰ながら批判する意識をまだ持っていた。日蓮宗教団内での加藤文輝の国家統制派への反発も、そのひとつの現れといえるだろう。
登美は、加藤や白土菊枝を巻き込んで女学校「橘学苑」の創設へと全精力をふりしぼる。