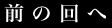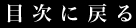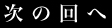第4回
戦争と初代校長
全体主義は、人びとの心を縛り、国や民族を神聖化して国民を一方向へと動かす。そのためには文化の基盤である思想、信条までも統制する。土光家が深く帰依していた法華信仰も、統制の荒波をかぶった。そこを抜きに土光が受け継いだ精神的な核は語れない。軍国化の時代状況をふり返り、統制の実態へと筆を進めよう。
1936年2月26日、陸軍の青年将校は、天皇親政をめざし、「昭和維新」と称して軍事クーデターを起こした。だが、昭和天皇は「速やかに暴徒を鎮圧せよ」と討伐命令を下す。後に天皇は、断固たる処置を採らなければ「金融方面の悪影響」でパニックが生じるという大蔵大臣の上奏を受け、「強硬に討伐命令を出す事が出来た」(『昭和天皇独白録』文春文庫)とふり返っている。天皇の態度は、はっきりしていた。軍が「叛軍の首領三人が自決するから検視の者を遣わされたい」と温情をかけてほしいと求めてくると、きっぱり断った。天皇は、斎藤実内大臣、高橋是清蔵相、渡辺錠太郎陸軍教育総監ら、「朕が股肱の臣(もっとも頼りとする家臣)」を殺した青年将校に憤激した。強い意志で決起者を叛軍と断じ、鎮圧を命じている。
ところが軍の最高幹部は叛乱将校に天皇の怒りを伝えるどころか、曖昧な物言いで幕引きを図る。青年将校と民間人17人が処刑されたが、テロの恐怖が社会を覆った。叛乱の鎮圧後、国民の厳しい視線を向けられた軍は、多くの将軍や将校を退役させる。内部で「二・二六事件」に関わった「皇道派」を切り捨てた。軍紀粛正を進めながらも、軍部は、これを転機ととらえ、「深く自省はするが、青年将校を駆ってここに至らしめたる国家の現状は大いに是正を要する」と開き直り、国政一新、軍備の拡充を要求し、日中戦争へと踏み込んでいった。
その思想的な柱とされたのが、天皇を統治の主権者とする「国体」観念であった。37年に文部省が編纂した「国体の本義」には「天皇は......現御神(あきつみかみ)として肇国(ちょうこく、国を開くこと)以来の大義にしたがって、この国をしろしめし(お治め)給う」と明記された。軍人に「神」と崇められることに天皇自身は、こう反論している。
「私を神だと云うから、私は普通の人間と人体の構造が同じだから神ではない。そういう事を云われては迷惑だと云った事がある」(『昭和天皇独白録』)
しかし、軍部を恐れる政府、官僚機構は、思想統制を強めていく。39年に東京地方裁判所の思想担当検事・斎藤三郎が作成した内部資料「右翼思想犯罪事件の綜合的研究」は、勢いづく国家革新グループについて「いわゆる反動団体と呼ばれ、あるいは『ファッショ』『右翼』『国家主義』団体と呼ばれたのであったが、これらの名称はいずれもこれら諸団体の指導精神の一斑をとらえたに過ぎない」と断定。集団の真の念願からすれば、「日本主義運動、日本主義団体」の名でよばれるべきだと結論づける。それではあまりに曖昧で、不明確だとする見方に対して、斎藤はこう記す。
「日本精神または日本主義は仏教、儒教、基督教のごとく個人の思想を祖述したものではなく、日本民族の悠久なる歴史とともに発展したものであり、その深遠なる根拠を国体及び国民性の中に求めねばならぬものであるから、これを説く者の個性により内容を異にするのはむしろ自然の事とせねばならない」(『現代史資料4 国家主義運動1』みすず書房)
「説く者の個性」で内容が違っても「自然」となれば、それを客観的に理解するのは不可能になる。もはや論理を超えている。
「日本主義はこれを理屈によって解釈すべきではなく、直観によってこれを体得しなければならぬとの論は、(中略)一面の真理を主張するものとせらるる」
「日本主義の特色の第一はまずその国体観念に現れる」
と、斎藤は書いた。国家権力に最も忠実な検事の文章だけに背筋がうすら寒くなる。
ナショナリズムの縛りは、庶民の信仰にも及ぶ。日蓮宗教団内では、時流に棹さす「天皇本尊論(最も大切な信仰の対象は仏教開祖の釈迦ではなく、天皇)」と、伝統的な「法主国従論(仏法が主で、国家体制はそれを実現させるための従)」が衝突した。内部抗争に文部官僚が圧力を加え、やがて宗教界全体の統制へと日蓮宗は呑み込まれていく。
*
土光登美は、抗争の当事者だった僧侶、加藤文輝を、女学校の初代校長に迎えている。なぜ、登美は加藤に大切な女子教育を託そうと考えたのだろうか。息子の敏夫に受け継がれる精神の核を探って、日蓮宗内の対立と統制の経緯を追ってみよう。
発端は、1938年4月、日蓮宗僧侶の高佐日煌貫長を中心とする身延山久遠寺での「皇道仏教行道会(こうどうぶっきょうぎょうどうかい)」の設立にさかのぼる。1896年に奈良県五条市の旧家に生まれた高佐は、生家の没落により7歳で日蓮宗寺院に引き取られ、16歳で出家得度をしたという(ホームページ「現代教学の検証 第1回 高佐日煌の教学(1)」善龍寺住職・澁澤光紀)。
その後、高佐は朝鮮釜山の寺の婿養子となり、「朝鮮キネマ株式会社」を立ち上げて、日蓮宗の伝道映画を上映する。事業意欲は旺盛だったようだが、映画会社は倒産。釜山を去り、日本に戻ると、横浜の日刊紙や伝道雑誌「日蓮主義」の編集長を務めたという。
実社会でもまれた高佐が唱える皇道仏教は、「万世一系の天皇陛下」を本尊と唱えた。日蓮宗で極めて重要な曼荼羅については、「本仏果海の十界当祖ではなくて、日本国民が天皇陛下の御稜威(みいづ、威光)を奉戴して分担精勤する諸職業であります」(『皇道仏教行道会の宗義』「現代教学の検証 第1回」より)と述べる。つまり天皇のもとに一体となって国民が働く姿が日本国体の曼荼羅の容態だという。非常に現世的で、国体思想に沿った宗義といえよう。
高佐ら行道会のメンバーは、日蓮宗内の皇道仏教化をめざして活発に動きだした。
「南無妙法蓮華経は、神人の霊通する神秘の音である。これを言霊という。理屈ではない、法悦の極地において心霊の奥から鳴り渡る神の御音である」(『皇道仏教行道会講習摘録』皇道仏教行道会本部)
と、行道の実践を説く。「理屈ではない」は、前述の斎藤検事の日本主義に通じる。神秘現象への急傾斜に既視感を覚えるのは、われわれが現代に生きているからだろうか......。
39年8月、高佐は「中外日報」に「皇道仏教成立の概要」を三回にわたって連載した。これに対して日蓮宗内から「宗義を逸脱している」と批判の声が上がる。高佐は、すかさず反論し、宗教新聞に反論記事を載せた。
日蓮宗の最高指導者、望月日謙管長は、行道会の式典に、高佐らの活動を認めるような祝詞を託し、「皇道仏教」と墨書した六尺の大額を贈った。そのことで宗内に混乱が生じる。疑心が渦巻く10月11日、東京の池上林昌寺住職で、立正大学教授の加藤文輝は、宗門の運営を統括する宗務院当局に対して、行道会の教義や行事を公認しているのか、と伺書を出した。以下、その内容である。
「行道会の宗義行事は従来の祖師日蓮上人中心主義をしりぞけて日本国衛護曼荼羅を以て本尊となし、これに王仏冥合の教説を歪曲付会して天皇を信仰の中心となし、かかる見地より御宝前に祝詞を奏し拍手を打つ等宗内の秩序をみだり穏かならざるものありと思料せらるるが如何」
加藤は高佐より10歳ばかり年下だが、僧門の名刹に生まれている。その問いは峻烈であった。抗争は過熱する。背景には権力闘争も絡んでいた。皇道仏教行道会批判の波に乗じて、宗内の七大本山のうち四本山(本圀寺、妙顕寺、池上本門寺、法華経寺)の住職は連名で、行道会は宗門の公的団体ではないと各新聞に声明すること、高佐の宗義は不穏と思料されるので本人の宗内公職全部を罷免すること、といった要求を宗務院に突きつけた。本山側は「宗義擁護連盟」を結成し、加藤もここに加わった。
批判の高まりに行道会側は激烈に反応する。四本山を「国体明徴(天皇主権の国体を明らかにすること)への反逆者」とみなして「挙国一致の敵」と罵った。翌40年2月、高佐ら四名は、国家の官僚機構に訴える。文部大臣に上申書を出し、四大本山、宗務所長、大学教授らを「国体明徴の大義に背き重大時局下における宗教者の使命にもとり候」と断罪する。逆に宗義擁護連盟は高佐ら4名を「わが宗団を破壊せんとするもの」と非難し、「処断すべし」と宗務院当局に訴えた。
日蓮宗内の内紛は衆議院予算分科会でも採りあげられ、答弁に立った文部省宗務局長・松尾長造は「宗義上の問題であります。したがって私ども素人の容易に、ちょっと了解できない点もありまするし、特に宗派自体におきまして慎重に善処するよう只今注意を致しておる実情であります」と発言、文部省は宗派自体の問題として、宗務院に圧力をかけた。その結果、日蓮宗内に「宗綱審議会」が設けられ、そこで行道会と宗義擁護連盟がぶつかることになる。審議会の設置を、元日蓮宗現代宗教研究所所長・中濃教篤は、『戦時下の仏教』(国書刊行会)で、次のように解説している。
「この審議会設置ということは、これまで教学的には明らかに異端とされていた『天皇本尊論』なるものが、その異端性を脱却し、疑義の段階から検討の対象として市民権をうる段階へと歩を進めたということを物語る」
高佐らは、40年9月、立正大学学長はじめ6名の要人を「不敬罪」で警視庁に告発し、国家権力を導き入れようとした。翌月、告発は取り下げたが、太平洋戦争開戦後の42年4月にようやく抗争はおさまる。行道会は、警視庁特高第二課に「聖戦完遂のため」に「挙宗一体」となる「誓約書」を提出し、解散した。宗義擁護連盟もまた解かれた。
警視庁内には「天皇を本尊とし、ご利益を祈るのはかえって不敬ではないか」という意見もあった。天皇の威光を一宗一派で私物化することへの反発は、「説く者の個性により内容を異にする」日本主義の自己矛盾のひとつであろう。
かくして、「宗教団体法」(40年施行)のもとにあらゆる宗教の分派が統一され、教団は統制されていった。
*
土光登美は、行道会と激しいさや当てをくり広げる加藤文輝を、横浜鶴見に開校する女学校「橘学苑」の校長に招いた。加藤は校長就任を了承し、「橘女学校は仏教の学校です。子どもとはいえそれぞれ個性があります。頭がよいからといって、人間がすぐれているとは限りませんよ」と言った。登美は「どのお子さんにも入学していただきましょう」と無試験入学を決める。加藤は「女子教育は女子の手に委ねるべきだ」とも説く。そこで42年2月、登美は加藤と一緒に「まこと会」のリーダー白土菊枝を名古屋に訪ね、教育に加わってほしいと求めた。承諾を得るまでは帰らない、と登美は白土の家に一泊する。
後に白土が書きとめたところによれば、登美は白土をこう口説いている。
「日本はまた戦争を始めました。私はそう72歳でございます。いつ死んでもおかしくない年でございます。が、このまま何もしないで日蓮聖人のお前に行って、大聖人から、この日本のはじめた戦争にたいして何をしてきたかと聞かれて、何もしませんでした、とお答えするわけにはまいりません。そこで何ができるかと考えました。
どんなに偉い学者でも赤ちゃんのときはみんな、その母に抱かれてその乳を吸って育ちます。母が赤ん坊をむつきのうちから戦争などしないような人間に育つよう教えることで、正しい智慧を働かせる人間を世に送ることになるでしょう。女子教育をするのです」(「校主先生と橘学苑」『橘の教育探究50年』橘学苑)
白土は、橘学苑に教師として加わった。満州時代にお手伝いの少女を育てあげた話を書いたベストセラー『満洲人の少女』(月刊満洲社)の印税を、事業資金として寄付をする。42年春、28名の女子生徒が入学し、橘学苑はスタートした。加藤は大政翼賛会の理事にも名を連ねていた。43年秋、加藤は宣撫班の班長として中国へ赴いた。登美が校長に就任する。
加藤は、大陸で軍隊とともに動き、日本語教育などに携わった。だが、宿痾(しゅくあ)ともいえる結核を患い、帰国を余儀なくされる。加藤は「病む防人の詩」という詩を雑誌に投稿した。
大君の われは防人 幾山河 越えてきつるも 胸病みて ふたたびたたず 肇国ゆ
ことし多けれ この秋ぞ 国は危うし 太刀撫ぜて ひさも嘆けど 肉のおき
痺く枯れたる 術なかりけり (「言論報国」1944年11月発行)
加藤が病床に伏していたころ、高佐貫長は意気軒高であった。著書『国体信仰講座』を行道文庫から発行し、「行道塾」という活動を敗戦まで続ける。戦後、しばらく沈黙していたが、「十字仏教聖徒団」なるものを立ち上げ、日蓮宗内で復権していく。
登美は、首都圏の空襲が一段と激しくなった45年4月、題目を唱える家族に見送られて黄泉へと旅立った。8月15日、日本は敗戦を受け入れ、「帝国」は滅んだ。翌日、加藤は「若者を戦地へ送った責任」をとって服毒自殺した。天皇は自ら現人神ではないと否定し、「人間宣言」を行うが、威光を借りて思想統制をした官民の責任はかき消された。
橘学苑の碑には、登美が学校創立の精神とした言葉が刻まれている。
「正しきものは強くあれ」
「正しきもの」とはどのような人間か、「強くあれ」の強さとは何か......。登美は加藤が肺を病んでいることは知っていただろう。まさか自害するとは予想していなかったにしても、正しきものこそ強くあれと願った背景に加藤への思いを私は感じる。それは一個人への励ましというよりは、加藤的存在への普遍的なメッセージである。
*
土光敏夫は、こうして母が命をかけて残した女学校を受け継いだ。土光は、国家統制から開戦、敗戦に至る1936年から45年にかけて、働き盛りの40代を送っている。電力を国に管理され、産業が統制された状態で、発電用タービンの製造や軍と連携したジェットエンジンの開発、信州への工場疎開などで奔(はし)り回っており、とても信仰を顧みる余裕はなかった。しかし、52歳だった48年、第四代校長に就任した。この年、新入生はわずか8名だった。橘学苑はもうすぐ潰れる、と噂されていた。体を張って学校を背負わねばならない、と覚悟を決めていた。
校長となった土光は、戦後の混乱で離れかけていた白土菊枝を改めて仏教を教える講師として呼び戻した。そこには母や加藤に連なるある種の決意が感じられる。土光は、朝晩、決まって法華経を唱えた。後年、その目的をこう語っている。
「ぼくは安眠しないと次の日、動けない。そしてあくる朝起きたら、『きょうはもう少し、本気でやりますから......』と手を合わせる。ぼくみたいな凡人が生きていくには、精神の安定がいるわけです。つまり、お経をあげるのは、気持ちの上での区切りをつけることなんだ。過ぎ去った一日に過ちはなかったか。あるいはこれから迎える一日を正しく送れるかと。(略)あくまで自分の心の問題――安心ですよ。結局、自分のためなんだからね」(『日々に新た――わが心を語る』東洋経済新報社)
土光は、教団や宗教関係の団体からどれほど熱心に講演を依頼されても、決して引き受けなかったという。「個」の心の領域に集団、あるいは「公」の力が及ぶのを忌避したといえるだろう。