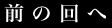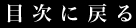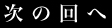第6回
解体から復興へ──石川島再建に懸ける
いま、「産業の血液」といわれる電力の供給体制が、戦後のGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の「ポツダム指令」による9電力体制への再編成以来、60年ぶりの大転換期を迎えている。昨年3月の東京電力福島第一原発事故を受けて、政府は「脱原子力依存」を宣言。2030年時点での原発の発電依存率を「0%」「15%」「20~25%」のいずれにすればいいか、と国民的議論を呼びかけている。
日本が脱原発を選択できるか否かは重要なテーマではあるが、並行して「電力自由化」が再生可能エネルギーの導入に合わせて急速に進行中だということを、ここでは強調しておきたい。電力自由化は、日本の将来を左右する重大な意味をもっている。
つい先日、経済産業省は「2014年に発電と送電を分離する」と決めた。この発送電分離によって、9電力会社(沖縄を入れれば10電力会社)がそれぞれ発電し、自らの送電網を使って電力を送り、配電して売る「地域独占体制」が解体される。電力会社が所有する発電部門と送電部門は切り離され、送電部門は広域をカバーする中立性の高い機関に変身。発電分野には新たな企業や団体が自由に参入してくる。その新規参入者も、従来の電力会社と同じように送電網を使える。電力の小売り部門も自由化され、消費者は、自分の好みに合った電力会社の電気を買えるようになる。
と、シナリオどおりに進めば、日本の電力供給体制は大きく様変わりをするだろう。ただし、自由化が成功するか否かは、新規参入の規模にかかっている。新規参入が少ないと実態的な独占が続き、自由化で電気料金が急上昇する恐れもある。既得権の壁を崩せるかどうかは、新たな競争者の参入にかかっているのである。
ふり返れば、戦時中、全国の発電と送電は国家統制で「日本発送電(日発)」という官主体の特殊会社に独占されていた。電力国家管理法によって、軍部と官僚が電力を牛耳り、それを起点に「国家総動員」体制が敷かれた。敗戦後、日本の新たな支配者となったGHQは、軍国の産業体制と、強力な労働組合「日本電気産業労働組合協議会(電産協)」の解体を狙って、日発を分割し再編成するよう、日本政府に指示した。
しかし、官僚とその傍で既得権の恩恵に浴する電力関係者は、日発の分割に異を唱える。壮絶な権力闘争のはてに日発は潰され、9電力体制ができあがった。
石川島重工の社長に就任した土光敏夫は、そうした時代の風を真正面から受けながら、「解体から復興」へと社業に打ち込んだ。官から民への転換で9電力が生まれると、重電の雄、石川島はタービンやボイラー技術を駆使して、電力事業に食い込んだ。
その後、全国の電力各社は地方を牛耳る"9頭の恐竜"に変わっていく。官であれ、民であれ、独占体の水は澱む。電力界の首座を占めていた東京電力は原発事故を引き起こし、ふたたび解体の風を呼び込んでいる。いままた産業界は「解体から復興」の難題に直面し、壮大なスクラップ・アンド・ビルドの気配がたちこめる。歴史は反復するという。
かつて「解体から復興」への時代の風にさらされた土光は、そのとき、何を思い、どう動いたのだろうか......。
*
1950(昭和25)年初夏、横浜市鶴見の石川島芝浦タービンでは役員会が開かれていた。
前年、デトロイト銀行頭取、ジョセフ・ドッジが勧告した財政金融引き締め政策「ドッジ・ライン」は、日本経済を不況のどん底につき落とした。1ドル=360円の単一為替レートが設定されたものの、輸出は振るわない。石川島芝浦タービンは、鶴見工場と木曽工場を残し、松本工場を石川島芝浦機械へ、辰野と伊奈の工場は芝浦ミシンに民需転換し、やっと再出発したばかりだった。
土光は持ち前の大声で役員たちを鼓舞していた。すると、いきなり会議室のドアが開き、石川島重工の笠原逸二社長が入ってきた。親会社のトップの突然の来訪に驚く間もなく、
「土光君、きみはちょっと廊下へ出て行ってくれんかね」
と、会議室から追い出された。とうとう来たか、と土光は観念した。
石川島重工は、そのころ、1億円以上の赤字を抱えて喘いでいた。戦後、資本金1億円で再出発した石川島は、農機具や鍋、釜の製造で辛うじて従業員の生活を支えた。海外からの兵士の復員や邦人の引き揚げに船が不可欠となり、GHQも小型の戦時標準船の建造作業の継続や、傷んだ船舶の修理を認めた。ようやく船台に槌音が戻ったのもつかの間、石川島重工は財閥解体の「過度経済力集中排除法」の指定を受け、東京3工場の分割を命じられる。石川島側は3工場が地理的にも技術的、経済的にも一体だと訴え、なんとか指定解除を勝ちとるが、この年、大インフレで、受注した戦時標準船の船底を二重にする改造工事が大赤字を出した。
国家予算が1兆円の時代である。1億円超の赤字は、首脳陣を一新するには十分な重みがあった。重工の新社長候補に土光が入った、と噂は立っていたが、タービン社内では「絶対に土光は出さぬ」と衆議一決した。そこでたまりかねた笠原社長が直々に役員を口説きにきたのだ。役員の連帯は脆くも崩されてしまう。
こうして、土光は「しょっぴかれるようにして、本社の社長に据えられた」(「私の履歴書」土光敏夫)のである。
1950年6月24日、土光は、石川島重工の社長の椅子に座った。鶴見から連れていった部下は経理の担当者だけだった。業績が悪化し、給料の遅配が続き、労使紛争が絶えない石川島に土光は裸同然で乗り込んだ。タービンの退職金の全額を投じて、土光は、石川島重工の株を求めた。家族は多く、母が遺した橘学苑の経営にも資金は必要だ。しかし土光は退職金をすべてはたいて、株価31円、32円と低迷する自社株を買っている。
「石川島と心中する覚悟だった」といわれる。
会社の再建には人心を一新しなくてはならない。土光は旧役員に辞職を求める一方で、若手3人の役員には残るよう促した。そのなかに田口連三という、土光と同じ設計部出身の鼻っ柱の強い男がいた。田口は土光の十年後輩だ。土光新社長に「きみは残ってくれ」と言われた田口は、「私一人のこれといわれても応じかねる。もともとイヤだったのだからもうやめる」と突っぱねる(「私の履歴書」田口連三)。土光も「残れ」と折れない。
そこで田口は二つの条件を出した。その一、代表権は社長だけが持ち、他の役員は専務も常務もなく、平取締役とする。その二、部長職より上の5人の月給について、その平均値を出し、それを役員給与とする。ただし、社長は別。経営責任は社長が全面的に負い、役員は先輩、後輩なく、横並びに、という案だ。従来の石川島の慣習に照らせば、とても承諾できる話ではない。組織秩序の大改革ともいえる。
ところが、土光は、
「わかった、のむ」
と、受け入れたのだった。
「明治人」の土光は、怒声を張り上げ、俺についてこいと剛腕で周りを引っ張るタイプのように思われがちだが、じつはそうではない。後年、経団連(日本経済団体連合会)会長に就任した土光に7年間秘書として仕えた居林次雄(いばやしつぎお)は言う。
「土光さんの猛烈会長ぶりは、それまでの歴代の経団連会長にはない迫力がありました。部下が、その場しのぎの取りつくろいをしようものなら、雷が落ちた。反応が遅くても叱られる。でも、基本的に他人の話をじっくり聞く人でした。物事を決めるときは議論を尽くし、非常に民主的に決定を下しましたよ。全然、独裁ではありませんでした」土光は、石川島の社長に就いたころにはもう「聞く耳」を持っていたようだ。二つの条件をあっさりと受け入れられた田口は、社長を支えようと頭を切り替える。
「社長、あなたは設計、生産、管理の方を重点的に見て下さい。営業は私が全責任をとる。みんながふうふう言うほど、注文を取ってあげます」と大見得を切る。田口は国家の経済政策と民間企業の膨大な経済データを、社内の総力をあげて集めた。そのうえで石川島の受注可能な目標数値(ノルマ)を各課別に細かくはじき出し、割り当てる。他社に先がけて「目標管理」の手法を採り入れた。
田口は、服装に頓着せず、裏地がボロボロの古ぼけた背広ばかり着ている土光に、
「社長、いくらなんでもこれでは困ります。いくら貧乏でも、貧乏くさい格好をしたら銀行あたりで信用してくれない。会社は注文をくれない。人間とはそんなものです」
と、ずけずけ言う。「きみのおかげで、背広を四着も注文させられたよ」とぼやきながらも土光は忠告を受け入れる。土光と田口のコンビは、絶妙の呼吸で会社をけん引する。
時代の歯車も、土光社長を押し上げた。社長就任の翌日、朝鮮半島の北緯38度線で北朝鮮軍が砲撃を始めた。その30分後、北朝鮮軍約10万の兵士が38度線を越える。東西の冷戦が熱い戦いに転じ、「朝鮮戦争」が勃発した。
日本国内の基地を出撃や後方支援の拠点にしたアメリカ軍は、船舶や輸送車両の修理、武器、弾薬の補給、製造を日本企業に発注する。そこから工業生産は上向いた。いわゆる「朝鮮特需」で日本経済は勢いづいた。造船需要も拡大し、石川島は、朝鮮戦争の間に、1万トン級6隻、8000トン級2隻の船を受注している。
1951年1月4日、早朝出勤が習慣化している土光は、会社の門の前に立ち、仕事始めで出社してくる社員たちにできたばかりの「社内報」を配った。社長自身が社内報を社員に手渡すなど石川島創業以来の椿事である。社員は目を丸くしながら社内報を受け取る。
その「年頭の挨拶」に、土光はこう記した。
「1951年を迎えていよいよ第20世紀の後半に入りましたが、待望の世界平和はますます遠い感を深くしております。朝鮮動乱によって米ソの関係はいっそう緊迫の度を加え、米国の非常事態宣言に続いて、西欧州の統一軍編制と世界は挙げて軍拡時代に入りました。終戦以来5年ようやく社会秩序と生活の安定を築きかけた日本にとって、この新しい年はなかなか重大な年であり、従って、わが社にとっても厳しい試練の年であります」日本海の向こうで戦争がつづく緊張感が伝わってくる。景気が好転したとはいえ、米ソの角逐が激化すれば世界を二分する大戦争に突入するかもしれない。ソ連に対抗して資本主義体制を守りたいアメリカは、日本に「反共の防波堤」の役割を課した。自衛隊の前身である警察予備隊が創設され、レッド・パージが強行される。その渦中で、日本発送電を9電力に解体する大手術が行われたのだった。
*
当時、日発の解体には、国家管理を信奉する左翼の野党はもちろん、首相の吉田茂を支える与党、自由党内でも大野伴睦(ばんぼく)や河野一郎ら実力者たちも反対していた。発電と送電を独占する巨大企業は政治家の資金源だったといわれる。日発を覆う殻は石のように硬い。
そこにくさびを打ち込んだのは「電力の鬼」の異名をとる明治人、松永安佐エ門と、東京電燈の生え抜きの木川田一隆(のちの東京電力社長)、政界では一年生議員で大蔵大臣を任された池田勇人の三人だった。松永は木川田を秘書役に使って、GHQ顧問で大きな権限を握っていたT.O.ケネディに近づく。根っからの自由主義者の松永が日発の解体・9電力分割案を説くと、ケネディは納得した。裏で「闇の金」が動いたともいわれる。
ケネディは松永と池田勇人をつなぐ。政府は、法律改正に向けて「電気事業再編成審議会」を設け、松永は会長に選ばれる。しかし他の委員は「基幹産業は国家が統制すべき」と論陣を張る。70歳をとうに越えていた松永は、委員を子ども扱いして罵倒する。
「戦時中は官僚にあごでつかわれ、いまは占領軍に鞠躬如(きっきゅうじょ/身をかがめて)として、目も鼻も口もないばけものだ」(「私の履歴書」木川田一隆)独立独歩で実業界をのし歩いてきた松永には、統制に甘んじる連中が情けなくて仕方なかった。審議会で孤立しても、「こういうものに多数決は存在しない」の一点張りで押し通す。大蔵大臣の池田は通産大臣を兼任し、松永の9電力分割案を含む日発解体案を国会に提出した。だが、国会議員の反応は鈍い。再編成案は審議未了に持ち込まれてしまう。
万事休したかにみえた。ところが、1950年11月22日、GHQは超法規的なポツダム政令「電気事業再編成令」「公益事業令」を発し、再編問題に終止符を打ったのである。
その後、最後の日発総裁に就任した小坂順造が松永と激しいさや当てをくり返したが、GHQの強権が発動された以上、9電力への分割は避けられない。日発は解体され、51年5月に民営9電力体制がスタートしたのであった。
電力界の官から民への転換は、重電各社を海外へと向かわせた。重電の首脳たちは、電力を含む産業技術の最先端に触れようとした。石川島の土光社長は、51年の暮れに羽田を発ち、17年ぶりにアメリカ各地を見て回り、ひと月を過ごしている。
その印象を社内報に、こう書いた。
「アメリカは、17年以前と当然ながら非常に変わっていた。第一に国家的形態が整ってきた。よくよく米国は歴史が新しいうえに、各州のモンロー主義のために、国といっても性質が変わっていたが、二度の大戦を経、ことに今次大戦では連合国の主役を演ずることとなり、戦後は自由国家群の主導力として大きな責任を負うこと等から、孤立主義を捨て国家的形態も整えられたと思う。同じ社内報で、新入社員には、次のように檄を飛ばす。
次に圧倒されるばかりの、大きな経済機構の目まぐるしい動きである。経済活動は夜も停まらない。工場は三交替、少なくとも二交替で、GEの工場を訪れたとき、午前3時にホテルの窓から見ると、トラックも乗用車も昼と変わりなく動いていた。その生産力は驚くべきものがある」(「石川島」1954年4月1日発行)
「......戦後のわが国情は、狭い国土と乏しい資源を以って、近い将来に1億を超す人口を養わねばならぬ状況にある。これは何とも仕方ない。いわば宿命である。ここにおいて、この人口を養う途は、産業、わけても高度の機械工業を興す以外にはない。(略)われわれは消極的態度を捨てて、唯一の資源ともいうべき人間を、大いに活用する研究と努力を尽くすべきである」(前同)その文面には、明治人特有の「国を背負う」気概がみなぎっている。国といっても官僚が好んで使う「国家」ではなく、生身の人間が集まって暮らす「くに」である。