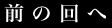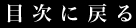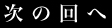第7回
活況のなかで起きた「造船疑獄」
霞が関の中央合同庁舎第6号館は、一般に「検察合同庁舎」と呼ばれている。法務省系の省庁や機関が入る、地上20~21階建てABCの三つの棟は、低層部でつながり、重厚な外観を呈する。「巨悪」と対峙する東京地検特別捜査部も、この建物のなかにある。
東京地検特捜部の設置は、旧日本軍が本土決戦用に蓄えた軍需物資や接収したダイヤモンドなどの貴金属類を、フィクサーの辻嘉六らが闇ルートで処分した「隠退蔵物資事件」の捜査に端を発している。終戦前日の1945年8月14日、当時の鈴木貫太郎内閣は、総額2400億円相当(現在の数十兆円)ともいわれる膨大な軍需物資を、米軍に接収される前に安く民間に払い下げる法案を閣議決定した。ところが、その隠退蔵物資は正式に払い下げられる前に軍人や官僚、政治家を介して横流しされ、忽然と消えた。辻らが得たカネは、鳩山一郎や河野一郎らに渡り、自由党結党の資金に化けたという。
進駐してきたGHQは、隠されている旧日本軍の物資を自らの管理下に置こうと考え、東京地検に「隠退蔵物資事件捜査部」を新設させた。これが特捜部の始まりである。
とかくメディアは、「正義の特捜」と「巨悪の政界」の対立を煽り、特捜部は次々と汚職を摘発。その出自のせいか、特捜のエリートには駐米大使館の一等書記官経験者が多かった。
ただし、こんにちでは「正義の特捜」対「巨悪の政界」の図式が世論誘導の手段であることが徐々に明らかになっている。捜査段階での検事による証拠改ざん、供述調書の虚偽記載......と不祥事が続き、「正義」の看板は色あせてきた。政治的思惑による「国策捜査」も珍しくはなく、対立図式そのものが虚構と唱える声も大きくなっている。
特捜部は、歳月を経て変質したのだろうか。
いや、必ずしもそうではない。「正義の特捜」対「巨悪の政界」の図式は、日本の独立回復間もない1954年に起きた贈収賄事件を機に強調されるようになった。それは、土光敏夫も巻き込まれた「造船疑獄」である。政官財の逮捕者71名、そのうち34名が起訴され、17名が執行猶予付き有罪判決を受けている。
日本造船工業会副会長だった土光は、吉田茂総理の秘蔵っ子で自由党の幹事長、佐藤栄作(のちに首相)への贈賄に絡む特別背任容疑で逮捕された。検事総長は、法務大臣の犬養健に佐藤の逮捕請求許可を求める。だが、犬養法相は「指揮権」を発動し、国会の重要法案の審議停滞などを理由に佐藤逮捕を見送らせた。
この指揮権発動で「検察が政治に屈服した」とメディアは書き立て、「正義の特捜」、「巨悪の政界」という二項対立が定番化されたのである。
しかしながら、造船疑獄の経緯が詳(つまび)らかになるにつれ、指揮権発動は、政府と検察の単なる衝突ではなかったことが判明している。指揮権発動は、特捜部の強引な筋立てを危惧した検察幹部が政界に持ちかけて行われていた。強制捜査を止めるための苦肉の策だったようだ。暴走しがちな遺伝子を持つ特捜部を検察幹部が抑え込むという側面もあった。
政治とカネの問題は、権力に巣くう業病だ。その激しい発作といえる造船疑獄の渦中で、土光はいかにも土光らしくふるまった。もちろん、土光が墓の中まで持っていった秘密もあるのだろうが、取り調べた検事が舌を巻くほど、土光らしさを貫いている。
*
1952(昭和27)年3月8日、土光は、待ちに待った報せを受けて喜んだ。サンフランシスコ講和条約の発効を50日後に控えて、GHQは、航空機、兵器の製造許可を日本政府に指令した。それを受け、政府は政令を改正し、航空機の研究や生産を許可できるようになったのだ。4月26日、独立を回復する2日前、航空機関連工場314件と航空機25機、兵器研究所を含む850件の旧軍需工場が、米軍から日本側に返還された。
これで大手を振ってジェットエンジンの研究開発を再開できる。戦時中、陸軍の「火龍(かりゅう)」に搭載する「ネ130」の開発に携わった土光にとって、ジェットエンジン開発の再出発は、生き別れたわが子と再会したように嬉しかった。
ただ日本が研究開発を禁じられていた7年の空白期間に、世界の航空技術は長足の進歩を遂げていた。朝鮮戦争には、ソ連が旧ドイツの研究者を連れ帰って開発したミグ15と、アメリカが国力を傾けて開発したF86が、歴史上初めてジェット機どうしの空中戦をくり広げた。終戦前、木更津で特攻機「橘花(きっか)」に「ネ20」を積んで短時間の試験飛行しか成し得ていない日本と世界との差は、絶望的なほど広がっていた。
土光は、しかし彼我の差など眼中にない。石川島重工で航空機開発の準備を整える。各メーカーの代表による「ジェットエンジン研究合同委員会」が発足すると、旧海軍航空技術廠(空技廠)でネ20の開発に取り組んだ経験を持つ技術者や有望な若手技術者を委員会に送り込んだ。そのなかには東北大学を卒業して石川島に入社した長男の陽一郎も入っていた。
土光は、空技廠出身の技術者に、ある人物の入社勧誘を命じた。土光が白羽の矢を立てたのは、空技廠にその人ありと謳われた、ジェットエンジンの第一人者、永野治元海軍少佐だった。永野は、空技廠で師匠の種子島時休元海軍大佐と組んでネ20の開発をけん引した。全精力をジェットエンジンに注いだ永野は、戦後、燃え尽きたかのように気力を失い、家族を抱えて職を転々とした。九州の炭鉱にもぐり込んで石炭掘削機をつくるかと思えば、ミシンメーカーの技術開発に転じる。6回も職を替わり、その時は小松製作所の技術部長を務めていた。完璧主義者で、独特の「美学」を内に秘めた永野には、戦後の混乱は耐え難いものだった。何をする気力も失せた、と公言していた。
永野は、小松製作所を代表してジェットエンジン研究合同委員会の初会合に出席し、参会者の頭に冷水をぶっかけるような発言をしている。
「日本でジェットエンジンをやろうなんてむだなことだ。外国での進展状況や、すでに欧米のメーカーが大々的に進出して量産している現状からしても、いまからやっても日本ではできっこない。それに、日本の企業の実情や、政府の姿勢からしても無理だ」(『ジェットエンジンに取り憑かれた男』下、前間孝則、講談社+α文庫)
この永野を、土光はあえてスカウトした。そして、消えかけていた技術者魂を奮い立たせる。土光の「火の玉」のような闘志が永野に乗り移っていく。永野は記す。
「昭和二十七年は、日本の航空解禁の年でした。われわれの暮らしがただ夢中で生き延びていた姿から、何がしかの夢を追うところまでもち直し始めた時期でもありました。そんな年の暮近く、私は石川島に入社して技術部長となりました。当時石川島もやっと息をついている姿でしたが、土光新社長の下に小柄ながらも火の玉のような意欲に燃えていました」(IHI「しんらい運動ニュース」昭和52年3月20日号)永野入社の3年後、土光は、種子島元海軍大佐が日産ディーゼルを退社するのを待って、石川島の顧問に招聘する。空技廠を代表する頭脳を招き入れ、ジェットエンジン開発の先端を切り拓く決意を内外に示した。
土光の「空」への進出は次代をにらんだ挑戦だった。一方、「海」での事業拡大は会社の屋台骨の強化に直結した。そのころ、政府は、海運、造船を振興し、貿易の動脈を担う外国航路の再建に乗り出していた。年ごとに必要な船の建造計画を立て、必要な経費の一定比率に財政投融資を充てる「計画造船」が行われた。
1953年には、「外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法」が制定され、海運、造船への国家助成はさらに手厚くなった。造船各社は海運会社と組んで、一隻でも多く、計画造船の枠を確保しようとしのぎを削る。石川島重工の社内報「石川島」(昭和28年10月1日発行)は、「受注旺盛! 活況呈する造船部門」と題して、こうリポートしている。
「当社は七次(計画造船)船で香椎丸を受注したトランパー界の雄日鉄汽船一社と組んで、絶対不敗の態勢をもって臨んだ。その間、運輸省、開発銀行の両当局を始め、船主、造船所等適格船主の選考をめぐって活発な動きを示し、難航の末9月15日午後5時半ついに最後の断が下され、貨物船20隻(うち移民船1隻を含む)15万7千総トン、輸送船5隻、6万4千総トンの適格船主が運輸省から発表された。当社と組んだ日鉄汽船も悠々と適格の選に入ったことは同慶の至りにたえぬ次第である」土光は、日本造船工業会の副会長に就任し、業界全体のパイの拡大に打ち込んだ。会社にあっては、工場にたびたび足を運ぶ。昼間は仕事に没頭し、夜の8時から食堂の二階で労使交渉に臨んだ。土光は、身体を反り返らせ、タバコを濛々(もうもう)とふかしながら、テーブルを叩いて「企業が伸びるには、組合が強くなければダメだ」と持論をぶつ。組合員たちは「オヤジを落とせ」を合言葉に土光と談判をした。
1954年に入ると景気は一気に下降する。土光はグループ企業の立て直しのために東奔西走し、席の温まる間もなかった。
4月2日午前6時30分、いつものように土光は手提げ鞄をぶら下げて、鶴見の自宅前のバス停に立っていた。社長就任後も、通勤にはバスと電車を使った。バスで鶴見駅まで出て、国鉄の京浜線に乗り換えて通っていた。
道路の向かい側の停留所にバスが停まった。数人の男が慌しく下車し、土光の家に入っていった。おやっ? と、土光はいぶかった。
応対に出た妻の直子は「ご主人はいらっしゃいますか」と訊かれ、「いま出たばかりですから、まだバス停にいると思います」と言った。男たちは玄関で踵を返し、バス停へ急いだ。小雨がぱらつく停留所にスプリングコート姿の中年男がたたずんでいた。
「土光さんですか」
「はい、私が土光ですが......」
「ちょっとお宅まで戻ってください」
東京地検特捜部の検事たちは、そう言って、土光に帰宅をうながした。特捜部の検事は一時間半におよぶ家宅捜索の後、土光を「造船疑獄」に連なる特別背任容疑で逮捕した。土光は久しぶりに会社から呼び寄せた自動車に検事と同乗し、「安心しておいで」と家族に言い残し、東京地検へ向かった。東京地検は、赤レンガ造りの最高裁判所の裏側、弁護士会館前の古い4階建ての焼け残りビルに入っていた。土光の身柄は、取り調べのために東京小菅の拘置所南端、急ごしらえの木造二階建て「新南舎」に移された。
当時、船を新造すると船価の1%程度がリベートとして造船会社から海運会社へ割り戻されるのが慣例になっていた。これが裏金となって政界にばらまかれた。海運会社トップの逮捕から始まった造船疑獄は、収賄側の政治家の追及に移り、自由党の佐藤栄作幹事長にターゲットが絞られた。海運会社社長の供述から、佐藤幹事長は「利子補給及び損失補償法」を成立させた見返りに船主協会、造船工業会からそれぞれ1000万円、計2000万円を自由党に供与させた「第三者収賄」と、船会社から個人として200万円受け取った「受託収賄」の容疑をかけられた。土光の特別背任容疑は「第三者収賄」に関連している。
捜査の最前線にいた河井信太郎主任検事は、自著『検察読本』(商事法務研究会)に自由党幹事長の「S氏」は請願にきた船会社に対して、こう要求したと記している。
「よろしい、それじゃそういう法律案を自民党(ママ)でまとめてやろう。その代わりこの前の総選挙をやったときに自民党(同)に二〇〇〇万円の借金が残っているから、その二〇〇〇万円の金を持って来い。そうしたらこの法案を自民党でまとめて出してやる」河井検事は、4月14日未明、佐藤幹事長を極秘裏に任意で取り調べた。『佐藤栄作日記』第1巻(朝日新聞社)には、そのようすが、次のように書かれている。
「新聞社の諸君が囲いをといたのが(深夜)十二時半。それから検事正官舎に出かけ、河井検事の取調べを受く。(略)党寄附の船主協会並びに造船工業会のものは単純な政治資金寄附で法案とは関係なしと明記さる。然し選挙当時の幹事長借入八〇〇〇万円の内訳並びに此れが返済資金の内容は一切口外せぬと述べた。理由は困る人が出来るからとの事。而して河井君は、之は具体的に説明された方がよいとの事であったが、小生は申す考えなしと断る」検事と佐藤幹事長は激しい駆け引きを展開していた。
*
土光は、春とはいえ底冷えのする小菅の木造の新舎で伊藤栄樹検事の取り調べを受けた。土光の態度は真摯だった。伊藤は『秋霜烈日――検事総長の回想』(朝日新聞社)という著書で「これはまいった。実に立派な人だ」と感じさせられた被疑者の筆頭が土光だったと述べている。
「そのままでいいからといくらすすめても『お調べですから』といって、調べ室の入り口で襟巻をとり、机の前に姿勢を正して対座して、質問を待つのであった。質問に対しても、毅然として迎合せず、必要なことは的確に述べる。まことに立派な被疑者であった」20日間の拘留期間中、土光は壁に向かって法華経を唱えた。拘置所の他の収容者は、土光がどこの誰か知る由もなかったが、その姿を見て、いつの間にか「先生」と呼ぶようになった。政治家と業界の贈収賄の舞台は、赤坂の有名料亭だった。伊藤検事らは芸者十数人を調べ上げたが、土光の名前はついに出てこなかったという。
検察と佐藤の攻防の焦点は「第三者収賄」だ。マスメディアは「大上段に振りかぶった追及の仕方」と興奮気味に伝えているが、党への政治献金との違いを立証するのは困難だった。第三者収賄で佐藤個人が私腹を肥やしたともとれない。特捜部の暴走への懸念が検察上層部に広がった。検事総長は表面的には法務大臣の犬養健に佐藤の逮捕請求許可を求める。が、犬養はそれを退け、ついに指揮権を発動した。司直の手は佐藤に及ばなかった。
『指揮権発動――造船疑獄と戦後検察の確立』(渡邉文幸、信山社出版)は、指揮権発動を政治家に入れ知恵したのは内閣法制局長官の佐藤達夫だったと看破している。
「佐藤達夫が、指揮権発動の妙手を着想し、緒方副総理、吉田首相に提案した。真の知恵者として佐藤は、指揮書の理由まで考え出した。そして政府首脳と佐藤総長、馬場検事正の検察首脳、政治権力と検察権力との政治的妥協が図られたというのが真相とみられる」土光は不起訴となり、無罪放免された。土光の右腕、田口連三は、この年のクリスマスの夜に関係者と弁護士、総勢200人が集まってドンチャン騒ぎをして憂さを晴らしたと洩らしている。
とはいえ、造船疑獄は財界に大きな衝撃を与えた。もはや個々の企業が政治家に「つけ届け」をして、見返りを求める商習慣は通用しなくなった。経団連は「経済再建懇談会」という政治資金調達機関をつくり、そこが各企業から集めたお金を「自由経済の保険料」として自民党に献金するパターンを確立する。懇談会は、のちに国民協会、国民政治協会へと姿を変えていく。
後年、土光は経団連会長に就任し、政治献金の廃止を試みる。その思いは、小菅の拘置所で壁に向かって法華経を唱え続けたことに根ざしていたのかもしれない。