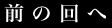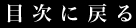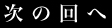第8回
ブラジル国家事業への参入――石川島の挑戦
日本のモノづくりは危機に直面している。少し前まで日本の「お家芸」といわれていた家電、テレビ部門では、中国、韓国に大きく差をつけられた。安い人件費と自国通貨安を武器とする両国に押されっぱなしだ。ロンドン五輪で金メダルがゼロだった男子柔道とどこか重なって見える。いつか日本が上った坂道を中国、韓国が駆け上がっている。
今後、東日本大震災の復興需要は見込まれるものの、欧州経済危機に直結する超円高、原発の縮小に伴う電力料金の値上げ、慢性化している後継者不足......と、製造業の前途には暗雲がたなびいている。日本が開発力と品質の確かさ、ブランド力で付加価値の高いモノをつくり続けるには、政府、金融機関、民間企業が縄張り意識や行きがかり的な事情を捨て、総力を結集しなくてはならないだろう。
そのためにも、いま一度、日本のモノづくりの土台が築かれた1950年代後半から60年代にかけての「突破力」を再確認しておきたい。あの時代、地方から都市に集中する「若く、安い労働力」を使って、日本は「アジアの工場」の地位を得た、といわれる。しかし、個々の企業の現場には、そうしたマクロの流れでは解決できない矛盾や壁が数多くあった。そこを突破して、創意工夫の企業文化が養われている。こんにちの製造業の不振を「栄枯盛衰」の四文字で片づけてしまうのはまだ早いと思う。
土光敏夫は、時代の突破者のひとりだった。
*
1958年12月11日、土光は、真冬の東京羽田空港を発ち、プロペラ機を乗り継いで76時間半、灼熱の太陽が照りつけるリオデジャネイロに降り立った。数年来、仕込んできた「石川島ブラジル造船所(イシブラス)」の建設計画が、やっとブラジル政府に承認され、定礎式に参加するために出張してきたのだった。62歳の土光は、長旅の疲れも見せず、先乗りで派遣され、ブラジル側との交渉に当たってきた社員たちをねぎらった。
それにしても、石川島重工のブラジル進出は途方もないプロジェクトだった。当時、石川島の資本基金は26億円。これに対して、イシブラスへの投資額は40億円。銀行筋は、「身のほどを知れ」と猛烈に反対した。
ブラジルは政情も不安定だった。軍部と自由主義者、大衆主義者(ポピュリスト)が激しく対立し、大統領と反対の立場をとるジャーナリストの暗殺未遂事件も起きていた。1954年8月には、軍部に辞任を強く求められたヴァルガス大統領は、次のような遺書を残してカテテ宮殿で自決した。
「またも、民衆の利益を脅かす諸勢力が結集して私に襲いかかってくる。(中略)私はブラジルの搾取にたいして闘った。民衆の搾取にたいして闘った。諸君にわが生命を与えた私は、いま私の死を捧げようと思う。何も心残りはない。私はいま永遠の道に向かって冷静な心で一歩を踏み出し、そして私は歴史に入っていく」(『概説ブラジル史』山田睦男編)
主力銀行の第一銀行はイシブラスの計画を知り、「狂気の進出計画」と反発した。マスメディアは「土光の愚行」と書き立てる。
土光は、銀行筋を説得した。財閥企業ではない石川島が成長するには海外拠点がどうしても必要なこと。ブラジルは鉄鉱石やボーキサイト、銅、原油やウランなど天然資源に富んでいるため、日本の資源確保に欠かせない存在であり、プラントを輸出すれば相互補完関係が深まること。日本とブラジルの間には、1908年以来の集団移民のつながりがあり、ブラジルには日系人社会が築かれていること。ブラジル南北の旅客や物資の移動は8000キロに及ぶ大西洋沿岸の海上輸送に頼っており、船舶需要は堅調であること......と、意を尽くして説いた。
土光には打ってきた布石への手ごたえもあった。石川島がブラジル相手に船の建造を請け負ったのは、1950年、「SALTE〈サルテ〉(S[saude]=健康、AL[alimento]=食糧、T[transporte]=輸送、E[energia]=エネルギーの開発)計画」に基づくタンカー3隻が最初だった。石川島はブラジル石油公社(ペトロブラス)にタンカーを納めた。53年には海軍省から軍用貨物船を2隻受注する。この船は、平時は大西洋岸の滞貨を運搬し、非常時に1800人の兵隊を運ぶ。従来のブラジルの船はディーゼルが主流だったが、これを機に石川島が得意とするタービンへとブラジル海軍は切り替える。
石川島が軍用貨物船を納入してしばらくした後、その船の評価を決する「事故」が起きた。船をリオ軍港に接岸する際、船員が目測を誤って岸壁に船首を激突させた。そのようすを社内報「石川島」(1955年10月1日発行)は、こう伝える。
「アンカーはチェーンが切れ海没。ブイのチェーンがシャフトに6回もからまってプロペラ翼一枚破損し、航行不能となってしまった」
この一報が入ったとき、船舶輸出部は「大変な損害だ」と緊張感に包まれた。ところが、「結果においては損害も少なく、修理工事も少なくすんだのでブラジル海軍は当社建造の船は頑丈で宜しいと益々評判を良くした」と社内報は記す。ブラジル海軍はさらに2隻の軍用貨物船を発注した。その後も大西洋岸の測量に携わる気象観測船を2隻、石川島は受注し、ブラジルとの関係を着実に固めていった。
もっとも土光自身、最初からブラジル進出を考えていたわけではない。すでにブラジルには1000社以上の国際的大企業が進出し、「世界の名店街」と呼ばれていたのに造船会社はひとつもなかった。何か落とし穴があるのではないかとブラジルを徹底的に調査させた。政治、経済、気候、風土と何十冊もの調査書が積み上がった。ブラジルの六法全書もすべて翻訳させている。それでも釈然としなかった。
慎重な姿勢を変えさせたのは、政治状況の変化だった。前述のヴァルガス亡きあと、選挙で大統領に選ばれたのは、チェコスロヴァキア系移民の家系に生まれたクビチェクだった。クビチェクは、経済発展が民族独立の条件と訴え、経済ナショナリズムを前面に押しだす。「50年の進歩を5年で」というスローガンを掲げた。本来50年かかる経済発展を大統領任期中の5年で達成すると宣言し、大胆な経済計画を立てる。
クビチェク大統領は、通信、エネルギー、道路インフラ開発などを「METAS〈メタス〉(目標)計画」にまとめ、これによって重工業を発展させる方策を採った。ブラジルに大規模公共投資開始の号砲が鳴り響く。クビチェクはブラジル平原のど真ん中に超近代的な首都ブラジリアを建設する計画をぶちあげ、政権引き継ぎ直後の1956年から60年の間に新首都を落成する。海運、造船の分野では「商船基金法」が発表された。外国船から入港税を徴収して特別会計とし、造船所と船主に低利で融資をする法律だ。造船のために策定された法律といってもいい。
これを機に、遠巻きに眺めていた世界の造船所が、一斉にブラジルへと群がったが、他に先がけて海軍やペトロブラスに船を納入してきた石川島は有利だった。他社の羨望を尻目にブラジル進出を確定したのである。
しかし一難去って、また一難。ブラジル国内で外国資本への反旗が翻った。その急先鋒はブラジル海員組合だった。石川島が進出してくれば、ブラジルの造船界は駆逐され、乗っ取られてしまうと警戒した。海員組合の全国大会では反イシブラスで衆議一決。スクラムを組んで石川島の進出を阻もうとした。
土光は重役をブラジルに遣り、懸命に海員組合への説得を重ねた。「イシブラスの社長はブラジル人であり、石川島は技術移転に全力を尽くす。イシブラスに何年か勤めれば、工員の技能水準は確実に高まる。数年でブラジルの造船能力はイギリスと肩を並べるだろう。石川島の進出はブラジルの国益にかなう」と懇々と説いた。この説得が奏功し、海員組合の反対論は沈静化した。
いくつもの難所を通過して、1958年12月13日の海軍記念日、新造船所イシブラスは定礎式を迎えたのだった。
*
朝からリオの夏らしい晴天が広がっていた。土光と石川島リオ事務所の社員十数名は、リオ港の造船所敷地へと自動車を走らせた。埠頭へ向かう道々、警官に何度も車を止められた。クビチェク大統領が定礎式に参列するとあって特別警戒態勢を敷いているのだ。が、警官は自動車のなかを覗いては「ああ、造船所へ行くのだな」と日本人の集団を簡単に通してくれた。「造船所」はすでに威光を放っていた。
リオ港の埠頭は、南端の海軍工廠を起点に、東北に向かって「コ」の字形に開いている。その一番北の端、建設中の鉄鉱石積み出し埠頭に、イシブラスの建設予定地は連なっていた。といっても、リオデジャネイロ港湾局の手で埋め立てられたのは敷地のごく一部で、大部分は海のままだった。水しぶきを上げて、漁師の子どもたちが楽しげに泳いでいる。
土光は、埋立地の白く輝く砂の上に立って、あたりを見回した。南には停泊中の船とリオ市中心街の高層建築のスカイライン越しに、突起物を伏せたような奇岩ポム・ヂ・アスーカルがそびえる。北側には水路を隔てて、大学都市のスマートなビルが並ぶ。すぐ背後には、佃島を想わせる漁師町が広がっていた。
造船工場が完成すれば、この明るくカラリとした風景は変わるだろう。「50年の進歩を5年で達成するには、これしかない」と土光は拳を握りしめた。
「さぁ、行こう」と土光はスタッフを促し、式典会場の古い造船所へと急いだ。
午前10時30分、クビチェク大統領が随員を従え、祝杯の準備が整った会場にやってきた。ブラスバンドがブラジル国歌を奏でる。大統領は、土光や安東義良駐ブラジル大使と親しげに握手を交わし、掲示された図面に視線をはわせた。土光が「南米一」の造船所の建設計画と事業の概要を説明すると、クビチェクはうんうんと頷いた。面長で細身のクビチェクと、角張った顔ががっしりとした体に載った土光、ふたりが並ぶとユーモラスなほど好対照だった。テープカットを前に、大統領が演説をした。
「ブラジルは、現在、各種工業の振興に邁進しております。1956年、57年は自動車工業の発展を図り、初期の目的を達成しました。58年、59年はブラジルの運輸に欠くことのできない船舶の造船に着手すべき年であります。われわれは、このブラジルの国家経済の重要な事業の完遂に努力しなくてはなりません」
クビチェクのメタス計画は、重工業を間違いなく発展させていた。1956~61年の間に鉄鋼業は100%、機械工業125%、電気通信工業380%、輸送用機械工業に至っては600%の成長を記録する。こうした工業化は官民混合経済で推進されたが、必要な資金の調達は外資の導入や国際通貨基金からの融資、さらには通貨の発行に委ねられた。やがて通貨膨張は、すさまじい物価の上昇を招くことになるのだが......。
土光とクビチェクは手を携えて、テープをカットした。合図の紐が引かれると、祝賀ムードを弾き飛ばすような轟音が響いた。
ガシャーン! ガシャーン! ガシャーン! ガシャーン! ガシャーン! ......
岸壁の際につないだ杭打ち船が、埋め立ての掘削のために蒸気ハンマーをけたたましく打ち下ろした。海中に初めて打ち込まれる鉄杭に、太陽光がギラギラと反射した。シャンペンが抜かれている間も、ガシャーン! ガシャーン! ガシャーン! と、あたりを圧する杭打ちの音は鳴り響いたのだった。
*
数日後、ブラジル政府発注の船、5800トン5隻の契約が交わされ、石川島はリオ随一の高級ホテル、コパカバーナ・パレスホテルの黄金の間を借り切り、記念パーティを開いた。海軍大臣夫妻を始め、紳士淑女が大勢集い、煌びやかで盛大な祝宴が催された。
すっかり悦に入った土光は、パーティが終わり最後の客を送りだすと、突然、大声を張り上げた。
「みんな御苦労! これから飲みにゆく。飲み足りない奴は、おれについてこい。今日はおれの奢りだ!」
現地に駐在していた山本勝律は、そのときの感激を、手記に綴っている。
「私は案内役。四、五軒バーを回ったと思います。一人抜け、二人抜け、それでも六、七人が残りました。酔いざましに、コパカバーナ海岸のプロムナードを、全員よろよろ、一列縦隊で歩きました。 突然、土光さんが、暗黒の海に向かって走り出しました。全員びっくり、急いで後に続きました。土光さんは、波打ち際で止まり叫びました。『小便をする。全員横に並べ』。大西洋に向かって砲列がしかれました。壮大な気分でした。前代未聞の出来事だったと思いますが、土光さんの一面を見た思いで、懐かしく感じます」
翌年、操業を開始したイシブラスは、別名「イシコーラ」と呼ばれた。ポルトガル語で学校は「エスコーラ」という。イシコーラとは、イシブラス学校の意だ。イシブラスに何年か勤めたら、腕前を上げ、高給で引き抜かれたりすることから、そう呼ばれるようになった。創生期の石川島造船にも、同じような雰囲気があったという。
日本からは125人の選りすぐりの技術陣が送り込まれた。第一陣の派遣技術者は、出発前の座談会で、期待と不安が入り混じった胸中をこう語り合っている。
日向野(船殻)――移民とかブラジルとかいうと、日本ではパッとしないから新天地で......といういわゆる一旗組、あれを世間ではすぐ考えちゃうんですよ。
桜井造船部長――確かに一部の考え方の代表ですね。
日向野(船殻)――だから近所でいってるそうです。「日向野さんが会社をやめてブラジルに行くそうだが、石川島あぶないんじゃないか」(笑)
斎藤(船殻)――うちでは家内の母をおいて行くことになるので言いだせないで弱ったんですが、イザ切り出してみると「娘は斎藤にやったんだから」と案外割り切ってくれてホッとしました。ところがその後、テレビでワニが出ちゃったんです。
日向野(船殻)――そうだ。アマゾンなんか出ちゃったんだ。参りましたね。「お前住みよいなどといっていたがトンデモナイ所だ」と母からやられましてね(笑)。
山北(パイプ)――私の両親は、いくらなんでもブラジルとはといって反対したんですが、明治の初めにオヤジが滋賀から上京した時よりも短い日数で着くんだと説明したら、それで納得しちゃったんです。
日向野(船殻)――しかし飛行機で3、4日といってもね、船でひと月半というとやはり皆驚きますよ。...... (「石川島」1959年10月1日発行、以下、引用同誌)
座談会に出席している日向野ら7名は横浜港から「ぶらじる丸」でリオに向かっている。生活習慣への心配も口をついて出てくる。
細川(電気)――カトリックの盛んな所で、私のような無宗教の者はヒケメを感じませんか。
桜井(造船部長)――心配ないでしょうね。今も言ったように人のことには干渉しない、いい意味での個人主義に徹していますからね。
高須(総務部長付)――人種的偏見も非常に少ないそうですね。
桜井(造船部長)――いい例がコパカバーナの海岸です。ベンチにギッシリとアベックが並んで、抱き合ったり、せっぷんしたり、てんでにわが道を行っているんです。そうかと思うと、中にハサまって一人ポツンと腰かけてるのもいる......(笑)。
仕事の面では、「技術を発揮すればいい、誇りもある」と言いつつも、どうやって「和」を保つか、腐心している。職長の日向野は、こう語っている。
「チームワークの問題ですね。あらゆる職種の人たちの集まりだから性格も異なるわけで、どうしたらうまくまとめられるかに、心を砕いています。ことに家族が来られるまでの間、ホームシックから、わずかのことに怒りっぽくなったりするでしょうしね。スポーツなど、人の和といった意味からも大いにやりたいと考えています」
坂道は上らなければ新たな眺望は開けない。たとえハイパーインフレが待ち受けていようが、いま、そこにある可能性に新興国は懸けねばならなかった。ブラジルも、日本も一気呵成に経済成長の坂道を上ろうとしていた。