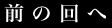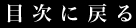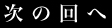第9回
戦後最大の合併の舞台裏
67年前の8月15日正午、昭和天皇はラジオを通じて「終戦の勅書」を発表した。
「8・15」は、戦没者の慰霊と民主主義国家としての再出発の日ととらえられている。甲子園では球児が黙祷を捧げる。「8・15」は大切な節目の日である。
ただ、敗戦を機に世の価値観がすべてひっくり返ったのかというと、そうでもない。むしろ戦後の混乱をかいくぐって、なお受け継がれてきた物事の系譜に現代日本の宿命を感じる。善し悪しの問題ではなく、そういう社会に私たちは生きているということだ。
小説家の高見順は、1945年8月16日の「日記」にこう記している。
「北鎌倉駅を兵隊が警備している。物々しい空気だ。円覚寺、明月院の前、建長寺にも、これは海軍の兵隊が銃を持って立っている。『文庫』へ行くと、横須賀航空隊の司令官が少壮将校に監禁され、航空隊はあくまで戦うと頑張っているという。(略) 黒い灰が空に舞っている。紙を焼いているにちがいない。――東京から帰ってきた永井君(※永井龍男)の話では、東京でも各所で盛んに紙を焼いていて、空が黒い灰だらけだという。鉄道でも書類を焼いている。戦闘隊組織に関する書類らしいという」米軍が進駐してくる前に、都合の悪い「過去」を焼き捨ててしまえ、と焚書する人びとの姿が目に浮かぶようだ。だが、書類は焼き捨てられても、人間は残る。軍人は職を失っても生きていかなくてはならない。戦争遂行の国家総動員計画を立てていた官僚にも生活がある。「8・15」は、彼らが軍事一辺倒から経済優先へと乗り換えるプラットフォームでもあった。
重工業界は、そうした戦時体制が遺した「人脈」を活かして羽ばたいた。
この連載でも度々、名前が出てくる永野治元海軍少佐は、その筆頭だろう。
戦時中にジェットエンジン「ネ20」の開発に心血を注いだ永野は、終戦直後、虚脱状態に陥った。妻が肺炎にかかり、日常生活に難渋する。永野は、仕事一途で家族を顧みなかった生き方を悔いた。仕事を辞め、小学校に上がったばかりの子どもを抱えて、1年間妻の看病に専念。10年連れ添った妻を看取っている。永野は身も心も消耗した。土光敏夫に石川島重工に引っ張られ、ようやく航空機エンジンの開発に本腰を入れる。1957年、田無市(現西東京市)に航空機部門の広大な工場が開設されると、永野は工場長を任され、欧米の航空技術に追いつこうと奮闘した。
海軍の技術力は、本道の造船部門でも民間事業で昇華している。1950年代に中東やアフリカで大油田が発見され、石炭から石油への「エネルギー革命」が起きた。石油を運ぶタンカーが数万トンから十数万トン、それ以上へと大型化するのは必至だった。
そのころ、土光率いる石川島は、年々売り上げを拡大していた。ただし、ドル箱は産業機械や陸用ボイラー、タービンなど「陸」の技術だった。1959年、311億円の総売り上げに占める「海」=造船の割合は、25%にとどまる。造船の不振は、設備の小ささに起因していた。隅田川河口の佃島や豊洲の造船所は、水深も浅く、最大で3万トン級の船しか造れない。三菱や日立の8万トン、5万トン級の造船設備には太刀打ちできなかった。
石川島が大型タンカーを建造するには、他に適地を探す必要があった。どこかいい場所はないか、と土光はアンテナを張り巡らせる。横浜市が磯子沖を埋め立て、工場を誘致する計画を知り、4万坪の用地を買い入れた。とはいえ埋め立て完了までには数年かかる。
時間が惜しい。そこに同業の「播磨造船」の業績不振の報が舞い込む。播磨は日本3位の造船メーカーだが、1958年から60年にかけて、受注残高が3分の2に減り、売上高は半減という惨憺たる状況だった。売り上げの9割以上を造船に頼る播磨は、不況の波をもろにかぶり、四苦八苦していた。「陸」への進出も模索していたが、はかばかしくない。
ここで、土光は、ブラジルに造船所を建てた余勢を駆って、戦後最大の「合併」を仕掛ける。ライバルの川崎重工の砂野仁(いさのまさし)元社長をして「かっさらわれてしまった」と悔しがらせる、電撃的な合併劇であった。
*
1960年早春の夜、土光は、赤坂の料亭の玄関で約束の1時間も前から人を待っていた。夜の宴席は極力断り、自分の時間を大切にする土光が、料亭で首を長くして人を待つなど前代未聞のことだった。相手は播磨造船の六岡周三社長である。東大船舶工学科出身の六岡は、経営者の間でも粋人で通っていた。小唄の名手で、洒脱な都会人だ。土の匂いがまとわりつく土光とは、対極のタイプであった。
だからこそ、というべきか、趣味や性格が違う分、会えば話題は経営観や技術論に集中し、案外話は合った。もともと石川島と播磨は、石川島がタービン機関、播磨はディーゼル機関を得意にしており、互いが船舶用エンジンを供給し合う仲だった。前年の夏、土光と六岡は所用で会食し、それぞれの弱点について語り合っている。ただし、この時点では土光はまだ動かなかった。
土光がわざわざ赤坂に宴席を設け、六岡と会おうと決心した背景には金融筋の仲介があった。第一銀行(現みずほコーポレート銀行)が播磨造船の合併先を探していたのだ。第一銀行が先に話を持ちかけたのは川崎重工だった。川重の砂野は「私の履歴書」(日本経済新聞社)に、合併の返答に窮した理由をこう綴っている。
「当時、造船界が不況であったうえ、造船部門の強い二つの造船所がいっしょになっても、たいしたメリットは期待できないという考えが大勢を占め、話は停滞、一か月余りが無為に過ぎてしまった」
川重の返事が遅れている間に、第一銀行首脳は土光に水を向けた。土光は「三日間だけ待ってくれ」と言い、六岡と直接、話を詰めようとしたのだった。
六岡は定刻に料亭に現れ、土光とサシでの話し合いが始まった。ともに技術畑を歩んできたので、合理主義では共通している。合併で「陸」と「海」の強みを補完し合う利点は、すぐに共有され、話は進んだ。重要なのは、いかに合併実務を進めていくか。土光は記す。
「......この合併話は、秘密厳守とし、"事"は慎重に運ばれた。まず、両社から各三人の合併準備委員が選ばれた。石川島側は、経理担当常務、経理部長、調査室長、播磨側は財務担当専務、財務部長、調査課長である。 連絡事務室は、ちょうど両社の中間にあるビルの一室、毎週二、三回、一回半日のペースで会議は続けられた。その中身は、それぞれの欠点、弱点を洗いざらいさらけ出すことであった。例えば、公表している決算諸表ではわからない含み利益や含み損失まですっかり見せ合った。万一、この合併がうまくゆかずご破算にでもなれば、その以後、お互いに競争ができないといういわば背水の陣であった。 六人の委員たちは、この秘密会議に参加するため、上司、同僚、部下、親兄弟にまで、心ならず苦しいウソをつかねばならない状態だったようだ」(「私の履歴書」土光敏夫、日本経済新聞社)「腹の見せ合い」は半年近く続き、1960年7月1日、土光は全従業員に播磨造船との合併を伝え、午前10時、東京会館で六岡と記者会見に臨んだ。新会社の社名は「石川島播磨重工(通称IHI)」、合併比率は石川島の株式(額面50円)3株に対して播磨造船の株式(額面50円)5株とする。手続き上、播磨造船は解散の形をとるが、従業員は引き続き勤続加算される。「海」と「陸」の結婚で、資本金102億円、従業員1万5000人、年間売上高約600億円の巨大企業が1960年12月1日をもってスタートする、と発表された。
メディアが「戦後最大の合併」と騒ぐ陰で、川崎重工の砂野は「煮え湯を飲まされた」と悔しさを募らせた。このころ、土光には「辻斬り強盗」「ダボハゼ経営者」といった悪名がつけられていた。土光の強引でねばり強い売り込みは、しばしば業界のしきたりを無視した。三菱重工や川重、日立造船などの営業マンは、商談が始まると「石播(いしはり)の姿は見えないな」と念を押したという。砂野は、こう語っている。
「それにしても、船舶受注の商売にしろ、また合併のような経営問題にしても、石播には過去にずいぶんやられたもんだ。こちらが口もとまで運んで、これから食べようという矢先にかっさらわれてしまったのだから......」(『評伝 土光敏夫』榊原博行、国際商業出版)もっとも、土光にすれば、くずぐずしているそっちが悪い、合併にはタイミングと意思が重要なのだ、と居直りたい気分だったろう。土光は、すぐさま新生・石川島播磨重工の造船部門を託せそうな人間を探した。あちこちでいい人材はいないかと訊ねた。 そして、ひとりの男の名があがる。真藤恒(しんとうひさし、1910~2003)、播磨造船から呉造船所を拠点とするアメリカ系のナショナル・バルク・コモンキャリアーズ(NBC)に転籍していた設計技術者であった。真藤は、のちにIHI社長を経て、土光が「第二次臨時行政調査会(第二臨調)」の会長となる1981年には日本電信電話公社の総裁に就任。民営化に伴って初代NTT社長、会長を務める。その後、リクルート事件に連座して非公開株1万株を譲渡された事実が発覚し、NTT会長を辞任。有罪が確定すると、一切の公職や経営の一線から身を引くことになる。
土光との出会いを機に、真藤は経営の中枢に入り、波乱に富む人生を送るのだが、呉NBCの造船責任者だった当時は「経済船型」を考案した工学者として知られていた。
土光に真藤を「売り込んだ」のは、元海軍大佐の西島亮二だった。九州帝大出身の西島は、戦時中に呉海軍工廠で艦船建造の生産合理化を担っている。西島は部品の規格化(制式化・JIS規格の前身)や「必要な物を、必要な時に、必要な量だけ生産する」ジャストインタイム生産方式を採用し、コストダウンや工員数の低減を図った。工場のスペースに余裕が生まれると、こんにちのコンポーネント化やサブアッセンブリに通じる手法を採り入れ、作業時間を短縮する。その結果、艦船の製造工数は最大で3分の1以下に圧縮されたという。そうした先駆的な生産技術が最大限に注入されたのが戦艦大和だった。西島は海軍の生産技術の「生き字引」であった。
土光はブラジルの大造船所を建設するに当たって、この西島を顧問として雇っていた。石川島の造船部長だった桜井清彦は、
「造船所建設のプランニングをできる人が、石川島では少なかったのです。それで、戦前、戦艦大和の生産計画にたずさわった、元海軍技術大佐・西島亮二さんに、顧問になっていただいたのです。私も技術士官でしたから、先輩に当たる人です」(『土光敏夫――無私の人』上竹瑞夫、学陽書房)と回顧している。 真藤は九大で西島の8年後輩だった。1942年から44年にかけて、真藤は海軍艦政本部に出向し、西島の秘書的役割をこなした。ここで船の生産管理の基本を叩きこまれた真藤は、戦後、タンカー大型化の波が押し寄せるなかでズングリむっくり型の「経済船型(真藤船型)」に行きつく。大量の石油を運べるようにするために、従来の船舶設計の常識を覆し、船の幅を極限まで拡げた。が、そのままではスピードが落ちて、運搬効率が下がってしまう。そこで昔の帆船にヒントを得て、船首に丸い鼻のような膨らみ(バルバスバウ)を持つ「経済船型」を考え出したのだった。
船の生産管理技術は、戦艦大和から大型タンカーへと継承されたといえよう。真藤自身は西島から学んだことを、こうふり返っている。
「後年の私にとって大いに役立ったのは、造船の技術行政の面でどこを突っつけばうまくいくのか、といったポイントを学んだことである。のち、私が造船会社のマネジメントに携わるようになったとき、改めてそのことを痛感したものだ」(『習って覚えて真似して捨てる』真藤恒、NTT出版)*
土光は、六岡に「真藤くんを呼び戻そう」と促した。1960年8月、自ら、呉NBCに電話をし、真藤本人に「至急上京してくれ」と告げた。土光と真藤は、築地の「藍亭」という料亭で夕食をともにしながら、語り合った。
誰かをスカウトする際、引き抜く側は大抵「ポスト」や「温情」をちらつかせて、相手の気を引こうとする。ところが、土光は一切そういう話はせず、仕事のことばかり喋った。
「播磨は造船の技術力、経営能力、営業能力が弱いために困難になっている。オレのところ(石川島)はもともと機械屋で造船が弱い、ご存知のとおりだ。この二つが合併したら大世帯になるけど、造船部門をきちっと切りもりする人がいないんだよ。 オレは新会社の社長をやることになった。造船部門を育てていきたいのだが、なにせオレは造船の専門家じゃない。よーくわかる専門家がほしいのだが、適当な人がいないもんだから苦労している」(『わが心を語る――日々に新た』土光敏夫、補章「土光さんにホレた私~真藤恒」、東洋経済新報社)土光は、それ以上、踏み込まなかった。真藤は、初対面の土光についてこう記している。
「......私は播磨から呉に出向していた以上、私の人事に関しては播磨の六岡(周三)社長が全責任をもっており、自分がいう立場にないと(土光は)考えていたようだ。 ハラの中では、明らかに『来てほしい』ということなのだが、私の一身上のことはいわず、あくまで播磨サイドで私を納得させ、六岡さんのほうから推薦するのが筋、との考え方である。このことで、私はすっかり土光さんの人柄にホレてしまった。 夕食をともにしながら、二時間ほど話をしただろうか。そのとき、私に造船業の将来性、在り方など、『きみ、どう思うか』といろんな角度からきかれた。私の意見を徹底的に引きだすようにしたが、これは私の能力テストでもあったわけで、このへんはなかなかずるい、タヌキオヤジの一面である」(引用同前)
真藤は、IHIに常務取締役兼造船事業部長として迎えられた。真藤は、「揉み手営業」が横行する造船業界にショックを与える。ある商船会社に造船事業部長就任の挨拶に行き、社長から意見を求められた真藤は、幅の狭い、細長くて割高な船では役に立たない、とピシャリと言った。すかさず「うちならもっと広幅のものが造れます」と売り込んだ。
「それで、いくらでできるのかね」と商船会社の社長。
「世間相場はトン当たり117ドルですが、私のやり方なら114ドル50で十分です。しかももっといい船ができます」と真藤は応えて、経済船型の説明をした。船会社の社長も海千山千だ。「だが、それで予定どおりのスピードが出なかったらどうするか」と訊ねた。
「そのときは船価を引きましょう。まあ、0.5ドル引いて114ドルではどうでしょうか。しかし逆に予定どおりスピードが出たら、どうしてくれますか」と真藤。
「あんたに褒美をやろう」と社長ははぐらかしたけれど、IHIはトン当たり「114ドル50」という破格の値で契約をした。
造船業界内は、蜂の巣をつついたような大騒ぎとなる。117ドルの相場にこだわる他社は、「石播は大赤字になる」と盛んに誹謗した。土光は「ミスター・ダンピング」とまたぞろありがたくないあだ名をつけられる。
しかし、船が完成してみると予定の速度が出て利益も上った。すると、世界中の船が、ズングリした胴体に丸い鼻がついた形に替わっていく。5年もたたないうちに経済船型は国際的に主流となった。
真藤は、社内報「あい・えぃち・あい」(1960年12月1日発行)で「事業部長としての抱負」と題し、こう述べている。
「要するにだれでもやるようなことをやるのはだめなので、他人に一歩先んずることです。私は造船屋ですが、部品の流れの工程管理と工作物の幾何学的な正確性を向上させれば、当然いい船が安くできるはずです。作業者の体力にたよって生産性を向上するなどと言うのはおかしな話で、たとえば管理者は設計(特に基本設計)や現場指導の問題にもっと頭を使えということです。その精度が競争に勝つか負けるかの要点だと考えています」この生産管理の思考は、戦中の西島海軍大佐らの艦船造りから継承されたものだろう。限られた資源と労働力で、戦艦大和を建造するには、生産管理は必須だった。製造工程数を最大で3分の1以下に圧縮した事実は、戦時下の現場でも、モノづくりを「最適化」しようとする意思が働いたことを物語っている。
しかし、個々の製造現場の「部分最適」を図ることは、システムや組織の「全体最適」にはつながらなかった。戦争という行為自体が不合理で、最適化とは縁遠かったからだ。
戦後の産業界が背負った宿命のひとつは、この部分最適を全体最適化する難しさであろう。土光が陣頭指揮を執るIHIは、部分と全体の矛盾も成長の活力に変えて、突き進んでゆく。産業界は高度成長の美酒に酔った。