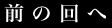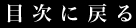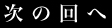第10回
サラリーマン社長の「分」――石川島播磨から東芝へ
組織に人事はつきものだ。誰かを抜擢したり、他所から引き抜いたりする背景には、主導権を持つ者の「思惑」が隠れている。その思惑をめぐって、上から下まで、さまざまなかけ引きがくり広げられる。内閣の閣僚人事などというものは、当選回数や能力だけでなく、ゴマすりや「滅私奉公」の度合いで決まったりもする。権力中枢も、微分すれば、いじましさの連鎖で構成されているようだ。
詩人の中桐雅夫(1919~83)は、「会社の人事」という詩を残している。
「絶対、次期支店次長ですよ、あなたは」
顔色をうかがいながらおべっかを使う、
いわれた方は相好をくずして、
「まあ、一杯やりたまえ」と杯をさす。
(中略)
やがて別れてみんなひとりになる、
早春の夜風がみんなの頬をなでていく、
酔いがさめてきて寂しくなる、
煙草の空箱や小石をけとばしてみる。
(後略)
「みんな」のリフレインが、「日本株式会社」の高度成長を支えたサラリーマンの切ない心情を見事にとらえている。「みんな」の寂しさは、中間管理職だけでなく、程度の差こそあれ、トップに上りつめた者にも内在するだろう。人事は自ら決することはできず、与えられた場所で生きるしかないという宿命において......。
*
石川島重工と播磨造船を合併させ、石川島播磨重工(IHI)の初代社長に就任した土光敏夫は、会社組織を事業部制に移行した。全社を「産業機械」「原動機」「化工機」「船舶」「航空エンジン」の5事業部に分割し、石川島、播磨という出身母体に関係なく、すべての社員をいったん本社に移した。その後、差別なく、平等に5事業部に再配置する。
その結果、新しい職場では「上役も同僚も、いったい石川島出身なのか、播磨出身なのか、わからない」状態になった。今風に言えば人材を大胆にシャッフルしたわけだが、当時、土光はこれを「ミキサー人事」と呼んだ。合併にありがちな派閥的思惑を封じるために、野菜をミキサーにかけて混ぜるような人事を行ったのである。それによって、石川島の「がめつさ」と播磨の「おっとり」と言われた社風も、混ぜ合わされる。
「陸(に強い石川島)と海(に強い播磨)の結婚」は、規模の威力へと結実する。旧播磨の遊休状態だった相生ドックは、フル稼働に転じた。横浜・根岸の埋立地に建設した横浜工場は、造船、機械の両部門の主力へ浮上した。1962年に日章丸(13万トン)、66年には東京丸(15万トン)、出光丸(21万トン)と世界最大級のタンカーが、次々と進水する。石炭から石油へのエネルギー革命は、大型タンカーを産み落した。
イギリスの「グラスゴー・ヘラルド」誌(1963年1月号)が62年の世界の造船所進水量を発表すると、なんと相生工場が28万7713総トンで世界1位に輝いた。相生工場は、63年、64年と世界一を維持し、企業別でも63年にIHIはトップに躍り出る。
造船部門の大躍進の立役者は、事業部長に抜擢された旧播磨出身の真藤恒だった。博士号を持ち、「経済船型」を開発した真藤は、けた外れの「営業マン」でもあった。播磨から出向する形で、アメリカのNBC(ナショナル・バルク・キャリアーズ)の呉造船所を切り盛りした経験が、IHIという大舞台を与えられて生きた。1年の3分の1は海外に出張し、自分で片っ端から注文をとった。ライバル社の三菱造船関係者は、
「あの人は、現地の船主と直接交渉し、その場で契約してしまう。ウチなんかは、現地の営業マンから連絡を受けて本社が見積もりしたり、書類をあちこち回しているうちに、商談をさらわれてしまうのだから......」(『評伝 土光敏夫』榊原博行、国際商業出版)と、脱帽している。
61年3月期から63年3月期の造船大手5社(新三菱重工、三菱造船、三菱日本重工、日立造船、三井造船)の平均成長率は、売上高21%増、税引前利益18%増と、いまから考えれば羨ましい成長ぶりを示している。が、IHIは、さらにその上をいった。同期間に売上高42%増、税引前利益30%! じつに大手5社の2倍近い数字をあげている。この高成長の原動力が造船だったのである。
*
土光―真藤ラインは、業界の常識や既得権者の支配にも果敢に挑んだ。古い殻を破るためには向こう傷を恐れなかった。土光は、凄まじいカミナリをしばしば周囲に落としたが、ひとたび問題解決の割り切り方を決めると、その方法は部下に任せた。大局を見て叱りつけても、いったん部下の方法論を認めたら、毅然として動じない。そこを部下は「意気に感じる」のだ。
このパターンで、土光―真藤コンビは、ギリシャの大船主、アリストテレス・オナシスに立ち向かっている。オナシスは、合併前の播磨造船に発注した船が建造されると、タービンの減速ギアに不具合があるとクレームをつけ、引き取りを拒否。国際係争事件となった。争いは、ロンドンの「国際海事審判所(アービトレーション・コート)」に持ち込まれる。造船会社は、船主から注文をもらう側だから立場は弱い。海事審判所の裁定に従わなければ、その造船会社は業界でボイコットされ、世界市場で相手にされなくなる恐れがあった。
しかし、真藤にはオナシスの主張は「言いがかり」としか感じられなかった。
クレームをつけられたタービンの減速ギアに技術的な問題はない。船の値段は、世界情勢によって刻々と変わる。発注されたのはエジプトとイスラエル、英仏がスエズ運河の保有をめぐって戦っていた「スエズ動乱」(1956~57年)の最中だった。スエズ運河が使えなくなって、欧州と中東、アジアを結ぶ航路はアフリカ喜望峰周りの大迂回を余儀なくされる。ただでさえ、戦乱は船腹不足を招き、船の価格を押し上げる。スエズ動乱で船価は高騰し、海運ブームが押し寄せた。
だが、オナシスの発注した船が完成したとき、動乱は終わってブームは去り、海運界は不況に陥っていた。オナシスは契約通りの金額で船を引き取れば大赤字を出す。そこで言いがかりをつけて、国際海事審判所に訴えた、と思われた。IHI側に非がないのに黙って裁定に従うのは我慢ならない。とはいえ、「20世紀最大の海運王」と呼ばれたオナシスの影響力は強く、審判での勝ち目はなかった。
そこで真藤は、争いの対処法について、世界の大手船会社や荷主に訊ねて回った。真藤自身、こう綴っている。
「すると、『真藤さん、あの船主はいつもこういうことをやるんです。それで荷主や同業の船会社も困っていますよ。石播が、裁定でもし敗れても、私たちはあなた方を応援します。船の注文も出しますから、頑張ってください』と多くの荷主や船主から言われた。 何と、船の関係者の多くがこれまでに泣かされてきていた。みんな立場が弱いので黙って、その要求を受け入れてきただけなのである」(「財界」1983年9月13日号)実態を知った真藤は、裁定で敗れたら賠償金を払わねばならないのか、と訊ねる土光に「裁定に従わなくてもいい」と進言する。『土光敏夫 21世への遺産』(志村嘉一郎、文春文庫)をもとに二人のやりとりを再現する。
「これは業界の制裁事項で、法律を犯すことではありません。最終的には、当事者同士の意思で裁定には従わなくてもいいのです。ただ、これをやると、土光さんと私の名前は、世界中の造船関係者の間に、悪名として広がるでしょう」と真藤は言った。
「しかし、ほんとうに払わなくてもいいのかね」と土光は訝る。
「ロンドンやノルウェー、ニューヨークなどの大手海運業界や荷主の意見を聞いて回りましたら、ここで一戦やってくれという意見が、かなりあります。『アービトレーションの裁定通りになると、悪い習慣が残るから』と、みんなが応援してくれそうです。大騒動になりますが、うまくすると、前渡し金だけ返せば賠償金は払わなくても済むかもしれません」
「じゃあ、やってみるか」
「しかし、これを実行すると、日本の政府、中でも外務省と通産省、そして業界から相当な圧力を受けます。圧力は、外国より国内の方がきついでしょう。マスコミも一斉に書き立てるでしょう。2年か3年かかりますが、その間、会社の名前と社長の名前に傷がつきます」と真藤は念を押した。
「正しいことをやるのだから、そんなことはかまわない」
「万一、途中で挫折したら、ものすごい悪影響が出て、石播の商売が続けられなくなるかもしれません。ここのところだけは、腹をくくっておいてください」
「ようし、わかった。腹をくくってあたろう」
土光は世界の海運王を向こうに回して、大喧嘩を仕掛けた。案の定、国際海事審判所の裁定は石播の敗訴だった。莫大な賠償金を吹っかけられた石播は、支払いを拒否する。日本の海運、造船界は蜂の巣をつっついたような大騒ぎとなった。外務省、通産省は露骨に圧力をかけた。マスコミは石播に集中砲火を浴びせ、駐日ギリシャ大使は抗議をしてきた。まさに四面楚歌に追い込まれる。だが、土光は節を曲げなかった。真藤は述懐している。
「世論の判断では、石播が不利であった。土光さんは社長としてマスコミにもそのことを問われても、『全部社長の土光の責任でやっている。それだけのことだよ』と押し通した。この間、担当の私には何も問い合わせはなかった。それで、船の注文はと言うと、欧米をはじめ国内の船主からもどんどんまいこんできていた」(「財界」1983年9月13日号)かくして、石播は国際的な海事紛争を抱えながらも、兵庫県の相生造船所が世界一の建造量を達成する。逆に国際審判で勝ったオナシス側の営業に支障が出始め、ついには「和解」の申し入れが届く。土光の一度こうと決めたらテコでも動かない「土性骨」が、実質的な勝利をもたらしたのだった。
*
1964年11月、土光は、社長の座を副社長の田口連三に譲り、真藤を副社長にすえた。すでに68歳、自らは会長に納まり、経営の第一線を退いて、「第二の人生」への夢を膨らませていた。
ところが、翌65年4月19日、日韓交渉妥結後、初めての訪韓経済使節団の団長として土光がソウルを訪れ、学生デモの洗礼を受けながら経済パイプづくりに勤しんでいたころ、新聞紙上で「東芝の岩下文雄社長辞任、土光後任社長内定」と大々的に報道された。
話の出どころは、東芝会長で、土光にとって「師匠」でもある石坂泰三だった。「財界総理」といわれた石坂と土光の縁は深い。二人が出会ったのは1951年。石坂が石川島の工場を見学に来たのが最初だった。当時の東芝と石川島では「格」が違った。東芝は天下の名門、石川島は「町工場から、やっと脱皮した程度」(土光)だった。東芝の下請け仕事も多かった。
だが、格上の大社長でも土光はまったく気にせず、工場を案内し、昼時には工場内の会議室で店屋物の弁当を出した。下にも置かない歓待に慣れている石坂は、「土光君というのは、聞きしに勝る合理主義者だね。率直すぎて、かえって気持ちがよい」と同行の東芝重役に洩らしたという。ほどなく土光は東芝の非常勤取締役を委嘱され、「何でも気づいたことを言ってくれ」と石坂から頼まれる。土光と石坂の関係は深まった。
土光が石播を軌道にのせ、そろそろ引退を、と考え出したころ、石坂はこう言った。
「きみは大工の棟梁としては一流になったが、このまま終わるつもりかね。木と同じで、人生には必ず節がある。これからは一企業のワクを超えて、"国家"という巨大なビルづくりをやってみてはどうか」
常々、石坂は「信念を貫き通そうとする者の行方には、重い十字架が待っている」とも説いた。その石坂が会長を務める東芝はというと、名門性にあぐらをかき、いつの間にか業績が急速に悪化していた。
一高、東大出のエリート社長の岩下は、「短期で気ぜわしい習癖のため、よく部下を叱りとばした」と『東芝の悲劇』(三鬼陽之助、光文社)は伝える。そのため部下は岩下を敬遠し、重要な情報が届かなくなる。イエスマンの側近政治がはびこる。
一方で、上流趣味の岩下は、東芝の社長室や会長室にバス・トイレを付け、外国人のパーティに呼ばれるとタキシードに着替えて出かけた。専用の料理人もつけ、エレベーターは天皇の「お召し列車」のように他人を入れず、一人で乗り降りした。
大企業病が東芝にじわじわと蔓延していた。
土光は、石坂から内々に東芝の社長就任を持ちかられていた。しかしながら、ソウルで韓国の財界人との会議に出ていた時点で、東芝から正式な要請はまったく届いてはいなかった。新聞辞令が先行してしまったのである。
「岩下相談役、石坂会長留任」という観測記事が飛び交うなかで、岩下が反撃に出る。
「わたしが相談役になるという見方もあるが、そうはならない。会長として残るつもりでいる」と開き直ったコメントが経済紙に載る。4月23日夕刻、小雨にぬれた羽田空港に土光ら訪韓経済使節団を乗せた航空機が着陸した。タラップを降りた土光は、間もなく、記者団に迎えられ、質問を浴びせられた。「岩下会長でもいいか」と問われ、
「受けるかどうかはこれからの問題だ。まだ具体的には考えていない。受けるとなれば、いろいろ研究し、相談をしなければならない。この話はこのくらいで勘弁してくれ」
と、土光は応えた。
それから5日間、実際には「土光の返事待ち」であったにも関わらず、東芝からはまったく音沙汰がなかった。東芝内部では、さまざまな暗闘があったようだ。そして、4月28日朝、東芝の役員会議が始まる1時間前に、土光と、石坂、岩下の三人が初めて顔をそろえる。ぎりぎりのタイミングで「土光の社長就任、岩下辞任」が決定。土光は社長として乗り込むにあたって、注文をつけなかった。岩下の会長就任ものんでいる。ただし、社長室に入って、真っ先にバス、トイレを「こんなものいらん」と業者を呼んで壊して、改装させ、重役室も大部屋に移し、秘書の数も減らした。
土光にとって、新聞辞令が発表されてから、社長就任が決まるまでの10日間は「人生で最も長い日々」であっただろう。人事という、自分ではどうしようもないものの前で、土光の胸にも中桐雅夫の詩に通じる「切なさ」が去来したのではないか。
土光は、後に毎日新聞経済部長の羽間乙彦のインタビューを受けて、「第二の人生」への夢が破れた状況を、こう語っている。
「ブラジルに行くつもりだったが、年をとりすぎたな。石川島ブラジルという造船会社をつくり、それがむこうの経済に貢献したと認められたんでしょうね。勲章と永住権をもらいました。最初、播磨造船との合併が軌道にのったら行くつもりでしたが、こんどは東芝へ来てしまった。わし自身、年をとりすぎたし、むこうの造船会社にいく必要がなくなった。ブラジル人に『何かよい仕事はないか』と冗談にいったら、『牧場がよいだろう』というんです。『安いのを買ってくれ』と頼んでおくと、しばらくして五〇万ドルで牧場があるといってきました。商売でいうと五〇万ドルという金はたいした額ではない。『じゃあ買おう』といって、日本円にしたら一億八千万円になる。これでは高すぎて買えません(笑)」(「サンデー毎日」1966年10月2日号)土光は、サラリーマン社長の「分」をわきまえていた。