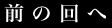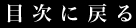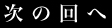第11回
「さびつくより、すりきれるほうがまし」
日本を代表する経営学者、野中郁次郎一橋大学名誉教授は、常々、企業経営にとって、言語化できる「形式知」と、現場経験から得られる言葉では表現しにくい「暗黙知」の相互変換の重要性を説いている。野中氏は、「よみがえれ日本の経営」と題された全国紙のインタビューで、福島第一原発事故を起こした東京電力の「失敗の本質」は「オープンな知の総動員体制をつくれなかったこと」と指摘し、その理由をこう述べている。
「東電は木川田一隆さんが社長だった1960年代から70年代初め、他社に先駆けて『社会貢献』をめざし、現場での教育も含めて総合的な研修体制を整えた。現場を回る人たちは電信柱に登り、地域に密着し経験を重ねた。そうした現場感のある人が経営陣になっていったのです」(「朝日新聞」2012年9月1日付)
「ところが霞が関との交渉がうまいとか、論理的に正しい経営計画をつくるとか、総務、企画の能力にたけた人が出世する構造に変わっていった。こうした能力は言語化できる知識、すなわち『形式知』が基本です。一方、言葉にうまくあらわせない現場経験から得られる『暗黙知』がある。私は形式知と暗黙知を相互に変換させながら、新たな知を生み出すことが重要だと考えます。東電は知を創造する回路がうまくまわっていなかったように思います」(前同)
形式知と暗黙知の断絶は、しかし、こんにちの東電だけの問題ではない。右肩上がりの高度成長期、すでに大企業のなかでは経営と現場の乖離が生じている。
1965年春、土光敏夫が師匠の石坂泰三に担ぎ出されて、社長として単身乗り込んだ東芝も、そのような状況だった。ライバル関係の重電三社は、三菱が「殿様」、東芝は「侍」、日立は「野武士」と呼ばれてきたが、1960年代前半、東芝は他の2社にくらべて純利益が急激に減少。減配に次ぐ減配で、日立には大きく水をあけられていた。
東芝の病根は、経営者、組織、子会社、販売、技術と多方面に広がっていた。外様の土光は、従業員6万3000人、資本金、社員数とも石川島播磨重工の約3倍の大東芝の改革に着手する。その方法は、大きく分けて「現場めぐり」「組織に活力を与える機構変革」「チャレンジ・レスポンスの浸透による社員の意識改革」の3方向にくくれる。
土光の手法を見ていくと、形式知と暗黙知の間に回路をつなぐことと見事に合致する。もちろん、土光の頭のなかに形式知、暗黙知という単語などなかった。ハンガリー出身の化学者にして哲学者のマイケル・ポランニー(1891~1976)が、「暗黙知」の概念を世界で初めて示すのは1967年だ。当時、野中氏は、まだ富士電機の社員だった。
土光は、形式知、暗黙知という考え方が叙述される以前に、経営の本質を実践を通して知っていたといえるだろう。そこに土光の、いやホンダを創業した本田宗一郎やソニーの井深大にも通じる、高度成長を先導した明治人の普遍性が感じられる。
*
1965年5月28日午前7時30分、土光は、日比谷の日本電信電話公社ビルに着いた。東芝社長としての出社初日、ビルに社員の姿はない。一般社員の出社時刻は8時30分、前任社長は10時ごろに顔を出していた。
怪しんだ守衛が、
「どなたでしょうか?」
と声をかけると、土光は、
「こんど御社の社長に就きました土光というものです。よろしく」
と珍妙な挨拶を返す。
慌てた守衛は、最敬礼をして8階の社長室に案内した。土光は早朝出勤の習慣を東芝に持ち込んだ。たちまち他の役員たちが内々に非難の声をあげる。
「わざわざ早朝出社することはない。小企業ならいざ知らず、そんなことで大企業の体質が変わると思ったら大間違いだ」
「上の者は、どっしり構えておればいい。だいいちあの調子に合わせていたら、身体がもんたよ」
幹部連中は、土光の早朝出勤がいつまでつづくものか、と様子見を決め込む。ところが、早朝出勤が中断することはなかった。土光にとって、朝早く起きて法華経を唱え、妻の手づくりのヨーグルトと野菜ジュースの朝食を摂り、7時30分に出社するのは長年体に刻まれたリズムだった。自然な習慣なのだから変えるつもりもない。
それでいて土光は役員に早朝出勤を求める素振りをみせなかった。逆に「おれは雇われてきた。東芝では一番の後輩なので、よろしく頼む」と下手に出ている。他人に早朝出勤を強制しない一方で、7時30分から始業の8時30分まで社長室を開け放ち、掃除係の女性だろうがヒラ社員だろうが「誰とでも会う」と宣言し、実行する。やがて社長室には長蛇の列ができてくる。
こうなれば役員たちも重役出勤をしてはいられない。自発的に8時30分には顔を揃えるようになった。
土光は、身近な重役を掌握する一方で、全国30カ所を超える工場、営業所、支社の訪問を開始する。まず初出社から2、3日後、川崎市の堀川工場の労働組合本部を、一升瓶片手に訪ねた。組合三役は本社に呼ぶことが通例だった東芝にとって、前代未聞の社長訪問である。
工場、営業所めぐりは、本社での仕事の合間を縫って行われたので、ほとんど夜行列車で行き、その日の夜行で帰る強行軍だった。70歳の誕生日を迎えても、土光は夜行出張をくり返した。「私の履歴書」に土光は記している。
「上から下まで、全従業員と話し合う楽しみがあった。この工場めぐりで、はじめて知ったのだが、東京に近い川崎ですら、今まで一度も社長が来たことがない、という工場があったのには驚いた。彼らは、私を『オヤジ、オヤジ』と呼んで歓迎してくれ、のちには私の自宅に遊びに来る者もあった」
強烈な太陽が照りつける真夏のある日、土光は、東京・江東区のタングステンやモリブデンの精錬工場を視察した。古い工場は外壁のひび割れが酷く、そこをモルタルで塗りつぶしているものだから、外観は壁に蜘蛛の巣が張っているようだった。
工場のなかは蒸し風呂のように暑かった。土光は、女子社員が用意したオシボリで額から滴り落ちる汗を拭いつつ、3時間に及ぶ視察を終えた。以下、『土光さんから学んだこと』(本郷孝信、青葉出版)を参考に、視察後のようすを再現しよう。工場長の説明を受けた土光は、こう感想を語った。
「効率の悪い古い建物を、よく活用したものである。工場長から建物の破損した個所は、すべて、従業員の手によって、補修されたものと聞いて感心した。今後の需要増加に応えるには、工場の生産設備も、能力も限界にきている。新工場建設の計画を考えているから、従業員はもうしばらくの間、辛抱して欲しい」
江東区の工場は、土光のメガネに適ったようだ。同行していた本社の部長が「せっかくの機会だから、遠慮なく感想や質問をのべるように......」と従業員に呼びかけた。総務の責任者だった武田文男(のちに東芝ケミカル常務取締役)は、従業員の声を代弁してやや無遠慮に言った。
「ここは都内の工場です。もっと早く視察を受けることを、従業員は期待していましたが......」
ここで、「財界の荒法師」の異名を持つ土光の口から、高調子のひと言が発せられた。
「任せられる人間には任せる。急いで来る必要はない」
「権限委譲」の強い信念は、逆に武田ら社員を勇気づけた。
現場めぐりと並行して、土光はピラミッド型の組織に、権限委譲で活力を与える機構変革を大胆に行った。従来の専務会や常務会を廃止し、新しく「経営幹部会」に一体化させる。経営幹部会は、常務以上の役員が社長とともに経営方針を検討し、決定する最高機関とした。
続いて、事業部グループ制をやめ、グループ責任者としての「担当役員」も改め、機能別の分担役員に変えた。つまり、事業部長が上の担当役員の決裁をもらわなければ物事を処理できなかった仕組みを、事業部長に決裁権を与える権限委譲を行ったのだ。これは事業部を一つの会社ととらえ、事業部長を社長と見立てる「事業内閣制」へと発展する。社長を補佐する集団が事業部内閣で、事業部経営会議が閣議に相当する。この会議で自主的に売り上げや利益目標を設定し、それを遂行する。予算も組めるし、その行使も可能だ。部員の海外出張なども部長判断で決められる。事業部の独立性が格段に高まった。
ただし、最後の責任は、社長が負うことになる。そこで土光は、社内のコミュニケーションの大切さを口が酸っぱくなるほど説いた。日々の仕事は事業部に任せ、自主的な判断で行えばいい。社長や役員は、その活動を外側から管理して、援護する。事業部の自立性とやる気を最大限に引き出す。が、しかし、それは「放任」ではない。事業部に目標を達成させるためには厳しい要求も必要だ。要求への素早い反応がなくては経営判断を狂わせる。この要求と反応を活用する手法を、土光は「チャレンジ・レスポンス経営」と呼んだ。
土光によれば、イギリスの歴史家、アーノルド・トインビーの著作を読んでいて、チャレンジに「挑戦」だけでなく、「参加を促す議論、呼びかけ」「説明の要求」などの意味があることを知り、こう名づけたという。チャレンジとレスポンスは、社長と事業部間だけに求められるのではなく、役員と事業部長、事業部長と部員など、あらゆる局面で必要とされた。土光は、コミュニケーションが硬直化する上意下達のピラミッド構造を心底嫌った経営者のひとりだ。一貫して、社員に自分を「さん」づけで呼ばせた。
「だいたい私は、会社の組織図は、社長をいちばん上に、次に役員、部長、課長と下に書いていあるが、あれはいけないと思う。会社の組織は、本来、太陽系みたいなもので、太陽を中心に、いろいろの惑星が自転しながら軌道を描いて回っているべきだ。仕事上では、社長も社員も同格なのである。その同格という意識を持つには、ディスカッションするのがいちばんいい。『チャレンジ・レスポンス』は、そのディスカッションシステムでもある」(「私の履歴書」土光敏夫)
土光は、一般社員にもチャレンジ・レスポンスを浸透させていく。
社長交代に伴い、スタッフから新しい社是社訓をつくってはどうかと提案された。ありきたりの経営者なら、これ幸いと自分流の社訓をひけらかしそうな場面だが、土光は言下に「ノー」と応える。「変化の激しい時代に固定した物の考え方は許されない」「スローガンが逆に新しい物の考え方を阻む」と指摘し、「つくるなら、毎日変わる社是社訓をつくれ」と、半ば冗談で言った。
そのやりとりを覚えていたスタッフが、毎月発行される社内報「東芝ライフ」に「トップ指針抄」というコラムを設け、その時々の土光の社内外での発言をコンパクトにまとめて連載を開始する。月々の「土光語録」は蓄積されて一冊の本ができあがる。
それが超ロングセラーとなる『経営の行動指針』(産業能率大学出版部)だ。結果として「毎日変わる社是社訓」のように語録が並び、東芝という企業の枠を超えて、ビジネスパーソンに読み継がれていく。
一般には、「社員は三倍働け、重役は十倍働く」や「常にビジョンを描いておけ、それが人々に希望を植えつける」が、土光語録としてよく知られているが、むしろさり気ない語りに土光の人間性がにじんでいる。
たとえば「顔を見たらコミュニケーションを行なえ。廊下の行きずりでも書類一枚分ぐらいの連絡はできる」は、いつ誰とでも対話をしたがった土光らしい。この語録の解説で、「コミュニケーションをはばむ半ば本能的な心」として、土光は次の五つをあげている。
誰かが伝えるだろうという「依存心」、まとまってから伝えればいいという「横着心」、上司はこの程度のことは知らなくてもいいと見切る「老婆心」、悪い情報を上司に伝えると気の毒と思う「かばいあい根性」、自分だけ知っているという「優越感」だ。
これらの心を「征伐」しないと、どんなコミュニケーション制度をつくっても「魂は入らない」と土光は断言する。その上で、いつでも、どこでもできる対話の例として「廊下コミ」をすすめ、こうダメを押す。
「それを『顔対顔(フェイス・ツー・フェイス)』でやるのだ。文書や電話では、相手の真意をつかんだりニュアンスをとらえることができない。重要なことなら千里を遠しとせず飛んでこいというのも、目がどれほど光っているかを確かめたいからなのだ」
人を単なる「数字」や「データ」として扱わない。人間への興味の深さが表れている。
「六〇点主義で速決せよ。決断はタイムリーになせ。決めるべきときに決めぬのは度しがたい失敗だ」
これもスピード重視の土光ならではの言葉だ。「完璧主義」を求めて時機を逸すれば、100点の答案も50点になる。逆に60点の出来でも自信を持って速やかに動けば80点の結果を生むかもしれない、と期待を寄せ、その理由を、こう説く。
「『運』というものは、そんなときにむいてくるものである。事業には運をかけねばならないことがある。その場合には、いかにして決定するかではなく、ただ決断することがたいせつなのだ」
経営の修羅場を乗り越えてきた人でなければ、この台詞は吐けない。速決を説く土光の脳裏には、石川島重工と播磨造船の電撃的合併の決断がよぎったのかもしれない。人生においても完璧主義で時機を逸し、速決で局面が打開されることがある。「結婚」などは、その最たるものではないだろうか......。
次のひと言も含蓄に富んでいる。
「穴を深く掘るには幅がいる」
土光は、専門家像と人材開発が論じられた会議の席上で、こう語っている。
「専門家が深く進むのは当然だが、狭くなるとは不可解だ。ほんとうに深まるためには、隣接の領域に立ち入りながら、だんだん幅を広げてゆかねばならない。深さに比例して幅が必要になる。つまり真の専門化とは深く広くすることだ。そうして、この深く広くの極限が総合化になるのだ」
逆に広さを求めるゼネラリストには、深さが求められる。
こんなイギリスの諺も、土光は「年配者を励ましてくれる」と語録に載せている。
「さびつくより、すりきれるほうがまし」