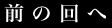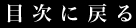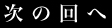第12回
「わしが、経団連を潰してやろうか」
政治にはカネがかかる。選挙ともなれば、多額の運動資金が必要だ。政治勢力を保とうとして、子分や仲間にカネを配りたがるボスもいる。
一方、民間の企業や団体の側から眺めると、公共事業をはじめ政治の周りには「利権」が転がっており、そこに近づくために特定の政党や政治家にカネを贈りたくなる。
現在、日本では政治家個人への献金は原則禁止されているが、政治家の指定する資金管理団体や後援会などを通じての個人献金は可能だ。企業や団体については、政党の本部や支部、政党が指定する政治資金団体への献金のみ認められている。国から補助金を受け取っている企業や、赤字が3年以上続いている企業は献金してはいけない。
と、企業献金は制限されているのだが、政治家が支部長を務める政党支部への献金などは、政治家個人への献金と大差なく、「抜け道」と批判されてもいる。政治とカネの問題は、いつの時代でもくり返される永遠のテーマだろう。政治が権力闘争と利権調整によって成り立っている限り、そう簡単に解決できない。政治はカネという風を受けて回る風車のようでもある。
1974年4月、経済団体連合会(経団連)の会長に就任した土光敏夫は、その巨大な風車に突っ込んでいった。自民党への政治献金を経団連がとりまとめることを返上する、と宣言したのだ。「政治オンチは困る」「政治資金集めをしたことないから、あんなキレイごとが言えるのだ」と、老獪な経済人たちは反発した。批判の嵐にうんざりしながらも、土光は持説を通そうとする。新会長は経団連という組織のなかで徐々に孤立し、一歩間違えば「裸の王様」という状況に追いつめられた。
*
石油ショックが日本の経済、政治、外交、そして国民生活を激しく揺さぶっていた。
1973年10月、第四次中東戦争が勃発し、エジプト・シリア両軍とイスラエル軍がシナイ半島とゴラン高原で交戦すると、OPEC(石油輸出国機構)のペルシャ湾岸6カ国は原油公示価格の70%引き上げを決定した。中東の産油国が、とうとう欧米の石油メジャー抜きに原油価格を決めたのである。さらに友好国以外への原油供給の削減、アラブ首長国連邦はイスラエルを支援するアメリカへの石油輸出禁止を発表する。中東産油国は、石油を通商外交の武器として、メジャーの支配体制に挑みかかった。
石油輸入の大部分を中東に依存する日本は戦慄した。首相の田中角栄は、命綱である石油を確保しようとアラブ寄りの外交政策に転じる。11月、アメリカのキッシンジャー国務長官が来日し、「われわれは中東紛争の解決に全力を傾けている。中東和平は進んでいる。日本も政策変更などしないで、静観してほしい」と圧力をかけてきた。
田中は日本の苦境を伝え、キッシンジャーに訊き返す。
「仮に日本がアメリカと同じような姿勢を続け、禁輸措置を受けたら、アメリカは日本に石油を回してくれるのか」
「それはできない」
「事態の進むままに任せるのでは、国民の理解は得られない。何も手を打たないのは、日本が窒息死するのを黙認するようなものだ。何らかの形でアラブの大義に共感する必要がある。日本は独自の外交方針をとるしかない」
キッシンジャーから憎悪のまなざしを浴びながら、田中は言い切った。
政府は「国民生活安定緊急措置法」「石油需給適正化法」を公布、施行し、世界の石油をかき集める。エネルギー消費を抑えるために「総需要抑制策」を採って大型公共工事を凍結、縮小した。そのため消費は落ち込んだ。その一方で、トイレットペーパーや洗剤など原油価格の変動と直接関係のない物資の買い占め騒動が起き、灯油を求めて燃料店やガソリンスタンドに長蛇の列ができる。ここで「千載一遇の好機」とばかり石油元売り会社が値上げに踏み切り、商社が物資の買い占めに狂奔する。便乗値上げでインフレーションは加速し、1974年の消費者物価指数は23%も上昇。「狂乱物価」という造語が生まれた。
国民がパニックに陥っていたころ、じつは石油は足りていた。1974年1月、通商産業省(現経済産業省)は前月の原油輸入量実績を発表し、中東からの輸入が10%増えた事実を認めた。設立間もない資源エネルギー庁は、石油ショック以前に産油国と結んでいた取引契約どおりに石油を確保できたこと、メジャーの供給削減が少なかったこと、アラブ諸国がさほど生産を削減しなかったことなどを輸入増の理由としてあげている。
しかし、経済は人間の心理で動く。供給不安に端を発した恐慌は拡大し、企業の設備投資は抑えられ、1974年の経済成長率は-1.2%と戦後初めてマイナスを記録し、高度経済成長に終止符が打たれた。狂乱物価に手を焼く通産事務次官、山下英明(えいめい)は「諸悪の根源は石油産業」と発言し、企業への批判が高まった。74年1月に経団連が「便乗値上げ自粛宣言」を行ったことで、かえって財界への非難が集中する。
そうした不況と逆風のなかで、土光は経団連会長に就いたのだった。
*
1974年4月18日、土光は会長就任確定の記者会見で政治献金への疑問をまっさきに口にした。
「自民党は、党員と支持者を基盤とすべきで、企業を基盤にするのはおかしい。経営者も自民党を支持するなら、個人として(自民党の政治資金調達機関である)国民協会に入るべきだ。だいたい、経団連が政治資金の取りまとめ役を代行している点について、誤解を受けている面がある。早晩何らかの形で是正していきたい」
企業批判にも言及する。
「社会と企業の間にミゾがある。これは社会も企業も激変しているためのズレだろう。しかし、経団連がそれに対して閉鎖的であったのかもしれない。社会情勢に歩調を合わせる努力が必要だ」
5月の会長就任会見では「政治にはカネがかかるが、かけすぎると民主主義が滅ぶ」と断言した。「日本列島改造論」を一枚看板に船出した田中政権は、外交で日中国交回復を実現したものの、内政では地価高騰を招き、石油ショックの狂乱物価を引き起こした。産業界は、土地投機と便乗値上げに奔(はし)った。両者の癒着を糾弾する世論を受けて、土光は従来の政界との関係を一新する方針を打ち出したのである。
7月7日に第10回参議院議員選挙が行われると、企業ぐるみ選挙を批判してきた市民運動家の市川房江が全体の2位で当選した。この「七夕選挙」では保守と革新の逆転も取り沙汰されたが、辛うじて自民党が過半数を制した。ついに土光は爆弾発言を行った。
「経団連は、国民協会の献金事務をいっさい返上する」
さらに自民党の派閥解消を訴え、「夜陰に乗じて今後も派閥に献金するような企業があったら、われわれの仲間として付き合わない」と抜け駆けは許さない姿勢を示した。
経営者が政治献金するのは自由だが、カネは国民協会が直接集めるべきであり、経団連はカネ集めに手を貸さない、と述べた。自民党への絶縁宣言ともとれる過激な物言いだった。
「あのバカヤローが」
と、日本商工会議所会頭の永野重雄は烈火のごとく怒った。自民党が潰れて、自由主義経済体制が守れるのか、と......。足もとの経団連のなかにも土光発言を苦々しく聞いている人物がいた。その職員の名は、花村仁八郎(にはちろう、1908~97)。戦時中に経団連の前身、重要産業協議会に入って以来、総務畑を歩いてきた男である。
花村は、1953年から54年にかけて起きた造船疑獄の影響で、企業の政治献金への社会的不信が高じたのをきっかけに、個々の企業が政治家に直接カネを渡すのを改め、経団連がまとめ役となって自民党に献金する形をつくりあげた。土光が毛嫌いする「献金事務」を仕切ってきた裏方だ。花村の手法は巧妙だった。まず「経済再建懇談会」という献金窓口機関をつくり、自ら事務局の責任者になった。そして、企業の負担額を「公平」にするため、俗に「花村リスト」と呼ばれる割り振り表をこしらえた。
花村リストは、会社の資本金、自己資本、利益、当面の利益予想などを基準に30~40に細かく企業を分類したものだ。このリストに則って、各企業に献金額が割り当てられる。もっとも財閥系で歴史のある企業は、たとえ資本金や利益に差があっても献金額は同じにした。会社の「格」への配慮は「財界政治部長」の異名をもつ花村にしかできない芸当だった。花村は「自由経済体制を堅持するための保険料として献金をお願いしたい」と大企業を説得して回った。政財のパイプづくりを、こう回顧している。
「花村リストは自民党の幹事長、経理局長ら執行部にも渡してあります。時には、リストを持って党の幹部が直接、会社を訪問することもありました。 昭和三十年から三十年以上、政治献金とかかわってきたわけですが、私としては事務的な奉仕のつもりで淡々と処理してきました。しかし、ある時点、節目では政界を動かすほどの役割を持っていたのですね」(『政財界パイプ役半生記 経団連外史』花村仁八郎、東京新聞出版局)
土光が自民党に愛想を尽かす契機となった前述の「七夕選挙」でも、花村は裏で動いた。
「当時はまだ政治資金は青天井で、約百億円を七夕選挙用に自民党に献金しました。十五年前の百億円といったら、かなりの額です。 だが、田中さんから『とても足りない。もっと増額してほしい』と私のところへ電話で直接に追加資金の要請がありました。『足りない』というのは簡単だけど、各企業を回って献金をお願いする身にもなってほしい、とその時、思いましたよ。 田中派の大番頭で投票日直前まで自民党財務委員長だった西村英一さん(後に自民党副総裁)が田中さんの代理で面会にやってきて『頼むから、あと二百億円どうにかしてくれ』と頭を下げました。百億円プラス二百億円ですからね」(前同)
そこで花村は前経団連会長の植村甲午郎(こうごろう)に頼んで、大企業や業界団体のトップ7、8人を集め、「保革逆転の危機です。自由経済を死守するには"生きガネ"を出すしかない。選挙に負けてから政治資金を出しても、どうにもならない」と説得した。
「その結果、二百億円は無理でしたが、確か百六十億円集まりました。最初の百億円と併せて計二百六十億円。田中さんは、このカネをばらまいたんです。選挙の方は、保守系無所属を入れて、自民党がどうにか過半数を七人上回りました」(前同)
まことに生々しい証言だ。財界の集金事務を仕切ってきた花村は、土光の「政治献金返上」にカチンときた。だが、動じたそぶりは見せなかった。
「政治資金の出し手である経済界にも当然、批判の声が国民から上がったもので、新聞記者の人たちが土光さんに『経団連がカネを集めて自民党に渡していることをどう思うか』と質問すると、『いやオレは知らん。オレは政治献金に反対だ』なんてね。 時には『カネ集めは経団連というより花村という個人がやっているんだ』と、かなりひどいことを言ったりしましたが、その後も私は黙々として企業から政治献金を集めました」(前同)「黙々と」企業からカネを集め続ける花村のしたたかさに恐れ入る。経団連の新会長と事務方の首領は対立した。ふたりは人事をめぐっても火花を散らしている。
土光の会長就任と同時に前任の事務総長が退任した。次席の花村が事務総長に昇進するとみられていたが、土光は事務局の最高ポストを空けたままにした。経団連の定時総会の直前、後任の事務総長として通産省の元事務次官の名前があがってきた。
ここで花村は、猛然と土光に抗議をした。
「通産OBを事務総長に就任させることには反対です。どんな会社でも、一番上のポストに、よそから人をもってくると、社員や職員の士気に影響します」
土光は「何も決めておらんぞ」と怒声を張り上げる。
「それじゃ、そのまま決めないでください」
花村は経団連が官僚の天下り先にされることに反旗を翻す。通産省の出先機関になれば、政策に対してものが言えなくなる。経団連の役割は、自民党への献金事務ばかりではない。時々の経済政策に対して、是々非々で直言することこそ経団連の真骨頂だった。政府との間には緊張感が必要で、官への対抗意識は強かった。花村の抵抗に会い、土光も天下り人事を強行するわけにもいかず、事務総長の座は、1年近く空席となった。
*
土光は、徐々に孤立した。笛吹けど踊らない経団連の職員に業を煮やす。朝早く出勤しては、事務局のスタッフに矢継ぎ早に支持を出し、素早い回答を求めた。IHIや東芝で実践した「チャレンジ・レスポンス」を採り入れたのだが、会員企業から「民僚」と呼ばれるような仕事ぶりが身についた職員の反応は鈍い。
「ここでは、日本語が通じないのかっ!」
と、土光は声を張り上げ、両手で机をバーンと激しく叩く。日に何度も会長室からバーン、バーンと机を打つ音が響いた。秘書たちは震え上がり、まともに口もきけない。秘書課長は早々にお役御免となったのだが、後任がいなかった。
この当時、経団連は、政策提言や立案をする調査部門と、組織全体の事務を扱う総務部門がタテ割りで分かれていた。前者は大学出のエリート職員がそれぞれのテーマに基づいて活動し、後者は東大卒の花村が高卒組の事務方を含めて統率していた。秘書は、総務部門から選ばれる。しかし、土光に太刀打ちできる人材はいない。
困り果てた花村は、理財部調査役で商法の解説書など19冊の本を書いていた居林次雄に白羽の矢を立てた。花村から居林を推薦された土光は「面白い。ひとつ使ってみよう。わしはまだ一冊も本を書いたことないから、その男を試してみるか」と受け入れた。
1975年4月、新任の秘書課長、居林は会長室を訪ねると、さっそく強烈な一撃をくらう。
「きみら経団連の連中は、国鉄と同じように潰れないと思って、怠けているんだろう。わしが、経団連を潰してやろうか」
大抵の職員は、ここでビビって気圧されてしまう。居林は違った。何を、と反骨心を燃え上らせた。
「違います。経団連は、そんな怠け者の集まりではありません。たとえば、ニクソン大統領時代のドルの大幅切り下げで、石川島播磨重工が数百億円の為替差損を被った時、私は大蔵省企業会計審議会の幹事として、石川島が潰れないよう『企業会計原則』の手直しに加わって、税法の取り扱いで無税と定めました。株主総会の決算では配当もできる制度を確立しました。経団連の職員は、怠けてなどいません」
土光の居林を見る目が変わった。だが、事務局スタッフへの怒りが鎮まったわけではない。誰それを呼べ、と担当者を呼びつけては怒鳴りつける。スタッフは肝を潰して逃げる。しかし居林は、着任から一カ月、毎日怒鳴る土光に言い返し続けた。
あれから37年、居林は土光との真剣勝負の日々をこう語る。
「経団連の総務部門と調査部門に大きな壁があったのを、初めて知りました。土光さんは、会長に就任されてから、ずっと総務スタッフを叱咤しておられたのだけれど、政策提言に関わるわれわれには伝わってこなかった。
怒鳴っている内容を聞くと、朝、公定歩合を下げろと言って、夕方、まだ下げていないのか、バーンってケースもありましてね。そりゃ、無理でしょ(笑)。できませんとはっきり言えばいいんだけど、大学出は論文を書く調子で序論、本論、結論と順序立てて説明しようとするから、ぐだぐだ言いわけをするな、バーンっとなる。結論はこうです、理由はこう、と逆にやればいいんだけどね。
私は、毎日、言い返しました。若気の至りですな。まだ40代だったからね。ひと月の間、土光さんとやりあいました。そしたら、激論が続いたせいで、とうとう声が出なくなったんです。ある朝、会長、声が出ないんですよ、と言うと、うははははーっと笑って、見ろ、おれに毒気を当てるから、そういう目に遭うんだ。罰が当たったんだ、と喜んだのなんの(笑)。それから、私は、まったく文句を言われなくなりました」
居林が秘書課長で張りついて、土光と総務スタッフの間の溝が少しずつ埋まっていった。花村は、晴れて事務総長に昇格した。企業献金は、自民党の体質改善を前提に続け、段階的に個人献金へ切り換える方向で見直される。経団連詰めの記者たちは、居林を「猛獣使い」とか「ジジ殺し」と呼んだ。
「会長に就任されて3年目くらいに、花村事務総長が私学振興財団の理事に就きまして、たまたま調べていたら、土光さんがものすごくたくさんのお金を学校に寄付しているのがわかったんです。
そんな話、まったく知りませんでした。たまげちゃって。花村さんと、どうしよう、これは、と相談しました。発表しないでやっておられるのだから、知らないことにしよう、と。
そこから皆、尊敬したね。周りは格好いいことばかり言って、裏で何かやっているような人ばかりだから、そりゃ、尊敬されますよ。政治献金返上も、土光さん、自信があったから言えたんです。本当のところがわかるまで、時間がかかりますね」
石油ショックのどん底から、日本経済を引っぱり上げようと、土光の奔走が始まる。