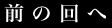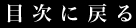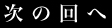第13回
原発導入──技術への「誇り」と原子力への「恐れ」
政府の電力エネルギー政策が迷走している。
野田内閣の閣僚でつくるエネルギー・環境会議は、国民の多くが脱原発依存を求めていることを受け、「2030年代に原発稼動ゼロ」を可能とするよう、「あらゆる政策資源」を投入する「革新的エネルギー・環境戦略」をまとめた。原則的に原発の新増設を認めず、運転期間を40年と定め、「40年廃炉」を進める方針だ。
ところが、原発がある自治体や経済界、アメリカの原子力産業界などから反発の声が上がると、野田内閣は同戦略の閣議決定を見送る。「戦略を踏まえ、不断の検証と見直しを行う」という短い文章だけが閣議決定された。「原発稼動ゼロ」の枷(かせ)を外したといえよう。
経団連の米倉弘昌会長は「雇用、国民生活を守る立場から、原発ゼロに反対してきたが、やっと(ゼロが)回避されたようだ」と胸をなで下ろす。脱原発依存の識者からは「原発ゼロが骨抜きにされる恐れがある」と懸念が示される。
日本の電力エネルギー政策は、どちらへ進もうとしているのか。「2030年代に原発稼動ゼロ」は総選挙用のポーズで、空手形に終わるのだろうか。
ただひとつ確実なのは、日本はエネルギー資源に乏しく、再生可能エネルギーを普及させるには時間とコストがかかるということだ。
土光敏夫は、エネルギー資源不足という日本のアキレス腱に対し、原発の推進で応じようとした。土光が育てた石川島播磨重工は原子炉格納容器や蒸気発生器を製造している。社長として迎えられた東芝は、長くGE(ゼネラル・エレクトリック)を師として原子炉や発電設備一式を電力会社に納入してきた(現在、東芝はGEのライバル社ウェスティングハウス・エレクトリックを傘下に入れている)。
原子力産業界の一員であった土光が原発を推進したのは当然のことと思われる。が、その言動をたどると、技術に対する「誇り」と「恐れ」が微妙に入り交っていることに気づく。いつしか原子力ムラは技術を過信して、土光ら原発導入世代の「恐れ」を忘れ、東京電力福島第一原発事故を招いた。今後、原発を廃炉にするにしても維持するにしても、技術の高さが求められるのはいうまでもない。土光が原子力発電に求めた原点を確認しておくことは、迷走する原発政策を考えるうえで無駄ではないだろう。
*
土光が原子炉の実物をアメリカで目の当たりにしたのは、1956年の秋だった。読売新聞社主で政界に進出した正力松太郎が、原子力委員長に就任し、イギリスから「コールダーホール型黒鉛炉」を半ば強引に「購入」しようとしていたころである。
この時期、原子爆弾開発の副産物の原子力発電は、商業化をめぐって国際的な先陣争いがくり広げられていた。アメリカは、1954年に小型原子炉を搭載した原子力潜水艦「ノーチラス」を世界に先がけて進水させた。同年、冷戦の敵、ソ連は民用では世界初の原発「オブニンスク原子力発電所」の運転を開始する。ただし、総発電量は6000kWと少なく、商業化にはほど遠かった。
冷戦の間隙を突くように、イギリスは軍事用に開発したコールダーホール型炉を発電用に改良し、日本に売り込んできた。正力は、56年5月、イギリス原子力公社の首脳、クリストファー・ヒントンを日本に呼んだ。ヒントンは講演活動を行い、原発の発電コストの安さを説いて回る。翌月、こんどはアメリカからブルックヘブン原子力研究所の調査団が来日し、アジアでの原子力利用について原子力委員会と意見交換した。
アメリカ側は、原発と核兵器開発の結びつきを憂え、慎重な態度を崩さなかった。日本側が原子炉の購入を持ちかけると、ペンシルベニア州シッピングポートに建設中の商業用原発が稼動し、詳細なデータが得られる1961年ごろまで待ってはどうか、と応じた。原発購入を追い風に総理の椅子を引き寄せようとしていた正力は、とても待てない。イギリス炉の購入へと舵を切った。
外務省は、アメリカと正力の板挟みで困惑する。炉の購入を決める前にイギリスに専門家を派遣して調査をしてはどうか、と原子力委員会に提案。コールダーホール1号炉が運転を始めて間もない1956年10月末、経団連の初代会長石川一郎を団長とする訪英原子力調査団が派遣される。一種の時間稼ぎともいえる調査団の派遣であった。
日本がイギリス炉を買って、アメリカの機嫌を損ねてはまずい。そこで設立されたばかりの日本原子力産業会議(現日本原子力産業協会)は、訪英団の出発にひと月ばかり先立ってアメリカへ民間使節団を送り込む。このなかに石川島重工の社長だった土光も加わったのである。戦前、戦中から発電用タービンを開発し、エネルギーや資源の問題に関わってきた土光の目には、1基で数十万kWの莫大な発電量が期待される原発は「夢の電源」と映った。産業の血液である電力の大量供給は、経済成長を加速させる。使節団には東京電力の木川田一隆、三菱造船の丹羽周夫(かねお)、鹿島建設の石川六郎、電力界のプロデューサーといわれた松根宗一ら、錚々たる経営者、識者が顔をそろえていた。
民間使節団は、サンノゼのGE原子力施設本部を振りだしに、アルゴンヌ、オークリッジの研究所など1か月で30ちかい施設や政府機関を訪ねる。ウェスティングハウスが建設中のシッピングポート原発では、中心の原子炉容器が9時間前に運び込まれたばかりで緊迫した作業が行われていた。視察の合間に本場のゴルフコースに出て息抜きをする団員もいたが、土光は原子力技術をひたすら吸収しようとした。
使節団の通訳兼案内役で、正力の懐刀(ふところがたな)だった柴田秀利は、著書『戦後マスコミ回遊記』(中央公論社)にこう記している。
「......専門的な説明となると、見たこともない、記号と数式を並べ立てられ、たちまち素人は理解の圏外にはね飛ばされてしまう。当然頭が痛くなり、眠くもなる。眠り込んでしまえればまだよいが、遠慮していると頭痛が残り、こうした勉強のつらさをいやというほど味わわされた。難しい数式のことなどで、一番よく理解し、サラッと説明してくれたのは、いつも土光さんだった。蔵前(東京工業大学の前身、東京高等工学校の通称)出身の工学士さんだけに、さすがに物わかりがよい。中でも私が最も期待してきたのはプラスチックの将来性で、やがてアイソトープ処理によって、基礎資源の鉄にとって代わる可能性があるという......」(括弧内筆者註)使節団は、発電技術だけでなく、アイソトープなど幅広く原子力利用に触れていたことがうかがえる。使節団はアメリカからイギリスに渡り、石川一郎らの訪英原子力調査団に合流した。イギリス原子力公社は盛大なレセプションを催し、原子炉売り込みのダメを押す。一行はコールダーホールを視察した。原発は、黒鉛ブロック3万個を積み上げた、天をつく大建造物であった。技術に少しでも明るい団員は、輸入するなら地震対策が必須だと直観した。ブロックを積んだような建造物は、地震の揺れにひとたまりもない。アメリカとイギリスの原子力開発を見て回った土光は、次のような意見を述べている。
「技術者の土光敏夫氏は、沸騰水型と加圧水型の長短両所を的確にとらえ、やがては沸騰水型も利点を発揮するようになるだろうが、現在では、耐圧容器が大きすぎる欠点があり、加圧水型がすでに安定性の上では、実証ずみであることを見てとってきた。それと同時に、将来は増殖炉の開発いかんにかかっており、日本でもできる限り研究対象を、未来に向ける必要のあることを勧告した」(『戦後マスコミ回遊記』)土光は、イギリス炉よりもアメリカで開発されている軽水炉の2タイプ、沸騰水型と加圧水型に着目し、加圧水型が最も安定性があると評価している。土光のこの見方は、エンジニアとしての「中立性」を裏付けるものだ。原発に限らず、水力発電、火力発電を通して、日本の重電メーカーはアメリカ企業の強い影響下にあった。東芝や日立、石川島などは、発明王エジソンの工場にJPモルガン銀行が出資して拡大したGEと、三菱はロックフェラー財団を後ろ盾とするウェスティングハウスと提携し、技術移転を受けてきた。 土光の石川島は、GEと深い関係にある。GEは沸騰水型の開発を推し進めていたので、系列的には沸騰水型に肩入れをしたいところだろうが、ウェスティングハウスの加圧水型に軍配を上げている。日立の首脳も加圧水型の安定性に注目したが、「技術的に見て、今すぐ取り入れるとすれば、ガス冷却型のコールダーホール以外にないことを指摘し、その点では皆の意見が一致した」(同前)という。
訪英調査団は、帰国後、耐震設計の必要性を特筆した報告書を政府に提出した。
かくして正力が執心したイギリス炉を原子力委員会が購入し、茨城県東海村に据えつけて商業発電の口火が切られる。イギリス炉を置く東海発電所の運営は、民主体で設立された新会社「日本原子力発電」(民間80%、政府20%出資)に委ねられた。
ところが、だ。1959年に契約が成立し、64年に完成するはずだった東海発電所は、トラブルに次ぐトラブルで竣工が大幅に遅れた。最大の難関が耐震性である。耐震設計に手間取った。さらにイギリス製の圧力容器の鋼板にはヒビが入っていた。日本側は交換を求めたが、イギリス側は応じない。しびれを切らして、日本側は日本製鋼所に圧力容器を発注し、調達する。このことがイギリス側のプライドをひどく傷つけ、わだかまりとなった。建屋が造られ運転が始まってからも、出力不足や蒸気漏れなどのトラブルが続く。
結局、日本原子力発電がイギリス側から全施設を引き渡されるのは1969年。予定の倍の歳月がかかっている。その間にコールダーホール型炉は競争力を失い、アメリカの軽水炉ブームが起きる。日本では、まず関西電力がウェスティングハウス-三菱を主契約者に福井県美浜町に加圧水型の原発をつくり、70年11月に運転を始めた。4か月遅れで東京電力は、福島県大熊町の福島第一原発1号炉を稼動させる。こちらの主契約者はGEで沸騰水型である。土光が社長を務めていた東芝、手塩にかけた石川島播磨は、圧力容器製造の下請けで入っている。
このとき、土光は東電の首脳に「アメリカから自動車を1台輸入するのと違って原子力プラントは複雑なシステムなので、当初から日本のメーカーの技術者にチェックさせてほしい」と何度も訴えた。その背景には複雑で危険を伴うシステムへの「恐れ」がある。
だが、東電の首脳は「世界一のGEが自信をもってつくった原子力プラントだ。しかもアメリカで商業運転されており、何ら問題はない。(納入業者の分際で)余計な口出しはしないでもらいたい」とピシャリと撥ねつけたと伝わる。東電はGEの沸騰水型炉を一切設計変更せず、そのまま持ち込み、スイッチを入れれば動く「ターンキー契約」を結ぶ。福島第一原発1号炉は滑り出しこそ設備利用率60%以上を記録したが、73年に地下廃液スラッジ・タンクから床面や建屋外に放射性廃液が漏れる事故が発生。その後も不具合が続き、設備利用率は73年に48.5%、74年は26.2%。75年16.3%と落ち込んでいく。
土光は原発の技術を日本で独り立ちさせたいと願っていた。石油ショックで日本経済が激しく揺さぶられ、その思いはさらに強くなる。財界総理と呼ばれる経団連会長に就任すると、原発のPRに努めた。記者団を引き連れ、一泊二日の日程で福島第一原発の視察ツアーを企画し、自ら案内役を買って出たのである。
現地に着くと、土光は真っ先にふんどし一丁になって黄色の防護服に着替え、原子炉建屋のなかに入った。記者団と随行者も慌てて着替え、恐る恐る建屋に踏み込む。首からガイガーカウンターの入った放射能測定機をぶら下げて巨大な施設を見て回った。カウンターの目盛はずっとゼロの近くを指していた。
秘書課長として土光に付き従っていた居林次雄は、こう証言する。
「まる1日、原発施設を回って、放射能はゼロ。記者の顔つきが変わりました。皆、最初はすごい数字が出るのではないかと震っていたのが、ゼロですからね。へぇーとあくる日から記事が変わるんです。どんどん推進の側へ。この人は、こうやって洗脳しちゃうんだとわかったね。そういうことは口にはしませんよ。ただ、実直に行動しているだけなのでしょうけど、東電の平岩外四社長はじめ、随行者がピッタリくっついたところでやるから説得力がある。もっとも原発の旗振りをする裏では、技術のチェックには厳しかった。原発で小さな事故が起きたら、その電力会社の副社長を呼びつけました。たいてい現場の技術責任者を連れてきて申し開きをしますよね。でも『この箱のなかはアメリカ製なものですから、契約でなかには入れません』といった情けない答弁ですよ」
福島第一原発の視察ツアーの宿では、土光と記者たちの間でさまざまな対話が行われた。ある記者が「なぜ、東海村にあんなに巨大な原子力研究施設が必要なのですか」と訊いた。
土光は答える。
「軽水炉は故障が起きると、一々アメリカにそのデータを持って行って、シミュレーションしてもらって、それまでのデータと照らし合わせて修理をすることになっている。膨大な研究蓄積を持つアメリカに照会しないと修理ができないままでは、本格的な原子力発電は無理だ。日本の経験でデータを集積してシミュレーションを行い、日本自身で故障を修理するには、東海村のあの巨大な研究施設が必要なのだ。もうすぐアメリカに頼らなくても修理ができるようになるだろう。原子力発電については、アメリカの核の傘の下から抜けだして、日本が国産技術で立ち行く日がくるのは近い」(『財界総理側近録』居林次雄、新潮社より、土光発言部分を要約)当時、通産省の官僚と松根宗一や中山素平、今里広記ら財界資源派と呼ばれたグループは、カナダからCANDU(Canadian Deuterium Uranium)炉と呼ばれる重水炉を導入しようとしていた。土光は松根に誘われてアラスカに天然ガス工場の視察に行くほど、彼らとは仲がよかった。が、しかし居林によれば「CANDU炉の話が出たら、終始機嫌が悪かった」という。
「イギリス炉に始まって、いろいろな型を押しつけられて、やっと軽水炉主体で、重水炉については、動燃(動力炉・核燃料開発事業団、現日本原子力研究開発機構)が研究を進める態勢ができていました。ここでカナダからまた炉を入れるなどと余計なことは言うな、ですね。カナダ産の技術はカナダにしかデータが蓄積されていない。何度、同じ過ちをくり返すのかという思いですよ。CANDU炉導入の話は、とうとう潰しましたね」
タービン設計に始まり、欧米の技術を追いかけてきたエンジニア土光にとって、国産技術の確立は生涯の大命題だった。その情熱は、石炭液化や自然エネルギーの開発にも向けられる。古びた自宅に太陽熱システムを取りつけた。ソーラーシステム振興協会が設立されると、その会長を引き受ける。東京渋谷のソーラーハウス展示場を、これまた記者を引き連れて視察して宣伝に貢献する。土光は石炭液化を石油代替エネルギーの切り札と考え、その技術開発に政府と民間が資金投下するよう仕向けて、1980年に「新エネルギー総合開発機構(NEDO、現新エネルギー・産業技術総合開発機構)」が創設される。海水からウランを集める装置にも興味を示した。
土光ほど、自前の石油代替エネルギー技術にこだわった経団連会長は後にも先にもいない。原発については失敗をくり返さないよう、メーカーや電力会社どうしで事故情報を共有する仕組みをつくろうと呼びかけた。だが......電力産業界の東京電力を頂点とする序列は変わらず、原子力ムラは閉鎖的なグループのタコつぼ集団となった。
科学技術庁原子力局で原子力法制に関わった元官僚の島村武久は、退官後の雑誌での対談で、日本と西ドイツの原発導入方法の違いについて興味深いことを語っている。日本がイギリス炉を丸ごと買ったのに対し、西ドイツはアメリカから技術導入はしたけれど自らの手で炉をつくった。
「後発国として外国に学ぶことは必要だったのですが、ただ、そっくり丸ごと買って、サッサと作る日本のやり方と、少し時間がかかっても、お金を払って技術を買って自分の力で作っていった西ドイツの行き方とどっちがよかったのかなと考えますね」(『島村武久の原子力談義』電力新報社)と島村はふり返っている。
「日本はその後も動力炉をアメリカから次々と導入した。これは電力会社がやるんですね。政府は何をやるかというと、新型炉の開発。原子力委員会の提案によれば、高速増殖炉の研究とか、そういうことに対する金を政府が手当てする。つまり主として原研や燃料公社の経費を出す。電力会社は外国から炉を買う。そういうコンペティショナルな炉には政府の金は出さない。民間でおやんなさいという行き方をとった。 ドイツは、最初の国産炉に対して政府が金を出した。ほかの余計なものはやらずに、まず軽水炉の研究から始めたわけです。同じように占領によって研究が禁止されていて、解除を待って同時にスタートした両国の行き方の差が、そこではっきり分かれた。今日では日本の稼動率が非常にいいということを誇っているわけですが、ずっと前から西独は日本よりもっといい」(同前)自前の技術にこだわった土光の思考はドイツのやり方に近い。そのドイツは福島原発事故後、早々と脱原発を決めた。歴史にifは禁物だが、土光がもしも生きていたら、この日本の難局にどんな処方箋を書いただろうか。