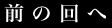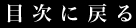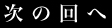第14回
中ソ訪問で起きた経団連襲撃事件
尖閣諸島の領有権問題をめぐって、日中関係は国交回復後40年間で最悪の状態に陥っている。領土問題はナショナリズムを燃え上がらせ、ときに見境のない行動に走らせる。
中国の胡錦濤国家主席は、かつて日本と中国の関係を「政冷経熱(せいれいけいねつ)」という造語で表現した。「過去の歴史問題」で政治が冷え込む一方で、経済分野では互いを求め合い、過熱する状況を指す。ここ数年、政治分野での歩み寄りも模索されたが、いまや断絶寸前。経済まで凍てつきそうだ。もしも一線を超えたら、取り返しのつかない事態となる。
それだけは絶対に避けねばなるまい。「熱願冷諦(ねつがんれいてい)」という言葉がある。熱心に願い求め、冷静に本質をつまびらかにすることの意だ。この姿勢をとり戻すために、もう一度、日中の国交を回復させた世代の行動をふり返ってみよう。政治で国交回復の「井戸を掘った人」は田中角栄元首相だが、経済界で真っ先に中国の扉を叩いたのは土光敏夫であった。
*
経団連会長に就任して2年目、石油ショックで落ち込んだ景気にやっと立ち直りの兆しがあらわれ、土光に「外」を眺める余裕が生まれた。国際的な経済問題に踏み込もうと考えた。では、どこから訪問するか......。
一般的な経済人なら、アメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアの順番で回るところだが、土光は秘書課長の居林次雄を呼ぶと、こう指示を出した。
「隣の国、中国を訪問したい。国際貿易促進協会に話をして、中国訪問の意向がある旨を伝えてくれ。経団連副会長の皆さんにも、ぜひ、一緒に行っていただくよう話してほしい。記者団にも参加してもらおう。中国側と強く交渉するように」(『財界総理側近録』居林次雄、新潮社をもとに要約)
日中の国交が正常化し、「戦争状態」に終止符が打たれたとはいえ、中国はまだ国際的に門戸を開いてはいなかった。中国に渡るには、1954年に貿易を促進するために設立された日本国際貿易促進協会を介して中国側に打診し、招待されねばならなかった。
中国側は土光の意思を受け入れた。土光は、中国の経済発展の役に立ちたいと願い、まずは石油や石炭など中国の天然資源を日本に輸入し、それに見合うプラントを中国に立ち上げて、産業の近代化を図ろうと考えた。その方向で関連大企業の首脳に参加を呼びかける。訪中団は随員を含めて総勢50人ちかくに膨らんだ。陣容が整ってくると、土光は居林に洩らした。
「未だ中国とは十分にコミュニケーションができていないから、訪中したが最後、生きて日本へ帰れないかも知れないな」(同前)
居林はギクッとした。中国民衆の胸には、日本軍に国土を占領され蹂躙された思いが刻み込まれている。恨みはそう簡単に消えるものではない。共産党政府は資本主義国日本の経済団体に厳しく当たってくるだろう。土光の「帰れないかも知れない」という危機感は、そうした対中関係の難しさに加え、日本国内の反共、右派の言動にも起因していたと思われる。
田中角栄は、内閣を組んで間もなく「一番勢いのあるときに日中国交回復をやろう」と外相の大平正芳に持ちかけ、突っ走ったが、国内で最大の妨げが自民党内の反共、台湾派の反発だった。中国は国交回復の条件として、「中国は一つ」の立場から、日本と中華民国(台湾)が結んでいる日華平和条約の停止を突きつけてきていた。つまり台湾との断交を求められたのである。
これに対し、元蔵相の賀屋興宣(かやおきのり)ら右派は「日華条約消滅は不当」「台湾と断交した場合、在留邦人の生命、財産はどう保障されるのか」「台湾が安全保障上の真空地帯となる」「国際信義にもとる」と激しく反発した。右派に立ち向かったのは大平外相だった。「鈍牛」のニックネームとは裏腹に、台湾とは断交後も貿易や経済関係、さまざまな実務的関係が現実的に解決される、と胸を張って反論し、タカ派を押さえ込んだ。
そして田中は電撃的な日中国交正常化を成し遂げた。が、その後も右派の抵抗は続いていた。自民党の石原慎太郎らが結成した「青嵐会」は、台湾との断交に絶対反対を表明し、73年の「日中国交正常化1周年記念」にぶつけて「中華民国断絶1周年訪問団」を結成、台北市を訪ねている。
政治と経済は別とはいえ、土光が訪中に抱いた危険な予感は、外と内の両面から醸されたものだったのだろう。
*
1975年10月、土光率いる経団連訪中団は北京空港に降り立った。熱烈な歓迎を受け、滞在先の北京飯店に入った土光は、中国への警戒心を解く。北京飯店のロビーに掲げられた世界地図を見て、土光は居林に言った。
「北方領土は日本側に入れて、国境線が引かれているね」
同じ共産主義国でありながら、中国はソ連に追随せず、まさに一線を画していた。北方四島を日本の領土と認めている。
歴史的に領土紛争が生じると、当事国は周辺国との合従連衡(がっしょうれんこう)を探る。その伝でいえば中国と日本は対ソ戦術で手を結べる間柄にあるようだった。一方、日中間の尖閣諸島問題については、国交正常化時の「棚上げして後世に託す」という先送り方針を双方とも採っていた。中国の首脳からは日本との協調を求める思いがひしひしと伝わってくる。土光は中国側と包み隠さず話し合う決心をした。
人民大会堂では盛大な宴席が設けられた。土光は、日本では夜の酒席には一切出席していなかった。居林が秘書に就任して、真っ先に取り組んだのは各方面から土光に寄せられる宴席や講演の依頼を片っ端から断ることだった。土光の宴席嫌いは知れ渡っている。土光が下戸だと信じ込んでいる者も少なくなかった。
ところが、土光は山海の珍味が盛られた丸テーブルに着くと、中国要人に勧められるまま、喉も焼けつくような強い酒、茅台(マオタイ)酒を一気に飲み干した。空になった杯を相手に見せ、談笑しているとまた注がれる。土光は嫌な顔ひとつせず、グイッとあおる。あまりの酒豪ぶりに周囲のものは目を丸くした。居林は、そのときの光景をこうふり返る。
「土光さんは人民大会堂ではシャンとして、絶対に醜態を見せまいと気を張っていました。北京飯店へ戻る途中では、さすがに足もとがふらついているようでしたが、80歳目前の土光さんが、あの強い茅台酒を日中親善のためと腹をくくって飲む姿には涙が出そうでした。日本で宴席を断り続けた私には心中が察せられてね......。
ただ、中国側の秘密主義というか、不可解な動きには辟易しました。毎晩、一日の強行軍が終わって土光さんが就寝後、夜中の12時から秘書長の私が中国側の責任者に翌日の訪問先の希望を伝えました。それを向こうは持ち帰り、翌朝、やっと、その日のスケジュールを示します。どんなに早く訪問先の希望を伝えておいても、このパターンが変わらない。朝になるまでどこで誰と会うかわからない。いらいらしました。何回も強硬にあらかじめ全スケジュールを明らかにしてくれと申し入れて、土光さんの次に稲山嘉寛さんが経団連会長になった頃、やっと訪中前に日本でスケジュールを受け取れるようになったのです」
*
日中の経済界に新たなパイプを通した土光は、翌76年8月、こんどはソ連へと足を向け、したたかな近隣外交を展開した。モスクワでソ連商工会議所会頭らと科学技術や原発関連の協力について話し合った後、避暑地のヤルタに滞在中のブレジネフ書記長に会いに行った。製鉄工場の労働者からソ連の最高首脳に成り上がったブレジネフは、土光も舌を巻く。海千山千だった。はるばる訪ねてきた土光に、
「今朝は早起きして、孫たちと水泳をしてきました。9時から朝食と決められていて、1分でも遅れると妻がうるさいんですよ」と雑談から切りだし、それが延々と続いた。
孫だの、妻だの、子どもだのの身辺雑記的な話の合間に、「土光さんがシベリア上空を飛んできたら、大森林、大河川など天然資源の豊かさがバレてしまうからまずい、と皆警戒したんだけど、まぁいいじゃないかと私が言って、飛行を認めたんです」「チュメニやヤクートの油田や天然ガスのプロジェクトに日本も参加していただく話が進んでいます。土光さんも乗りだしてくれませんか」と重要な案件がポツポツと入る。
雑談と高度な政治的話題を混ぜて語るブレジネフに対して、土光は話の腰を折っては失礼だろうと聞き役に回っていたが、1時間以上も相手の独演会が続いて、さすがに我慢の限界に達する。「実は......」「実は......」と口を挟もうとしていた土光が、何度目かの「実は......」の後に意を決して、エネルギー資源をめぐる経済協力の重要性を語り、日本の経済界は前向きだと伝えた。ブレジネフはいよいよ気をよくして饒舌に喋る。会談は予定をオーバーして2時間半に及ぶ。昼食時にさしかかり、上機嫌のブレジネフは山中の宮殿での昼食パーティに土光を招いた。
このとき、同行していた経団連副会長たちは、口々に「島」「島」「島」と土光にせっついた。島とは北方四島のことである。北方領土について切りだせ、というサインを送った。居林は語る。
「ブレジネフの機嫌があまりにいいので、周りの人たちは、北方領土の話をぶつけろ、と土光さんに言うわけです。島の二つ、三つ返還すると言うかもしれない、と思ってね。だけど会談中、土光さんは北方領土については、触れようとしませんでした。後で、なぜ北方領土を持ちださなかったのかと訊ねたら、『外交官でも大使でもない者が、軽々しく島の問題を口にして、ニェット(ノー)と言われたら、どうするんだ。それがマイナスの実績になって、コミュニケに入る。万事休すだろう』と言われました。日本政府にも国民にも相談しないで、勝手なことが言えるか、と土光さんは考えていました。でも、宮殿に向かうクルマのなかでブレジネフ書記長に『日本人の国民感情が大切ですよ』と強く申し入れたと言っていましたね。土光さんは自信ありげでした」
土光とブレジネフがくつろいだ雰囲気で談笑している写真が新聞に掲載された。
帰国した土光を待っていたのは非難の嵐だった。「経済優先のために、北方領土をないがしろにするのは許せない」と糾弾されたのだ。横浜市鶴見の土光の自宅に2日間にわたって右翼グループが押しかけた。経団連も直接抗議を受け、居林ら秘書たちは「聞き役」に回って「礼儀正しく」対応する。ナショナリズムの炎はひとまず消えたかに見えた。
しかし、この年の2月に明るみになった「ロッキード事件」で、日中国交正常化の立役者だった田中角栄が逮捕され、東京地検特捜部に受託収賄罪と外為法違反容疑で起訴されると、政財の「癒着」に批判が集まった。大企業の「社会的責任」が問われ、経団連にも逆風が吹き寄せる。時代の空気は、首相の犯罪で濁りきった。
そして1977年3月3日、事件は起こった。
*
午後4時、東京・大手町の経団連ビルに散弾銃や日本刀を持った背広姿の4人の男が押し入った。「新右翼」といわれる民族派右翼のメンバーたちだった。4人組は「楯の会の者だ」と受付で名乗り、6階に上がって女性秘書課員にピストルを見せて「団長室(会長室)に案内しろ」と迫った。
「楯の会」とは、作家の三島由紀夫が民間防衛の実践組織として大学生を対象に1968年10月に結成した組織だ。三島は、70年11月、市谷の自衛隊を楯の会の会員4人と訪れ、応対した東部方面総監を人質にとり、憲法改正のための自衛隊の決起をバルコニーで叫んだ後、切腹自殺をした。会員の森田必勝(まさかつ)も続いた。この「三島事件」で世間に名が知られた楯の会は、最盛期には83人が集まったが、71年2月に解散していた。
経団連に侵入した男たちは、7階の秘書課に移動すると、会長室との境界にロビーの植木鉢、テーブル、パーテーションなどを集めてバリケードを築く。居合わせた職員と来客12人をいったん秘書室に閉じ込め、全員を壁に向かって立たせた。天井に向けて、「バーン、バーン、バーン」と三発の銃声が響いた。「隊長」と呼ばれる日本刀を持った男が「危害は加えない。われわれは死ぬだけだ」と言い、人質の男性を会長室に、女性を秘書室に分けた。4人組は「日本財界首脳諸君へ」と題した檄文を差し出し、千賀鉄也常務理事に読むよう促す。その後、男性1人、女性7人を解放し、千賀理事ら4人を人質に会長室に籠城した。
「YP(ヤルタ・ポツダム)体制の打倒」を訴える檄文は、次のように書き出している。
「三島由紀夫・森田必勝烈士と楯の会会員が、自衛隊を衷心から敬愛し、かつ信頼していながら敢えてあの市ヶ谷台の挙に及んだに等しく、われわれも敢えて今日この『檄』を日本財界首脳諸氏に対して叩きつける。 大東亜戦争の敗北によって廃墟と化した戦後日本の復興に、財界が少なからぬ寄与をし、如何にその指導的役割を果してきたか、これまでの歴史的事実を、われわれは決して軽んずるものではない。 しかしその反面において、諸君らの営利至上主義が、どれほど今日の日本を毒し、日本の荒廃と混迷を促し、社会世相の頽廃を煽ってきたか、その罪状看過すべからざるものがある。ロッキード疑獄が投じた政治の混乱は、国民の政治不信を抜き差しならぬところまで追い込み、自由社会の根幹をすら揺るがすに至った。 それだけではない。 日本の文化と伝統を慈しみ、培ってきたわれわれの大地、うるわしき山河を、諸君らは経済至上主義をもってズタズタに引き裂いてしまった。」檄文は、この後、水俣病やスモン病患者への心痛に敬虔な反省をしたか、ヘドロ公害、瀬戸内を死の海に追い立てる大企業体質を直視したか、と詰問し、天を恐れぬ所業は日本を、全人類を亡ぼすと断じる。さらに自分たちの悲願は、日本に無条件降伏を強い、アメリカを中軸とする戦勝国の戦後処理で日本の弱体化を敢行した「ヤルタ・ポツダム体制」を打倒することだ、と強調する。
「東洋の君子国といわれた日本の栄光は、いまやかけらほども見出すことはできない。 すべては日本民族の弱体化を眼目としたヤルタ・ポツダム体制の歴史的呪縛にその源泉を見る。だがしかし、この三十年間に及ぶ戦後体制を最も強力に支えてきた勢力が、金権思想、営利至上主義の大企業体質そのものであったことも韜晦をゆるされぬ事実である。 われわれはかくの如く断じ敢えてこの挙に及ぶ。古代ローマは平和を貪ることよって自ら亡んだ。祖国日本が同じ轍を踏むのを座して看過できない。」と、檄文は行動を理由づけ、天皇陛下万歳でしめくくられる。
*
この日、土光は大阪に出張していた。午後5時過ぎに宿舎のロイヤルホテルで記者団から事件の発生を知らされたが、顔色ひとつ変えず、マスコミ関係者との夕食会に臨んだ。その席上、土光は、こう語った。
「......経団連会長室を襲ったのは右翼だ、との情報だが、本来私は右翼であり、右翼から襲われるなどということは、おかしな話だ。大体木の芽どきにはこの種の行為がありがちではないか。私の自宅もいままで無防備だったが、こんなことでは警戒しなければならないということか」(朝日新聞1977年3月4日付朝刊)夕食会後には、次のようにもコメントした。
「檄文の内容は聞いた。趣旨はわかった。不幸な出来事だが、しかし今ここでどうこういえない。彼らの冷却を待つほかないだろう。世の中にはいろんな考えの人がいるが、これまで企業は企業として日本の復興と経済の発展にベストをつくしてきているし、世の中を憂えているのはわれわれも同じなんだ。大企業が世の中を悪くしているわけではない。彼らは誤解している。凶器を持って押し入り、人質をとるなどしなくても、彼らが冷静で、自信があるなら、わたしはいつでも話し合いに応じる。四日は予定通りのスケジュールをこなしてから東京に帰る」(読売新聞1977年3月4日付)夜遅く、経団連に籠城する4人組が大阪の土光と話したいと電話をかけてきたが、土光は就寝しており、取り継がれなかった。内心はともかく、土光は表面的にはまったく動じたそぶりを見せず、粛々とスケジュールをこなしていく。
居林は、事件の発生時、休暇をとって自宅で静養していた。妻から「何だか、経団連が占拠されていますよ」と教えられ、慌てて大手町に向かった。経団連ビルの周りは黒山の人だかりで、野次馬をかき分けて入るのに苦労した。現場に着くと、警視庁の公安部員に「誰が捕まっているか、電話をして確かめてください」と頼まれた。居林が述懐する。
「警視庁の人に、ちょっと誰々さんと名前を呼んでください、と言われて、呼びかけると相手が『はい』と返事をしました。もう殺されるのではないかと肝を潰しながら、ちょっと女の人から放してくださいよ、と説得して、わかりました、と。たまたまブラジルから来ていた日系の方も捕まっていて、その人も早目に解放されました。
電話では、経済外交とか何とか言って、共産主義に尻尾を振ってと非難されましたね。そんなことありませんよ、国民の感情を大事にしていますよ、となだめました。警視庁はしきりに突入すると言うから、まぁ、待って、待ってと抑えてね。大変でしたよ。立て籠もっている側、突入するという警察側、両方なだめるのですから」
4人組の最年長者は「大悲会」の会長、野村秋介だった。野村は1963年7月に、当時
建設大臣だった河野一郎の平塚市にあった私邸に石油をぶちまけて全焼させ、懲役12年の判決を受けて服役する。出所後、既成右翼との絶縁を宣言し、新右翼のリーダーとして活動していた。籠城中の野村は、朝日新聞の記者と電話でこんなやりとりをしている。
――いまのあなたの胸のうち、何でもいいから話してもらいたい。
「これ、僕個人の話だよ。若い人についてきただけだ」
――目的は。
「状況をつくることだよ。戦後三十年がいろんな意味で行きづまってるでしょ。文化、政治経済の一つ一つについ
て、日本人みんながどうしていいかわからない。かといって共産党や公明党にやらしても何もできないよ。いずれ
にしろこれが第一弾だ。戦後体制にピリオドを打ちたいんだよ。ぼくたちは......」
――いま、行動に出てどう思う。
「そうね。こういう歌がある。内田良平という僕らの先輩の『五十年 国を憂いて草莽の野にさまよいて泣きに泣
きけり』」
――いま泣いていますね。
「泣いてるよ」
(朝日新聞1977年3月4日付)
野村は朝日の記者に30分にわたって応答をした。
――あなたは四十二歳なのに、ただのコマンドか。
「若い人を伸ばさなくては。僕は捨て石になっただけ。年配者だから、みんなを死なせたくないだけだ。生命につ
いては生身の人間だから考えているよ。だけど状況次第さ。若い人についているだけで何もしていない。バリケー
ドも若い人たちがやった」
――この日のために何回ぐらい会議をもったのか。
「十五、六回かな。都内の喫茶店とか事務所とか。最終的には二日の午後二時、横浜に集まった。皇居をよう拝
して、靖国神社、明治神宮にも行ったよ。事件前にはサイパンにも行った。バンザイ岬で、飛行機がそのまま沈
んでいるのを見た。戦って死んだ偉い人たちのことを思うと何も言えないね。だれの責任だっていえないよ......」
――なぜ三月三日、桃の節句を選んだのか――。
「きょうは三月三日、旧暦で桜田門外の変、井伊大老がやられた日。いまは昭和幕末なんだ。だからこの日を選
んだ」
――あなた奥さんあるんでしょう。
「いる。しかし、出るときも何もいわなかつた。ただ、ひとこと、カーちゃんごめんよ、そういって出かけてきた
だけ」
――いまの部屋の雰囲気は。
「ゆったりやってるよ。人質も、みんなテレビを見ている。ほかの仲間は銃口を外に向けている」
――散弾銃は使わないでしょうね。
「人質の人たちには使わない。撃つとすれば機動隊だ。向こうがやれば、こっちも......」
電話はいったん切られた。午後11時頃、野村はふたたび電話に出る。
――土光会長に何を望むのか。
「僕は別に会う必要ないと思っている。僕は今回、コマンドだから指令に従っているだけ。僕は年配者だし、失敗
したら責任はとる。ただ、状況の中でどんな方法がよいか模索してるんだ」
――では、どうして土光会長に会見を申し込んだのか。
「いや、僕は土光さんはどうでもいいんです。ただ、こういう状況をつくればいいんです。僕個人があの檄文を書
いたんだけど。土光さんは個人的には立派な人だし......。いま、日本が転換期にきているわけで、土光さんは関
係ないんだ......」
この対話には奇妙な屈折が感じられる。親しみ深い自衛隊で人質をとって立て籠もった三島と、土光を立派な人と言いながら経団連を襲撃した野村には同じような屈折感が漂っている。そこが、この事件を収束させる、ひとつのポイントでもあった。
*
4日の午前零時過ぎ、三島由紀夫の未亡人、平岡瑤子が「私で役に立つなら」と経団連ビルに駆けつけた。6階の一室から7階に立て籠もる男に電話で語りかける。
「あなたはそれでよくても、周りで必ず精神的打撃をこうむる人が出るはずです。私の主人がやったようなことをしてほしくありません」
電話の向こうに沈黙が生まれた。しかし、表だった変化は見られない。たまりかねた瑤子は公安三課の刑事と7階の秘書室に入り、「あなた方の考えは、すでに新聞やテレビで報道され、目的を達成したはずです」と直接男たちに迫った。4人は会長室で話し合った。最年長の野村が「遺書も用意してあるのだから」と自決を主張したが、他のメンバーは瑤子の説得が効いたのか、投降へと傾く。発生から約11時間後、4人組は立て籠もった部屋を片づけ、「手錠をかけないこと」を条件に投降した(野村は経団連襲撃事件から16年後、築地の朝日新聞東京本社に中江利忠社長を訪ね、社長たちと話し合った後で「天皇弥栄(すめらみこと いやさか)」と三度唱え、拳銃で自決する)。
土光は大阪での予定をすべて終えて帰京した。財界は動揺していた。経団連は左翼から労働者の敵と攻撃されるのには慣れていたが、右翼の襲撃を受けたのは前代未聞である。
右翼が財界を襲った例をたどると、戦前、1932年の「血盟団事件」にまでさかのぼる。日蓮宗の僧侶だった井上日召が率いる血盟団は、蔵相を辞めたばかりの井上準之助と、三井財閥の総帥、団琢磨を殺害した。これを機に日本は右へ、右へと傾き、軍国化が進んだ。すでにエンジニアとして社会に出ていた土光が、血盟団事件を覚えていないはずはない。土光と同じ日蓮宗を信奉する団体がひき起こしたテロ事件は、むしろ強く印象づけられたのではないだろうか。右翼に財界が狙われるのは不吉な前兆と受け取れる。
だが、土光は自らの信念を曲げはしなかった。経団連襲撃事件からひと月も経たないうちに、またも経団連訪中団を組織して中国を訪れた。新日鉄会長の稲山嘉寛ら8人の副会長も同行している。中国の工業化を懸命にサポートした。そうした流れから、1977年12月、上海に国策の製鉄所「宝山鋼鉄」が設立され、新日鉄が全面的に支援をする形が生まれていく。
かくして歴史の紆余曲折を経て、日中の経済パイプはつくられたのだった。