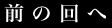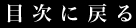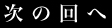第15回
「お国のため。最後のご奉公」──動き出した土光臨調
東北の被災地の復興が進まない。福島県では放射性物質の除染が遅れ、長引く避難生活に人びとは心身とも疲れきっている。予算不足で断念される事業も少なくない。そうした状況下、東日本大震災の復興予算で、被災地の再生とは無関係と思われる事業に大金が使われている。
たとえば、農林水産省の「鯨類捕獲調査安定化推進対策費」として23億円が2011年度補正予算の復興枠に盛り込まれた。これは水産庁への補助金と反捕鯨団体の妨害活動への対策費に回されている。農水省は「被災地の宮城県石巻市は鯨肉の加工が主要産業」だから復興予算で妥当と説明するが、石巻はサバ、カツオ、イカなどが水揚げされる国内屈指の水産基地。「鯨関連の商売はあるが、全体からみればほんのわずか」と地元業者は言っている(「朝日新聞」2012年10月8日付)。
その他にも、外務省のアジアや北米の青少年との交流事業72億円、国土交通省が管理する全国の官庁施設の改修や耐震補強事業100億円、同じく国税庁関連の施設改修事業20億円、経済産業省の中小企業への補助、法務省が管轄する刑務所の建設機械整備費なども復興予算に組み込まれている。
財務省が査定した復興予算は特別会計で管理される。5年間に少なくとも19兆円程度が投じられ、そのうち10.5兆円が「復興増税」で賄われる。増税で確実に手当される予算だから「何でもあり。流用してしまえ」と各省庁は奪い合う。
一方で、国債や借入金、政府保証債務などの公的債務残高は2012年度末に1000兆円を突破しそうだ。財務省は国家財政の危機をしきりに訴え、先の国会で消費増税法が制定された。政府は「消費増税分を社会保障に」と喧伝しているが、どう使われるかわかったものではない。財務官僚が二言めには口にする「財政規律」が最も求められているのは、当の財務当局と中央省庁ではないだろうか。
復興予算が役所の縄張りの拡張に利用されるいま、私たちは改めて重要な政治課題を思い起こさねばなるまい。「行政改革」だ。予算の編成も含めて、国や地方の行政機関や特殊法人の機構、制度、運営などの改革が急務だろう。本来、行革は、行政の合理化、効率化と行政費用の抑制を目的とする。
しかし官僚国家の日本では、中央官庁の権限にメスを入れるのは至難の業とされてきた。
その行政改革に80歳をとうに過ぎた土光敏夫は「老骨に鞭を打って」体当たりをしている。土光が会長を務めた第二次臨時行政調査会、別名「土光臨調」は「増税なき財政再建」をスローガンに行政の手術に乗りだした。「お国のため」が口癖の土光は、行革をどうリードしたのか。土光は、その国民的人気を行革という政治ゲームに利用されただけなのだろうか。土光が挑んだ行革の光と影、可能性と限界へと筆を進めよう。
*
田中角栄とともに日中国交正常化を成し遂げた大平正芳が、首相在任のまま選挙運動期間中に倒れた。総選挙が公示された1980年5月30日、新宿の街頭で第一声を上げた大平は、翌日、過労と不整脈で虎の門病院に入院する。一時は記者団と会見をするほど持ち直したが、二度と国会の赤絨毯を踏むことはなく、6月12日早朝、逝去した。
偶然にも田中と大平の首相としての最後の大きな公務は「外遊」だった。国際関係の緊張がもたらすエネルギー危機への対応、いわゆる「資源外交」だった点も共通している。
田中は文藝春秋の金脈報道を機に「金権批判」で火だるまになりながら、1974年11月、ニュージーランド、豪州、ビルマ(現ミャンマー)歴訪に旅立った。外交のメインテーマは、豪州との「石炭、鉄鉱石、ウラン」の輸入契約のこじれを正すことだった。原子力発電に欠かせないウランに関する交渉では、核開発につながる「濃縮」を議題に、緊迫したやりとりが行われた。ウラン調達の見通しをつけた田中は、「日本は豪州におけるウラン濃縮を原則として好ましいと考えるものであり、豪州と協力してその可能性を研究する」と語っている。資源の確保を自主独立路線で模索した。
大平もまた、イラン革命後に起きたテヘランでのアメリカ大使館人質事件や、ソ連のアフガニスタン侵攻への対応に追われるなか、アメリカ、メキシコ、カナダを訪問している。同盟国アメリカは、日本にイラン制裁への同調と、アフガン危機の周辺諸国への波及を抑えるためのパキスタン援助を求めてきた。大平はアメリカとの協調路線をとるが、「日本には日本独自の利害や立場があり、必ずしも全面的に米国に同調するわけには行かない」ことをどうやってアメリカに納得させるかに腐心した(『大平正芳回想録──伝記編』鹿島出版会)。
1980年5月、ワシントンでカーター大統領と対面した大平は、日本はアメリカと「共存共苦」の姿勢で臨むと表明。アメリカが求める防衛力整備も受け入れ、対米協力路線を鮮明にする。メキシコでは石油の供給を日量10万バレルから30万バレルに増やしてほしいと申し入れるが、ロペス大統領の確約は得られなかった。カナダでは、アメリカの単独行動を防ぐために自由主義諸国の連帯を呼びかける。さらに大平はカナダからユーゴスラビアに飛びチトー大統領の葬儀に参列し、ハードな日程を終えた。その直後、選挙戦に突入し、急死したのだった。
田中も大平も外遊の公式日程はかなり前に決まっていたので、政治生命の終焉と外遊が重なったのは単なるめぐり合わせかもしれない。しかし、ともに青年期に戦争を経験し、敗戦、連合国軍の占領から講和、復興、高度成長と、時代とともに政治の階段を駆け上がる過程で、外交的には自主独立路線を志向した。日中国交正常化は、その象徴といえるだろう。
そうした二人が、日本のアキレス腱であるエネルギー資源を確保する外遊を節目に、政治の表舞台から退場している。田中は「闇将軍」として政界で隠然たる力をふるってはいたものの、ロッキード事件で起訴され、刑事被告人の身となった。時代の地下水脈は複雑に絡まっているとはいえ、田中と大平の退場は、時代の移り変わりを印象づける出来事だった。
*
財界にあって、土光敏夫もまた自主独立路線を堂々と主張していた。評論家の草柳大蔵との対談で、1968年のソ連訪問に触れて、こう語っている。
「あのとき、アメリカのGE、ジェネラル・エレクトリックのやつが、石坂泰三さんに土光をソ連に行かすのをやめさせてくれと言いおった。もしソ連に出かけたら、アメリカのビザがおりなくなるおそれがあるとおどすんだね。だからわしは、ビザがおりなくてもいい、アメリカがそんな狭量じゃ仕方ないね、と言ってソ連行っちゃいましたよ」(「週刊文春」1972年9月11日号)
草柳がアメリカとは自由化でもいろいろあっただろうと問うと、次のように応える。
「どうもむこうの財界人というのは怠慢でね。日本がアメリカの品物を買ってくれない、買ってくれないと言うんだけど、売る努力というのを全然しないんだな。アメリカが日本に売れるものはなにかという研究もまるでやってない。製品の品質だって、日本のもののほうが断然いいんですよ。これもGEなんだけど、わしのところにきて曰く、日本のテレビは調節をちょっとすれば、きれいな画面がうつる。あとはいじらなくてもいい。ところがアメリカのはそういうわけにはいかんというんだな」(同前)
こんにちの財界首脳で、これだけ率直にアメリカ観を語れる者がいるだろうか......。
時代の変化は足並みをそろえてやってくる。大平が亡くなる直前、土光も経団連会長を退任した。土光は新会長に新日鉄の稲山嘉寛を指名し、名誉会長に収まる。日中経済協会の会長職を除いて、公職のほとんどを辞退した。もう84歳、残り少ない人生を好きなように過ごしたい、と願った。
秘書室長の居林次雄には「少し時間的余裕ができたようだから、日本中の原子力発電所を行脚して、安全性の総点検をしてみようか」などと洩らしている。「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」といった心境であろう。
ところが、土光の清貧な暮らしぶりと財界でのカリスマ性を眺めて、目を爛々と輝かせている政治家がいた。自民党の保守傍流で、総理の座をうかがう中曽根康弘である。
自民党は大平の弔い合戦となった総選挙で大勝した。後継総裁候補には、派閥の領袖である中曽根の名もあがったが、大平派の鈴木善幸が「和の政治」を唱えて新総裁に選ばれる。「今度こそ」と自信をみなぎらせていた中曽根は、「先に名のりをあげたら叩かれる」と風向きを読んでいるうちに党内の流れが鈴木に傾き、またもや「次」に回された。
*
「待った」をかけられただけではない。中曽根派を出た渡辺美智雄が大蔵大臣に選ばれたのに対し、中曽根自身は自派の宇野宗佑が辞めた後の「行政管理庁長官」をあてがわれる始末だった。行管庁長官は国務大臣とはいえ、利権と遠い、伴食大臣(ばんしょくだいじん)。閑職とみられていた。運輸大臣や通産大臣を歴任した中曽根にとって「降格人事」にも等しい。派閥内では「子分の跡継ぎに親分が行くのか」と囁かれる。口の悪い永田町雀は「これじゃ雪隠詰(せっちんづ)めだ」などと噂し合った。
しかし、中曽根は「ここが勝負どころ」と行管庁長官に就任する。田中角栄と同い年の中曽根は、すでに62歳。宰相の座を狙うには、そう時間が残されているわけではない。鈴木内閣に密着して時勢をつかみ、機を見て大勝負に出る戦術を選んだ。新閣僚が顔をそろえた1980年7月17日の夜、中曽根は記者会見で機先を制するかのような発言をした。
「行政改革は今内閣の最大の課題の一つで国民の強い要請もあり、誠心誠意、一生懸命その実をあげていきたい。行革は内閣全体としてやっていかねばならず、初閣議の席上、首相が陣頭指揮で声をかけてくれと(鈴木首相に)お願いした」(「朝日新聞」1980年7月18日付)
中曽根は、行革を内閣の使命に押し上げ、「80年代の状況を見こして、行政の哲学、体系を考えたい」とビジョンづくりを鈴木首相に申し出る。行革を政権奪取の切札としつつ、そこに戦後政治からの脱却、国家像の転換を巧妙に仕込んだ。社会保障費などを削って「小さな政府」に変え、生まれた財源を国防や海外援助に向けようと中曽根は考える。福祉国家から総合安全保障国家への転換を行革に託そうとした。
英国では「鉄の女」マーガレット・サッチャーが、ひと足早く首相に就任し、規制緩和や民営化を通して「小さな政府」への脱皮を図っていた。中曽根は、連日、行管庁の加地夏雄事務次官ら幹部クラスを集めて御前会議を開く。そこから、行革の命運を左右する仕掛けが浮上する。「第二次臨時行政調査会」の設置である。
「第二次」というのは「第一次」があったからだ。池田勇人内閣の1962年2月から9月にかけて、三井銀行会長の佐藤喜一郎を会長とする第一次臨時行政調査会が設けられている。貫禄のあるメンバーがそろった第一臨調は、1000頁を超える答申を出した。首相の補佐機関としての「内閣府」、首相ブレーンの「内閣補佐官」などの新設を提言する。内閣補佐官は予算編成で主導的な役割を果たす、と位置づけられた。省庁再編で実際に内閣府が設けられるのは2001年だから、40年ちかく時代を「先取り」していたといえる。
この画期的な第一臨調答申は、しかし官僚からは猛反発を食らう。なかでも予算編成権を脅かされた大蔵省は、答申を「素人の作文」と蔑み、感情的に反発した。第一臨調答申は、池田首相が病気で退陣し、経済が高度成長期に突入して「小さな政府」論が後退するとともにお蔵入りとなった。
中曽根と彼に知恵を授けた加地事務次官らは、低成長のいまだからこそ、官僚たちを狼狽させた臨調をふたたび立ち上げ、行政の刷新をしようともくろんだ。1980年9月中旬には第二臨調設置が閣議決定され、11月末、国会で設置法案が成立する。あれよ、あれよと言う間に政治主導で第二臨調の立ち上げが決まった。
ただ、財界は、一連の動きを中曽根のパフォーマンス、大風呂敷と突き放していた。耳に心地よい理念やビジョンより「実」が伴うかどうかが大切だ。財界の関心は、行政改革が財政再建と結びついているか否かに寄せられていた。もっと言えば、「増税をしないで行革で無駄を削り、財政危機を凌げ」と望んでいたのだ。経団連は鈴木政権発足直後、「増税を前提とせず、徹底した行政改革を」と政府に要望している。
中曽根の個人的思惑はともかく、行革が社会的課題として急浮上した背景には、国債の増発による財政危機があった。1970年代前半、「日本列島改造論」の看板を掲げた田中内閣は大量の建設国債を発行した。続いて福田内閣は石油ショックのダメージを和らげようと赤字国債(特例国債)の発行に踏み切る。膨れ上がった国債残高は、鈴木内閣が誕生した当時、82兆円に達していた。その償還と利子払いに充てられる国債費は毎年25%前後の伸びを示す。地方債の40兆円と合わせると日本人一人当たり約100万円の借金を背負った、とメディアは警鐘を鳴らした。赤字国債依存から脱することが、大平政権以降の政治テーマになっていたのである。
公的債務残高が1000兆円を超えようとしている現在から眺めれば、たかだか百数十兆円の国債残高と思うかもしれないが、財政の病巣が拡大し始めた30年前も危機感は募っていた。財政危機の構造は同じだ。危機を克服する手段はいまも昔も変わらない。政府には、財政危機に対して、特殊法人の余剰金の吸い上げや補助金カット、公務員の人件費削減、不公平税制の是正、優遇税制の見直し、所得税や法人税の引き上げ、大型新税(消費税)の導入(増税)などの選択肢が与えられている。
現代の野田佳彦政権は選挙公約を翻して消費増税を選んだわけだが、大平内閣は一般消費税の導入を政策の柱にして1979年の総選挙に臨み、惨敗を喫した。後継の鈴木内閣にとって大型新税を選ぶことは禁じ手となる。鈴木は、首相就任直後、税の自然増収を模索し、当面は歳出の見直しで対応する、と述べた。増税と財政再建は切り離されたかに見えた。
が、しかし80年12月、自民党税調は法人税率の2%引き上げを含む1兆3900億円の大増税を柱とする「81年度税制改革案」を決定した。印紙税や酒税、物品税など幅広く増税する方針案だ。財界には、ろくに歳出削減の努力もせず、財政再建を口実に増税をくり返されてはたまらない、と鈴木政権への不満が鬱積する。
「風見鶏」は機敏に反応した。財界の嫌悪を感じ取った中曽根は、第二臨調に財界を取り込まねば行革の成算はない、政権奪取も遠のく、と読む。第二臨調の会長にはカリスマ性を備えた人物を配し、組織をいわば神格化して行革に反感を抱く官僚たちを抑え込もう、カリスマのもとに各界の代表者を集め、第二臨調の権威を高めよう、と動きだす。明治維新で天皇が朝敵征伐の証に官軍の大将に与えた「錦の御旗」に相当する人物を、中曽根は欲したのである。
そして白羽の矢を立てられたのが、経団連会長を辞めたばかりの土光敏夫であった。
*
中曽根は回想録『天地有情』(文藝春秋)に、1967、68年頃、東芝の社長だった土光を食事会に招いて話を聞き、意気投合した、と記している。「荒法師のようで、太っ腹で、ひじょうに頑固で、また寛厳よろしきを得るところがあった」と述懐する。土光を首相の鈴木に推薦した局面については、次のように書いている。
「......八〇年暮れから土光さんを頭の中に置いていて、明くる年の正月参賀で、天皇陛下をお待ちして列立しているときに、皇居の梅の間で、隣の鈴木さんに『第二臨調の会長さん、誰にしますかね』といったら、『いい人いますか』というので、『土光さんはどうですか』といったら、『うん、あの人なら据わりがいいですね』って。鈴木さんという人は、そういう表現をする人でしたね。それで決まりでした」
皇居の梅の間での鈴木首相への人事の打診は、権威づけにはもってこいのシチュエーションだったが、「それで決まり」とはいかなった。中曽根は旧知の経団連事務総長、花村仁八郎に土光の説得を委ねる。土光は、要請をきっぱりと断った。
「冗談ではない。わしはもう84歳を過ぎた老骨で、やっとの思いで経団連会長職を引退させて貰ったばかりであるから、臨調会長というような大役は引き受けられない」(『財界総理側近録』居林次雄、新潮社)
「行革の責任者はもっと若い者に」と辞意は固かった。土光の意向は政府に伝えられるが、鈴木首相も中曽根行管庁長官も引きさがらない。行革で形勢逆転を賭けた中曽根は、行管庁の元官僚を介して、出張先の名古屋から東京へ新幹線で移動中の土光に「大至急会いたい」と伝える。わざわざ新幹線に電話を入れて熱意のほどを示したわけだ。中曽根は帰京した土光とホテルニューオータニで会い、正式に臨調会長への就任を求めた。土光は「日本には明治生まれはもう5%もいない。このような年寄りを使うこともあるまい」と拒んだ。
しかし、外堀は徐々に埋められていく。土光が経団連に戻ると、稲山はじめ大槻文平ら幹部が「財界をあげて支援するので臨調会長に就任してほしい」と声をそろえて言う。行革は官僚機構にメスを入れ、痛みを強いる。その先導者に求められるのはカリスマ性とともに身綺麗さである。叩けば埃のでる体では、他人に我慢を要求できまい。その点、倹(つま)しい生活を貫く土光の右に出る者はいなかった。花村は居林に「土光説得」の厳命を内々で下し、経団連内で行革を担当していた調査役の並河信乃を新たに土光の秘書につけた。
ついに明治人の土光は「お国のため。最後のご奉公」と臨調会長への就任を受ける。1981年2月26日、衆議院本会議で土光を会長とする臨調人事が賛成多数で承認された。中曽根は土光を「表」の象徴に持ち上げる一方で、自民党や官界との調整という「裏」の汚れ役に伊藤忠商事会長の瀬島龍三を指名する。瀬島ほど多くの謎を秘めたまま人生の幕を閉じた現代史のキーパーソンはいない。
1911年に富山県西砺波郡の農家に生まれた瀬島は、陸軍大学を首席で卒業し、太平洋戦争時には陸・海軍の最高統帥機関である「大本営」の作戦参謀を務めた。ガダルカナル撤収作戦、インパール作戦などを指導した後、関東軍参謀に任命され、満州へと赴任した。
敗戦後、ソ連の捕虜となり、シベリアへ抑留される。46年9月、瀬島はウラジオストクから空路東京に護送され、東京裁判に訴追側証人として出廷した。証言後、ふたたびシベリアへ戻され、56年まで11年間に及ぶ抑留生活を強いられた。
その間の詳しい収容所生活を瀬島自身は語っておらず、後にアメリカに亡命したソ連の諜報員、対日工作者らは、瀬島がソ連の工作員として訓練されたと証言している。大本営の参謀時代には、ソ連の対日参戦の情報をつかんだ欧州駐在武官からの最高機密電報を握りつぶしたという説もある。帰国後、繊維商社の伊藤忠に入った瀬島は、さまざまな案件に情報力と行動力をもって当たり、同社を総合商社へと成長させている。
瀬島への毀誉褒貶は激しい。国士、愛国者と尊敬される反面、尊大で自身を大きく見せたがり、秘密主義者と批判されてもいる。いずれにしても記憶力はずば抜けており、頭のキレは抜群だった。たとえば物事を説明するときに、○○には五つのとらえ方がある、一何々、二何々、三云々、と大局を押さえ、ポイントを要約して語る癖があった。参謀本部で叩きこまれた流儀のようだ。技術者から経営者に出世した土光と、まったく異なるキャリアと個性をもつ瀬島。ふたりの間には、臨調のスタート時から微妙な空気が滞留していた。
*
1981年3月初旬、土光と鈴木首相の正式な会談を前に、経団連側のスタッフと瀬島が意見をすり合わせる会合が持たれた。瀬島は、その席で「内閣総理大臣を長とする行革推進本部を設置すること」と書いたペーパーを持ち出す。政府と自民党が一体となって行革を進めるには、双方のトップである総理を頂点に置いた本部が必要と示した。瀬島は、行革論議のコンテンツよりも臨調を運営する組織的環境を重視していた。
土光の臨調担当秘書となった並河は、瀬島のペーパーを見て、「こんな事務的なものでは意味がない」と思わず口走る。瀬島のこめかみがピクッと動いたようだった。
並河が回想する。
「余計なことを喋ったもんだと思いますけど、瀬島さんは自民党筋と調整して、党が本腰を入れるには総理を本部長にしてやれ、と土光さんの口から言ってほしかったのでしょう。それはそれで大事かもしれないが、総理と土光が会ってする話かなぁ、と。僕らは、もっと大事なことを言ったほうがいい、年寄りのホワホワした話で終わらせず、証拠というか、何か紙に書いて渡そう、と考えました。そして、土光の気質を熟知している秘書室長の居林さんらと相談して、総理に突きつける四カ条の原案を僕がつくりました」
居林が「四カ条」に込めた思いは、文案を作った並河とは少しばかり違っている。居林は、政府が呑めない難題を証文に入れたら、総理も行管庁長官も証文に判を押せまい。ならばそれまで、と席を立てばいい、とぎりぎりまで土光の臨調会長職返上を探っていたのだ。
それぞれの意図を織り込んだ四カ条が紙にタイプされた。
一、行政改革の断行は、総理の決意あるのみである。臨時行政調査会会長を引き受けた以上、審議を十分に尽くして満足のいく答申をとりまとめるよう、最大の努力を払うが、総理がこの答申を必ず実行するとの決意を明らかにして戴きたい。
二、行政改革に対する国民の期待は、きわめて大きなものがある。アメリカのレーガン政権を見習うまでもなく、この際徹底的な行政の合理化を図って「小さな政府」を目ざし、増税によることなく財政再建を実現すること......。
三、行政改革は、単に中央政府だけを対象とするのではなく、各地方自治体の問題を含め、日本全体の行政の合理化、簡素化を抜本的に進めていくこと......。
四、またこの際、3K(国鉄、健康保険、米=生産者米価)の赤字解消、特殊法人の整理、民営への移管を極力図り、官業の民業圧迫を排除するなど民間の活力を最大限に 活かす方策を実現すること......。
「答申の実行」「増税なき財政再建」「地方の行政改革」、さらに強力な労働組合を有する国鉄や電電公社などの「民営化」は、どれも針の穴にラクダを通すほど難しい。とくに財界の悲願「増税なき財政再建」は、政府の手足を縛る。現実的には不可能に近かった。
「これならば政府も手が震えて、証文に判が押せないだろうな」と土光も満足気だった。
ただし、かけ引きでは政治家が一枚上手である。3月11日、官邸の朝食会で土光から証文を見せられた鈴木首相は「政治生命を賭けます」と証文に判をついてしまう。土光は退路を断たれた。朝食会に同席した中曽根は、回想録で述べている。
「『増税なき財政再建』というのは、これはやれるかなと一瞬迷ったが、やるといわなければいけなかったから、『やります』といって......(笑い)。そして、党と内閣が一体の推進本部をつくって私が本部長代行になって、七月緊急答申をやるというようなことまでいいました。すると、鈴木さんは『この仕事をやりとげれば、自分はもうこれでいい』といいました。つまり、鈴木内閣の仕事はこれに尽きるという意味だったのでしょう」
四カ条には行革の大方針がすべて示されていた。
ここに第二臨調という高度な政治ゲームの開始が告げられたのである。