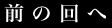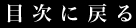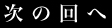第16回
「増税なき財政再建」、シーリングで機先を制する大蔵省
財政危機はウィルス性疾患に似ている。財政赤字というウィルスが増えすぎると国家の機能は蝕まれ、破たんする。この厄介なウィルスは、景気の変動に乗じて侵入してくる。
日本経済は、戦後復興期から高度成長期にかけて右肩上がりで成長した。経済企画庁の予測を超えた成長は、税収の自然増をもたらし、国や地方自治体の財政を膨張させた。
官民の金の流れを支配したのは大蔵省(現・財務省)だった。予算の編成と配分、税の徴収、金融の三大権力を握る大蔵省は、予想以上に膨らむ国の財布で追加補正予算を組み、特別会計の余剰金や積立金などの隠し財源をこしらえる。政治家は、大蔵省に取り入り、あるいは圧力をかけて、その金を引き出す。有権者の要望に応える形で大蔵省に要求を突きつけて、道路を造り、鉄道を引いて、橋を架ける。利益を誘導し、選挙で票を稼ぐ。各省の官僚は利権を持つ企業や団体に天下った。出先機関や特殊法人が次々と設立され、行政機構は肥大して、利権獲得競争がいっそう過熱する。
このパターンが定着し、財政は硬直した。
1970年代前半、「日本列島改造論」の看板を掲げた田中角栄内閣は、公共施設を造るための「建設国債」を大量に発行した。列島改造論は、地方に産業を分散して人口の都市集中に歯止めをかけ、地方圏が自立することを構想した。国土維新ともてはやされたが、高速道路網や本四架橋など公共事業の候補地があからさまになり、土地投機を招く。全国の地価が火の粉を吹いて舞いあがる。そこに石油ショックが襲いかかった。景気は落ち込み、民間企業は合理化と賃金カットで耐え忍ぶ。製造業は15%ちかく人を減らした。
不況の底で、福田赳夫内閣は赤字国債(特例国債)の発行に踏み切る。ついにウィルスが国庫に入った。赤字ウィルスは瞬く間に増殖し、鈴木善幸内閣が誕生したときには、国債残高が82兆円に達していた。地方債の40兆円と合わせて、国民一人当たり約100万円の借金を背負ったことになる。対GDP比の国債比率は30%を超え、財政運営に赤信号が灯る。政府は「財政再建待ったなし」の状況に追い込まれた。
一方、役所の行政機構は、民間企業が身を切り刻んで石油ショックの荒波を乗り越えている間も漫然と膨らみ続けた。公務員の給与や年金、退職金は当たり前のように上がる。民間の不満が鬱積し、もはや財政と行政の改革は切り離せなくなった。
そこで第二次臨時行政調査会(土光臨調)は、財政と行政の一体改革を自らの使命としてスタートしたのだった。土光敏夫は鈴木総理との事前会談で「増税なき財政再建」の確約を取りつけた。鈴木首相は、行政改革の実行に「政治生命を懸ける」と言明する。行革担当の行政管理庁長官、中曽根康弘も「政治生命を懸ける」と続く。次の宰相の座を狙う中曽根にとって、鈴木との一蓮托生は危険な賭けではあったが、あとには引けない。
政界と財界は行革で手を握り、マスメディアも土光臨調の発足を賑々しく盛り上げる。行革は時代の趨勢へと高まった。
が、しかし、行革のメスを入れられる官僚は内心穏やかではない。官庁のなかの官庁を自負する大蔵省は「増税なき財政再建」を臨調主導で行われたら、メンツを失う。それが既成事実となって、予算の編成と配分という権力の源泉に踏み込まれると警戒した。省は国家なり。臨調をいかにコントロールするか。大蔵省は策を練った。
自民党の政治家も本音と建前は別だった。国民が支持する行革に正面から反対するわけにはいかないが、具体的な各論で、補助金カットや特殊法人の整理で自らの利権が侵される局面になれば、反旗を翻すのは間違いない。また傘下に公務員の労働組合を擁する日本労働組合総評議会(総評)も、総論では行革の意義を認めているけれど、自治体や国鉄、電電公社、郵政などの組合員の雇用や給与に斬り込む各論には反対するはずだ。
土光臨調は、表面的にはメディアのバックアップもあって華々しく立ち上がったが、内側には多様な利害の対立と主導権争いを抱え込んでいた。それらにどう折り合いをつけて、行革の「実」をとるか。臨調とは、言いかえれば高度な政治ゲームであり、調整のドラマだった。攻防の焦点は、1982(昭和57)年度予算を「増税なき財政再建」の方針で組めるかどうか。増税せず、国債の発行も抑え、徹底的な歳出カットで「小さな政府」へと方向を変えられるか否かにあった。
*
1981年3月16日、永田町の首相官邸大客間で臨時行政調査会の第1回会議が開かれた。
「秘」の印を押された「第1回臨時行政調査会議事録」に参加者の発言が記録されている。冒頭、鈴木首相は、財政再建の重要さを力説し、「短兵急なお願いではありますが、昭和57年度予算の編成に向けて、当面の要請にこたえる具体的改革案を、この夏までに御提出いただければ幸甚でございます」と第一次答申の提出期限を夏、7月10日と区切った。いかにも急な話だが、国の予算決定の過程を考えればぎりぎりのタイミングだった。
例年7月ごろに大蔵省が各省に示す「シーリング(概算要求基準)」が閣議決定される。シーリングとは歳出の増大を抑えるための要求限度額であり、国の重点投資項目を示したものでもある。これに従い、各省は8月末をめどに、政策の実施に必要な経費を要望書にまとめて大蔵省に送る。この各省の概算要求を大蔵省が査定を通じて削り、閣議決定を経て12月末に政府予算が決まる。7月10日という答申期限は、大蔵省のシーリングに間に合うかどうかの微妙なタイミングであった。スケジュールは審議の流れを左右する。
官邸での臨調会議、鈴木首相の挨拶の後、中曽根行管長官が行革の課題をあげた。
「今日、我が国行政情の諸問題を顧みますと、高度成長社会から安定成長社会への移行という時代の大きな流れの中で、行政が、巨額の財政赤字を始めとする多くの困難と経済の発展、高齢化社会への移行、科学技術及び情報メカニズムの発達、国際的役割の増大等に伴う新たな課題にどのように対処するのかがいろいろな局面で問われております」(第1回臨時行政調査会議事録)
さらに「民間や地方の活力を生かし、行政と民間との間や国と地方との間の効率的な役割分担を図ることが重要であります」と訴えた。中曽根は「小さな政府」への転換でバラまき福祉の財源を削り、安全保障や科学技術振興、海外援助に振り向けようとイメージしている。総合安全保障型の国際国家を志向していたといえるだろう。
続けて、土光は、持ち前の大声で決意を表明する。
「我が国の行財政は、おそらく数年先には全く手の付けられない状態になることが必定であると思います。政府は行財政の立て直しに全力を挙げるとの姿勢を表明されましたが、我々としても、例えば行政としてなすべき仕事の範囲、程度や行政の諸制度を抜本的に再検討するなど、国民の立場から行政の在り方についてはっきりした考え方を一致協力して打ち出し、真に国民の求める新たな時代に即応する行政の実現を図りたいと考えております」(同前)
そして「最も肝心なこと」とことわって、「政府、特に総理は、この調査会の意見を単に尊重するというのではなく、勇断をもって必ず実行していただきたい」と迫った。鈴木首相に約束を守れ、と公の場で念を押したのである。土光の行革にこめた執念が伝わってくる。臨調における政官財の主導権の争奪が始まった。
*
政府の諮問機関の活動は、スケジュールと委員の人選、事務局体制で決まるといわれ、審議が始まった時点で大勢が決しているケースもある。
第二臨調の事務局は、中曽根に行革の知識を刷り込んだ行政管理庁の官僚が押さえた。事務局長に行管庁事務次官の加地夏雄、臨調準備室長(第一次長)に佐々木晴夫、第二次長に山本貞雄が就任する。第1回の臨調会議で、事務局長の加地は、臨調のテーマを再確認したうえで、「議事録の非公開」を委員に告げた。
「議事録も非公開です。そこで(略)会議があるたびに大変、お忙しい先生方の所へ大変な取材というのがでてくると思うんです。そこでそれを、なくするために、この調査会でスポークスマンと申しましょうか、その時の会議が終わった時に大きな会議の事項でございます、審議の流れでございますが、審議の非公開の原則がありますから、その原則の範囲内で会議の状況っていうのは、どなたかが、やはり、記者会見をいたしまして、ご説明してゆくのが、どうであろうというふうに考えています」
「どなたかが」と言いながら、結局、スポークスマンは加地自身が務めることとなる。情報の蛇口を握ったのは事務局であった。事務局は委員の人選にも大きく関わっている。
まず会長の土光を含めて9人の委員が選ばれた。
財界からは土光と伊藤忠相談役の瀬島龍三、旭化成工業会長の宮崎輝の3人。官界から元大蔵事務次官で資本市場振興財団理事長の谷村裕、旧内務官僚で日本赤十字社社長の林敬三。労働界からは総評副議長の丸山康雄と全日本労働総同盟顧問の金杉秀信。学界からは行政学者の辻清明、そして言論界より日本経済新聞元社長の円城寺次郎が選出された。
当初、財界枠は2人といわれていたが、経団連など財界5団体の代表が「行革推進五人委員会」を設けて、全面的なバックアップを表明して1人増えた。
委員の陣容は財界主導のようだが、大蔵省出身の谷村、労働界の丸山と金杉ら、一癖も二癖もある人物が並んでいる。そのなかで副代表には新聞人の円城寺が選ばれる。政府の審議会委員を数多く務めてきた円城寺は、官僚を動かす独特のコツをつかんでいた。
政治家や官庁への根回し役を買って出たのは瀬島だった。瀬島は中曽根と連携しながら、行革の実行部隊と目される政府・自民党一体の「行政改革推進本部」の設立へと動く。「表」の土光、「裏」の瀬島、「審議」の円城寺とトロイカ体制が敷かれた。経団連の行革担当調査役で土光に秘書として付いた並河信乃は、三人の関係をこう語る。
「土光さんは、自分にできないことを瀬島さんに任せた。ひと言でいえば、汚れ役。ただ瀬島さんを信頼していたかどうかは知りません。自民党内の情勢分析などは瀬島さん経由で入りました。それを聞いて、土光さんは土光さんで動く。ただ瀬島さんの情勢報告は、誰でも知っている話が多かった。結果が出るまで肝心なことは言わなかったのでしょう。円城寺さんは審議会のボスのような人で、役人の操縦術を心得ていた。気難しい人ですが、土光さんには全面協力でした。論理の組み立て、ものの言い方とか、書き方、役人の世界で通りやすい筋立てを知っていた。われわれは斧で木を伐るような直接的な表現をしがちですが、それでは役人の世界では通らない。審議会で延々と議論してきた円城寺さんは、そこをわきまえているから事務局を手なずけられる。事務局も彼には相談しやすい」
土光、瀬島、円城寺のトロイカ体制で委員会は始動する。
とはいえ、わずか9人の、それも行政運営については素人の委員が、国防から医療、教育、下水道整備にまで及ぶ広範な行政の改革に向けた緊急答申を7月までに書けるはずもない。具体的な政策論議は「専門委員」に委ねられた。専門委員こそが臨調の実戦部隊だ。その数21人。そこに各省からの出向者が多数を占める調査役78人が入って、手足となって動く。さらに参与39人、顧問5人も加わる。事務局スタッフを含めて、総勢200人ちかくに増えていく。3月23日の第2回臨時行政調査会の会合の席で、円城寺は釘を差した。
「小さな政府といって臨調だけが大きなものになったのではしょうがないですが。やっぱり顧問、参与のこと反対はしないけれども、なってもらったら、ちゃんと意見を聞くという、そういう運営をしないと形だけの大きな臨調を整えたって、これはおかしなことになるのでね」(第2回臨時行政調査会議事録)
しかし、このとき、各省間で専門委員や調査役、参与の椅子取り合戦は始まっていた。ようすを見ていた大蔵省は、情報を出すから議論に参加させろ、とアプローチしてきて、実務の鍵を握る調査役に12人も送り込む。専門委員会の重要性を知った他省はOBの事務次官経験者を専門委員に押し込んでくる。その顔触れは、元建設事務次官・大津留温、元運輸事務次官・住田正二、元農林事務次官・中野和仁、元通産省重工業局長・赤澤璋一らだ。行管庁も元事務次官の河合三良を専門委員に入れて、総合調整のポジションを握る。
文部省だけが出遅れた。土光臨調の存在を軽視し、京都大学総長を専門委員に選ぶほど鈍感だった。その遅れが、後に文教予算の削減という手厳しい結果を呼び込むのだが、ともあれ、ほとんどの省が調査役にエース級の課長補佐クラスを投入してきた。事務局長の加地は調査役のリストを眺めて、「へぇー、こりゃすごい」と舌を巻いた。
官の包囲網を感じた土光は、23日の第2回臨調会議で他の委員とこんなやりとりをしている(以下、第二臨調の会議における出席者の発言は当時マル秘にされていた議事録に基づく)。
土光「オイルショック後の大変問題になった時には、なんとかしてつぶれないようにもっていったわけです。政府はそれをやっていないんですからね。政府は過去にやるべきことをまだやっていないんだから、研究してもらわなければ困る」
瀬島「4月13日に大蔵省の説明がありますね。その時に、いま宮崎委員がおっしゃった緊急課題に対する要点(税収の見通しデータ)を、特に大蔵省から委員会に説明してもらうそうですが」
土光「説明も必要だけど、こちらも主導的にこういうことをやってもらいたいということを言わなければ、向こうはこういうふうにすればできるということをもって来ないから。今度は」
金杉「(略)4月13日の財政の現状と課題が大蔵省であるでしょ。これを6日の日の1時間で、キチッと説明しておいた方がいいんでないですか」
土光「それもいいですがね。私が希望したいのは、この委員会は、政府の説明を了承する会ではないのです。ですから我々はどうあるべきかを、皆さんの意向によって決めたいのです。(略)今さら政府の説明を聞いてどうだこうだと言うんじゃ、ぼくは遅いと思うんだ。私、昨年も増税されちゃ困るという条件を出している。増税されて、皆、ワァワァ言うんじゃおかしいじゃないか。実際に、4千億増税されて、皆、ブウブウ言っているけれども」
大蔵省のレクチャーに耳を傾けようと言う委員に土光は憤っている。
土光の苛立ちをよそに、政治家の周辺からは行革を煽る、さまざまな発言が飛び出す。鈴木首相は来年度予算の収支のアンバランスを埋めるために、「約2兆円の行政改革を実効あるものにできるかどうかにわかに確定できないが、補助金、助成金などについて行革と併せて検討しなくてはならない」と金額の目標を口にした。
大蔵大臣の渡辺美智雄は衆議院本会議で大型新税の導入を問われ、「増税は念頭におかず、思い切った歳出カットに私も政治生命を懸ける」と同調する。大蔵省にとっても、財政赤字の解消は積年の願いだから歳出の削減自体に異論はない。ただし「歳出カットだけでは財政再建は難しく、いずれ増税が必要」というのが大蔵省内のコンセンサスだった。
最も強気な発言をしたのは中曽根だ。3月26日、ホテルオークラでの専門委員との懇親会に臨んだ中曽根は、「これまで行革が挫折したのは、各省庁のセクショナリズムもあるが、幹部が業界団体や政治家に手を伸ばして反対してきたからだ。今度の行革は、不合理な反対運動ができないようにしなければならない」と述べた。
そして官僚の抵抗に対して、「悪質な者は配置転換、左遷する方針が(3月17日の)閣議で了承されている」と吼えた。額面通りに受け取った官僚は震え上がった。かと思えば、郵政省からは電気通信事業を担う日本電信電話公社を民営化し、電力会社のように九つの地域別に分社化する案が浮上する。20兆円超の累積債務を抱える国鉄の民営化論は語られていたが、黒字経営の電電公社のそれはやや唐突だった。
行革の風に乗ろうと、あちこちで観測気球が打ち上げられる。誰がどっちへ走っているのか見当もつかない状態で、行革という手段だけが目的化されて華々しく持ち上げられる。
*
ドタバタは4月6日、専門委員会が初めて招集されても収まらなかった。この会合で中曽根の挨拶が終わり、さて専門委員会の座長を誰にするか、と議事が進んだところで、世界経済調査会理事長の木内信胤(きうちのぶたね、1899~1993)が、突然「私が座長をやります。私は審議会に慣れているから......」と言いだした。
木内は戦前、戦中にかけて横浜正金銀行(現・三菱東京UFJ銀行)のバンカーとして鳴らし、戦後は吉田茂首相のブレーンを務めた。歴代内閣の経済指南役とも言われたが、寄る年波には勝てない。土光臨調で国鉄分割民営化を推し進めることになる加藤寛・慶応義塾大学教授は、専門委員たちの困惑を次のようにふり返っている。
「木内さんがいろいろ座の進行をやってくださったんですけど、木内さんはお年で耳が遠いんです。したがってこっちで発言していても全然聞いていないわけです。それで別の人に指名しちゃったりというようなことがあったりしました。(略)そんなことで先へ進まない。どうしていいかわからないという状況になっちゃったんです。そんなわけでもう一回練り直そうということになって、四月中旬ごろでしたか、次の会合を開いたときには、今度はきちんとプログラムをつくり、メンバーのグループ分けをしたんです」(『土光さんとともに730日──行革奮闘記』加藤寛・山同陽一、経済往来社)
まさに手探り状態で専門委員会は起動し、メンバーは三つの部会に分かれた。周りが手を焼く御意見番、木内は第一専門部会の部会長に祭り上げられ、行政改革の「理念づくり」を委ねられる。木内の下に社会システム論で知られる東大教授の公文俊平、ジャーナリストの縫田暉子、元毎日新聞編集主幹の林卓男が専門委員として付いた。緊急答申のための具体的な議論は、第一特別部会と第二特別部会に振り分けられる。
第一特別部会のテーマは「政府の歳出削減や収入確保」だ。亀井正夫・住友電気工業会長が部会長に就き、元官僚の赤澤と住田、ウシオ電機会長の牛尾治朗、武田薬品工業の梅本純正らが専門委員に入った。公文は第一特別部会の専門委員も兼務している。
第二特別部会は「行政の合理化、効率化=公務員数の削減や官業の見直し」を担当する。慶大教授の加藤が部会長に選ばれ、元官僚の河合三良と大津留温、旭リサーチセンター専務の山同陽一、元全農林委員長の鶴園哲夫らが専門委員に就任した。
臨調の委員が会議の運営に手間取るのを横目に、大蔵省は陣地を確実に広げていた。4月13日の臨調会議で、大蔵省主計局長が中期財政展望に基づく歳入、歳出の見通しや国債依存度、国債発行残高について説明をした。そのなかで1982年度の財源不足は2兆7700億円と明示し、歳出削減の必要性を強調する。
もっとも経団連の並河らも同額の歳入不足を予想し、地方交付税交付金の削減や福祉、教育関係費の見直し、農業助成金の見直しで十分補えると数日前に発表しており、説明内容に目新しさはない。臨調の委員から「財政危機を煽るものだ」「歳入不足はもっと減る」「参入見通しは確かか。税収が伸びない場合もあるのか」と数々の疑問が投げかけられる。大蔵省は当たり障りのない回答で、その場をしのぐ。大事な数字を握るのは大蔵省だ。結局、「今さら政府の説明を聞いてどうだこうだとう言うんじゃ」と反発していた土光自身が「ほかにデータもないのだから、大蔵省の財源不足額を前提に論議せざるを得ない」と言った。
2兆7700億円という金額の確認で、大蔵省のペースにはまる。これを受けて、臨調事務局は、補助金カット、国有財産や特殊法人の資産売却、公務員の新規採用凍結などを念頭に入れた検討項目の「たたき台」をその場で提出する。肝心の第一、第二特別部会がまだ何の議論も始めていないのに、官僚たちは平仄(ひょうそく)を合わせてペーパーを用意していたのである。
翌日、委員だけの懇談会で、土光は事務局の秘密主義に不快感を露わにした。
「議事録をもっとしっかり整理しておいてほしい。我々は毎回の議事録がほしいが、これまでにまとまった議事録が出ていない。(略)議事録には、委員の発言を列記してもらわないと。とにかく、速記にはいたらないにしても発言の要目ぐらいは書いてないと、後で整理するのに困る」
事務局長の加地は、土光に抵抗する。
「その点については第2回調査会の際、申し上げたのですが、専門委員の方からも調査会の議事録が全部ほしいといわれており、参与についてもおそらく同じような要望があると思われる。そうなると調査会の審議内容がオープンになる」
土光は正面から斬りつけるように言う。
「その問題は別である。調査会の議事録を外に出すということではない。ただ議事録をきちんと整理して委員に配布すればよい」
「わかりました」と加地事務局長は引き下がった。土光は少人数の委員だけのフリートーキングとあって、正式な臨調会議の場よりもストレートに発言している。9人の臨調委員と専門委員との役割分担、会議運営のまずさに、「今までの調査会の進行については不満がある。政府はこんなやり方をしているから能率が悪いんで、これでは会社なら潰れてしまう」と苦言を呈した。
さらに事務局が「理念づくり」を担った木内のメモを配布すると、「このようなものは調査会の前に、事前に渡してほしい」と土光。第一次長の佐々木晴夫が「事務局としては、できるだけ事前に御説明にうかがっているつもりですが」と言い返す。
「説明に来なくてもよいから事前に必要な資料は配布してほしい。今度、事務局の事務所ができるのだから、そこでやれば十分です」と土光はピシャリと撥ねつけた。
このやりとりを官民の事務的な習慣の違いで片づけるのは簡単だ。だが、日常の習慣にはその組織の価値観と文化がしみ込んでいる。石川島や東芝、経団連とはまったく違う官の流儀に土光は戸惑い、苛立ちながらも、何とか調整したいと会議に出て、マスコミの取材を受ける。秘書室長の居林次雄によれば、珍しく土光は「夜、眠れない」とこぼしたという。
政府・自民党は、4月20日、鈴木首相を本部長とする「行政改革推進本部」を発足させ、首相官邸で初会合を開いた。30分の予定が1時間30分ちかくに延びるほど活発な話し合いが行われる。議論は、予算編成と臨調の緊急答申をどう調節するかに集中した。大蔵省が示す「シーリング(概算要求基準)」と緊急答申を整合させるのは言うまでもないが、例年シーリングを閣議で決めるのは7月下旬。緊急答申の後にシーリングが決まる順番だ。
臨調を重んじる中曽根らは、「答申の後でシーリングを決めたらいい」と主張した。が、蔵相の渡辺は、予算編成の主導権を渡すまいと激しく抵抗した。「シーリングを早めに決めないと概算要求を最終的に決定する期限の8月末に間に合わない」と自説を押し通す。結局、シーリングは例年よりひと月以上早い、6月中旬から下旬に決め、各省庁が緊急答申までに独自の歳出見直しをすることで政府と自民党は合意した。
あらかじめ渡辺蔵相説で落としどころは決まっていたのかもしれないが、喧々囂々、敵味方に分かれて激論を交わすのが自民党のやり方だった。それでいて、最後は何かのサインでもあるのか、急転直下、議論は収束する。政権政党の中枢は不思議な力学で動いていた。
シーリングを答申の前にするか、後にするかは、段取りの問題ではない。大蔵省は、予算編成権に指一本触れさせず、何が何でも答申前にシーリングを決めたかった。シーリングで予算に重石をかければ、臨調の答申もそれに従わざるを得なくなる。大蔵省の主計官は、大蔵省の影響力低下を憂える元大蔵官僚にこう言ったという。
「絶対大丈夫です。まず、シーリングをいつにするかが"関ヶ原"です。ついで、第一次答申が"夏の陣"。これさえ乗り切れば、大蔵省はビクともしません」(「週刊現代」1981年9月3日号)
大蔵省の作戦は猟人が獲物を追いつめるように周到だった。データを武器に大きな数字の枠を設定し、全体の流れを方向づける。重要なスケジュールを区切って議論の網を絞っていく。先兵として送り込んだ調査役が縦横無尽に動いて、各論を詰める。全体から部分へ、じつに巧妙に攻めていた。
4月30日、臨調事務局は、行管庁が入る第四合同庁舎の仮住まいを離れ、永田町の三宅坂、全国町村会館の隣の古びた永田町庁舎の事務所に移った。同日、第一特別部会と第二特別部会は、それぞれ第1回の会議を開催し、緊急答申へと突き進む。特別部会は、ゴールデンウィークの休みを潰して、大蔵省の担当者からレクチャーを受けた。
それに対して臨調事務局から反発が出る。役所間の縄張り争いである。歳出カットの具体論が審議の俎上にのるにつれ、いよいよ政官財の間で壮絶な火花が散る。