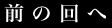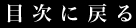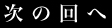第17回
「官の掌のうえ」と知りつつの改革
「昭和は終わっていない」
などと言うと、時代錯誤もはなはだしいと笑われるだろうか。
だが、尖閣諸島や竹島、北方四島などの領土問題、保守政権が一貫して推進してきた原発政策の破たん、1000兆円を超える財政赤字といった国の根幹に関わる難題は、すべて「昭和」から積み残されたものだ。「昭和」の延長上にある。
私は「昭和」を、単なる時代の呼称ではなく、大陸進出から日中、太平洋戦争へと突き進み、敗戦で国家が崩壊した後、新たな権力者となったアメリカに軍事、政治、外交で従属しながら重商国家を目指した大きな枠組み、ととらえている。敗戦で「昭和」は前後に分断されたかに見えるが、官僚機構や金融体制は戦時中のしくみが温存されており、時代の底流でつながっていると考える。
枠組みの分岐点は、1951(昭和26)年、冷戦を背景に結ばれたサンフランシスコ平和条約と旧日米安保条約だった。当時の吉田茂首相は、軍事面を米国に依存して負担を軽くし、経済発展にエネルギーを注ぐ選択をした。吉田自身は、将来の再軍備も視野に入れて、辰巳栄一・元陸軍中将ら旧軍人をブレーンに使っていたようだが、平和条約の締結後、吉田流重商主義は保守本流の基本原則とされた。
その結果、日本は繁栄を謳歌する一方で、アメリカ従属のツケとしての領土問題、アメリカの「核の傘」の下での原発推進、バブル期の日米構造協議で突きつけられた公共投資拡大(10年で430兆円)による財政赤字などの難題を背負ったといえよう。
ここで親米か、反米か、と単純化して考えるつもりはない。ただ、この枠組みが強化されてきたプロセスを知らなくては、将来の選択肢も見えてこないと思われる。
じつは土光敏夫が行革の最前線に立った1981年は、日本がアメリカ側に急傾斜した年でもあった。第二次臨時行政調査会で活発な議論が展開されていた5月8日、鈴木善幸首相はワシントンでレーガン大統領との初会談に臨んだ。会談後の共同声明には、「日米両国間の同盟関係は、民主主義及び自由という両国が共有する価値の上に築かれている」と、共同声明で初めて「同盟」という表現が使われた。「軍事同盟色強まる」と新聞各紙が一斉に報じたことを私も覚えている。
会談後の昼食会で、鈴木は日米の「適切な役割の分担」を説明していて、うっかり「(日本の)周辺海域数百カイリの範囲内と、航路帯(シーレーン)1000カイリ」の防衛に言及する。アメリカ側はこれを「公約」と受け取り、日本に防衛の増額を強く求めた。「増税なき財政再建」に政治生命を賭けた鈴木にとって、防衛費は厄介な重荷となる。
ハト派を自認する鈴木は、帰国後、メディアの報道に対して、日米同盟関係に「軍事的意味合いはない」と不満をぶちまける。外務省の高島益郎事務次官が「軍事的な関係、安全保障を含まない同盟はナンセンス」と述べたと伝えられ、激怒した。伊藤正義外相までも「軍事問題が含まれているのは当然だ」と言い、共同声明をめぐる騒動の責任をとって辞任する。
土光は、政権中枢にいる人間たちの言葉の軽さに戸惑いながら、行革へとのめり込んだ。
*
第二臨調は、1981年7月10日の緊急答申(第一次答申)に向けて、ようやく関係者の役割が分担された。土光ら9人の委員が構成する臨調会議を最上位に、翌82年度予算編成に向けて、政府の歳出削減を検討する「第一特別部会(座長/亀井正夫・住友電気工業会長)」、行政の合理化や効率化(公務員数削減や官業の見直し)を担当する「第二特別部会(座長/加藤寛・慶応義塾大学教授)」がそれぞれ具体案を作成する。第一、第二の特別部会は6月22日までに「報告」を臨調会議に上げる。それを土光、瀬島、円城寺、元大蔵事務次官の谷村裕らの委員が修正して緊急答申にまとめる、という段取りだった。
行管庁の官僚を中心とする臨調事務局は、特別部会の議論の内容が外に漏れるのを警戒した。会議のたびに配られた資料は、討議終了後に回収されている。
情報が統制されるなかで、全体をコントロールしたのは大蔵省だった。大蔵省は、例年よりひと月以上早く、各省に示す予算方針「シーリング(概算要求基準)」を閣議決定させた。しかも、その内容は予算の伸び率をゼロとする「ゼロ・シーリング」だった。「増税なき」と謳うからには82年度の予算は徹底的に緊縮させる。各省とも伸び率ゼロで予算を切りつめろ、と大号令を発したのである。各省はゼロ・シーリングの方針に従って、大蔵省との折衝に入る。臨調の答申が出る前に予算編成の実務は始まっていた。
6月8日、赤坂プリンスホテル4階の富士の間で、臨調委員の第2回懇談会が開かれた。フリートーキングとあって、委員たちは思いのたけを述べあった。土光の「増税なき財政再建」という大方針に元大蔵官僚の谷村がしきりに揺さぶりをかけた。「秘」の印が押された議事要録をもとにやりとりを再現しよう。
谷村 7月10日に(緊急答申を)決めるということであるが、どういう積りで決めるかということは議論しておかな
いといけない。臨調は財政のつじつまを合わせるだけでは何にもならないし、予算を編成するためにあ
るのではない。本来、行政とは何か、どうあるべきかを究明する場である。
土光 そうであるが、今の場合、(昭和)57年度予算を増税なしで行って、それからそのあとをどうするかは別の
問題として扱うことだ。鈴木総理もそういう方向でやるべしということで進行している。
瀬島 7月10日の答申は、(1)増税なしの予算編成、(2)もっと先に芽を出せるもので実行可能なもの、を中心
にとりまとめるということであろう。我々の調査会の本格的な活動は7月10日以降である。
土光 とりあえず緊急問題でスタートせざるを得ないのである。
土光は、増税なしの予算編成を緊急答申の眼目とした。瀬島も同じ意見だ。しかし、谷村は、素人談義だと言わんばかりに抵抗する。
谷村 来年度の問題をどうするかは、財政をどうしたらうまく辻つまを合わせることができるかという話で、公共
事業をある程度横ばいにするかしないかということは、今後10数年もの間財政計画をどう樹てていっ
たらよいかということにウェイトがかかっていて、行政改革の問題という面は非常に少ない。と同様に、た
とえば緊急避難としていわれている(国有)資産処分の問題、これは、そもそも予備資産をもつのがけし
からんとか、あんな山を研修林と称して持っていたってしかたないから売ってしまえとか、こういう話をし
て行政改革の問題となったと思うけれども、それは、来年度の予算を作るための手練手管という感じが
強い。(略)予算を作ってあげましょうではなく、こういうことも将来あるのだから今年は、この問題を規定
の方針だからやるのではなくて少しストップしておきましょうと考え方を提案することでいいのではない
か......。
口調は丁寧だが、大蔵省が持つ予算編成権には指一本触れさせまいとする執念が伝わってくる。谷村が議論を蒸し返し、停滞させて時間を費消させれば誰が得をするのか。言うまでもないだろう。元大蔵官僚は「小さな政府」論への脅しめいた台詞も吐く。
谷村 世間が小さな政府を要求するのなら、言葉は悪いが行き届いた政府を要求すると言ってはいけないので、
政府はあくまで行き届いた政府をやるべきなんですが、水も漏らさぬようなことはなかなかできないという
ことも世間にわかってもらわないといけない。よく(土光)会長は節約と言われるが、どうもそのあたりが
ここ20年くらいの間に、経済がよくなり生活水準がよくなればなるほど文句の種が増えている。これは基
本的に考えなければならないと思う。
土光 そうなんだけれども、とにかく朝テレビや新聞を見ると、世の中というものが簡素公正でないという国民の
非常な不信感がある。その中には当を得ていないものもあるが、いろんな例からそう感じられる。(谷村委
員も)大蔵省では非常に正しいことをしてこられたわけだが、これからお互いに話し合っていこうとしてい
るので、行政改革について一方的に問題ないとし、こちらが正しいからお前やめておけとはこの際言わな
いことにして進めたい。
土光の皮肉もなかなか強烈だ。「大蔵省では非常に正しいことをしてこられたわけだが」と谷村に一発かましている。谷村も負けるものかとやり返す。
谷村 たとえば、昔のようにバナナのたたき売り(みたいな恣意的な予算付け)が通用する世の中ではない。そう
いうことをすると公正取引委員会から不当表示だといって追っかけてくる。
土光 バナナのたたき売りなんというのも、庶民的に考えればよかったし、そういうのもあってよかったのだが、
いまは流行らない。
谷村 いや、それをやったら公正取引委員会が不当価格表示だと言ってくる。
円城寺 バナナのたたき売りを公正取引委員会で押さえたことがあるかね。
谷村 ないですよ。
議事録の向こうにムッとして口をへの字に結ぶ谷村の顔が浮かび上がってくるようだ。緊急答申の締切までひと月近くになっても、委員たちは、このような討議をしている。
*
第一、第二特別部会では具体案をめぐって委員が口角泡を飛ばしていた。政府の歳出削減に斬り込む第一部会の議論は、否応なく関心を集める。第一部会で真っ先に俎上にのせられたのは医療や福祉に関わる「社会保障関係費」だった。さらに「文教及び科学技術関係費」「地方財政関係費」が続く。財政支出を押し上げている「公共事業関係費」にも大ナタが振るわれるかとメディアは注目していたが、早々と「現状維持」が確認された。政治的にカットしやすいところから手をつけている。これまで大蔵省が削りたくても削れなかった厚生、文部系の予算を、行革に乗じてバッサリ切ろうとしていた。
では、どのような議論を経て社会保障費が削られるのか。現在も財政を悪化させる元凶のようにいわれる「医療費」に焦点を当ててみよう。
この当時、自営業者や退職者が加入する国民健康保険の国庫負担が増大していた。国の赤字を減らすため、従来は費用を負担していなかった都道府県にも一部を肩代わりさせる案が示された。国と都道府県が国保の加入者とともに保険費用を負担することになる。
これに対して「地方への付け回しだ」と猛然と反対する者が現れた。元自治事務次官、首藤堯である。自治省で地方行政を差配した首藤は、第一特別部会の参与に選ばれている。6月18日の第一特別部会第16回会議で、首藤は国民健康保険の運用にかかる費用の都道府県の一部負担案に猛然と噛みついた。
「今回の行革は地方への付け回しをしてはならないというのが基本方針だったと思う。やってはならないことを、やるのにそぐわない場所で、便宜的にやるのは問題だ。医療保険は国の制度であり、すでに医療保険の負担者は決まっている。地方公共団体が負担していない分野で、なぜ、便宜的に負担しろと言うのか。こんなことをすれば地方公共団体は協力しないし、第二臨調に対する支援もこれまでだ」
専門委員で武田薬品工業社長の梅本純正が、民間企業の経営者らしい反論をする。
「増税なき財政再建を断行するには、さしあたり財政の中期展望による2兆7700億円の要調整額を削減する必要があり、14兆5000億円にのぼる補助金の削減が中心にならざるをえない。補助金のうち80%が法律補助であり、かつ79%が地方公共団体に対するものである。特別部会として審議するからには、少なくとも補助金に触れた議論はすべきである。この点において、医療費を抑えるのであれば、少なくとも最大の補助金である国民健康保険の補助金(2兆3000億円)については、監視指導体制をはっきり確立すると打ち出さないと、とても増税なき行政改革の金額は出てこない。国、都道府県、市町村が一体となってやることが一番適切であろうと考えた。都道府県その他に不満があれば、そちらの財源措置の方で検討してもらい......」
背景に「行革に聖域はない」との考えがある。しかし首藤は「筋論」で一歩も引かない。
「国民健康保険の指導監督責任は国にあり、都道府県は機関委任事務をやっているにすぎないのだから、知事に(費用を)もたせたからといって(医療費が)減るものではない。国民健康保険の国の補助金は、予算名目上は補助金かもしれないが、地方公共団体に対する財政補助ではなく、(国の)負担なのだ。医療保険は、国と保険者(保険組合など)と被保険者(加入者)でもっており、そういう制度を根本的に覆すというのなら問題は別かもしれないが、これは便宜的だ。シーリングで困ったから他人にツケを回しているだけだ」
首藤は、自分と梅本、どちらの意見が多数で、どちらが少数かはっきりさせろ、と部会長の亀井に迫った。亀井は燃え上った議論の火消しにとりかかる。
「これは挙手を採るべき問題ではないと思うが、中橋(敬次郎・元国税庁長官)さんから、自分らの財源により、と入れろという意見が出ていた。もっと強い表現で(都道府県負担を)いえという意見もある。首藤さんからは、絶対不賛成という意見が出ているが、もっと強化しろという意見もある。私どももいろいろ議論し、医療費をあらゆる方法で抑え込んでいかないと、これから先大変になる、都道府県も大変迷惑なことだろうが、ここで一つ、御辛抱願えないだろうかと、このような案となった。決して首藤さんの意見を無視したわけではない。反対意見も付記して調査会に(報告を)出すことも考えている」
最終的に首藤の筋論はかき消され、国民健康保険に関する都道府県の一部肩代わりが答申に盛り込まれる。首藤は、ゼロ・シーリングで困ったからといって便宜的に都道府県にツケを回すな、と憤慨したが、数年後には正式に都道府県の負担が決まる。その後、国庫負担額は減り、国民健康保険の加入者負担額は急上昇していく。
*
第二臨調は、社会保障制度の流れを変える分岐点となった。
行政の合理化、効率化に挑む第二特別部会は、報告書をまとめる段階になっても荒れに荒れていた。6月19日の第二特別部会第16回会議は、冒頭から専門委員の渡辺保男・国際基督教大学学長や鶴岡哲夫・元全農林委員長らの会議運営への憤懣が爆発した。
渡辺 資料を委員に朝渡し、帰りに回収。これでは家で勉強ができない。しかも外部には漏れている。こんなやり
方は困る。
鶴岡 政府の委員会、初めてだが、運営がおかしい。ヒアリングでは前日に資料が配布されたのに肝心な資料
は、朝、渡されてすぐ引き上げる。検討の暇がない。しかも翌日は別のものが出てくる。そんな中で審議
を進めるのが官庁の委員会か。(臨調は官僚の)隠れみのとか、そういうことがあるが、大変不満だ。ど
うしてこういう運営をするのか、我々の勉強を阻害しているではないか。(「第2特別部会第16回会議議
事録」)
部会長の加藤が「皆さんの不満は分かる。今までの不便は申しわけない。今後、工夫がなされ、良い方向を期待する」と頭を下げる。遅まきながら、会議の資料の持ち帰りは「OK」とされた。やっと議論が本題に入ると、答申の「まえがき」の表現で、民と官が激突した。仕掛けたのは旭リサーチセンター専務理事の山同陽一だった。
「第二特別部会の考え方をもっとはっきり出せ。一特(第一特別部会の考え方)は国民に対する痛みとして出てくる。新聞で見たが、痛みを与えることがありうると言っている。従って国は率先して公務部門がやってもらわなくてはならないということを、はっきり出す必要がある。そうしないと国民が痛むだけ。たとえば厚生年金や恩給にしても弱い者いじめと言われている。二特の原点として、公が率先してやるということがベースでなければならない」(同前)
山同の前に立ちふさがったのは、元建設事務次官の大津留温だ。「同感」と受けとめながら「国民に我慢していただく。それ以上に公も、ということで公務員が給与を我慢しろというのは、それは違う」と応える。参与で元産経新聞論説委員の千田恒が山同の意見に賛意を表し、「公務員の給料は国民の税だ。日本株式会社は再建の過程にある。最初に誰が、どういう姿勢をとるかは民間では当然。それを踏まえて議論すべし」と発言。公務員の行革に向けた姿勢と給与で激論が交わされる。
大津留 公務員給与が税金によるのはそのとおり。しかし公務員も労務を提供し、給与を得ている勤労者だ。全
体の奉仕者ということは厳正に、しかし税だから我慢しろというのは如何。
山同 公務員も国民など百も承知だ。財政破たんに対しての今の説明、納得できない。もう一つ、(公務員の)給
料は民間準拠、退職金は高い。年金も民が高いという話はない。(官庁は)潰れず、(公務員は)意に反し
て辞めさせられず、保護がある。官が率先(して行革に挑むことは)、おかしくない。これが二特の基本
だ。そう思って議論してきた。ここにギャップがあるとは、何のための議論だったのか。
千田 大津留さんは私の発言を誤解している。ここが分からぬと(第二特別部会は)公務員を救済する場と批判
される。
大津留 行財政改革に異議はない。仕事、人について徹底的に直さねばならぬと考えている。ただ(財政が)破
産かどうかは疑義がある。一般の公務員は民間の人と勤務態様、給与の差はない。そういう人(公務員)
の犠牲のうえでやるのは問題。労働権制限し、代償を決めている。それを曲げてというのは問題だ。
(同前)
加藤部会長は「まえがき」を「趣旨を踏まえて書き直す。大津留先生にも受け入れられるようにする」と議論を引き取る。結局、報告には官の積極姿勢は書き込まれなかった。緊急答申は、人事院の勧告で決まる国家公務員の給与削減には踏み込まない。公務員の人件費は、防衛費、公共事業費と並ぶ聖域として残った。
土光は部会の白熱した議論を見守っていた。臨調発足当初の苛立ちは消え、議論を側面から支える。時間の許す限り、メディアの取材を受け、行革の本質論に関わる官民の対立について「官尊民卑」をなくさなければだめだ、と持論を展開している。
「......経団連あたりでも、会議をやっていると、『政府は威張っている』なんていう批判がよく出る。ところが、そう言っている連中が、夜になると大臣だとか高級官僚を料亭に招んで、えらくおべっかを使っている。結局、みんながペコペコして民卑をやっているから、官尊も出てくるんだ。
僕はそんなバカなことはしない。文句を言いたいんなら、堂々と表門から行けばいいんだ。まあ、僕はそれをやりすぎて、ちゃんと先祖伝来の"土光"という名前があるのに"怒号"なんて言われてますが......
それにね"官尊民卑"をなくするには、民間と政府の間で、どんどん人事の交流をやる必要がある。民間も、これまでのように"天下り"などと言って、官僚出身者を何か置き物のように特別な扱いをするのをやめなければだめだ。会社に入ったからには、官僚出身も何もないんだから、同じ従業員としてこき使えばいい」(「現代」1981年7月号)
明治、大正、昭和と激動の時代を生きてきた土光は、この国の底に「官尊民卑」が根を張っていることを身にしみて感じていた。時代の表層は変われども、くぐもった意識は一向に解消されない。それが官僚支配を補強している。事実、増税なき財政再建を掲げた答申づくりも、官が用意した資料に沿って、文言の添削で委員どうしが火花を散らしてはいるものの、粛々と進んだ。
7月10日、予定通り第一次の緊急答申が発表された。歳出削減の項目には国民健康保険や児童扶養手当、公立文教施設、老人医療費などが並んだ。行政の合理化では国家公務員の定員を5年間で5%削減、特殊法人の常勤役員を3年間で2割削減などが明記された。
じつは、これらの内容は、大蔵大臣の諮問機関である財政制度審議会の78年から80年にかけての建議と、80年に大蔵省が刊行した『歳出百科』の記述にピタリと一致していた。『歳出百科』は「歳出の合理化・効率化について現実に即した議論に役立つこと」を目的につくられた冊子である。
経団連で土光の行革担当秘書だった並河信乃が回顧する。
「大蔵省に緊急答申づくりは歳出削減のチャンスでした。『歳出百科』のパンフレットに予算項目の問題点を洗い出していました。大蔵が動けばみんなが動く。悔しいですけどね。大蔵の協力が決まって、そうしたら一瀉千里。予算書を見たら、カットするのはこれじゃないかとメニューは自動的に見えてきますよ」
行革の「虎の巻」にされた『歳出百科』。
そこには「財政再建と行政改革」と題して、次のような記述がある。
「今日の大幅な財政収支の不均衡をみると、機構の簡素化や定員削減などの行政改革による経費の節減のみで財政再建が可能になると期待することはできません。
財政再建の検討に当たっては、行政の守備範囲や行政サービス水準そのものをどうするかという点についての国民の選択が求められています。
しかしながら、財政危機の下にあって、まずもって行政の徹底した簡素化、効率化を実現し、行政経費の節減に努めるべきことはいうまでもないことで、今後とも幅広い観点から行政改革の推進に不断の努力を傾注していく必要があります」
いったい何を優先すべきだと言いたいのだろう。行革の経費節減だけでは財政再建は不可能だとし、行政上の国民の選択が必要だと強調。そのうえで、行政経費の節減への努力はいうまでもない、と言い訳を添えている。「不断の努力を傾注」という官僚用語のいかに空しいことか。この曖昧さが、現在の1000兆円に及ぶ財政赤字を招来した根源ではないか。
中曽根康弘行管庁長官は、臨調の特別部会が招集された3月の会合で「(政府が)汗をかけばのめるような案にしてもらいたい」と言った。汗をかけばのめるとは「実行可能性」という表現に言いかえられ、官の影響力が強まった。敷かれたレールの上を土光たちは走らざるをえなかったのだ。そこを臨調の限界と切り捨てるのは簡単である。
が、しかし、誰かが、官の掌のうえと知りつつも飛び回らねば現実は変わらない......。緊急答申は、あくまでも第一次の答申であり、行革全体から見れば開幕を告げるブザーだった。行革の本筋は、いかに官僚が抵抗しても機構の合理化、効率化にある。
1981年の夏が過ぎ、日本国有鉄道の解体、民営化という国論を二分する大手術が始まる。