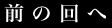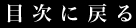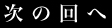第18回
裏臨調と国鉄民営化──瀬島龍三の策動
人びとの日常生活に欠かせない「公益事業」。私たちの周りには、運輸、郵便、電力、通信、水道、ガス、医療、公衆衛生......とさまざまな公益事業が存在するが、その経営をめぐる官民の主導権争いは、明治維新以来、150年ちかく続いている。
ひと口に公益事業といっても、それぞれ性質は異なる。互助性の高い医療分野では営利主義はなじまず、原則的に株式会社の病院経営は禁じられている。一方、電力は戦中の国家管理を経て、9電力(沖縄を含めて10電力)の民間企業体制が敷かれてきた(ただし、経営危機に陥った東京電力は資本の過半を政府が保有し、国有状態)。
公益事業には落とし穴がある。利益優先で臨めば、儲からない部分が切り捨てられ、公益性を損なう。逆に公益性にあぐらをかいて「親方日の丸」で運営すれば、非効率な無駄、赤字の温床となる。要は、官であれ、民であれ、公益を理由に認められる「独占」状態で、経営主体がどのように振る舞うかが問題だ。モラルが厳しく問われるのはいうまでもない。
2000年代、小泉純一郎政権は構造改革で民営化を加速させた。「官から民へ」の流れはやや弱まったとはいえ、いまも続く。その源流をたどれば、イギリスのサッチャー首相やアメリカのレーガン大統領が標榜した「小さな政府」に行きつく。1970年代、欧米諸国は経済が停滞した。その原因はケインズ的な「大きな政府」の経済政策の失敗にあり、経済の活性化には肥大化した政府を縮小するしかない、と考えた。
「小さな政府」実現の手段は、①財政支出の削減、②規制緩和による政府の役割の縮小、③公企業の民営化、である。欧州では、エネルギーや鉄鋼の基幹産業、自動車産業にも公企業が根を張っていた。これらが民営化される。
やや遅れた日本の土光臨調も「小さな政府」路線を追いかける。第一次の緊急答申で「増税なき財政再建」を謳い、歳出削減に斬り込んだ。緊急答申に盛り込めなかった規制緩和については、第二次答申の「許認可等の整理合理化」にまとめる方針が決まった。残るは民営化。そのターゲットは、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社の「三公社」に絞られた。そこから「針の穴にラクダを通すよりも難しい」といわれた国鉄の分割民営化が急浮上する。いかにして国鉄は、JR(Japan Railways=日本諸鉄道)グループへと変容したのか。その突破口となった土光臨調での「攻防」をクローズアップしよう。
*
1981年7月、第一次の緊急答申が政府に提出され、土光ら臨調委員はホッと一息ついた。経団連で土光の臨調担当秘書を務めていた並河信乃は、「緊急答申が終わると、いらいら、ぎすぎすしていた土光さんの態度がガラッと変わった。吹っ切れたのでしょう。こっちの言うことは何でも聞く。右へ行ってくださいと言えば右へ。左へといえば左へ。180度変わりました」と述べる。
政権与党の自民党との関係も好転した。党の行財政調査会長は旧知の橋本龍太郎だった。龍太郎の父、龍伍は大蔵官僚を経て、土光の故郷、岡山県から出馬して政界入りしている。土光は龍伍と親しかった。龍伍は政治家としてはこれからという50代半ばで亡くなったが、後継の龍太郎は「じいちゃん、じいちゃん」と土光を慕ってきた。暇を見つけては、経団連の会長室にふらっと遊びにくる。
龍太郎は田中派の政治家である。親分の田中角栄はロッキード事件の刑事被告人でありながら、闇将軍と呼ばれ、権勢を誇っていた。積極財政派で公共事業の元締めだった角栄が、土光臨調に(総論レベルとはいえ)賛同していなかったら、行革は挫折していただろうといわれる。橋本龍太郎も行革の枠組みのなかで独特の存在感を放っていた。
後年、橋本は総理大臣の椅子に座ると、土光の遺言を実行するかのように「中央省庁再編」の行政改革に取り組む。従来の1府22省庁は、1府12省庁に改められる。なかでも、予算の編成と配分、租税、金融を一手に握っていた大蔵省は、金融部門を剥ぎ取られ、財務省となる。金融政策は、新たに設立された内閣府金融庁に委ねられる。橋本の胸には「じいちゃん」の奮闘ぶりが深く刻み込まれていたようだ。
さて、場面を土光臨調に戻そう。
1981年夏のある日、並河は、臨調委員で、裏の仕事師、瀬島龍三に呼び出された。並河が出かけていくと、瀬島は「土光臨調を外から応援する応援団をつくってくれないか」と依頼してきた。行革を国民的運動へ昇華させる応援組織を求めていた。瀬島は、応援団長には本田技研の創業者、本田宗一郎の内諾をとってあると余裕綽々だった。
本田と土光のつき合いは長い。初めてふたりが顔を合わせたのは、日本が主権を回復して間もない1952、53年ごろだった。労働争議の頻発に悩む経営者たちが対策を話し合う会合で、本田は10歳上の土光が「労働組合は経営の敵ではない」と骨っぽく、石川島重工の労使問題の立て直しを語る姿に注目した。以来、折々に接していた。
とはいえ、応援団を立ち上げるには先立つものが必要だ。並河が「お金はどうなりますか」と訊ねると、瀬島は「本田さんはお金持ちだから大丈夫だ。場合によっては内閣の機密費をまわしてもいい」と答えたという。はたして、そう簡単に内閣官房機密費が流用できるものだろうか。大本営作戦参謀だった瀬島には終生「影」がつきまとう。
並河は、本田を訪ね、土光臨調の応援団長に就任してほしいと頼んだ。町工場から叩き上げて世界に冠たるホンダを築いた宗一郎は、ぎょろりと目を剥いて言う。
「土光さんの応援をするのはいい。だが、政府の提灯持ちはまっぴら御免。応援団をつくるなら、若手中心にしてくれ」
本田は「政府の提灯持ちはしない」と強調した。
並河は「あれでこちらも助かった。政府の提灯持ちは臨調事務局がやればいいし、好きな人がやればいい」とふり返る。並河は、本田の推薦するソニー名誉会長・井深大も引き入れ、本田、井深を代表世話人として「行革推進全国フォーラム」を立ち上げた。世話人には、都市社会学者で東京都立大学名誉教授の磯村英一、評論家の秋山ちえ子、日本青年会議所会頭の黒川光博が就く。行革フォーラムは、翌年「頑張れ土光さん 国民がついている」と大々的に宣言し、「行革推進国民会議」を開催。財界から学界、言論界、婦人団体、青年団体へと土光応援団は拡大していく。
本田の担ぎ出しを画策した瀬島は、しかし皮肉にも行革フォーラムと距離を置く。泥をかぶって政府との調整をする瀬島にすれば、「提灯持ちはしない」と鼻面にピシャリと叩きつけるように言われては立つ瀬がない。瀬島は、行革フォーラムとは一線を画した。
瀬島の活動を陰で支えたのは東急グループだった。総帥の五島昇は、中曽根康弘を「曽根さん」と呼び、宰相にしようと骨を折った。行革を軌道に載せれば、総理の座は間違いない。五島は、永田町の「東京ヒルトン(跡地には「ザ・キャピトルホテル東急」)」の5階のスイートルーム、506号と507号を用意する。ひとつを瀬島に仕事場として与え、もう一方を、後に東急エージェンシーの社長を務めることになる新井喜美夫に使わせる。官僚機構の特性や役人の性癖に詳しい新井を瀬島の相談役として付けたのだった。新井は「参与」として臨調に関わる。瀬島と新井は連絡をとりながら、官界に食い込んだ。
新井は自著に、こう記す。
「かかった経費は一切、東急持ちだった。五島という人物は仕事を押し付けるだけではなく、金銭的なサポートも忘れない。部屋を用意するだけでなく、われわれの飲み食い代も含め、すべて東急が負担してくれた」(『転進 瀬島龍三の「遺言」』講談社)
新井の部屋は、臨調事務局の官僚が勝手に食べたり飲んだりする「居酒屋ホテル」だったという。ともあれ、人間くさい対立や、合従連衡を孕みつつ臨調は先へと進む。
*
夏休み明けの9月、土光臨調は具体案をつくる部会を四つに再編し、翌年7月末の第三次基本答申に向けて動きだした。第一部会は武田薬品社長の梅本純正を部会長に「行革の役割と重要施策」を担当する。第二部会は三井造船元社長の山下勇を部会長に「行政組織と行政刷新」、第三部会は「国と地方の機能分担」をテーマとし、住友電気工業会長の亀井正夫が部会長に納まった。
そして焦点となる「三公社の在り方」は、第四部会に託される。部会長は加藤寛・慶応義塾大学教授。そのメンバー構成で、「おっ」と世間が注目したのは、元運輸事務次官、運輸経済研究センター理事長の住田正二の「部会長代理」就任だった。運輸省のエリート、住田が、三公社のひとつ、国鉄の大胆な改革に合意するのか。住田が反旗を翻した瞬間、第四部会の命脈は尽きる、とメディアでは論評されていた。
三公社のうち、国鉄は最も経営状態が悪かった。黒字の電電公社は、土光の弟子、元石川島播磨重工業社長・真藤恒が総裁に就き、民営化含みで改革に着手したばかり。土光―真藤ラインに遠慮して手を出すのはためらわれる。専売公社は大蔵省のおひざ元。ねちっこい反抗が予想され、こちらも俎上に載せにくい。自然と国鉄にスポットライトが当たる。
官の側に立てば、財政を圧迫する厄介者、国鉄を「スケープゴート」として臨調に差し出し、省庁の本丸に攻め込まれるのを防いだ、ともいえる。
では、従業員約40万人、北海道から九州まで総延長約2万キロメートルの鉄道路線を持ち、政府が100%出資する巨大公社・国鉄とは、どのような組織だったのか。
最高責任者の総裁は任期4年で内閣が任命した。次席の副総裁は運輸大臣の認可を要する。技術面は技師長が総裁を補佐した。この他に任期3年の理事(11~17人)が置かれ、民間企業の役員会議に相当する「理事会」で国鉄内部の重要な案件は処理された。
この当時、総裁は1976年に大蔵事務次官から天下りした高木文雄が務めていた。高木は、50%ちかい運賃値上げや人員削減を断行したが、国鉄は坂を転がる雪だるまのように累積債務を膨らませた。81年度の国鉄補正予算を見ると、事業収入2兆9333億円の85%が「人件費」に使われ、減価償却前のキャッシュフローベースで1兆円の大赤字となっている。赤字の大部分が過去の債務の利払いだ。さらに国の補助金が単年度7000億円。高木の総裁就任時に6兆円の累積債務が棚上げされたが、その後も借金は増え続け、総額16兆円に達している。毎年2兆円ペースで借金が増えるのは目に見えていた。
国鉄が赤字に転落したのは1964年、「夢の超特急」東海道新幹線が開通した年だった。以後、何度も再建計画が国会で審議され、策定されたが、ことごとく失敗した。
なぜ、国鉄は巨額の債務を抱え込み、危機的状況に陥ったのか。さまざまな要因があげられようが、ひと言で表すなら「政治」に翻弄されたからだろう。
公益事業としての国鉄は、ときに政治的判断で雇用の受け皿に使われた。戦後、引揚者を大量に雇い、従業員は一時60万人まで増えた。1949年、初代総裁・下山貞則は、ドッジ・ラインの財政金融引き締め策に呼応し、12万413人の人員整理に手をつける。同年7月4日、第一次整理3万700人の通告を行った。国鉄労働組合が反対闘争に入ろうとした矢先の翌5日、下山総裁は日本橋の三越本店に入ったまま行方不明となり、6日に常磐線綾瀬駅付近の線路上で轢死体となって発見された。これは下山事件と呼ばれる。
吉田茂政権は他殺説に傾き、新聞も労働組合員や共産党員の犯行を想像させる報道をした。警視庁捜査1課は自殺説、作家の松本清張はアメリカ軍謀略説を唱える。その後も三鷹駅で電車が暴走して6名が死ぬ「三鷹事件」、東北本線松川駅付近で列車が転覆して乗務員3名が死亡した「松川事件」が発生。いずれの事件も迷宮入りとなる。国鉄当局は共産党や労働組合が非難されるのを横目に人員整理を行う。が、慢性的な人員余剰は続き、人件費がかさんだ。
戦前から鉄道界には「我田引鉄」という言葉がある。衆議院選挙のたびに保守政党は鉄道敷設と引き換えに、その地域の票の獲得工作をした。鉄道が通り、駅ができるかどうかに地域の繁栄がかかっていた。戦後も整備新幹線などに我田引鉄は受け継がれ、採算の見込みのない路線が建設される。高速道路網が整備され、モータリゼーションが進んで貨物輸送が鉄道からトラックに移っても、貨物列車は「空気」を載せたまま走った。
こうした窮状にも国鉄の「理事会」は明確な意思決定ができず、労働組合の反抗を恐れて手が打てない。気がつけば、借金で火だるまとなっていた。
*
臨調第四部会は、膨大な累積債務と余剰人員を抱えた国鉄を、実質的に経営破たんしているととらえた。大赤字と余剰人員を清算し、将来に向けて自律的な責任体制を築いて再生するには民営化が必須と導く。さらに地域ごとの分割が不可避と方向づける。
高木総裁を筆頭に国鉄側は一斉に反発した。労働組合も真っ向から民営化を否定する。民営化で真っ先に路線を廃止されそうな過疎地の住民からも反対論がわきおこる。
第四部会の加藤部会長は、「臨調のある委員」に「自分は高木さんと親しいんだ。高木さんと意見を調整しておいたらどうですか」と仲介され、高木総裁と面談した。(『土光さんとともに730日──行革奮戦記』山同陽一との共著、経済往来社)
「絶対分割民営は表に出してくれるな。これを出すと、国鉄はまとまりがつかん。国鉄職員四十万人、その家族を入れたら百万を超している。その人たちを不安に陥れるわけにはいかんから、絶対言ってくれるな」と高木は加藤に語った。(同前)しかし、第四部会は方針を変えない。キーパーソンの元運輸事務次官の住田も、国鉄には匙を投げていた。運輸省と国鉄はすでに一枚岩ではなかった。16兆円の累積債務のうち、11兆円が高木総裁就任後のもの。運輸省は巨額債務の実態を調査するため、資料の提出を求めた。「こういう資料を出せ、ああいう資料を出せというわけですが、なかなか出さない。出しても、自分に有利な資料しか出さない。こんな国鉄は、もうだめなんだ」(同前)と住田は加藤に告白したという。
1981年11月9日、第四部会は「国鉄分割民営化」を臨調全体のコンセンサスにしようと、土光たち9名の委員で構成される臨時行政調査会の会議に論客を送り込む。その論客は角本良平。戦中に鉄道省に入り、東京、四国、門司などの鉄道管理局に勤務後、運輸官僚として東海道新幹線の建設計画に参加。退官後は交通評論家として活動する、国鉄の表も裏も知り尽くした人物だった。角本は、土光たちの前で国鉄の末期的症状を解説した。
分割論に対しては、北海道、九州、四国のように路線が域内でほぼ完結する地域はともかく、本州を複数のブロックに分けるのは「線路をちょん切れというのか」と反対論も根強かった。「秘」の議事録をもとに臨調委員との対話を再現しよう。円城寺が「地域分割については新幹線なども分割するのか」と問う。角本が答えた。
「麻薬患者の職員が出たり、管理局の部長が酔っ払い運転をするなど内部管理が急速に悪くなっている。以前は新幹線を含んだ大きな地域で考えていた。たとえば関東、中部というようなブロックを考えれば、東海道新幹線は一つだけ切ればよいと考えていた。ところが、この一年間、急速に内部管理が悪くなったため輸送にとらわれるよりも内部管理を重視したほうがよいと思う」つまり地域ごとに企業統治できる規模に切り分けなければいけない、というわけだ。内部管理が悪化した理由を問われ、角本は語る。
「政府が無理を言って、できないことをやれと言う。それを管理者ができることのように引き受けてきた。そういった嘘の積み上げであるから内部管理が崩壊するのは当然。しかも国鉄総裁以下、本社の人たちが現場管理に時間を割けない。重役が20人しかいなくて約40万人の職員の管理できるはずがない。20人の重役が国会の説明のために頭を悩ませている状態では経営が崩壊するのは当然」分割すれば、内部崩壊が収まるのかと訊かれ、こう返答した。
「地域分割した場合、20人の重役を200人にすることができ、国会に説明する努力が10倍になる。国会議員は票が欲しいわけだから地方にある企業は強いが、国鉄は全国の組織であることから国会議員に弱い(地域企業にすれば強くなる)。もう一つは地方自治体との間で十分話ができるということ」しかしながら、北海道、四国、九州の赤字路線が多い地域は、分割されたとたん経営が一段と悪化する。分割後の地方の見通しを質され、角本は極論を展開する。
「四国については鉄道を全部外したほうがよいと思う。四国の国鉄財産を全部売って高速道路をつくったほうが四国のためになる。とくに本四連絡橋の上にレールを乗せるのは何事かと思う。それだけで、四国の管理局で生じているのと同額の300億~400億円の赤字が出る。この際、岡山からバスで高知へ行くというような体制を作ったほうがよい」瀬島が「北海道の鉄道はどうするのか」と質問した。鉄道は有事には軍事物資や人員の移動を担う。冷戦下、対ソ国境に近い北海道は特別な場所だ。瀬島らしい問いだった。 「乱暴な言い方だが、いまの営業キロの三分の一ぐらいになるといい。私は、まだ国鉄にいた15年前に根室本線を廃止できないかと一生懸命考えた。当時から、そこに立派な道路をつくったほうが北海道の方のためにはるかに役に立つと、今でも考える」と角本。
円城寺は「地域分割すると経営が成り立たない地域」をどうするのかと問う。
「補助金がいる地域は多いと思う。東京、大阪地域以外はかなりの補助が必要である。現実、実質的に1兆6000億円の欠損を生じているわけであるから、この欠損がたとえば数千億円に収まるように追い詰めていかなければならない」
角本のレクチャーは土光ら臨調委員に強く印象づけられた。
1981年暮れ、臨調の関心が国鉄改革に向けられるなか、鈴木内閣は緊急答申を無視するかのように82年度予算で約3480億円の「企業増税」を決めた。土光は「総理は増税なき財政再建を果たすという約束を破った」と怒り、経団連の稲山嘉寛に「臨調会長を辞める」と漏らした。稲山が懸命に取りなして辞意は撤回されるが、鈴木への不信感は募った。
年が明け、年度末が過ぎ、臨調の議論は7月末の第三次答申に向けて沸騰した。第三次答申は基本答申と位置づけられており、行革全体の骨格を示すものだ。国鉄改革が最大の目玉である。行政組織の改革や公務員の削減も並行して検討されていたが、国鉄改革の陰に隠れてなかなか表に出てこない。いつの間にか改革色は褪せてしまう。
一方で、非公開が原則の臨調であるにもかかわらず、国鉄改革の素案や中間報告が次々とスクープされる。じつは瀬島は中曽根と連携し、錯綜する問題を処理するために「裏臨調」といわれる非公式な場を切り盛りしていた。産経新聞は裏臨調について報じている。
「臨調行政調査会(土光敏夫会長)の七月基本答申の目玉である国鉄改革案が具体化するとともに、"裏臨調"のスゴ腕ぶりがにわかに脚光を浴びている。数人の委員で構成し、臨調審議の表舞台とは別に、非公式に政府、自民党、関係団体などと折衝を重ね、実行可能な答申づくりへの地ならしを行う機動部隊である。(略)臨調、自民党内には『臨調と党が並行して審議しているウラで何サマのつもりだ』と反発も強い。しかし"裏臨調"でまとめた国鉄改革案はこうした声があるにもかかわらず定着しつつあり、五月十日に正式提案される臨調部会報告も"裏臨調"の線に沿って決定される見通しが強い」(1982年4月26日付)「裏臨調」とは瀬島にふさわしいネーミングではあるが、現実には既存の省庁や組織の側に寄った調整が進められた。瀬島は「政府が汗をかけば実行できる案を」と中曽根から申し渡されており、忠実に働いた。裏臨調がメディアを賑わせていたある日、並河は新聞記者に「裏でゴソゴソやるのはうちの爺様は嫌いなんだよな」とコメントした。その発言を知った瀬島は、並河を呼び出し、恫喝する。
「きみもあまり向かない仕事をやらされているようだが......」
婉曲的に土光の秘書を辞めろ、と追い込んだ。並河は、瀬島との「情報戦」を回顧する。
「まぁ、私も生意気なことを言っちゃいました(笑)。当時、理想派と現実派の争いとよく言われました。理想派の旗頭が土光さんで朝日新聞、東京新聞がバックアップ。現実派は中曽根―瀬島ラインで、読売新聞がついていた。毎日新聞は私のところにも来ましたが、組合系と近かったですね。産経新聞は独特のスタンスでした。一種の情報戦がくり広げられていて、同じ事実でも新聞によって見出しが正反対のこともありました。瀬島さん相手の情報戦はしんどかったです。そんな経緯もあって、本田さん、井深さんの行政フォーラムと瀬島さんは没交渉になった。もっとも汚れ役の瀬島さんがいなければ、第二臨調は前に進まなかったでしょうけどね」
瀬島自身は「裏臨調」の存在を一笑に付した。謎の裏臨調......、いったいどんなメンバーだったのか。現実派の頭目、中曽根は、自著『自省録』(新潮社)にあっけらかんと記している。
「臨調の委員たちも、一週間に四回も会議を開いて、それこそ徹夜も厭わず仕事に没頭してくれました。かたわら、私は臨調のほかに『裏臨調』という会合を開きます。毎週金曜日の夜八時、菊亭という赤坂の料亭で、慶應義塾大学の加藤寛さん、瀬島龍三さん、橋本龍太郎君、堀内光雄君、中村靖君、それに加地夏雄行管庁次官というメンバーで『現実問題として、どのように臨調を動かしていくか』という戦略を練りました。私が、行管庁長官時代から始めたこの『裏臨調』は、三十回前後開いたはずです」
裏臨調での戦略に沿って、加藤は「裏会議」と称された実務者の会合を重ね、第四部会の国鉄改革案がまとめられた。その内容は、国鉄労使はもとより運輸省、自民党の族議員にも衝撃を与える内容だった。第四部会の報告は、三本の柱から構成されていた。
一、国鉄を5年以内(1987年)までに分割民営化する。
二、具体案作成のために強い権限を持つ「国鉄再建監理委員会」を設置する。
三、具体案の検討中は、緊急対策として新規採用の全面停止、ならびに保全保安以外の新規工事を全面的に停止する。
各方面から、一斉に「反対」の大合唱がわきおこる。
「失礼だが(臨調のいう国鉄分割民営化は)ナマ煮えの感じがする。そうなったときの、あるべき姿を説明していただきたい。左側のガケに公共性、右側のガケに採算性というものがある。その尾根をいつも歩いているのが国鉄です。(臨調は採算性という)片方のガケだけを見て、歩いているという気がする」(国鉄総裁・高木文雄 産経新聞1982年5月18日付より)
「黒字なくして公共性なし、という理屈はわかる。だが、逆に公共性を犠牲にしてでも採算性を、というのではおかしくなる。わたしの町のように、香川県と同じぐらいの広さで、雪が三メートルも積もるところでは、国鉄がなければ孤立してしまう。バスを通すにしても、道路の改修工事に三十億も四十億もかかる。国鉄がなくなれば生活できず、過疎はますますひどくなる。線路をはずすことは国土放棄と同じだ」(北海道美深町長・長谷部秀見 朝日新聞1982年5月24日付より)
「分割や民営で国鉄を救えるはずはありません。確言してもいいです。民営にするとして、当面、日本に大変な土地コロガシ成金がでてくる。駅はいちばんいい所にあるし、敷地も広い。それが公有地という名で安く売り渡されていく。そうなれば、大中小の政治屋とか一部の人間が土地をコロがして太っていくのは間違いない」(作家・井上ひさし 毎日、朝日新聞1982年6月25日付 国鉄労働組合が出した意見広告「国鉄論議にもの申す!」より)
国論を二分する国鉄分割民営化、土光は、その内容を盛り込む基本答申を発表する直前、「静と動」ふたつの顔を世間に見せた。質素な暮らしぶりで夕餉にメザシを食べる姿と、政府の米価値上げに対して怒り心頭に発し、辞意を表明する姿......。今も語り継がれる「メザシの土光さん」の伝説は、基本答申発表直前の、ここしかないタイミングでつくられたのであった。