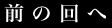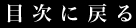最終回
「地獄の釜炊きでもして、日本の動きを見ていくよ」
今秋、JR東京駅丸の内側の「赤れんが駅舎」が、保存・復元工事を終えて、全面開業した。駅舎は全長約335メートル、幅約20メートル、尖塔の高さは45メートル。太平洋戦争中の東京大空襲で焼失した3階と南北ドーム屋根が再生され、日本近代建築の父・辰野金吾のデザインが98年ぶりに甦った。
復元費用は約500億円。JR東日本は、丸の内駅舎上空の「空中権」を三菱地所の新丸の内ビルディングなどに売却して賄っている。つまり、駅舎を往時の低さに抑えることで、手に入るはずの「容積率(敷地面積に対する建築延べ面積の割合)」を三菱地所に売る。容積率を上積みされた新丸ビルは、通常より高く建てられた、というわけだ。
売った側は売却益、買った側も床面積を増やして利益を上げる。空中権の移転という「打ち出の小槌」を振れば、ウィンウィンで、どちらも儲かる。行政が胸三寸で容積率の数字をいじれば巨利が生まれる。
日本の都市開発は、戦後、一貫して緩和される容積率を利用し、高層ビルを林立させる方向で進められてきた。鉄道の土地活用事業は、その先兵役だった。国鉄分割民営化は、都市開発のための跳躍板でもあった。広大な国鉄保有地が民営化で売り出され、不動産デベロッパーが群がる。地価は上昇し、バブル経済の地ならしが行われた。
JR発足から25年、丸の内赤れんが駅舎の開業に先立ち、記者会見に臨んだJR東日本の冨田哲郎社長は、こう述べた。
「98年前は明治、大正にかけて日本が欧米列強に追いつき、追い越せと坂の上の雲を目ざした非常に躍動感のあった時代。日本人自体も進取の精神、高揚感があったと思う」
東京駅は、進取の精神や高揚感といった「いまの日本にやや欠けている部分」を表現しているのではないか、と冨田は言葉を続けた。東京駅舎の復元とは、要するにJR精神の「原点回帰」である。前史の昭和ではなく、一足飛びに明治、大正に帰ろうというわけだ。斜に構えた見方かもしれないが、それほど昭和の国鉄、いや国鉄分割民営化は「苦い」記憶なのかもしれない。借金まみれで解体に追い込まれた過去より、雲を見ながら坂を上った時代に郷愁を抱いている。ただ、上がりきった坂の空にはもう雲はない。どこを目ざしてJRは走り続けるのか......。
*
土光敏夫は、「増税なき財政再建」という原則を踏みにじる鈴木善幸総理に辟易しつつ、1982年7月末、「万全を期した。こんどは政府が本気でやってほしい」と第三次基本答申を提出した。行革の骨格は固まった。鈴木も「国民が一番関心を寄せているのは国鉄再建。国鉄再建監理委員会設置法を早急にとりまとめて、最も近い国会に提案し、承認を受けて設置したい。これが国鉄改革と再建へのスタート」と応える。
9月24日、政府は行革大綱を閣議決定し、「国鉄改革の5年以内の実現」や「職場規律の確立」、「新規採用の抑制」など緊急10項目の実施が決まった。土光臨調が提示した国鉄分割民営化が、いよいよ具体的にスタートする、と思われた。
ところが......。10月12日午後3時、臨調ビル1階の特別会議室のドアが開けられ、事務局員が慌しく入ってきた。臨調会議の司会を務めていた土光の手元に通信社からのファクスが届けられる。土光は、紙に視線を落とした。
「鈴木首相、総裁選不出馬。自民党三役会議で辞意表明」
土光は、5分ちかく、わずか数行の文面をじっと見入った。その日の朝の新聞記事では鈴木の続投ほぼ間違いなし、と受け取れた。16日の総裁選告示に向けて敵対する福田派からの批判は高まっていたが、話し合い決着を探りながら、場合によっては「数」で決めると見られていた。それなのに、あっさり辞めるという。
表情も変えず、ファクスを見つめる土光の胸中には、どんな思いが去来していたのか。
ひと言の相談もなく、逃げた鈴木への憤りが渦巻いていたのだろうか。わしは86歳の老骨に鞭を打って臨調を切り盛りしているというのに、「命を賭ける」といったお前の言葉は嘘だったのか、と。午後5時過ぎから、記者会見がセッティングされた。記者連中は、土光が荒法師の本領を発揮して、机をゲンコツで叩きながら「敵前逃亡だ!」と吼えるのを期待した。土光が怒れば絵になる。だが、土光の態度は、恬淡としていた。
「......総理を信用していたが......。行革は日本として、どうしてもやり遂げなければならない。一刻の猶予も赦されない。次を継ぐ人は、空白を置かず、鈴木首相以上の熱意をもってやってもらいたい!」
過去をふり返らない、土光のもう一つの顔がそこにあった。
政局は目まぐるしく展開する。総裁選が告示され、中曽根康弘、河本敏夫、安倍晋太郎、中川一郎が立候補を届け出た。政治劇の真の演出者は、ロッキード事件の刑事被告人で裁判を抱える田中角栄だった。田中は鈴木に電話をし、「うちは中曽根で行く。鈴木派からは候補者を出すな」と命じていた。鈴木があっけなく降りたのは、田中の差し金だった。田中は出馬の相談にきた中川一郎に「池の鯉が飛び跳ねると、外に落ちて日干しになるぞ」と自重を促したといわれる。総裁選の3カ月後、中川は不可解な自殺を遂げることになる。
福田派は安倍晋太郎を立てて、総理の椅子を引き寄せようとした。ただし「数」では田中派にかなわない。派閥の領袖、福田赳夫は話し合いで後継者の安倍を官邸の主にしようと動く。10月22日の夕方から、鈴木首相と福田赳夫、田中派の重鎮で「趣味は田中角栄」と公言する二階堂進の3者協議が始まった。議論は夜を徹して行われ、「福田総裁、中曽根首相」の「総理総裁分離論」でようやく落としどころが見えた。田中派の代理人、二階堂は「長年にわたる怨念にピリオドを打つにはこれでいいのではないか」(『田中角栄──戦後日本の悲しき自画像』早野透、中公新書)と独断で進めようとした。
田中は、中曽根からの電話を受けて、「そんなもの絶対受けちゃいかん。蹴飛ばせ。あとは予備選だ」と指示を出す。田中が中曽根擁立にこだわったのは、自分が総理に就任する折、中曽根が協力してくれたからだった。「中曽根君には借りがある」と中曽根派の会合で明言している。と同時に、田中派内から鬱勃とわきあがる若手擁立論へのけん制である。後継者が首相になれば己の権勢は衰える。永田町における世代交代は、一種の「革命」である。竹下登が「10年経ったら竹下さん」などと軽口を叩くのを「まだ早い」と止めた。
総裁選は、田中派の後押しを受けた中曽根が圧勝した。
そのかわり、蔵相の竹下はじめ田中派が6人も閣僚に並ぶ「直角内閣」が誕生する。小派閥で、巧みに時代の匂いをかぎ分けてきた中曽根は、総理大臣に就任した。土光は組閣直前に中曽根と会談し、「初閣議で、行革を内閣の総力をあげて推進するよう、指示したい」との言質を取った。土光は、ほっと胸をなでおろす。
が、まだまだ政治に翻弄される。11月24日、政府は、国鉄再建監理委員会の設置を含む法案を国会に提出した。問題は、その中身だった。肝心要の国鉄の経営形態について、「効率的な経営形態の確立を図ること」と記すばかりで、分割民営化の文字はどこにもなかった。自民党の運輸族議員の巻き返しで、曖昧にボカされたのだった。
*
暮れも押し迫り、土光は、体調を崩した。血圧が極端に上昇し、東芝中央病院に入院する。積もり積もった疲労が土光の身体を弱らせた。長男の陽一郎は「もう、休んでほしい」と願った。1983年2月28日、臨調は第四次答申「臨調後の行革体制」を発表。3月半ばの第五次最終答申で、まる2年に及ぶ臨調に幕がおりる。土光は、会議に明け暮れた。
3月は旅立ちの季節でもある。土光が母、登美から受け継ぎ、校長を務める女子高校・橘学苑も卒業式が迫っていた。最終答申で「特殊法人改革」に斬り込まねばならない土光は、忙殺されている。「申しわけないが、今年の卒業式は出席できそうにない。子どもたちを送り出せないのは残念だが、お国のためだ。勘弁してくれ」と土光は学校側に伝えた。
それを聞いた生徒たちは、代表者を職員室に送り、教師に嘆願する。
「わたしたち、校長先生から卒業証書をいただけると思っていました。何とかお願いします。校長先生から卒業証書をいただきたいんです」
土光のスケジュールはびっしり詰まっている。結局、橘学苑は「日曜日」に卒業式を行い、土光校長が卒業生ひとりひとり卒業証書を手渡した。1982年7月にNHK特集「85歳の執念 行革の顔・土光敏夫」が放送されて以来、若い世代の間にも土光シンパが増えた。出張で新幹線ホームに降り立つと、向かいのホームから修学旅行の女子高生が「わーっ」「きゃーっ。土光さんだ」と手を振る。同伴する経団連の行革担当秘書・並河信乃が「会長、呼んでますよ」と言うと恥ずかしそうに階段をスタスタ降りた。
「土光さん、かわいーっなんて、子どもまでね。ちっともかわいくないがね(笑)。イメージって怖いな。土光という人、けっこういい加減な、悪(ワル)だと思いますよ。でも、よく見ると立派な顔をしているし、政府にもずばずば直言する。経済界がまだ人びとから信用されていました。土光さんは、国民とか、市民とかではなく、面白い表現をするんだね、『人民』って言ってた。自分も含めて、ふつうの人のことを『人民』ってね」と並河。
1983年3月14日、第二臨調は最終答申を提出し、土光もその役目を終えたかと思いきや、中曽根首相は臨調の顔を簡単には手放さなかった。使えるカードは徹底して使おうとした。第二臨調に続く「臨時行政改革推進審議会」の会長に就任してほしい、と言ってきかないのだ。土光は、会長代理に日経連会長の大槻文平を迎えることを条件に引き受ける。実務は大槻に任せ、自らは第一線から引く。6月に国鉄再建監理委員会が設立され、土光臨調の人脈で、亀井正夫住友電工会長が委員長に就任。加藤寛慶大教授、住田正二元運輸事務次官、隅谷三喜男東京女子大学長、吉瀬維哉日本開発銀行総裁が委員に任命された。国鉄分割民営化は、さらに激しい攻防がくり広げられ、JRが誕生する。
*
さすがの土光敏夫も、90歳を迎え、激務から解放された。それでも公職は120を超えていた。老いた巨樹が枯れていくように土光の体力は衰え、車椅子を使うようになった。1986年10月11日の朝、土光は車椅子から降りようとして転倒し、ベッドの角に頭を打ちつけた。東芝中央病院に入院してCTスキャナーで頭部断層写真を撮ると、硬膜下血腫が見つかり、左の前額部に小さな孔を穿って血腫を取り除く手術を受けた。術後の経過は良好で、ひと月も経たない11月5日、土光は妻の直子とともに皇居・松の間に入り、昭和天皇から勲一等旭日桐花大綬章を授与される。
無言で行われる親授式で、天皇から勲章を授かった土光は、目に涙を浮かべた。
冬が近づき、寒さを乗り切るために土光は東芝中央病院にふたたび入院した。年が明けると衰弱が深まり、見舞い客との会話が難しくなった。春を迎えて、やや体力は回復したようだったが、7月に入って肝炎を起こし、「面会謝絶」の札が病室の入口に掛けられる。
1987年8月4日午前4時8分、家族に看取られて、土光は黄泉へと旅立った。土光の遺体は整えられ、横浜市鶴見区の家へと向かう。午前8時ころ、橘学苑で合宿中だった運動部の生徒80人に迎えられ、自宅の門をくぐった。遺族に悲涙はなく、大往生であった。8月10日、日蓮宗の名刹、池上本門寺で葬儀が執り行われ、5000人が焼香をした。
土光自身は「灰になり土の中に消えた人間を、寄ってたかって祭(葬式)の主人公に仕立てる必要はない。そんなことをする暇があれば、亡き者に代わって志の一分でも継ぐ仕事をしてもらいたい......」(「21世紀へ生きる人たちへ 土光敏夫30の遺訓」『土光敏夫大事典』池田政次郎監修、産業労働出版協会)と語っていたのだが、世間がそれを許さなかった。
土光は質実剛健、質素倹約という生き方を終生変えなかった。変わったのは世のなかのほうだ。「人民」は一斉に物質的豊かさへの変化を求めたが、さりとて「消費は美徳」と完全には居直れない。その日本人の腹の底にあるメンタリティが、土光を時代の重石として使った。人びとは「パンとサーカス」にのめり込みそうになる「後ろめたさ」を土光への信認によってかき消そうとした。土光は、こうも語っている。
「もし、来世に天国と地獄があるとすれば、僕はためらいなく地獄行きを望むね。でなくとも、こんな"悪僧"であればエンマさんとつきあうほうがガラに合っているというものだ。極楽はたしかに楽しいだろうが、そんなラクなところでのんびりするのは性に合わない。やっぱり地獄の、それも地獄の釜焚きでもして、その釜の底から日本の動きを監視していく――あの世に行っても、多分、そんなところでしょう」(同前)*
土光敏夫という存在は、権謀術数の渦巻く政治のなかで、消費された。「志の一分」は、どう受け継がれたのだろうか。
土光の弟子を自認した真藤恒は、石川島播磨重工業の社長、相談役から電電公社最終代総裁に就き、行革による民営化で生まれ変わったNTTの初代社長、会長を務めた。「85歳の執念 行革の顔・土光敏夫」のなかで、真藤は、土光について、こう語っている。
「梯子を外される心配ないですからね。ああ言うてお前に約束したけども、事情が変わって、あの計画変えてくれとかね、そういうことは絶対にしない人ですからね。幹部になって社長とのやりとりの間でね、一番いけないのは、途中でこうやりましょうと動いとってね、途中で梯子を外されるのが一番困るんですね。あの人と仕事をしていると梯子を外される心配全然ないんですね。だからフルスピードでね、前へ向いていける。後ろを心配する必要がない」土光に請われて電電公社の総裁に就任したのか、と訊かれて、真藤は応える。
「うん。土光さんがお前行ってくれるかとおっしゃるから。当時は、臨調なんて問題が起こるとは、土光さんも私もつゆ知らんもんだから。ははは。あのころ、電電公社、不正経理とかナントカで、たるんどるということで、そのくらいのことならなんとかなるわいと。あっさり無条件でね、行きましょうと来たんだけど、(1981年)3月になったら臨調問題で、あっしまった、と。もう時遅しですね。へへへ。土光さんだって、自分が臨調会長になるなんて、夢にも思ってなかったわけですから、そのころは」心境を問われて、真藤は言った。
「毒を食らわば、皿までですね」土光が逝去した翌年、真藤がリクルート社から事業支援への謝礼として値上がり確実なリクルートコスモス非公開株1万株の譲渡を受けた事実が発覚する。いわゆるリクルート事件に真藤は連座し、1989年3月にNTT法違反の収賄容疑で元秘書ともども逮捕された。「土光さんが生きていたら、おれは破門だな」と悔やむ。90年10月に一審の東京地裁で懲役2年、執行猶予3年、追徴金2270万円の有罪判決を言い渡され、確定した。
晩年の真藤は「民営化は万能薬ではない」「競争状態をつくることが大事だ」「事業の独占を放置したまま民営化すると、逆に民業圧迫になる」と語っていたという。
土光臨調後、緊急の景気刺激策が採られ、政府の財政規律は緩められた。金融界の資金が溢れだす。円高、地価高、株価高のトリプル高でバブル景気の幕が切って落とされる。政府の税収は増え、いったん赤字国債はゼロになった。とともに財政規律ははじけ飛ぶ。
竹下登政権は、余った地方交付税を「ふるさと創生事業」として全国の自治体に使い道を指定せずに配った。「1億円」をもらった自治体の行動は、観光整備などに投資したり、使い道に困って宝くじを購入したり、温泉のボーリング調査や金のモニュメントをこしらえたりとさまざまだった。ふるさと創生事業は、ばらまき政策の典型といわれる。
やがてバブルは崩壊、急転直下、日本経済に不景気風が吹き荒れる。しかし、緩みっぱなしの財政規律は戻らない。建設国債、赤字国債は、ともに大量発行される。政府の財政赤字は数百兆円単位から、1000兆円に及ぼうとしている。
*
国鉄分割民営化の顛末は、どうなったのか。その最大の眼目は膨らんだ累積赤字の解消だった。分割民営化時点で、国鉄の累積赤字は37兆1000億円に達していた。このうち25兆5000億円を「国鉄清算事業団」が返済し、残りの11兆6000億円をJR東日本、JR東海、JR西日本、JR貨物などが返済するスキームがつくられた。民営化で市場原理を活用したJR各社は業績が好転し、返済が順調に進んだ。
一方、国鉄清算事業団の返済は滞った。土地売却で、極めて不自然な値付けが行われている。事業団が保有する国鉄跡地の資産価値は14兆7300億円といわれていた。1988年3月の実勢価格は30兆円以上とも囁かれた。にもかかわらず、事業団は7兆7000億円で売る見積もりを立てた。バブルのさなか、用地売却はさらなる地価高騰を招くと警戒され、政府は「その地域の地価の異常な高騰が沈静化するまで、これを見合わせる」と閣議決定する。事業団の土地は、売買を止められ、「塩漬け」にされた。
本来、需要と供給の関係で広大な土地が売りに出されれば地価は下がるはずなのだが、投機ブームの渦中では火に油を注ぐ、という理屈だ。実態は購入する側の大企業が高値でつかまされるのを恐れ、政治家に圧力をかけたのだった。事業団の収支よりも、買う側の企業の都合が勝った。土地開発に寄生する政治家は資金ほしさに赤字をつけ回す。
土地が塩漬けにされている間に利息はかさむ。1998年10月の清算事業団解散時には、債務額が28兆3000億円に膨らんでいた。
この28兆3000億円の借金のうち、16兆1000億円の有利子負債は国の一般会計に承継されて「国の借金」となる。年金等将来費用の3兆400億円は、国鉄清算事業本部が引き継ぐ。厚生年金移管金などの7000億円はJRが返済することとなった。残りの8兆4600億円は、債務免除である。借金の棒引きで帳簿上のけりがつけられている。
鉄道利用者の分割民営化への評価は、都市部では「JRになってサービスが良くなった」と良好だが、廃線にされた地方では生活の足を奪われ、過疎化が進んだ。
新JRに再就職できず、清算事業団に移された国労組合員ら1047名は、1990年に解雇された。国労組合員は闘争団を組織し、組合員の不採用は不当労働行為だと地元の地方労働委員会に訴える。地方労働委員会は組合側の主張を認め、JRの採用を認める救済命令が出されるが、JR側が拒否する。両者の対立は裁判に持ち込まれ、2010年まで続いた。国労側原告団910名のうち6名を除いて裁判上の「和解」を受け入れ、訴訟が取り下げられる。原告904世帯に対して、平均約2200万円の和解金が支払われ、国労はJRへの雇用要請を断念した。
*
行政改革、国鉄分割民営化とはいったい何だったのか。政治の舞台で、行革の旗を振り、総理の座にのぼりつめた中曽根康弘は、こう語っている。
「総評を崩壊させようと思ったからね。国労が崩壊すれば、総評が崩壊する。(国鉄分割民営化は)そのことを明確に意識してやったのです」(「AERA」1996年12月30日号)さらに、詳しく、意図を明かす。
「国鉄民営化は、国鉄労組を崩壊させました。国鉄労組の崩壊は総評の崩壊、つまり社会党の崩壊につながります。だから国鉄改革は、日本の基盤に大きな変化を与えたんですよ。もちろん私はそれを認識して実行に移しました。私が三木内閣の幹事長をしていた時、国鉄労組が8日間のゼネストをやった。私は徹底的に戦ってストを破った。そして202億円の損害賠償を要求して以降、法廷闘争となった。その時以来、国鉄の民営化と総評・国鉄労組の崩壊を狙っていたのです」(「文藝春秋」2005年12月号)まさに「戦後政治の総決算」、55年体制で生き延びる社会党に引導を渡す深謀が、国鉄分割民営化には込められていた。
中曽根が最高権力を揮(ふる)えたのは、田中角栄の政治生命の喪失と無縁ではない。ロッキード裁判で有罪判決を出されながら、選挙のたびに新潟三区で最も多い票を得て闇将軍の力を維持した田中は、1985年2月、子飼いの竹下らが派中派「創政会」を発足させて間もなく、脳梗塞で倒れた。すると中曽根は、田中を後ろ盾としていた国鉄総裁・仁杉巌を更迭して抵抗力をそぎ落とし、分割民営化は加速した。
歴史の大きな歯車の回転のなかで、行革のドラマは進行し、その利得を手にした者たちは、また次の歯車を回す。時代の遠景と近景が交差する群像劇は、いまも永田町界隈でくり広げられている。では土光の「志の一分」は誰に受け継がれたのだろうか。
当連載を大幅に加筆、改稿する単行本のなかで、その種明かしをしてみたい。ただ、ひとつ言えるのは、歴史はくり返す。現代にも、もう一つの国鉄が存在している。
それは......私たちの生活の最も重要な領域を牛耳っている。電力、である。
※当連載中、敬称を略させていただきました。取材にご協力いただいた皆さまに、心より感謝します。