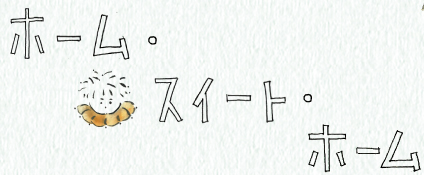2. 祖父の棺
昨夜、祖父が死んだ。享年八十八。心臓の病気で苦しみぬいて、とても安らかとは言いがたい死にざまだったらしい。
母から危篤の連絡をもらったとき、ぼくはギャラリーの仕事が忙しいなんてうそをついて病院に行こうとしなかった。
それでなにをしていたかというと、なにもしていない。新宿の駅前のカラオケボックスになんとなく入って、広い窓からただ喧騒を見下ろしたりしていた。
年末に倒れて、入院してからのお見舞いにも一度くらいしか行っていない。
めんどくさいとか、祖父の死を認めたくないとか、そういうわけじゃない。
ぼくは、祖父に会うのがいやだった。
長いあいだ教師として働き、退職をしてからもずっと教育に携わっていた祖父は、いつも正しさのなかにあろうとするひとだった。
その生き方は、そんなふうには生きられないすべての人をうしろめたくさせ、祖父自身のこともきつく縛った。なぜそうまでして正しくありたかったのかはわからない。なにひとつ語ってはくれないまま、祖父は死んでしまった。
重く冷たいヒトラーのような顔つきで、祖父は正しさを愛しぬいた。すこしでもそこから外れたり、口ごたえをしたとみなされれば、たちまち鉄鎚がくだされる。だからみんな、祖父の言うことにはしたがうしかなかった。自分の子供にはとくに厳しかったという。
長女であるぼくの母は、かつて祖父の猛烈な反対にあって、夢を捨てなければいけなかったらしい。それどころか、お見合いや結婚の相手さえ、祖父は勝手に決めてしまったという。
おかげで、父と母は、あべこべの靴下みたいにちぐはぐで、ちっとも仲がよくない。孫たちには比較的やさしかったけれど、初孫のぼくは、ずいぶんときびしく躾けられてきた。ちょっとした言葉遣いや、箸の持ちまちがえで怒鳴られたりすると、身がすくんで、ますます失敗を繰り返してしまう。
へたれなぼくは𠮟られてばかりで、めったに褒めてもらったことはない。
けれど祖父は、ぼくを本当の意味で否定したことなんて、ただの一度もなかった。
ぼくは昔から、女の子の遊びが好きだった。
お人形が、リリアンが、ビーズ遊びが好きだった。特別な意味なんてない。うつくしいから、きれいだから、それだけだ。
けれど三歳のとき、母に連れられて行った近所の公園で好きなもののことを口にした途端、まわりの大人たちから笑顔が消え、あっという間に居場所がなくなった。ぼくにとって意味がなくても、世間にはとっくに意味が用意されていたのだ。ぼくの手を痛いくらいに引っぱって、昼下がりの公園から逃げるように去っていく母の悔しげな顔は、いまも胸に焼きついている。
公園での一件があってから母は神経質になり、家の外や、祖父の前では絶対に、好きなもののことを話してはいけないと口を酸っぱくして言うようになった。
理由を聞かなくても、母のおびえきった表情を見ればわかる。
ぼくが正しくないからだ。
厳格な祖父はきっと、怒り狂うにちがいない。
それでぼくは、いつもピストルやミニカーを欲しがるような、ふつうの男の子になりきっていなくてはいけなかった。
⁂⁂⁂ この続きは、書籍『果てしのない世界め』でお楽しみください。 ⁂⁂⁂⁂