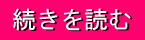先輩をめぐるドラマ―ハッテンしない韓流エピソードその2 終了
一ヶ月ほど経ったある日、店に崔先輩から電話があった。
崔先輩は渡日前のかの金銭トラブルを改めて詫びたが、その時により詳しい話をかいつまんでした。どうやら、間に、日本の暴力団組織の一員を名乗る者が介在しており、その者が属する、或いは居住するのが下町方面に当たる、皇居より東側にやや行った方面で、その男には我ながら情けないが実にウマいこと騙された、との打ち明け話であった。
アリラン・プレスリーは、「皇居より東へやや行ったところなら、今、自分が歌ってる店もその地域に入るのではないかと思いますので、先輩にかわって、その男を見つけ出し、自分なりに只では済ませません! 見つけて二度と立ち上がれぬ様にぶっ飛ばしてやります!」と一瞬熱くなって、「ああ、もうええから、ええから」と制する先輩に対して、強硬に、「いや先輩、自分が必ずその男を見つけ出して締めてやりますから!!」と言って、拳を握りポーズを決めると、電話を切った。が、受話器を置いたところで、このエピソードは実質、終わった。
性欲と差別はどっちが強い?
さて、それはそれとして、アリラン・プレスリーは昼間、日本語学校で結構な集中力(※当人比)を発揮して、極めて短期間で、日常会話は大方通ずる程にマスターし、と、同時に日本のヒット歌謡のレパートリーも新旧、新しいところでは「タイガー&ドラゴン」など30曲ほどマスターした。
と、それにしてもだ。
初めて店を訪れ、寮まで車で送ってくれた32歳のボーイ、キョウちゃんこと大野強市が初めて目の前に現れた時に自分の嗅覚からたちまち体の隅々によぎった、あの感覚。車中でもそこはかとなくジワジワと入り込んで来る御し難いあのサムシングが、キョウちゃんに限らず、そう、あのトラジ・ヴィソツキーとのトラブル時に自分を助けてくれたボーイの尹の発する香りにも感じた、とにかくあのアリラン・プレスリーのボキャブラリーでは表現し難い感覚に対して、当初、自分の中に抗うものがあったが、次第にそれへの箍が緩んでいくのを近頃、フッと感じることがあった。
「嫌だけど、どうもあの香りを入口に惹かれる何かがあるのだ」そうアリラン・プレスリーはつぶやいた。そして無意識の働きが「ハイ、今日はここまで!」とばかりSTOP!をかけたが、その出口はどうやら股間の先にあるらしいのだったが、まあよい。
そんなある晩。
錦糸町で、店の休日、同じく渡日している何人かの知人と飲み、良い按配のホロ酔い加減で、新小岩の駅から寮までの20分を、なかなか歌う機会のない李博士メドレーを口ずさみながら、夜遅く、家路に就いている時だった。
〈本日休業〉の店の前を通り、交尾する犬とアリラン・プレスリーの横を、大きな音でダンプカーが通り過ぎたその時だった。顔はよく見えないが、ツルンとした細面の20代後半の青年が、駐車場の陰から、ヒョイと現れるや、間髪置かず、「ちんぽ、好きテスカ?」と小声で言った。
他に誰も話しかける様な人物はおらず、明らかに、アリラン・プレスリーに向けられた言葉である。しかも、風向きがかわり、急にまた例の香りが青年からも漂ってきた。酔いも手伝い、ピクンと体、とりわけ下半身が妙な反応をした。
さて、その青年、日本語のイントネーションから、出身地まで俄かに量りかねるが、同胞であることは曖昧ながら解った。
そして次に驚いたのは、その言葉に対して己の思考回路を出し抜き、唇が先に動き、堂々と、「好きだよ」と答えた自分自身だったが、その自分に驚く間もなく、そう答えた以上、次なるシーンは誰もいない、夜も更けた駐車場の片隅で展開されるのが自然な流れだった。青年に〈ちんぽ〉を絞られ、男同士ならの「正にソコだ」という絶妙な舌使いからくる、その快感と更にかの香りにからまれるかの様に為されるままに果てていくアリラン・プレスリーは、その後も青年より口で丁寧に後始末を受けるのだった。
何か自分の心の、或いは鼻腔の奥にある襞に無造作に設置されていた幾つもの関門が、遂に開かれた様な気分だった。その一方、「何んということを自分はしてしまったのか」という、後悔の念にもかられ......たが、まあ、結局は気持も良かったし酔ってもいたし、どうでもよかった。
青年に自販機で珈琲(コッピ)でもご馳走しようとして、明るい、自販機が3台設置された場所へ移り、2人でウンコ座りをしながら、缶コーヒーを啜ったのだが、光線の下でしげしげと眺めると、青年のカオ立ちの中に、済州島出身者の面影をアリラン・プレスリーは見た。
そのカオ立ちの中に、あのトラジ・ヴィソツキーの子分で自分に散々嫌がらせをした実行犯、高の面影もまた見てしまった。
そして、母国語で話すと、明らかに済州島出身者のイントネーションであり、名を尋ねると、済州島出身者にしかいないとされる高とそいつも名乗ったのだった。
一度は開かれ、解き放たれたそれらの関門だったが、そんなつい先程の事実はまるで全くなかった、よって幻に過ぎなかったかのごとく態度に出て、それでも心中の整理がままならぬアリラン・プレスリーは、母国語で、それも流暢な、アボジ譲りの慶尚北道のイントネーションを、いささか酔っているとはいえ、一語一語強調して、"本土"の人間が又は慶尚道の出身者が、済州島、或いは全羅道の者を思い切り侮辱する時の言葉を狙撃銃の様に、缶コーヒーを啜る青年に向かって激しい剣幕でまくしたてた。
さっき迄、ちんぽを咥えていた青年も、アリラン・プレスリーの穏やかな外見からは俄かに想像し難い豹変ぶりに逡巡したが、すぐに反撃の構えに出るや、巻き返し、激しい口論の果て、いつしか、どちらともなく、まず正拳正段突きで相手の顎に強烈な一撃をくらわせ、それをモロに喰らった片方は、ぶっ倒れ、4、5秒意識が朦朧としたが、即、立ち上がり、今度は拳闘の様な構えで軽く跳ねると、身体をクルリと回転させるや、?拳道(テッコンドー)の決め技のひとつ、後ろ回し蹴りを、相手の左頬に思い切り決め、受けた方はぶっ倒れ、3メートル程転がった。
しかしすぐ、立ち上がり、同じく後ろ回し蹴りで、応戦し、今度はあちらを5メートル程先へ、見事にふっ飛ばしたのだった。
ゼイゼイと息の切れだした二人だったが、と、応戦が続くそこへ、アリラン・プレスリーの働く店の副支配人が数人のボーイを引き連れてたまたま通りかかり、喧嘩を止めた。
「何があった」
「あ、いやその......」
何が? しかも、あった? に一瞬我に返ったアリラン・プレスリーは口ごもったが、「まぁ、ええ、喧嘩は両成敗じゃ!」と、副店長がアリラン・プレスリーを一喝している間、ボーイらが、先ほどまで入念にちんぽを咥えていた青年を力尽くで引き離した。
その時、ツルツルとしたある種の、その、男好きのする好青年だった彼氏は、突然やくざっぽい仕草と荒い口調で、息も絶え絶えに、かの様な言葉を浴びせ、アリラン・プレスリーを脅そうと試みた。
「儂のバックには、組織がついちょる。そんでなァ、このどアホ、儂らのおじ貴は拳銃の名人で、それで、おじ貴は僑胞(キョッポ)でな、通称チャカ姜(カン)ちゅう儂らの世界なら皆知っとるピストルの名人、いや、それどころか神様や。何しろ、100m先のアリも一撃で仕留めるって話や、お前なんぞ、1キロ離れたところからだって、簡単に一発で仕留められるんじゃ! ええか、よく言うやろ、"月夜の晩ばかりやないで"ってな。これからは、いつお前の身体めがけてなぁ、バーン、BANG! とタマぁ飛んでくるか気ィつけろや! まぐろ船乗るどころの話やないで、このどアホ!」
と日本語に訳すと関西など西日本系の言葉が渾然とした様なニュアンスの横溢したかの済州島訛りの言葉をとにもかくにも激しく浴びせ、青年は両手をポケットに捩じ込み、思い切りワザとらしいガニ股で肩をイカらせ、あの刺激的な香りを仄かに残して、そそくさと去って行った。
蒲団に入ってもなかなか寝付けなかったが、アリラン・プレスリーは、怒りと快感とあの香り、それらへの嫌悪感やら複雑な何某かを交互に思い返し、そして更に青年の口から出たピストル名人について考えが及ぶのだった。
「チャカ姜って、本当にそんなに、拳銃持たせたらややこしい奴なんだろうか? そんな1キロ先から一撃で仕留めるなんて奴があるわけなかろう、人間は蟻じゃあない」
飛行機が羽田空港の周りを旋回し、蟻が次第に人の形に見えて来た時のことを思い出しながら、アリラン・プレスリーは睡魔に見舞われ眠りに落ちた。
ここまでの話のオチ
街を行くアリラン・プレスリーを占い師が呼び止める。
そして、駐車場でのあのことや、トラブルをまるでその場で見ていたかの様に言い当て、驚かすのだった。
そして、次に出た言葉には更に驚いた。
「夕べ、お前が格闘した男が属する組織は崔先輩を騙してふんだくった集団と関係がある。それにしても、くれぐれも、チャカ姜には気をつけろよ、何処でお前を見ていようと、奴がその気になれば、お前など一発でお陀仏だ。
もっとも奴が、『その気になれば』の話だが、奴はもう何十年もその気になっちゃいねえと聞く。でも油断はならねえ......」
占い師の問わず語りに呆気にとられ立ち尽くすアリラン・プレスリーに、占い師は左手を差し出し、日本の、確かここは新宿辺りであるのに、こう言った。
「はい、1000万ウォン(100万円程)」
「1000万ウォン! なぜ、そんな高いデスカ! しかもここ、ニッポン、オカシイだね!」
と、頭に血が昇った辺りで、目が醒めた。
画面ごとにコマ割りの為された4コマ漫画の様な展開だったが、夢オチはもし4コマ漫画ならご法度である。
「ハア、夢か」
外はすっかりと夜が明け、カーテンの隙間からまぶしい光が差し込んでくる。雀ではなく、カラスが数羽、大きな声で鳴いていた。
「ふう、夢だったか」
アリラン・プレスリーはそう今度は口に出して、ついさっきのことを自分に言い聞かせる様に繰り返した。
と、その時、夢の中で占い師の語った〈崔先輩を騙したダーティ・ワークを生業とする組織〉と、自分をいじめた、あのロシア人ポンチャッカー、トラジ・ヴィンツキーとはグルで、しかも、トラジ・ヴィソツキーはロシアン・マフィアとの太いパイプがある! 否、というより、奴の正体はマフィアそのものだ!
そんなことが唐突に閃いた。その閃きには我ながら強い説得力を感じたが、だからといってどうするわけにもいかず、腕組みと共に頷くや、渡日前から引きずっていたロシア人ポンチャッカーのエピソードは、そこで完奏というより、フェイドアウトという感で完結した。
 ※ この写真はイメージです。
※ この写真はイメージです。