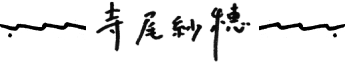思えば富山に行くことになったのは、最初から不思議な流れだった。2015年にアルバム『楕円の夢』リリースツアーを全国13か所で行うことになり、当初北陸公演は金沢で行おうという話になっていたが、現地で動いてくれそうな人の都合がつかないらしく決定できずにいた。他の場所はすでに詳細を決め始めていたところだったので、一斉告知をするために北陸公演も早めに決めたかった。
そのとき、石川でできないなら富山でできないかな、とふと思った。富山には行ったことがなく伝手もなかったが、すでにおんばさまのことを調べ始めていたので、立山にはたくさんのおんばさまがいるということが頭にあったかもしれない。その時点ではただの願望だった。すると数日後、突然富山からライブのオファーが舞い込んだのだ。ちょうどアルバムリリースの発表をしたタイミングだったので、依頼人のHさんも、もしかしたら長年ファンでいてくれて、発表を見て、富山にもリリースツアーで来てほしいということで連絡をくれたのだろうかと思ったが、聞いてみるとHさんはニューリリースの情報は全く知らないまま、オファーをくれたのだった。不思議なこともあるものだな、と思いつつそのスムースな流れに感謝した。富山のライブは6月7日に決まった。
立山は、雄山(おやま)、大汝山(おおなんじやま)、別山(べっさん)の総称という。周囲には剱岳、浄土山、大日岳などがそびえ、歴史的には地獄と極楽の混在する霊峰として信仰されてきた。剱岳はその名の通り、地獄の針山を連想させ、弘法大師がわらじ六千足を費やしても登れなかったという伝承がある不可登の山だ。1907(明治40)年に登頂された際には平安時代の錫杖(しゃくじょう)頭と刀身が発見されたほど長らく閉ざされた山で「登らねばならぬ立山と登ってはならぬ剱岳」という言葉もあるほどだ(五来重『修験道の伝承文化』名著出版)。
「登らねばならぬ立山」は修験の山で女人禁制がしかれたが、同時に女人信仰の山でもあった。秋の彼岸に山麓の雄山神社近くの布橋(ぬのはし)で行われる布橋大灌頂には、全国から女性が訪れ、その死後の救済を願った。この世からあの世へ橋を歩いて渡り、再び生き返るという擬死再生の行事である。男性が修験者となって厳しい登山や修行によって擬死再生を果たすのに対し、女性は橋を渡り、姥尊の護符や変女転男のお札、極楽行きの証明書である血脈などを受け取ることで男性に生まれ変わって(変成男子〔へんじょうなんし〕)浄土に行けると考えられた。女性がそのままでは極楽に行けないのは、血の穢れが問題とされたためだ。これは血盆教という大陸から入った考えが広まって一般化したもので、この女子皆地獄行きの風説を布教側も大いに喧伝して信者の女性を増やした。
「男にならないと極楽に行けないとか全然納得いかないけど、布橋の大灌頂はちょっと参加してみたいですね」
その日、主催のHさんに代わって、ライブ前に立山に行きたいとわがままを言った私のために車を出してくれた富山のデザイナーNさんと、そんな話をしながら立山博物館の展示を見て回っていた。地方ライブの主催の人が、自身は会場準備などで動けないために遣わしてくれる人やスタッフさんが、偶然自分の親しい人の知り合いであることがよくある。これも不思議なことだが、何かを一緒になしとげるための仲間というか、出会うべき人なのだろうという感じがする。Nさんもそうで、アルバム『楕円の夢』のPVのディレクションやジャケットデザインをお願いしていたデザイナー山野英之さんと、東京で勤めていた時に親しかったという。加えてNさんは得意の料理の腕前を活かして、古くから伝わる郷土料理を現地のおばあさんたちにリサーチし、若い人とその成果を共有すべくワークショップを開く活動もされていて、民俗学的な興味も共有できる人だった。現在は群馬の山間部に伝わる郷土料理や風習を調査中らしい。
私たちがまず博物館に向かったのは、8体のおんばさまが展示されているためだった。もともとは芦峅寺(あしくらじ)の姥堂に66体ものおんばさまが鎮座していたという。芦峅寺は立山の玄関口であり、芦峅寺の北西に位置する岩峅寺(いわくらじ)と共に修験の中心施設だった。共に神仏混淆の寺社だったが、明治の廃仏毀釈で雄山神社という名前のみ残された。
教科書的な知識では廃仏毀釈は仏教への弾圧としてとらえられるけれども、その被害は仏教にとどまらず、多くの民間信仰や風習が迫害を受けた。十九夜講など講と名のつく集会や、日待ち、月待ちなどの集い、「淫祠」の建立、婚姻葬祭などの過度な饗宴、旅芸人や乞食への施し、浄瑠璃や三味線を学んで仕事を怠ること、小さな祭りをたびたび行い群飲浪費することなどのほか、巫女の神がかりである口寄せや、博打、芝居や狂言の劇場設営、盂蘭盆会(うらぼんえ)の廃止、瞽女(ごぜ)も禁止された(安丸良夫『神々の明治維新──神仏分離と廃仏毀釈』岩波新書)。こうした伝統の数々を否定した明治政府は、近代的合理的な感覚を持った、ひたすら労働する国民を作り出すことを目指したのだろう。安丸はこうした姿勢を「啓蒙的抑圧」と表現している。
乞食の取り締まりが行われ始めたのもこの時代である。乞食とひとくくりにできないほど、明治以前の社会にはたくさんの放浪する物乞いたちが一般の人々と交渉を持ち、各自の役割を持っていた。遍路や六十六部と言われるような下級の旅の僧、門付けの芸人などは定住せず、生産せず、時にうっとうしがられながらも、その芸や信仰によって存在を人々に認められ、日銭を稼ぐことができた。働かぬ者は怠惰である、という糾弾が国民国家を形成する過程で採用され、神道以外の信仰はまがいものであるというイデオロギーと共に日本という国の歯車として回り始めた、そんなイメージが浮かぶ。
ただの老婆像と言ってしまえばそれまでのおんばさまも、もちろんいかがわしいものとされた。姥堂は壊され、おんばさまたちも散逸し、現存するのは博物館の8体と近くの閻魔堂の5体と言われる。むしろよく、それだけ残すことができたものだと思う。破壊と迫害の混乱の中で、村人たちが手分けして隠すことができたのがそれくらいの数だったのかもしれない。


博物館に展示されていた8体のおんばさまは、薄暗い館内のガラスケースの中で、白いお召し物を着て、赤いたすきを両肩からかけ、麻で編んだような帽子をかぶっている。いずれも黒っぽいが木造のものが多い。みんな右膝を立てているが、一人だけ左足を立てている。赤たすきにはそれぞれ、「祖先冥福子孫繁栄 信者合掌」「大慈大悲立山*(女偏に田が三つ)菩薩」と書かれている。それぞれの表情は見事に一体一体違っている。人懐こいゴブリンのような、異界の使者といった風情のもの、説明がないと男にしか見えないたくましいもの、般若のような八の字眉で口は笑い、見ていてぞっとするもの、一文字に結んだ口で表情もたくましいが、ふくよかさに女性性が感じられるもの、眼球がガラス製で異様な迫力をもち、顔もはげかけて古そうなもの、表情が見えにくいが微かに笑っているように見えるおとなしい印象のもの、しわが多く口を開け、猿の化け物のように見えるもの。にっこりと笑って、優しそうなもの。
立山のおんばさまは「姥」の字でなく「女+三つの田」で表される。かつて右手には穀物、左手には麻をにぎっていたとされる。地母神であり、生命を生み出す神だ。大日岳のふもとに祀られる山の神とも、布橋のかかる姥谷川が流れる来拝山の水の神とも言われる(福江充『立山信仰と布橋大灌頂法会──加賀藩芦峅寺衆徒の宗教儀礼と立山曼荼羅』桂書房)。
こうした大らかな自然神としてのおんばさまの由来に比して、ひっかかってしまうのが女人信仰のストーリーだった。血穢のために女性性が否定され、男子になるという形式を経てようやく女性の浄土への道が保証されるものになっている。本来生命賛歌であってよいはずの信仰が、その象徴である血を否定し、血穢を恥じたり血の池地獄への恐怖心をあおる過程で広まっていき、女性たちの支持を得てきたのは皮肉なことだ。そんな奇妙なねじれは、姥神というテーマを追いかけていくとしばしば出会うものだが、立山の他の史跡にもそんな不自然なねじれがいくつも残っていることに二度目の富山再訪で、気づくことになる。
博物館を出て隣接する旧芦峅寺、雄山神社に立ち寄る。鳥居をくぐって正面奥に立山を開山した佐伯有頼の墓がある。有頼は奈良時代の人で、狩人だったと伝えられる。701年、白鷹と阿弥陀如来の化けた熊に導かれての開山だった。有頼の「アリ」は顕現を意味し、「ヨリ」は、依代や憑依の「ヨリ」である。ちなみに大山の開山者もやはり狩人で依道といい、各地の修験の山の開山者は名前にこうしたシャーマン的な性質を連想させる音のつく者が多いという。
「立山開山御廟」と書かれた有頼の墓の裏手にまわったとき、私もNさんも固まった。
「今日ですね」
6月7日は有頼の入定の日だったのだ。開山者を弔う様子の者もなく、がらんとした境内には背の高い杉が幾本も立ち並んで、有頼入滅の日から1256年後の午後が静かに流れていた。