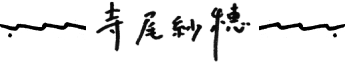齊藤泰助『山姥の記憶』という本がある。山姥というテーマを追い始めてしばらくして古書店で見つけた。その後私が山姥情報を追いかけていることを知って、わざわざ送ってくれた人もいた。桂書房という富山の出版社から出されたこの本が網羅するのは、中部各地の山姥伝説だ。丹念に調べられており、一読して、山姥や姥神を知る上で重要な本と分かる。新潟、長野、富山、石川、岐阜、静岡などに加えて神奈川の足柄山伝説にも触れられているのだが、新潟に関する記述は、能「山姥」ゆかりの地である上路(あげろ)の伝説が中心になっている。私も上路に行かなければという思いを持っていたのだが、その前にご縁が舞い込んだのが、新潟県阿賀野市にある高徳寺の羽黒優婆尊だった。ここは『山姥の記憶』には載っていない。しかし、この高徳寺が、今なお、姥信仰が熱く根付いている場所だったのである。
阿賀町から連絡をくれたのは、町の地域包括支援センターで働く社会福祉士の渡部一知さん。『彗星の孤独』を読んで、福祉についての考え方に共鳴した、と連絡をくれた。私も福祉の現場で奮闘する人の声を聞きたいと思っている、と伝えると彼は上京されたので、東京沼袋の「カフェ潮の路」にお連れした。つくろい東京ファンドの代表、稲葉剛さんたちが営むこのカフェは、ランチ代を次の誰かのために買うことができる「お福わけ券」システムをとっており、いつも近隣の人々や、事情があって生活保護を受給している若い人、おじさんたちなど、多様な人が集う。渡部さんから包括支援センターでの話などを聞きながら、ランチをいただく。渡部さんからは、阿賀野川で起きた新潟水俣病の患者さん、それも患者さんたちの運動に加わっていない患者さんの声を聞いてくれないだろうか、という提案を受けて、阿賀に向かうことになる。その後も何度も阿賀に行くことになったのは、私が興味のあった姥神や風の神など民俗学的な話題について、渡部さん自身も興味を持ってリサーチを繰り広げてくれたからだ。リサーチの中で、高徳寺やその他周辺の姥さまのことを見つけて教えてくれた上、取材の手はずを整えてくれた。
2019年7月19日、9時新潟着。ここから車で1時間弱、阿賀野市の高徳寺羽黒優婆尊に到着した。天平5年行基作と伝えられる優婆尊をまつるために400年ほどまえに開かれた寺という。一回りほど年上にあたるものの、若々しいすっきりとした顔立ちの平野住職が迎えてくれ、姥さまの由来を教えてくれる。
行基が出湯を訪れていた時、三途の川の老婆が現れ、「私は表は極悪忿怒の姿をしているが、内は愛憐大悲の情を持って人々を救おうとしています。すぐに私の像を彫刻しなさい」と言って、毘廬舎那仏の姿で空に消えたそうです。
三途の川の老婆はもちろん奪衣婆のことで、姥神と奪衣婆の習合はよくみられるが、奪衣婆の信仰は地獄を語る十王思想と共に室町ごろに広まった。この像が行基作だったとして、三途の川の老婆と結びつけられたのは室町以降のことになるだろう。高徳寺を立てたのは2.5キロほど東にはなれた華報寺の八代目住職だった。高徳寺のご縁起には「天正十四年華報寺住職八代和尚」が夢で「十字街に安置せよ。されば多くの人々を救うであろう」とお告げをきいて、優婆尊安置のために高徳寺を建立したと書かれている。華報寺がある集落は出湯といい、行基が訪れたという縁起に書かれていた場所である。
「優婆尊」は「乳母」からきた、として子育て、安産のご利益などが語られるが、在家で修行にはげむ仏教者を意味する「優婆塞(男性)・優婆夷(女性)」の意も見逃せない。猪苗代の関脇や金曲などもそうだったが、おんばさまが、「優婆夷霊」として祀られているところも多くあるからだ。部屋の壁の高い所に「うばさまごえいか」がかけられている。木彫りの台に金字で書かれた立派なものだ。
第一番
はるばるとまへりてをがむ
いちのきど いつもたへせぬ
ごくらくのかぜ
第二番
たまてばこ ふたをやここ
にぬきすて かけごをぬい
いでいづくなるらん
第三番
こづさんのみねよりみをろし
うばのたき ほとけのち
がいあらたなるらん
昭和十一年一月一九日
新津町 古川みさを
新津というのは新潟市内だ。民俗学者の松崎憲三によれば、優婆尊信仰は新潟市内、五泉市など県内、遠くは他県など各地に巫女的な人物を中心として講中を持ち、大祭など行事ごとに信徒が集まってくるともいう。松崎は下越の曹洞宗と優婆尊信仰の関わりをとりあげるなかで、高徳寺から北東に2キロほど離れた女堂の如意輪観音信仰に触れている(「民俗信仰を通してみた地方文化再編の実態──下越地方の曹洞宗寺院と優婆尊信仰」〈以下「優婆尊信仰」と表記〉『地域社会・地方文化再編の実態』)。ここの毎月20日に集まって和讃をとなえる「二十講」にはさまざまなレパートリーがあり、その中の「葬式の二十日様」には「一の木戸の優婆様」という歌詞があったり、「二十日待御詠歌」には上の羽黒優婆尊の御詠歌とかなり共通する部分が見られる。
はるばるとまいりておがむ
一の木戸いつもたいせん ごくらくのかぜ
五手箱二箱ここにぬぎすてて
かけごをぬぎていずくならん
五頭山やみねをたどりて
うばがたき佛のちかい
あらたなりけり
「木戸」というのは関所の門、入口という意味を持つから「一の木戸」は第一の関といった意味だろう。柳田国男が「せきのおば様」という一文を書いているように、姥神も奪衣婆もあの世とこの世の境目におり、奪衣婆は三途の川の手前で死者の魂が出会う第一関門であるから「一の木戸」と「優婆様」が結びつくのは自然だ。「たへせぬ」が「たいせん」と聞き違いになっていたり、「玉手箱」が「五手箱」になっているのは、漢字の見間違いだろう。「かけごをぬぎて~」の二番は意味がとりにくいが、玉手箱もかけご(掛籠)も、隠すもの、秘めるものであり、本心を隠すことや、偽りの心から解放されてといった解釈ができそうだ。如意輪観音は血盆経でとなえられた血の池地獄から女人を救ってくれる観音であるが、そこに奪衣婆(あるいは懸衣姥)としての優婆様が重ねられているのだろう。
住職がおもむろに額に入った写真を見せてくれた。額にマジックで「平成二十九年『酉年』」と書かれている。優婆尊の前の祭壇が写っている。2本の白いろうそくの炎、果物や酒など豊富なお供え物。その奥の少し高い位置から、下に向かって尾のようなものが赤く長く垂れている。一見して何なのか、どうやってこれができたのか、わからない。

「これは、2017年の酉年を迎える大みそかの夜の写真なんです。ここには赤い2本のろうそくを立てていたのですが、突然炎が大きくなり、30分ほどの間にこれができあがったんです」
改めてみると、それは溶けた赤いろうでできた2羽の鶏の長い尾のようであった。
「酉年を前にして、優婆尊が作られたものではないかと思っています」
と住職は言い、私と渡部さんもあっけにとられて、えー、と言ったきり言葉が見つからなかった。この奇跡のようなものを一部始終見ていた人の言葉と写真を前にしては、驚くよりほかない。どうやら、物静かな神様というより、非常に生き生きとしたアーティスティックな神様であるようだ。あとから、境内のご縁起を見直すと、行基が姥像を彫った天平5年もわざわざ「鶏年」と書かれている。ついでに言えば私自身も酉年なので、何だか不思議な気持ちになる。
「今はそれほどでもなくなりましたが、先代が住職をしていた時代には、優婆尊の御祈禱の際に、正座の状態のまま空中にはねる人が何人も続出し、異様な熱気だったと聞きます」
近代でもキリスト教福音派など宗派によっては礼拝の最中に「異言」と言われる言葉をしゃべりだす人が現れ、人々が熱狂していくようなことがあったと聞くが、それに通じるような濃密な信仰が少し前までこの場所にあったのだ。なにより住職が目にしたろうそくの鶏の件もほんの数年前の話というのがすごい。人々の信仰心が強いほど、見えない存在はエネルギーを得て生き生きとその力を暗示するのだろうか。祭壇の前には、「優婆尊」と書かれた大きな太鼓がおかれている。この日は18時30分から「逮夜」が始まる予定だった。経典を読誦する集いを法会というが、その前夜を逮夜という。そのため一度おいとまして夜にまたお邪魔する予定だった。住職は、優婆尊の好物といわれています、と「香煎」を下さった。家形に折りたたまれた紙に「優婆尊」と書かれ、麦だろうか? 粉が入っている。これに砂糖をまぜ、水で練って菓子として食べたり、香味のシソや蜜柑の皮と一緒に香煎湯として飲んだりするらしい。
「裏には地元の人たちが納めにきた優婆尊がたくさんいらっしゃるんですよ」

と住職。なんでも、このあたりには「一家に一優婆尊」という勢いで、それぞれの家に祀られていたというのだ。しかし、篤く信仰していたおばあちゃん、おじいちゃんが亡くなると、置き場所に困るのか、遺族が高徳寺に納めに来るらしい。そんな話は、他のどこの地域でも聞いたことがなかった。緊張しながら、住職のあとをついて廊下を歩いて行くと、息をのんだ。赤い着物を着せられてはいるが、一体一体顔つきも作りかたも大きさも違う姥さまが何体も安置されていた。目に異様な力のあるもの、顔が黒光りしているもの、憤怒の顔、おだやかな顔、悲しげな顔、福の神のような顔、右足を立てたもの、着物で足は見えぬもの、歯を見せて笑う顔。多くは、頭の上に綿をのせて白髪が表現されている。同様の姥像としては新宿・正授院の「わたのおばば」を思い出す。中には自作のものもあるのかもしれないが、これだけたくさんの像が残っているということは、作る職人がいたということだ。濃密な優婆尊信仰の形を目にして、なんだか信じられないような気持ちで高徳寺をあとにした。夜の逮夜はどのようなことになるのだろうか。