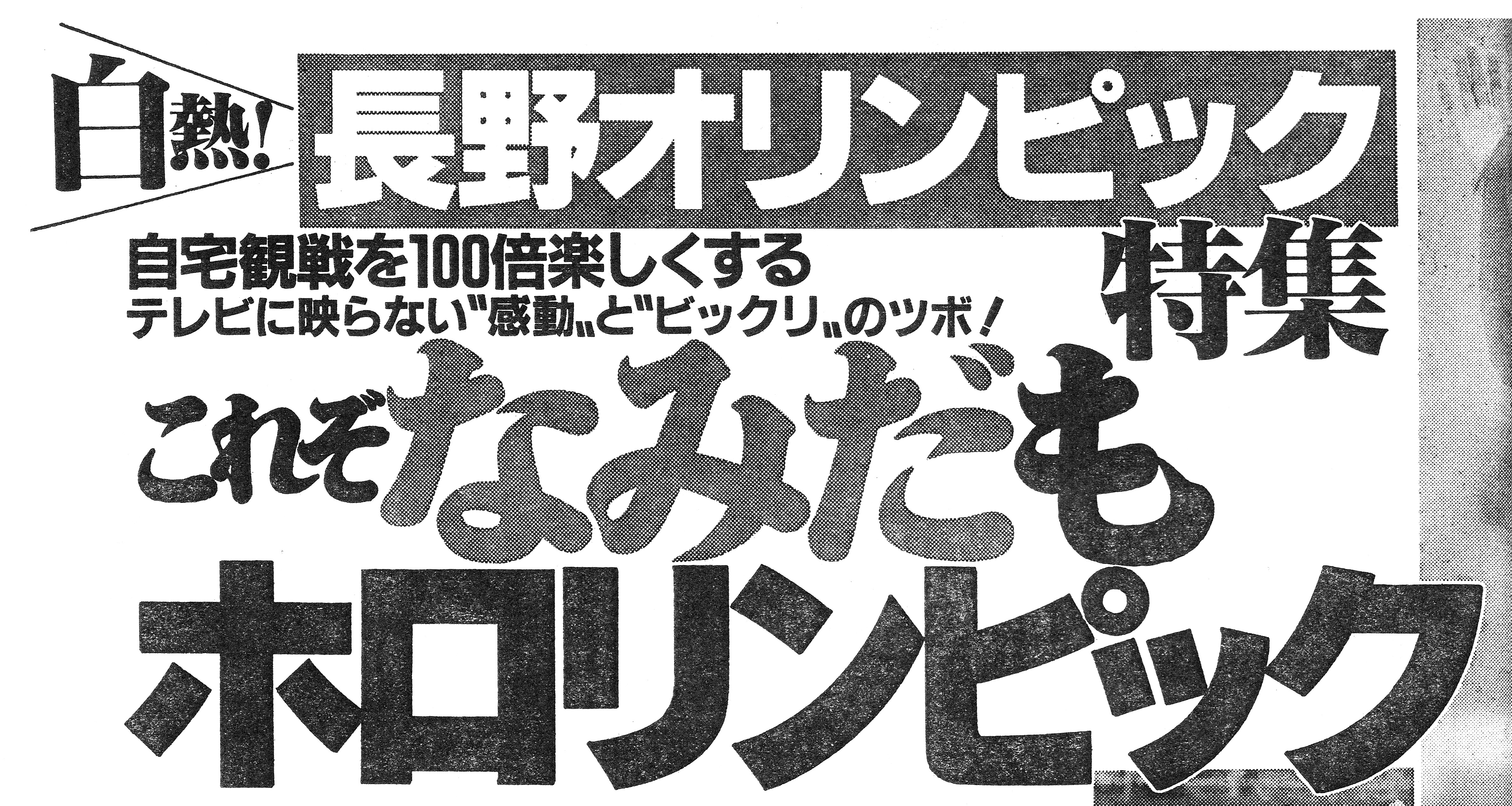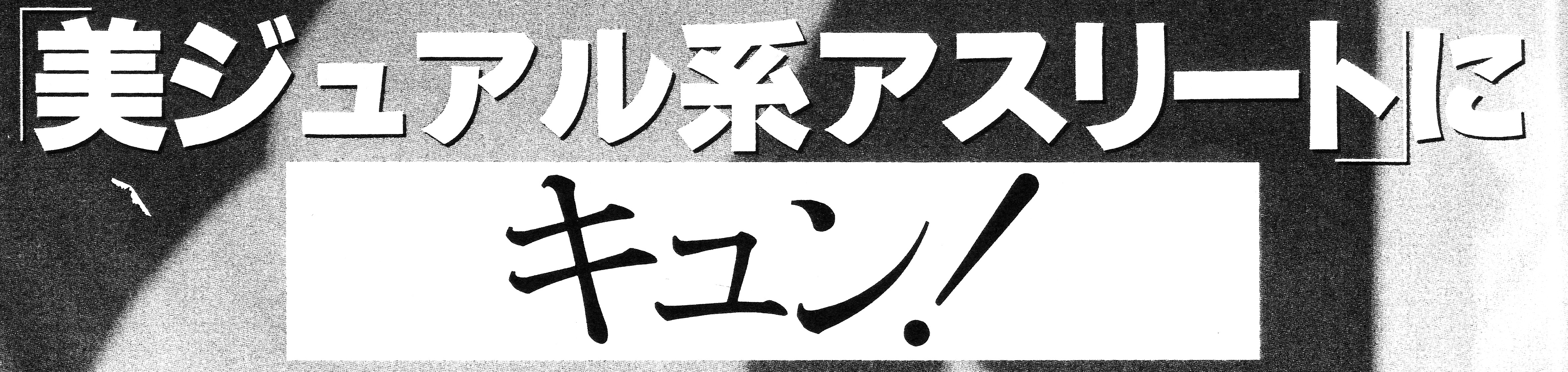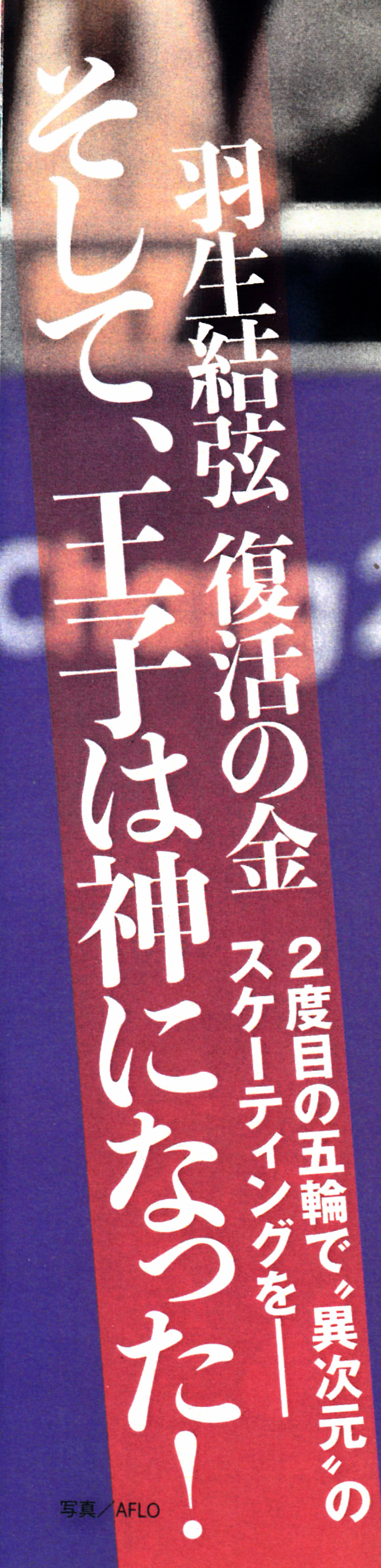ウィンタースポーツの季節が近づくと、「婦人公論」や「家庭画報」といったミセス向けの女性誌で、風物詩のように見かける言葉がある。
「氷上の貴公子」。
上品で優雅な明朝体である。
まるで歌舞伎や宝塚をとりあげるような華やかさだ。

「婦人公論」(中央公論新社、2018年3月27日号)
しかし、「氷上の貴公子」が誌面をかざるようになったのは、実はここ十年足らずのことにすぎない。
2010年のバンクーバーオリンピックで、日本人男子初の銅メダルを獲得した、髙橋大輔の活躍以降である。
それ以前はどうだったか。調べてみると、「貴公子」どころかフィギュアスケートの話題も、あるいはスポーツの記事さえ見あたらない。白洲正子や瀬戸内寂聴は似合っても、本来アスリートとは縁遠い雑誌なのだ。
では、同じ「ミセス向け」の雑誌でも、芸能や皇室など、幅広い時事ニュースをとりあげる女性週刊誌ではどうだろう。
女性週刊誌。
それは独特な世界である。
刺激のつよい色づかいと、文字で埋め尽くされた表紙。
コンビニや美容院、病院の待合室など、書店以外の場所でも身近なわりに、各誌の個性や読者層の違いを私はよく知らない。
昔はおばさんの読みものだと思っていたので、学生の自分が手にとるのも恥ずかしかった(今ではまったく平気だけど)。
でも、通学中に電車で目にする中吊りの見出しがどうしても気になってしまう。好奇心をおさえられずに、芸能人のゴシップ記事をこっそり立ち読みしたのが懐かしい。

「女性自身」(光文社、1998年2月17日号)
ちょうどそのころ。
日本で開催された長野オリンピック(1998年)では、モーグルやスキー・ジャンプが注目をあつめていた。
フィギュアスケートの扱いは明らかに今よりも小さく、他の地味な競技種目と同列の扱いだ。
無理もない。当時の日本男子フィギュアは、長野で初のオリンピック出場をはたした本田武史の15位が最高位。入賞にも届かなかった。
苦戦の状況は女子も同様で、荒川静香が2006年のトリノで金メダルに輝くのは、まだずっと先のことである。
しかし、数少ないフィギュアスケートの記事に意外なスターを見つけた。
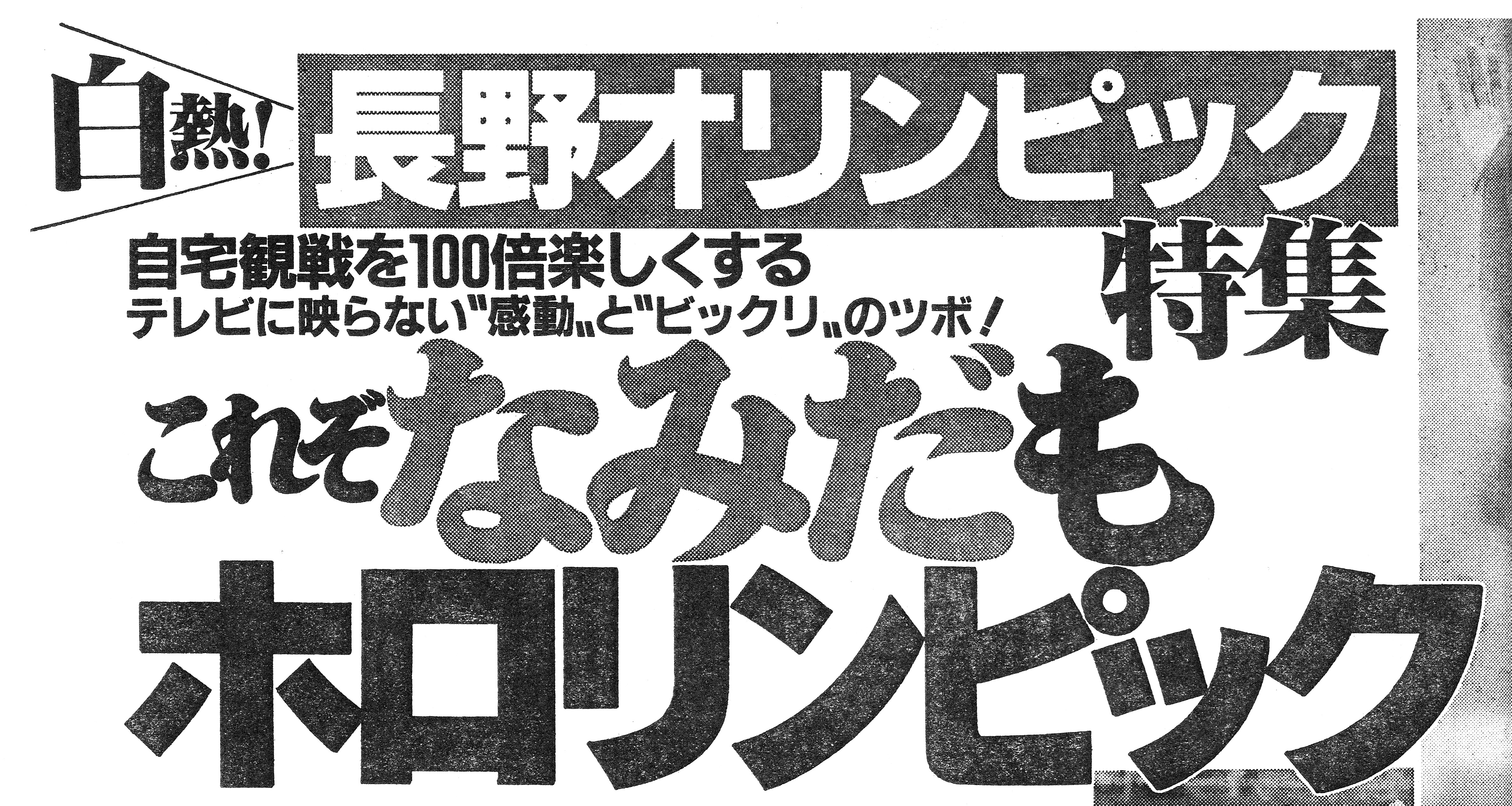
「女性自身」(光文社、1998年2月24日号)
それは、家族のサポートがなければ競技を続けることができないスケーターの苦労を取材した白黒記事のレタリング文字である。
前回もレタリングについて書いたが、「女性自身」は、90年代の終わりになっても手描き職人が活躍する貴重な現場のひとつだった。
写植書体の〈ゴナ〉がつかわれている「長野オリンピック」のほかは、「白熱!」も、「特集」も、よく見ると人の手で書かれている。
そして「ホロリンピック」!
オヤジギャグといってしまえばそれまでだけど、言葉の人情味がこんなにも伝わってくる文字が他にあるだろうか。
〈ゴナ〉に似ているようで似ていない、金属活字のような力強さもありながら、既成の書体には絶対にない文字。「不可分の関係」とは、まさにこのことなのだろう。
「なみだ」の部分を明朝体に変えているところがいい。
さらにつけくわえるなら、記事の本文が、活字の〈秀英明朝〉で組まれていることにもおどろいた。
もうすぐ21世紀という時代に、週刊誌のような発行部数の多いメディアで活字が現役だったのだ。
活字、写植、そしてレタリングつまり手描きを、迷いのない、しかし愛おしさに満ちた手つきで組み合わせ、ひとつの記事をつくりあげている。
雑誌文化の極みともいえる、たくましい技芸は、しかしついに爛熟期を迎えていた。
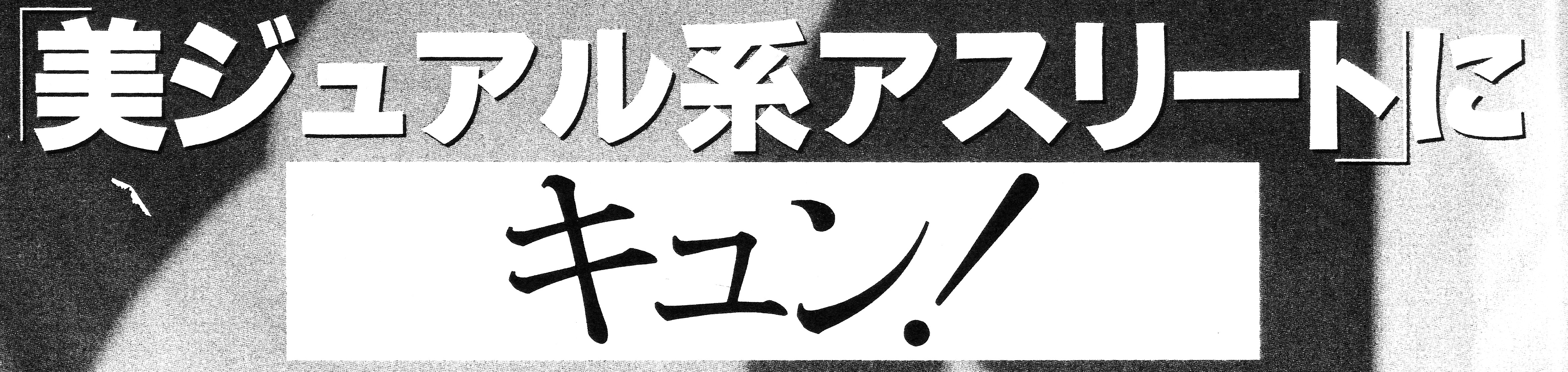
「女性自身」(光文社、2002年2月26日号)
長野から4年後。
2002年のソルトレークオリンピックでは、〈 「美ジュアル系アスリート」にキュン! 〉という見出しの記事が掲載されている。美女やイケメンの選手を紹介する内容で、いかにも週刊誌らしい観戦ガイドである。
たった数年で、レタリング文字や活字は誌面から幻のように消えてしまったが、情報量の多い見出しを、異なる書体の組み合わせとバランスで際立たせるテクニックは健在だ。
ここで注目したのは「キュン!」の部分。
「なみだ」という言葉がそうであったように、ここだけ明朝体になっている。
書体が変わると、文字の重力が変わる。風をはらんだような躍動感に心が動く。

「女性自身」(光文社、2006年3月14日号)

「女性自身」(光文社、2010年3月2日号)
この後の「女性自身」は、2006年のトリノオリンピックの時点で完全にDTPへ移行し、十年前の誌面とは書体が様変わりしている。
しかし書体の変遷とは、活字、写植、DTPという印刷技術の違いだけではない。
読者はもちろん、言葉を介して文字と出会う。
そして、時に言葉を導くのは、新たなヒーローの誕生である。
羽生結弦。
弱冠19歳にして、アジア人男性初の金メダルを獲得した、2014年のソチオリンピック。輝かしい栄光の瞬間を伝える巻頭カラーには、こんな見出しがおどった。

「女性自身」(光文社、2014年3月4日号)
その記事は、読者の目を釘づけにしたに違いない。
ただならぬインパクトを与えた理由は書体にある。
書体そのものが新しいわけではない。明治・大正時代から続く築地体の金属活字を、デジタルで復刻したフォントだ。
「婦人公論」ではおなじみの格調高い書体だけれど、それが女性週刊誌で、しかもロイヤルファミリーの話題ではなく、スポーツ記事でつかわれた。イメージの融合と分離が新しさを生んでいる。
この書体をひきよせたのは、「恋」という言葉の力だと私は思う。
「女性自身」にかぎらず、芸能人のスキャンダルやゴシップをあつかう女性週刊誌にとって、「愛」はお手のものだ。
「熱愛」「お泊まり愛」「略奪愛」に合う書体なら、いつも扱い慣れている。
だけど、恋。
あえて「恋」と表現されるべきものだったのだろう。
ただの試合速報ではない。イケメンアスリートの紹介でもない。もっと別の何かを読者に伝えたい、と、作り手が意図したからこそ、その要求にフォントが応えた。かつて職人が「ホロリンピック」の文字を書いたように。
言葉と文字のあいだに、脈々と続く営み。それは今も変わらずにある。
貴公子はプリンスへ、そしてとうとう人ならざる存在にまでなってしまった。
頂点を極めた先に目指す高みに、文字がどう応えるのか。その行方も楽しみだ。
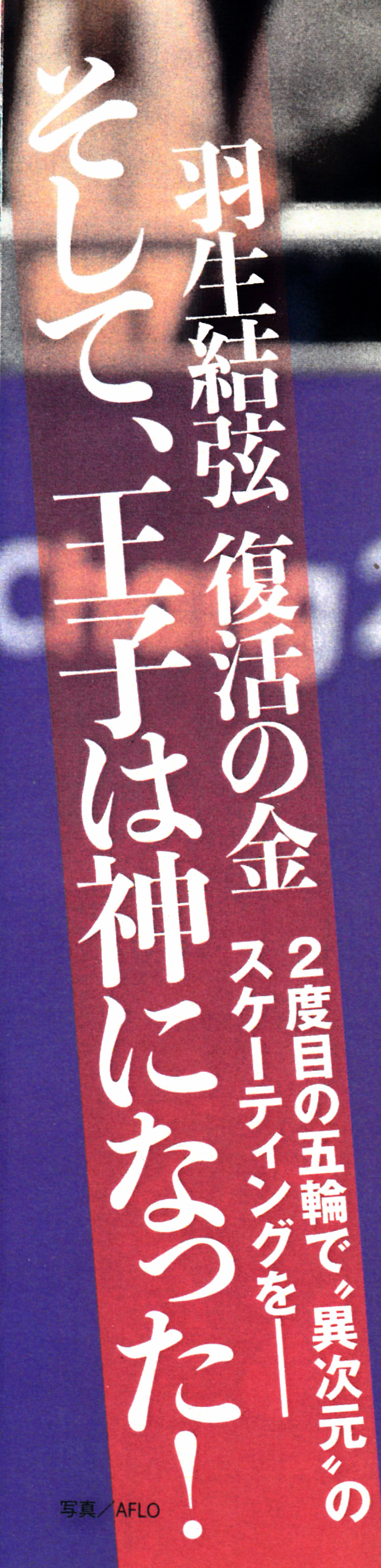
「女性自身」(光文社、2018年3月6日号)