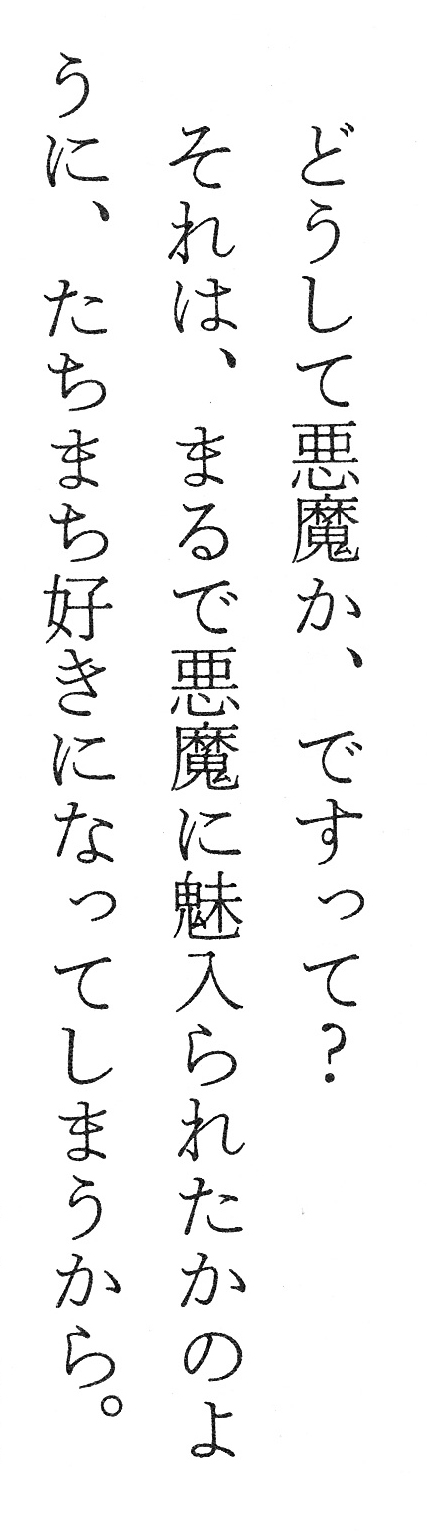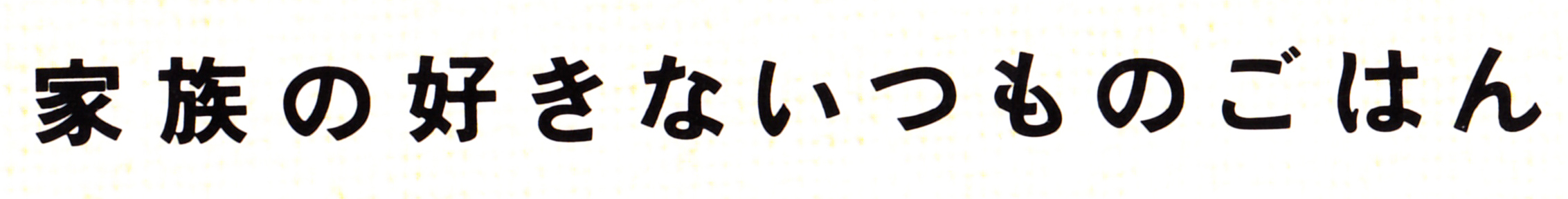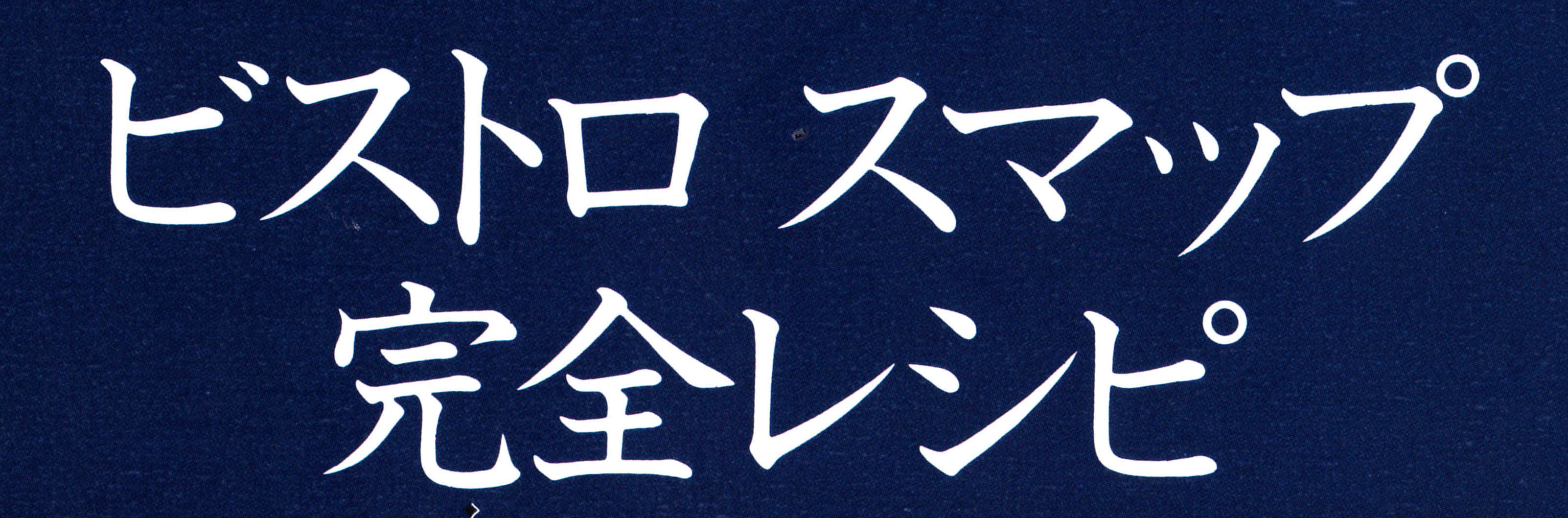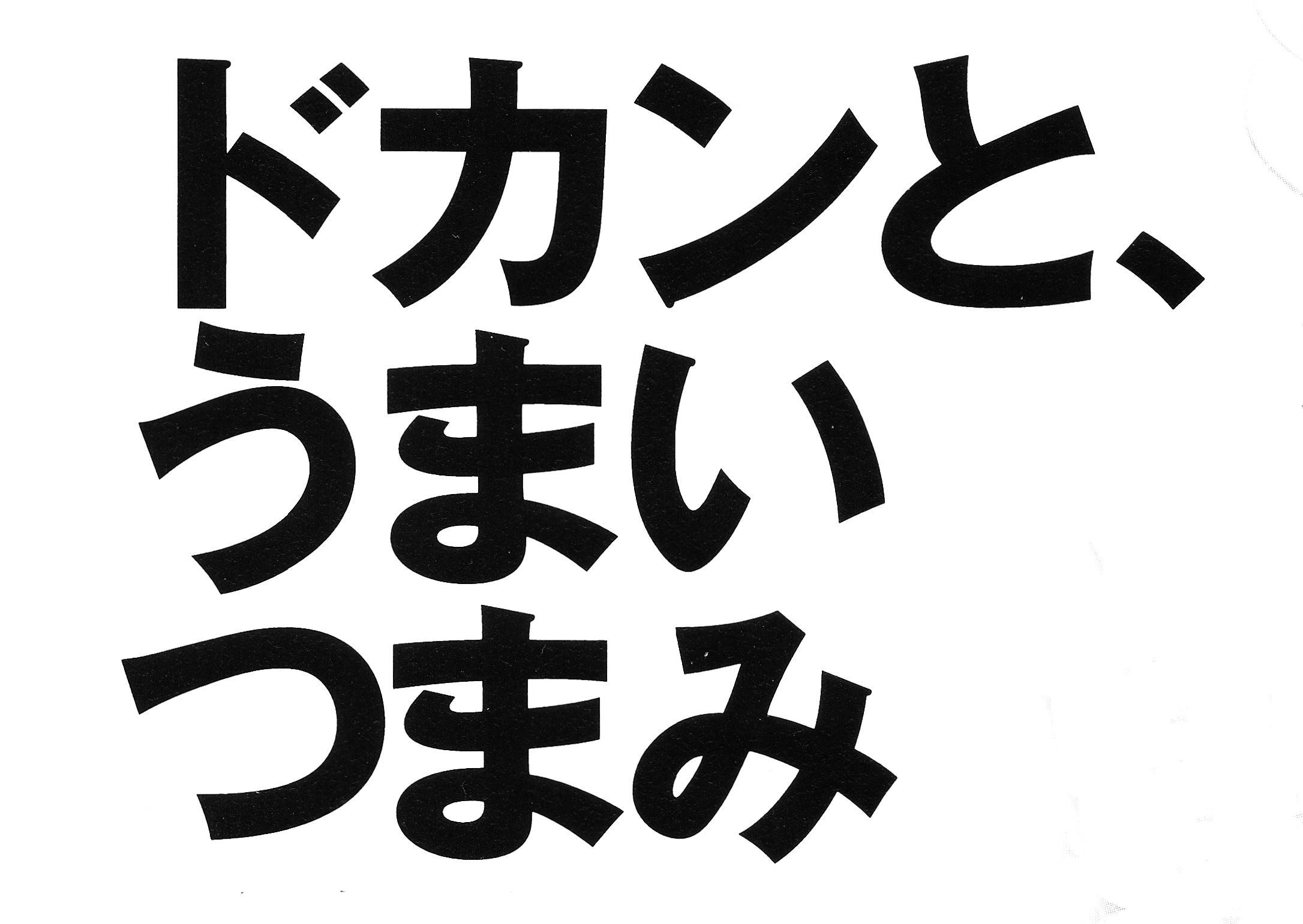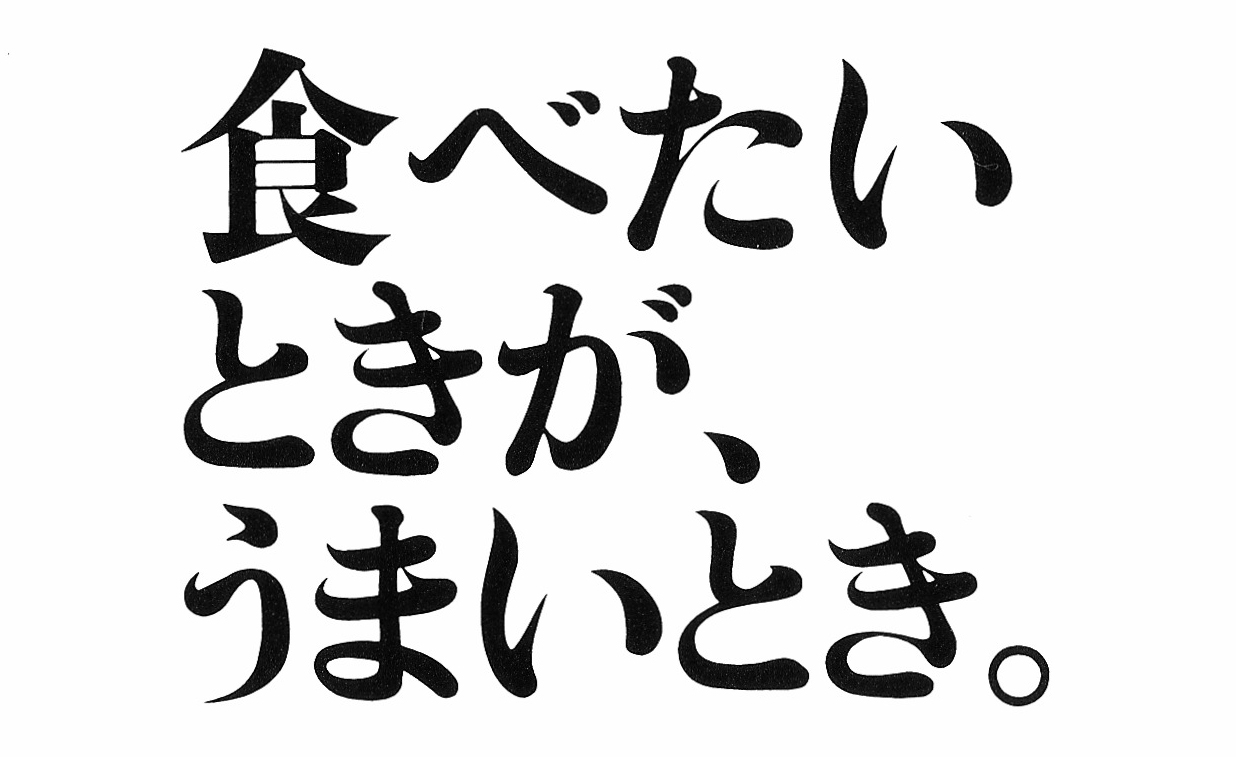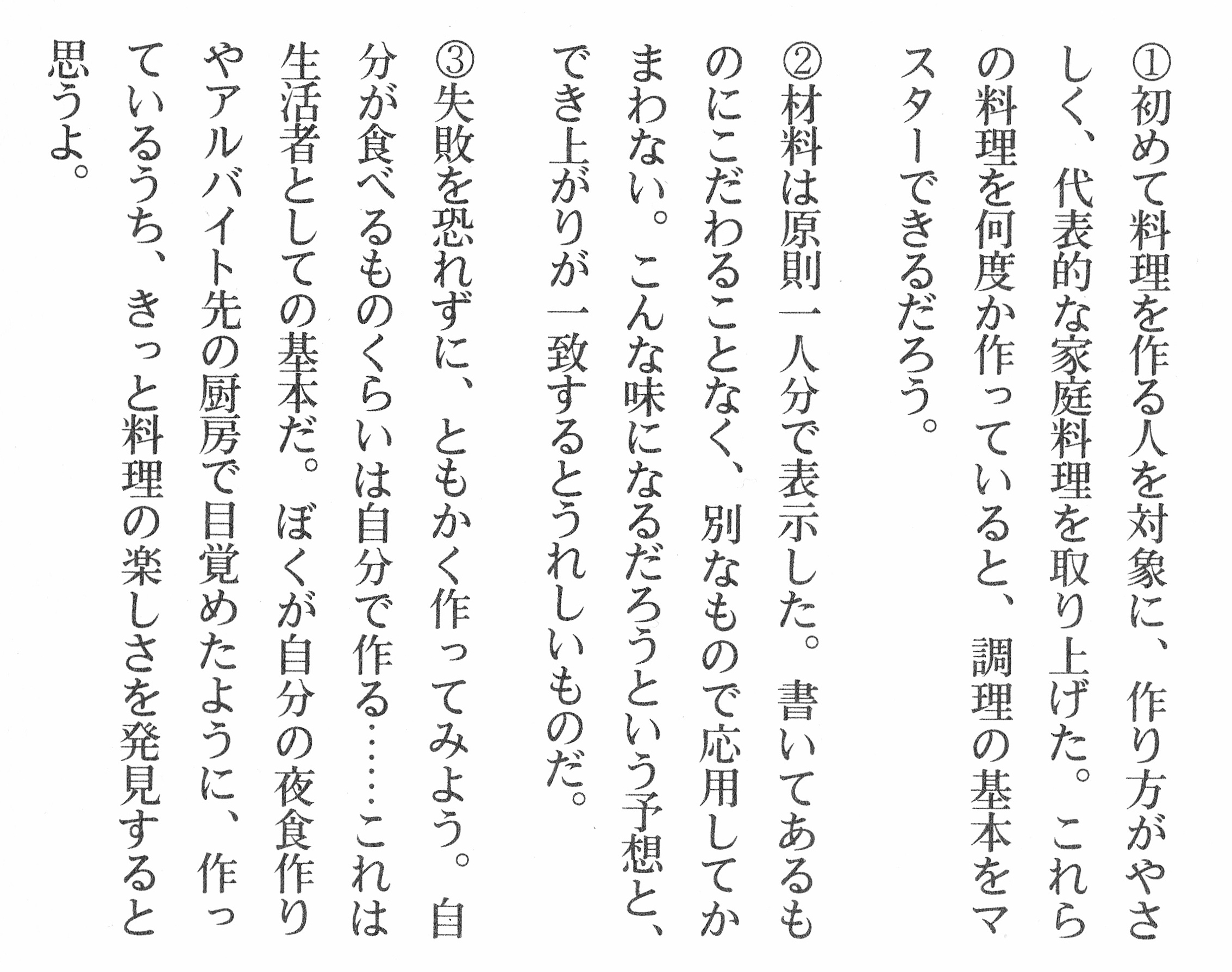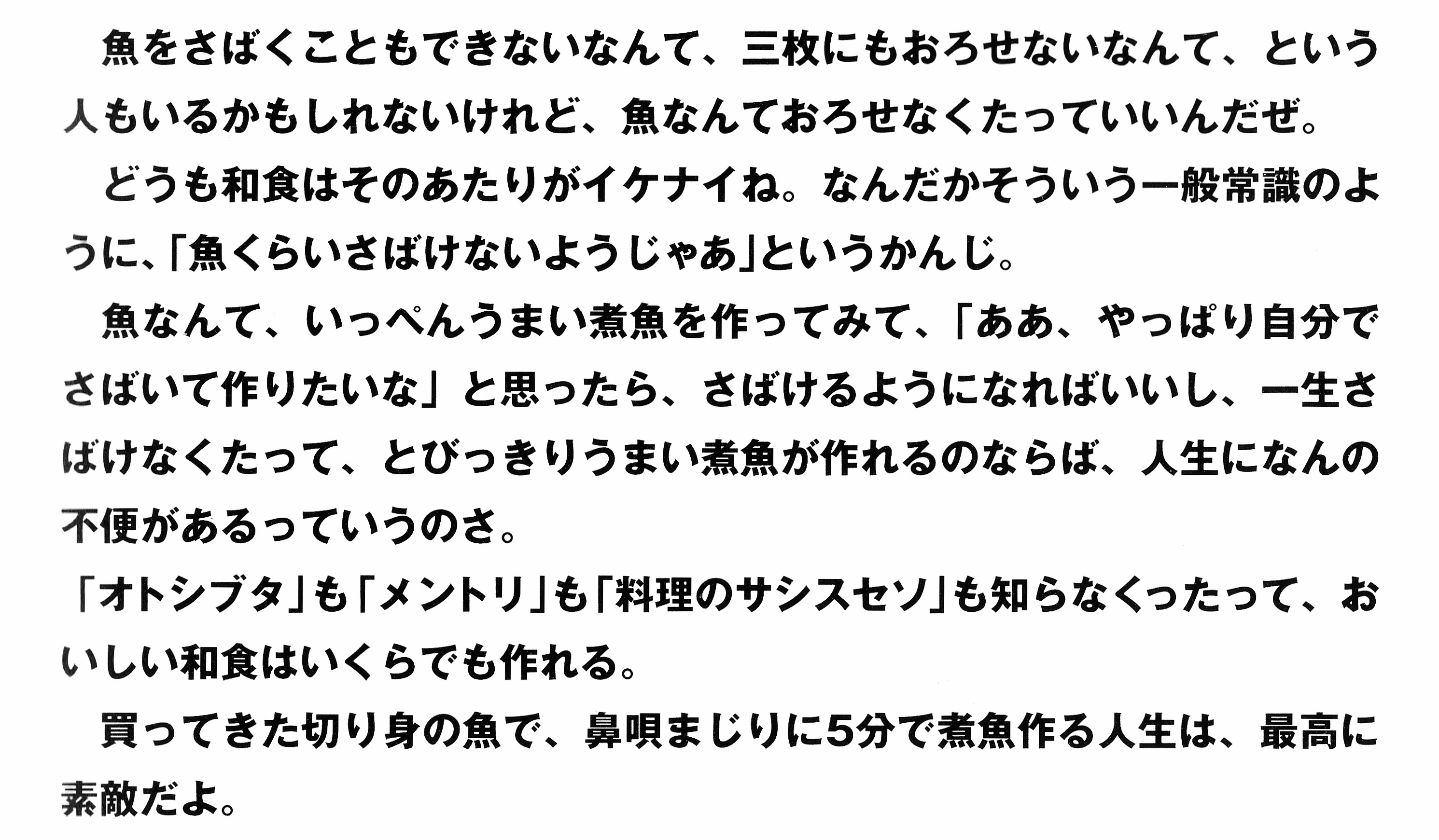『カラー新版 家庭の料理百科/婦人倶楽部料理百科シリーズ』(講談社、1975年)
子どものころ、電話台の横にあるマガジンラックから、母が持っていた料理本を勝手に抜きだして読むのが密かな楽しみだった。
かなり年季の入った『家庭の料理百科』の、料亭のように美しく盛りつけられた上品な献立や、外国料理の写真を眺めるのも飽きなかったけれど、いちばんくり返し読んだのは、小林カツ代の『楽々ケーキづくり』(主婦と生活社21世紀ブックス)だと思う。
初版の刊行は1982年。
面倒な型紙は要らない。無塩バターを使わなくても大丈夫。
ユニークなアイデアで、手軽に作れるケーキを紹介したレシピ集であるが、「お嫁さん」や「お母さん」に憧れる年頃の女の子にとって、それはもう魅力的な一冊だった。
「私のケーキ作りは仕事のためではなくて、まったく私個人の趣味から始めたのです。つまり――私のチビたちのために作ってやりたい!と思ったのがキッカケ。年子の子育てに目が回りそうな忙しさのなかで、猛然とケーキ作りを始めたのです。」(小林カツ代『最新 楽々ケーキづくり』主婦と生活社、1991年)
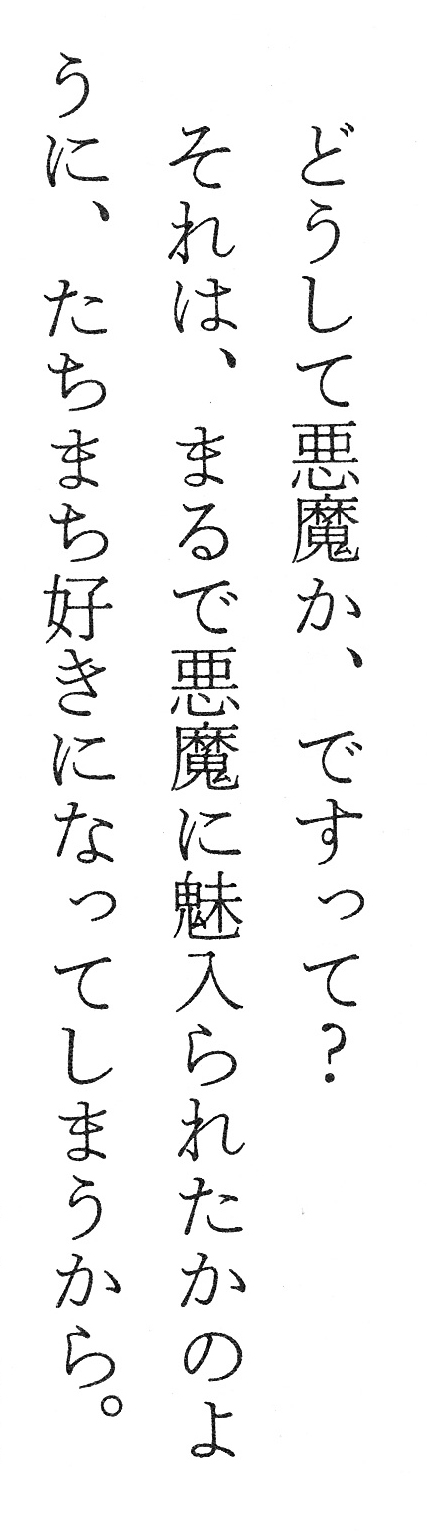
小林カツ代『最新 楽々ケーキづくり──常識を変えた新テクニック』(主婦と生活社、1991年)
あれが間違いなく深い「読書体験」のひとつだったと思うのは、童話の世界を思わせるイラストの手書き文字や、活字の記憶とともに、「女王陛下のキャロットケーキ」「悪魔のケーキ」といったユニークな名前一つひとつを、今でもずっと覚えているからだ。
ちなみに「悪魔のケーキ」とはアメリカ生まれのお菓子で、濃厚なチョコレートケーキのこと。大人になってから、偶然入った喫茶店で同じメニューを見つけたとき、懐かしくて思わず注文してしまったこともある。
小林カツ代の時短料理が世の主婦たちから支持をえた80年代。
家庭料理の変化とともに、洋書の影響を受けて料理本のスタイルも多様化していった。
80年代後半から多くの料理本を手がけてきたグラフィックデザイナーの若山嘉代子は、伊藤まさことの対談のなかで次のように語っている。
「その頃の日本の書店では、料理書というと冠婚葬祭のコーナーの一角、奥の棚にしか置いてなかった。でもニューヨークでは、インテリアの本などと一緒にライフスタイルの一環として目立つところに料理書が並んでいる。料理書をプレゼントする人も多い。後から聞くと、アメリカもずっとそうだったわけではなくて、八〇年代くらいから変わってきたみたいです。」(伊藤まさこ『おいしいってなんだろ?』幻冬舎、2017年)
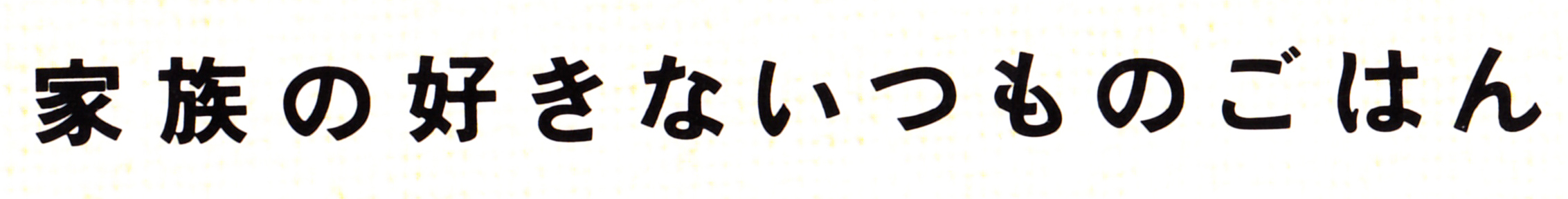
栗原はるみ『ごちそうさまが、ききたくて。』(文化出版局、1992年)
そんな時代の狭間に生まれた料理本には、今では見ることが少なくなった写植書体が使われている。
中でも特に古き良きクラシックな雰囲気を感じるのは〈新聞特太ゴシック体〉だ。
もともとは伝統的な金属活字の初号ゴシック体から作られた写研の写植書体で、文字に頼もしい手つきがあって、家の台所を守るしっかり者のお母さんを想像させる。いかにも料理を「こしらえる」という感じ。
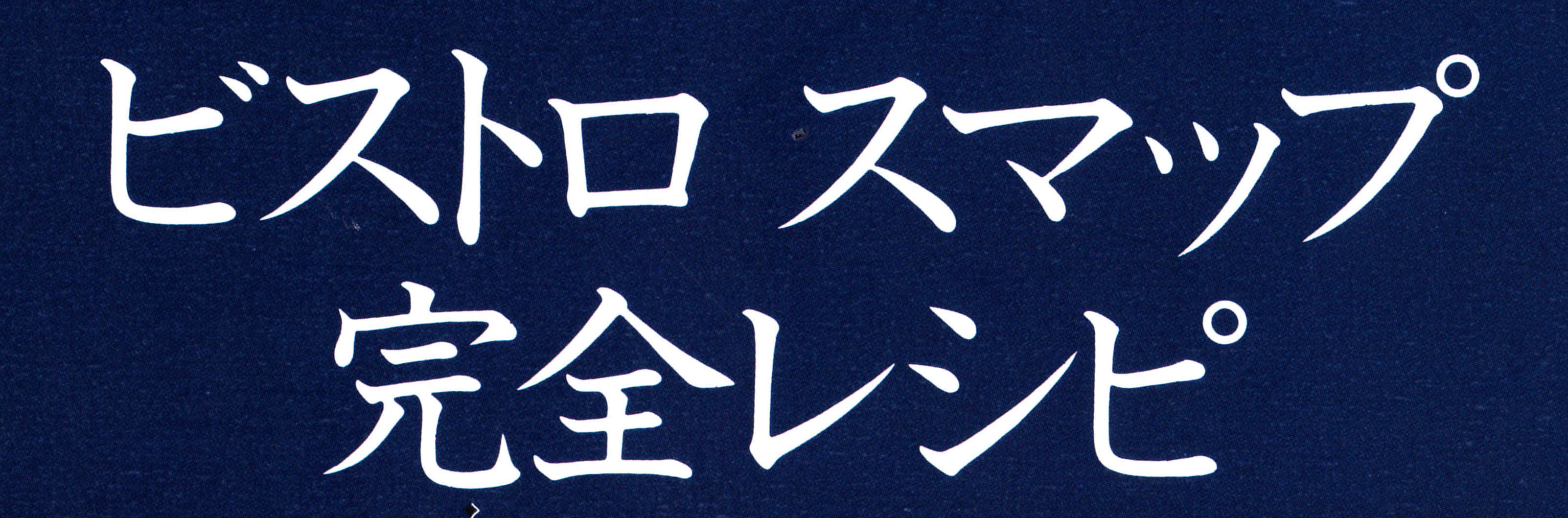
『ビストロスマップ完全レシピ』(発行・フジテレビ出版/発売・扶桑社、1996年)
「男子厨房に入らず」という固定観念を大きく変えたのは、1996年からフジテレビ系列で放送されていた長寿番組『SMAP×SMAP』の「ビストロSMAP」だという。
SMAPのメンバーがレストランのオーナーとシェフに扮し、来店したゲストのために料理を作って勝敗を競い合う人気コーナーである。
かつて「お嫁さん」に憧れていた少女たちが、「料理ができる男の人ってかっこいいよね」と口々に言い出したのも、そして「モテ要素」のなかに料理男子が加わるようになったのも、この番組の影響かもしれない。
「ビストロSMAP」で作られた数々の料理のレシピをまとめた本は、1997年の年間ベストセラー総合第一位を獲得した(トーハン調べ)。
このとき、やがて世を席巻するレシピのコミュニティウェブサイト「クックパッド」はまだ誕生していない。
本格的なインターネット時代の前夜に生まれた『ビストロスマップ完全レシピ』にもやはり写植書体が使われているのだが、改めて見ると、SMAPのファン層をターゲットにした料理本にしては、かなり意外な文字づかいである。
なぜタイトルの文字が教科書体なのか?
これではまるで冠婚葬祭のマナーやエチケットの本みたいなイメージではないか。
この書体が選ばれた理由について考えるとき、あるひとつのことに思いあたる。
男性アイドルの料理本に合う書体なんて、世のなかの誰ひとりとして正解を知らなかったということ。
当時、男性アイドルが、しかも家庭的なイメージや生活感が似合わないジャニーズのタレントが毎週料理をする番組は、常識では考えられないことだったのではないか。
彼らはテレビカメラの前でレストランのシェフという設定を演じていたのであり、料理をしているあいだ、ゲストとのトークはオーナー役の中居君に任せて、基本的に寡黙である。その距離感が書体にもあらわれているように思う。
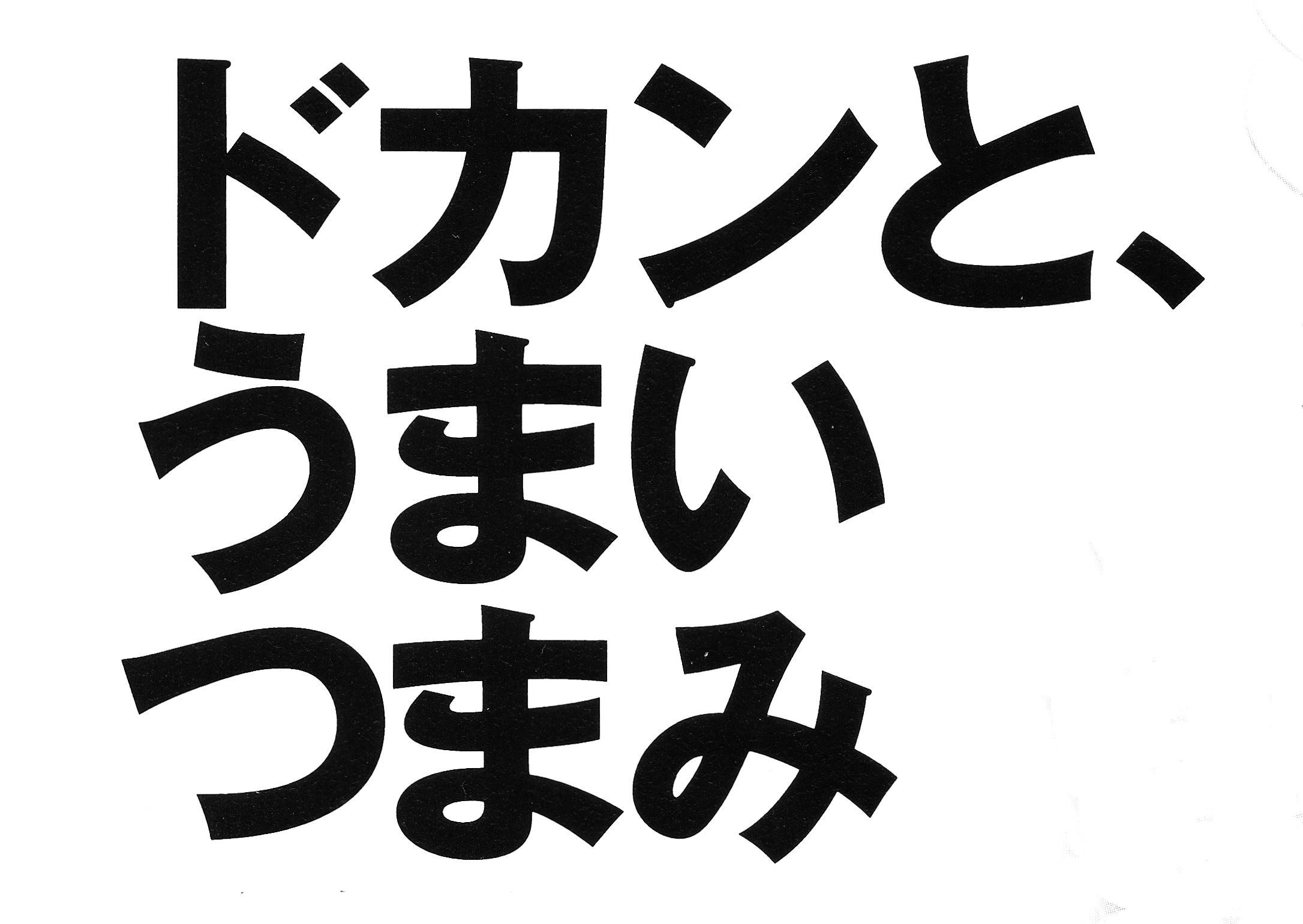
ケンタロウ『ドカンと、うまいつまみ』(文化出版局、1999年)
男子と家庭料理を自然体で結びつけたパイオニアといえば、料理研究家ケンタロウである。
センスのいい著書を数多く出版しているケンタロウだが、文化出版局から出ているシリーズが私は好きだ。デザインは『SWITCH』のアートディレクションもつとめていた白石良一によるもの。
ドカンとしているのは料理だけではない。文字もドカンとしていて、白い皿に映える料理のような潔い存在感にほれぼれしてしまう。
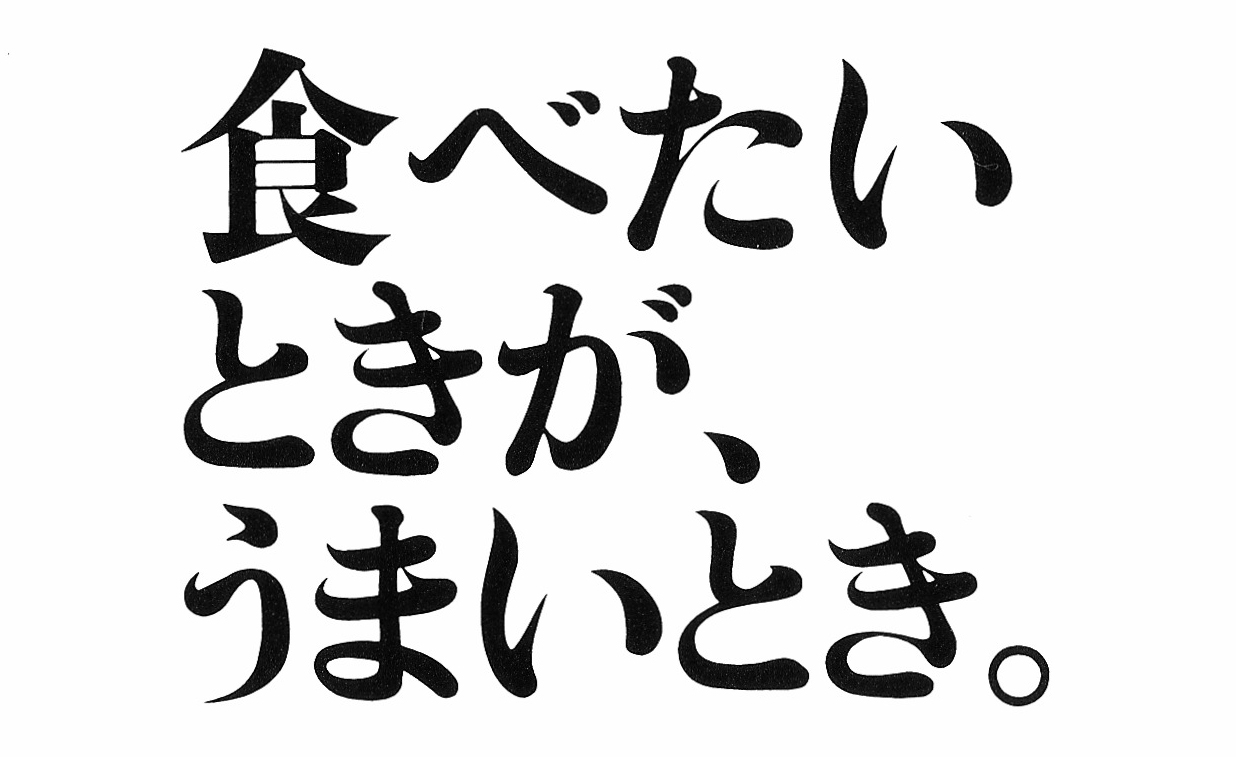
ケンタロウ『とびっきりの、どんぶり』(文化出版局、2002年)
ケンタロウといえば、豪快で、おしゃれで、カジュアルなイメージがすっかり定着しているけれど、最初からその個性的なスタイルが完成していたわけではないようだ。
もともとイラストレーター志望で、料理研究家を目指していたわけではなかった。料理本も読んだことがなく、母・小林カツ代の担当編集者にイラストを売り込んだのが料理の道に進むきっかけだったとインタビューで語っている。
初めての著書と、その後の本を文字づかいで比較すると、ビジュアルが大きく変化したことがわかる。
最初は、いかにも料理の先生っぽいというか、しゃちほこばって見える文字で、本人の身体に合った服をうまく合わせられていないという感じ。心なしか文章もきゅうくつそうだ。
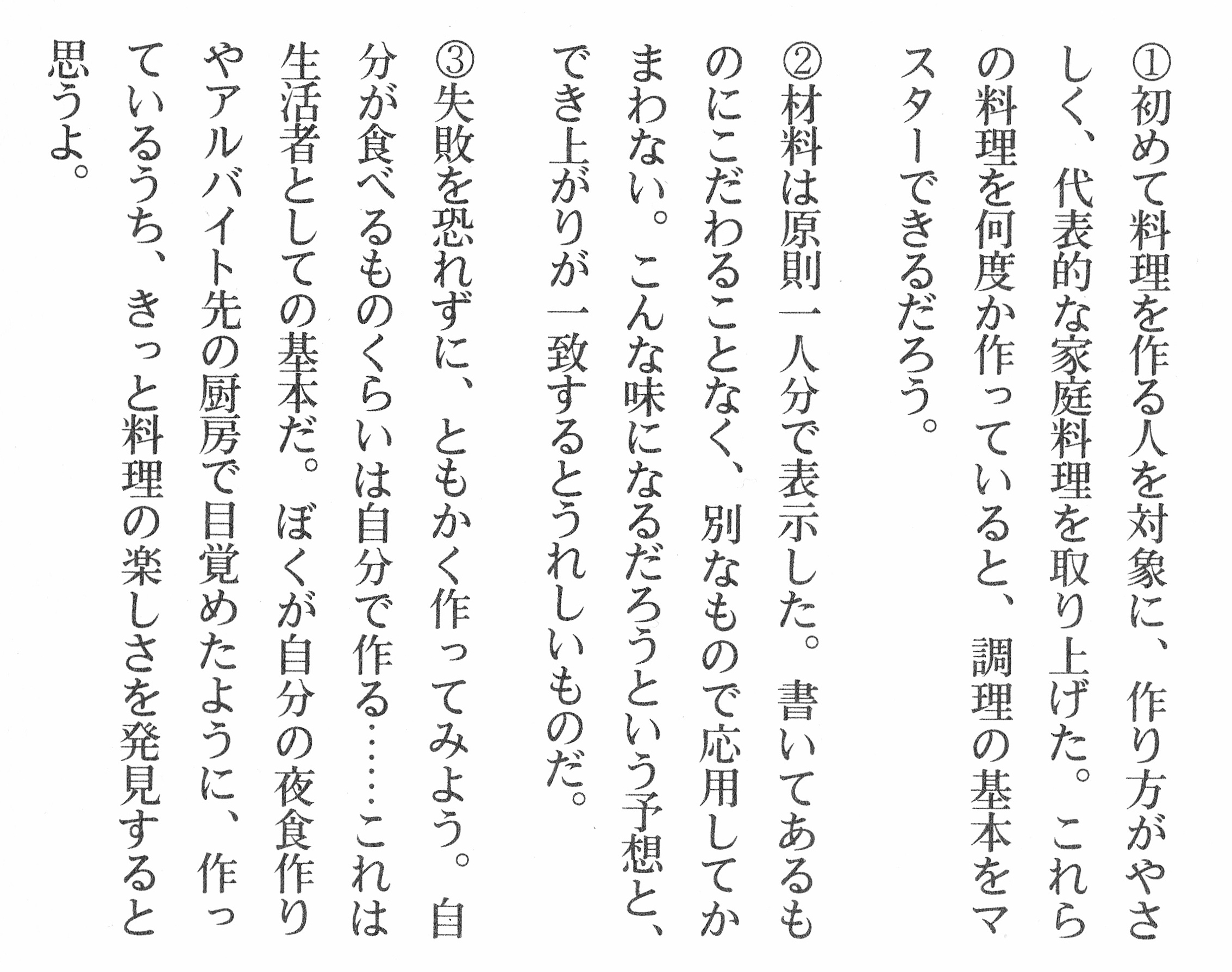
ケンタロウ『ケンタロウのはじめてつくる おとこの料理』(朝日新聞社、1996年)
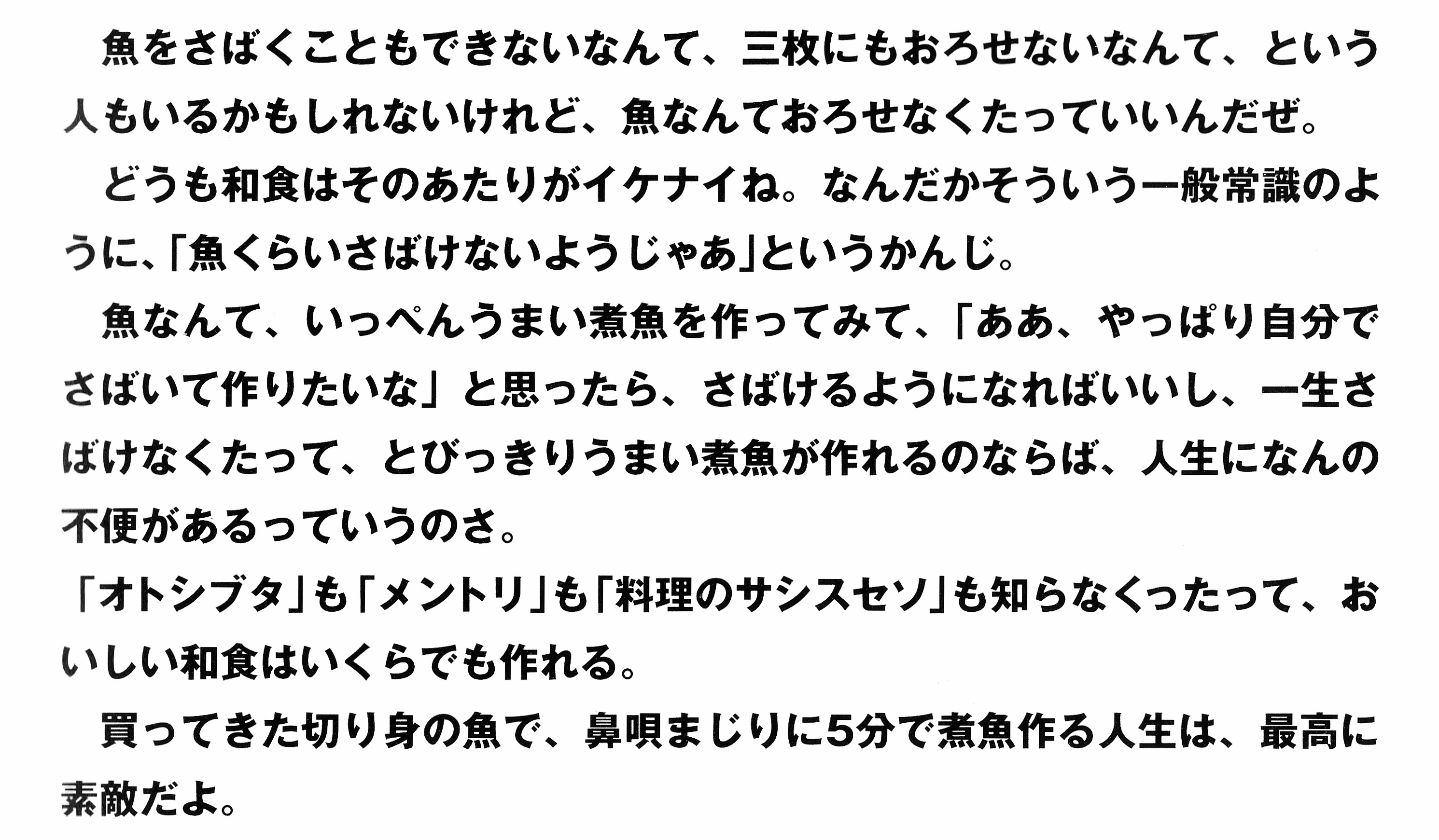
ケンタロウ『ケンタロウの和食 ムズカシイことぬき!』(講談社、2000年)
たった数年の違いだけれど、書体の変化とともに、語り口も軽やかになったみたい。
いや、作者の個性を見出したから、書体が変わったのだろうか?
好きな音楽や車、インテリアを語るように、料理を語る。
料理って楽しいものだという強い信念が伝わってくる。
そのイメージは、男性二人がゆるいトークを楽しみながら料理を作るテレビ東京の人気料理番組「男子ごはん」にも共通している。番組から生まれたレシピ集「男子ごはんの本」も人気で、料理のメニューにはケンタロウ本人の手書き文字がつかわれていた。
残念ながら今では彼の文字を見ることができなくなってしまったけれど、出演者のクレジットからケンタロウの名前が消えても、番組の放送開始当初から「男子ごはん」のタイトルの文字は一度も変わったことがない。
それはすごく素敵なことだ。

ケンタロウ/国分 太一『太一×ケンタロウ 男子ごはんの本』(角川グループパブリッシング、2009年)