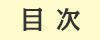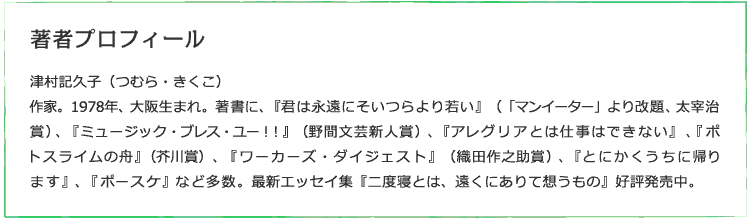夏から秋になるのは、とてもありがたいことである。暑くなくなる。それだけでもうれしいのに、日照時間が短くなるなんてなんと喜ばしいことか。明け方に、カーテンとカーテンの境い目から漏れる光が弱まり、その様子を凝視して、よし秋だ、と思う。夏場のその光は、まるでレーザーメスのようなのだ。夏の明け方に、わたしはまるで、隠れ家の扉を焼き切られるような気分になる。朝だけど、ぜんぜん仕事が進んでいない。夏の朝は、光も暑さも詰問してくるみたいだ。
それぞれの季節に良いところがあるけれども、気候は秋がいちばんありがたい。そのままじわじわと冬になるだけだからだ。春も悪くないけれども、忍び寄る夏の気配が恐ろしい。いやむしろ、夏はがぶり寄ると言ってもいい。夏は足音がでかいし声もでかい。夏だぞ! 暑いぞ! 照射するぞ! むしむしもするぞ! わしに備えろよ気を遣えよ! 捕まえるぞ! どこに隠れても逃がさないぞ! ぐはははは! 夏は嫌いを通り越して怖い。夏が人なら一生会いたくない。街ですれ違いそうになったら顔を伏せる。テレビに映ってもチャンネルを変える。
夏の悪口が長くなった。それと比べると、秋は憂鬱でうすら寒くて穏やかだ。書いていて、まるで自分の気性のようだと思う。個人的に、冬より秋のほうがぼんやり気分が沈むことが多いのは、冬は寒いので防寒に明け暮れ、落ち込んでいる暇がないからだろう。
春休みも夏休みも冬休みもあるのに、どうして秋休みはないのか、二学期は長すぎる、我々には休みが必要だ、と憤懣やるかたなかった小学生の頃は遠のき、今は秋がありがたい。なんといっても夜が長くなる。仕事がしやすくなる。秋は夜が長いから夜なべでもしましょうと言うまでもなく、わたしは年がら年中夜なべをしているわけだが、夜なべにも適した季節とそうでない季節がある。秋と冬は夜なべ向きだ。
わたしがどのぐらい夜なべに深入りしているのか。具体的に言うと、風呂から出てきて時計が午前3時を示しているのを見かけると、あと一時間したら仕事しよう......、などと思うレベルである。会社員だった時は、だいたい3時前から仕事をしていた。わたしは常に頭の中が曇っているので、夜中だから特別頭が働く、ということもないのだが、とりあえず、宵の口にけっこう寝た、という保証が自分の体に対して必要なので、だいたい21時か22時ぐらいから眠って、2時台に起き出し、そこからいろんな準備をしたのち、小説を書いている。
夜中の3時なんて想像もつかない、と言う人もたくさんいるかもしれない。わたしも昔はそうだった。3時はオールナイトニッポンの終わる時間で、そこから先は何の娯楽もない深遠だった。そこに取り残されたら、朝が来るまで孤独に過ごさなければならない。ラジオの生放送は、自分以外の起きている人を確認する唯一の手段だった。本を読んだり、音楽や録音した別の回を聴いたりするよりは、心強さが格段に違った。それに、次の日が休みならまだいいけれども、平日だと最悪である。学校に行かなければならない上に、眠れなかったとなると、日中にどんな悲惨なことになるのかは目に見えている。
そんな心細かった時期と比べると、今は図太くなったなあと思う。午前3時に起きている人なんていくらでもいることを知ったし、いちいちそのことを考えなくても、平気で録画したドラマを観たり、手芸の本を眺めたり、仕事をしたりしている。さすがに、外を出歩いたりはしないけれども、この世界に遅い時間などないのではないかという気がしてくる。
午前4時にもなると、何をするともなくぼんやり過ごしていたわたしは、だいたい観念して、お茶を淹れるために、電気ポットに水を汲みにいく。台所のある部屋からは、向かいの家の裏の様子が見える。玄関がこちら側の通りにないので、向かいの家に誰が住んでいるのかは知らないのだけれども、不思議なことに、そんなに深い時間でも電気がついていることがある。自分も大概な宵っ張りなのに、どうしたんだろう、と毎回思う。わたしも、どうしたんだろう、と思われているのかもしれない。