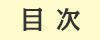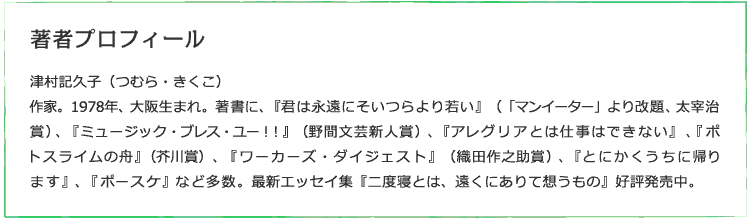大阪の住宅地に住んでいて、そんなに渡り鳥と接することはないのだが、わたしはわりとよく渡り鳥について考えている。『ワタリドリ(WATARIDORI)』という映画が好きだからである。10年以上前の映画なのだが、いまだ、前売り特典のフランス製であるというワタリドリカードを入手できなかったことをときどき思い出して、なんで前売り買わなかったんだと後悔している。人生の十大後悔みたいなものを数えるとしたら、ランクイン確実の失態である。遊べるらしい、ワタリドリカード。遊びたかった。
『ワタリドリ』は、渡り鳥が飛んでいるだけの映画である。鳥、いいよな、というだけの映画である。鳥を真横や上から撮影する時に驚かせないために、ジブリの映画に出てきそうな超軽量飛行機を開発し、一部の鳥は雛から育てて、本当に撮影クルーを親だと思わせる「すりこみ」をしたという。DVDの特典映像のドキュメンタリーでも、鳥の集団がめちゃくちゃ人に懐いてついていっていた。当時は、すごいなあ......、とただ驚いていたが、今考えると相当酔狂に思えて、ちょっとだけひく。しかしやはりすごい映画である。
鳥、いいよな、という気持ちを表現するためだけに、恐ろしいほどの手間をかけた作り手の側も大概だけれども、渡り鳥の側も大変である。北極から南極に渡るため往復でほぼ地球一周分を飛ぶというキョクアジサシや、雛に食事をやるために15日で3万キロも旅をし、飛べるようになった若い鳥は風に乗って5年も陸に降りないというワタリアホウドリなど、もうわけがわからないことになっている。キョクアジサシについては、最近まで野鳥の図鑑を作っていたというこの欄の担当編集者さんが、「頭が下がります」とのことであった。確かに、鳥にとっては単なる習性でしかないことなのかもしれないけれども、思わず尊敬してしまうスケールである。鳥が飛んでいるだけという概要に対して、作り手の情熱も対象も破格である。DVDを観直した後にいろいろ調べて、ワタリアホウドリのことばかり考えているのだが、だいたい30年ぐらい生きるらしく、50年生きた個体もいるし、理論上は80年ぐらい生きられるらしい。なんというか、人間でいるのがばかばかしくなったりしながら映像を観ていると、くちばしをやたらカタカタ鳴らしまくるコウノトリや、一列に長く長く並んで、お互いに盛んに鳴き合いながら歩いていくイワトビペンギンなんかは、人間がまだ感知していない、ものすごく斬新で奥深い娯楽を持っていたりするんじゃないかと勘繰りたくなる。
先月行った盛岡では、中心部の東側を流れる中津川沿いで、たくさんカモを見た。ハクチョウも来るらしい。うちの家の前の川に渡り鳥が来ました! という素敵な出来事が起こるわけである。しかもサケが遡上するらしい。市街地なのに生態系が豪華すぎだ。大阪でも渡り鳥は見られないのか、と少し調べると、環境省が、大阪城公園における渡り鳥の飛来状況をまとめてくれていた。カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロなどが来るそうだ。カモならわかるけれども、ハジロと言われるとわからない素人なので、キンクロハジロの画像を検索してみると、黒い半身に黄色い目で、頭の後ろ側へと垂れ下がった冠羽があったりして、なかなか主張が強い感じである。
本当は、今回は、自分が会社員だった時に、昼寝の場所をうろうろと変えていたことについて書こうと思っていた。最初に仕事をしていた「製本室」という場所から、製本室が廃止された後に試験室に移り、そしてまた倉庫となった元製本室であった場所に戻ったものの、倉庫となっていたため、毎日のように入れ替わるいろいろな機器や試料の隙間を探して、頭から膝掛けをかぶって眠りこけていた。あれは一種の渡り行為のようであった、という話なのだが、『ワタリドリ』を観直すと、作り手も鳥も常軌を逸していることに、自分のことはもはやどうでもよくなってしまった。会社を辞めた今は、仕事が終わるぐらいの早朝に聞こえてくる、姿の見えない鳥(たぶんセキレイ)の声が労いのように聞こえる。