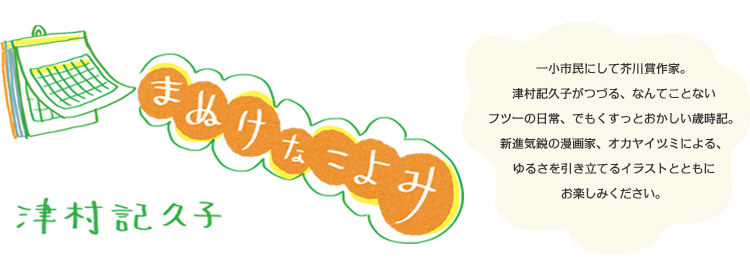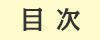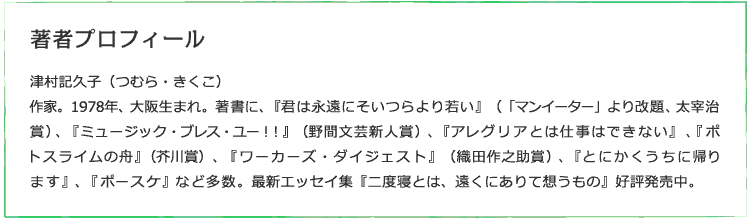ストーブ派だと思う。部屋のエアコンが、長らく冷房だけのものだったからかもしれないけれども、エアコンを暖房に使えるようになった今でも、だいたいストーブで寒さをなんとかしようとする。なので、冬場に出張などでホテルに泊まると、ストーブもないし寒くない、と不思議な気持ちになる。特に、部屋に入った時の違和感は強烈である。あの、あらかじめ部屋が暖まっている心地好さが、逆に居心地が悪いというか、冬場に「暖をとる」という行程を省いて部屋で過ごすことになるのはとても非日常である。なので、自宅に帰って部屋が程よく寒いと、妙に安心してしまう。荷物を降ろし、上着をかけ、ストーブを点け、その前に座り込む。その場を少しでも離れたら効果がなくなるストーブではなく、部屋全体を暖めるエアコンを使うようにしたら、もうちょっと活動的になるのかもしれないけれども、どうしてもストーブ離れができない。
皆さんはわたしよりもぜんぜんエアコンを使っておられるはず、と思うと、もはや「暖をとる」ことは一般的ではないのかしら、という疑問が芽生えてくる。わたしにとって、暖をとることは一大事だ。起床すると、まずストーブを点けて、しばらくじっとする。そして、カーディガンの上に更に上着を着て、レッグウォーマーを履き、靴下も重ねて履く。その後再び、しばらくストーブの前に座り込む。体を暖めるという以外何をするというわけでもなく、ひたすら、お茶を淹れるために立ち上がって電気ポットに水を汲みに行く気力が湧くのを待っている。気力というか、最近ではもはや「勇気を出す」という言葉の方がしっくりするぐらい、ハードルの高い動作になってしまった。ストーブの前で膝を抱えて、勇気を出せ、と自分を鼓舞している。その内容が、「水を汲みに行くこと」。どれだけ動けないんだ。
もしかしたら、エアコンであらかじめ部屋を暖めておけば、そんなまぬけな前哨戦は必要ないのかもしれないけれども、どうもストーブがいいようなのである。ストーブを点け、着込んだ上で暖をとることは、面倒で時間を無駄にする部分もあるのだが、着込んでいるうちに自分を組み立てているような感じもする。その感覚が、なんとなく好きなのだろうと思う。おしまいまで着込むことで妙な達成感を得てしまったりもする。これは、他の季節にはないことだ。実際には着込んでいるだけなのに、頭は「いい仕事した」と思っている。おめでたいことこの上ない。
ストーブを点けて着込むこと以外にも、寒さから暖かさへと移行する状況には、常に何か劇的な安堵が付きまとう。会社員だった頃にも、アホみたいに冷たい冬の道を自転車で走った後、地下鉄に乗り込んだ時の安心感はものすごいものがあった。吊り革を握った瞬間、このまま溶けてなくなるんじゃないか、と思うほど脱力する。会社に到着すると、すぐさま足元のストーブを点けて、のろのろと昨日の残りの仕事などを見直しながらお湯が沸くのを待ち、給湯スペースの電気ポットがピーッという音を立てたらすっ飛んでいってココアを作る。朝の一杯目のココアを口にすると、生き返るような心地がした。出勤することは決して好きではなかったけれども、とにかくその瞬間は幸せだったのである。それがたとえ月曜日の朝であっても。
点けたらその近くだけ温かくなる。ストーブの温かさはとても単純である。ストーブの近くに座りながら、私は何か、焚き火の近くにいるような気分になってくる。じっとして、火の揺らめきの代わりにらせん状のカーボンを眺めながら、いろいろなことを考えたり、考えなかったりする。子供の頃も、石油ストーブの前でじっとしているのが好きだった。熱源に手をかざして背中を丸めることには、何か人間の原始的な気持ちを満たしてくれるものがあるのかもしれない。いいこともいやなこともたくさんあるけれども、とにかく今は暖をとるのだ。ストーブの前で過ごす時間は、どこか慌ただしい日々から浮き上がっているように思える。