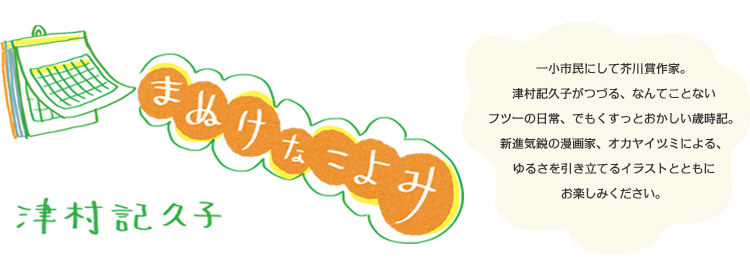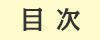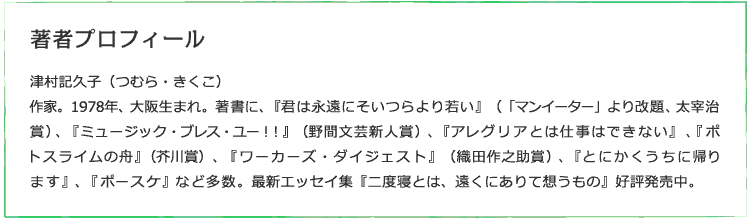前の会社に就職したての時だったので、10年以上前のことだ。入社して初めて年を越し、2月に入った頃合に、仕事を教えてくれていた一つ年下の先輩と「バレンタインデーは会社の人に何か配るのか」という話をした。わたしは、最初の会社をバレンタインデーなど迎えもせずに退職してしまったので、どうしたらいいかよくわからなかったのだが、先輩がチョコレートを配るというので、自分もそうすることにした。
1年目は、特に何も考えずに手ごろな値段のチョコレートを会社の男性全員に配布したと思うのだが、2年目に、「会社の男の人みんなが、はたしてチョコレートを欲しがっているのだろうか? むしろそこそこの食品なら何でもいいんじゃないのか? 味噌とか奈良漬けとか?」と疑問を抱いたことでどつぼにはまり、百貨店の地下食品売り場を1時間半ほどうろうろする破目になった。結局、それらは重いし匂いもきついので断念し、お菓子売り場を試食して回った結果、吹き寄せを買った。当時は、さまざまな年齢の日本人の男性に渡すお菓子として、それがもっとも中庸な位置にあると思えたからだった。いろいろな干菓子が入った吹き寄せは、個人的にもおいしかったので、わたしはへらへらと、「これはおいしいですよ」と勧めながら会社の人に渡して回ったのだが、喜ばれたかどうかはまったくわからない。何寄越してんだこいつという感じだったかもしれない。
その先輩が退職してからは、わたしはすっぱりとバレンタインデーにお菓子を贈るのをやめた。お返しを頂戴できたりすることはありがたくても、百貨店の地下で途方に暮れるのが相当しんどかったのだと思う。そんなに毎年毎年吹き寄せを贈るわけにもいくまい。
義理チョコとは言うけれども、世の中の男の人たちは、意外においしいじゃがいもやうどんや昆布の方がうれしいのではないか、という考えを拭い去ることができない。わたしが、女子が働く職場にいるおじさんで、バレンタインデーだがどんな食品が欲しいかと訊かれようもんなら、「ちりめん山椒」とか「柚子大根」などと答えて陰口を叩かれていたことだろう。
バレンタインデーにチョコレートを贈る習慣は、日本独自のものだという。いくつかのお菓子メーカーやチョコレートを取り扱う会社が、何年もかかって仕掛けて定着したそうだ。苦労はあっただろうが、結果的には大成功であったと言えるだろう。しかし、これが佃煮でもよかったんだ、と考えると、何か惜しい感じもする。バレンタインに、牛肉の佃煮を! ......だめか。バレンタインデーにチョコレートをという習慣が根付いたのは、チョコレートに対する、人々の思い入れがあってこそのものでもあるように思う。甘さが凝縮されている。食べる時にバリバリという音などしない。ぼろぼろこぼれない。チョコレートは、品の良い食べ物なのだろう。ついでに疲労回復にも効果がある。
チョコレートは、お菓子というか、「チョコレート」という独立したジャンルであるように見受けられる。最近の複雑化、高額化は抜きにしても、手にした時や口にした時、ドーナツやパンケーキやクッキーといった粉もんとは違った感慨がある。バブルから不況へと時勢が変化したせいか、この20年ぐらいで日本人は、目新しい食品よりは、保守的で懐かしい味わいのものとそのバリエーションを評価するようになったと考えているのだけれども(ドーナツ、パンケーキ、ラスクなど)、チョコレートだけはそれを逆走している。食べるのにリーフレットが必要な、複雑な味のチョコレートもある。一粒のチョコレートとリーフレットをつき合わせて、これからどんな味のチョコレートを口にしようか思案するところから始まるわけである。それは単なる「おやつを食べる」という行動ではなく、「チョコレートを食べる」という独自の体験になっている。
小学生の時に、よくよく珍しがってお食べなさい、というような注釈付きで、母親に4粒入りのゴディバのチョコをもらったことを思い出す。バレンタインデーのお裾分けとして、仕事先で頂戴したものらしい。それまでのわたしには、板チョコか、そうでないならお土産のマカダミアナッツの入ったチョコレートが「チョコレート」だった。わたしは、箱の中のそれぞれ味の違う、小さな凝った置き物のような四つのチョコレートを凝視して、いちばん興味のない、苦そうな黒っぽいものを手に取って口に入れた。思ったほど苦くはなかったけれども、一粒を一度に食べてしまったので、口の中で溶かすのに苦労した。一粒が自分の二日分のおこづかいより高いチョコレートを食べて、おやつとは感じなかったように思う。チョコレートはチョコレートである。それは、おやつ連邦の中の独立国として、どうにも凜々しく屹立している、とわたしはその時にぼんやりと感じた。