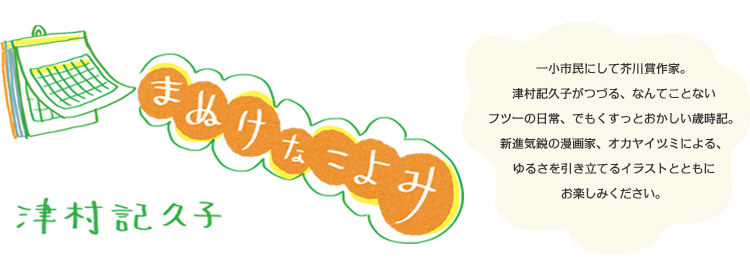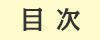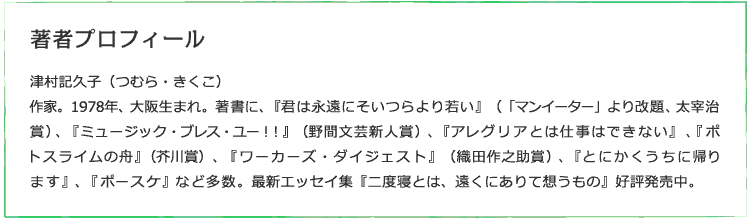うちの家には七段の雛飾りも、三段の五月人形もある。子供のイベントに力を入れる家系だったのかもしれない。稚児行列にも行ったし、七五三も大事な行事だった。雛人形と五月人形は、しばらくの間押し入れに眠っていたけれども、大きめの和室のある家に引っ越してから、またその季節になると母親が飾るようになった。といっても、さすがに全部組み立てるわけではなく、五月人形の鎧兜は床の間にちょこんと鎮座し、雛人形はたんすの上の段から少しずつ段差をつけて引き出して、すごく中途半端に飾る。三人官女まではまあまあ見られるのだが、五人囃子、右大臣・左大臣、仕丁の三人組あたりになると、記憶頼みではだんだんわからなくなるのか、それともどうでもよくなってくるのか、五人囃子の両側を右大臣・左大臣が固めていたり、仕丁と大臣たちがごちゃまぜに同じ段にのっていたりする。たんすを雛壇に利用するのが、ほんとに何をしているのかという感じなので、写真に撮っていろいろな人に見せていると、うちも雛人形を飾るのにたんすを利用しているというお宅がいくつかあって驚いた。
わたしは雛飾りがとても好きな子供だったので、雛祭りは正直言って自分の誕生日より楽しみだった。一年でいちばん楽しみだったといっても過言ではない。雛人形を出してもらえるばかりか、あられはもらえるし、ひし形のケーキも食べられる。おもちゃも買ってもらっていたような記憶がある。個人的には、盆と正月がいっぺんに来るという所感を持っていたのが雛祭りだった。
とにかく雛飾りは見ていて飽きない。まずお人形がきれいだとか、着物がきれいだということを享受し、三人官女では誰がもっとも美人かということを考え、その人間関係を想像し、五人囃子を順に凝視しては、笛の人が味でかわいそう、などと同情し、左大臣は見るからに老人なので体調を心配したり、その下の三人のおっさんは、足とか出してて場違いじゃないの、と無駄に咎めたりする。登場人物も多いが、小道具も豊富だ。三人官女の間にある白とピンクのおもちと、右大臣と左大臣の間にあるひし餅ではどっちがおいしいのかと思いを馳せ、茶道具や鏡台の作りの細かさに感心し、たんすにはいったいどれだけの着物が入っているのかと想像する。ここまで書いてみて、意外とお雛様とお内裏様には興味がないんだな、ということが自分でわかって驚いている。確かに、いてもらわないと困る人たちではあるが、下の段の人々のほうが、遥かにいろいろな話を持っていそうだと子供心に思っていた。結婚式は、新郎新婦よりも列席者の方がよくしゃべるしよく動く。
群像劇、グルメ、家具(インテリア)、そして食器など、雛飾りは、イギリスのお屋敷ものミステリーのごとく、人の興味を引くものが凝縮されている。ないのはお屋敷そのものだけだといっても過言ではないだろう。ものすごく高度で高級なお人形遊びでもあるのかもしれない。家具の配置をやたらにいじってはいけないシルバニアファミリーのようでもあるし、中身だけのドールハウスであるとも言える。こちらに正面を向いて並べられている雛人形たちは、何を考えているのか。同じ段の人形たちと言葉を交わしているのか、それとも、段をまたがって何かを伝え合っているのか。興味は尽きない。ちなみに、資料とするために参照したデジタル取扱説明書によると、三人官女では真ん中だけが既婚者だという。ちゃんと設定だってあるのだ。
小さかった頃は、雛壇が階段に見えて、雛飾りを設置中に駆け上がって死ぬほど怒られたことがある。なので、うちの雛飾りの段には、下から三段目ぐらいにわたしが駆け上がってできた凹みがある。人形たちが生きているように見えたというのではないけれども、雛飾りはそれだけで一つの世界を形作っていて、私は自分の家にそれが存在していることが不思議でならなかった。雛人形たちは、数週間だけ和室に滞在する、小さくて上品なお客さんのようだった。幼稚園に上がるか上がらないかぐらいの子供の重みさえ支えられなかった薄い雛壇は、ますます雛飾りの完結した世界を強固にし、わたしは来る日も来る日も雛飾りを眺め続けた。