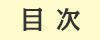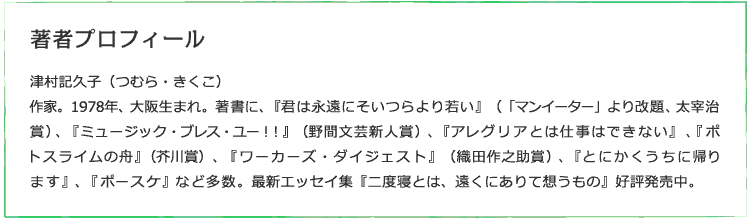幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、と順調に卒業をしてきたはずなのだが、よく感情移入されているような、素敵な卒業式に参加したことがない。小学生の時は、公立中学に進学し、人間関係がそのまま中学に持ち越されるため、卒業しても会えなくなる友達は少なかったので、あまり思い入れはなかったし、中学、高校、大学に関しては、その場所を出てゆくという感慨よりも、次の生活への不安が大きかったので、式典に関しては上の空だった。なので、「友達と別れてしまう」とか、「これから大人への階段をのぼることになるのね」などと、卒業式らしい思いに駆られたのは、幼稚園の卒業式だけだったということになる。しかも幼稚園を卒業する式典は、正しく言うと卒「園」式なので、わたしはたぶん、様式美的な卒業式を迎えたことは一度もないのだ。
学校生活は常にそこそこ楽しかったのだが、今もあまり未練というものがない。学校は、毎日毎日通う場所なので、3年も同じことをしていれば、もう飽きてしまうのだろう。かといって、次の新しい生活に期待をしていたかというとそうでもなくて、めんどうだなあと気が滅入っていた。たぶん、卒業式で泣いたり、特別に感じ入ったりする人は、新生活への強烈な期待も持っているのだと思う。わたしにとっては、新しい生活を軌道に乗せるのはとても難しいことで、心の機微に触れる暇もなくひたすら不安なのだが、卒業式は一応、生活と生活を区切る大事な日でもあり、その心はおおむね「やけくそ」だった。
中学の卒業式は、おそらく人生でも五指に入る不安からのやけくそ状態だった。なにしろ、入試がまだ残っていたのである。第一志望の公立高校に受かっていないのに、中学を卒業も何もあるか、なんでこんな時に放り出すんだよ中学! という理不尽さへの怒りが大きく、卒業式自体のことは何も覚えていない。もうまったく一切なのである。記憶にございませんなのだ。なのに、その日は卒業式だからもういい無礼講だ、という理由で塾を休み、友人の家の近所の公園でドッヂボールをしていた。式典のことはぜんぜん覚えていないくせに、この時の様子や気持ちははっきりと思い出せる。あんなにちくしょうと思いながらボールを投げていたのは、あの瞬間以外ない。もういい、何もかもいい、自分は数日のうちに死ぬ、受験に落ちて死ぬ、だから今は思い切り遊ぶぞうおおお。その「遊ぶ」の象徴が公園で球技。しかし、その後先のないプリミティブさが、わたしとしては本質的な意味での「遊ぶ」であった。
わたしと友人たちは、サルのように遊びまくった。中学を卒業させられ、受験の本番もまだ(すべり止めには受かっていたが、本当の集大成ではない)という状況で、我々には明日などないとばかりにボールを投げ、ぶつけまくり、よけまくった。わりと簡単に、明日はないなと思うのだけれども、あの時ほどやけになったことはない。なので本当に、歌などに歌われる情緒的な卒業など糞食らえだと思っていた。受験のことばっかり考えていたが、もうこの日ばかりはと塾を休んでギャアギャア言いながらドッヂボールをする。このやけくそ感がリアルな卒業なのであるし、今も結構そう思っている。卒業を美しいものとして描ける人は、公立高校の受験とかしなかったんだろうか、とわりと素朴に疑問に思う。
ひどい卒業式の記憶というと中学がいちばんなのだが、高校もかなりやる気がなかったと思う。仲の良い友人と、いつものように「王将」に行った。その道中でわたしは、電気グルーヴのオールナイトニッポンの「あの島この島行きたいな」というコーナーがいかに好きだったかということを語っていた。さすがに大学には受かっていたので余裕はあったけれども、家からはとても遠いところにあったので、自転車通学→2時間かけて電車通学という変化には気が遠くなるものを感じていた。とにかく、絶対に特別な話はせずに、日常をやろうとしていた。これからも、意地でも気楽な日々を続けるのだと。
学校生活に未練はない、と書いた。けれども、中学の卒業式の日には、ちょっと戻ってみたいと思っている。その時ドッヂボールをした友人たちと、今は行き来はないのだけれど、友達とやることというのはまさにあんな感じなのだろう。不安を押し殺して、もう後がないのに塾をさぼって、何かその年なりのつらい覚悟をして、げらげら笑っていたのである。苦しくて、楽しい日だった。その日いっしょだった友人たちに、とても感謝している。