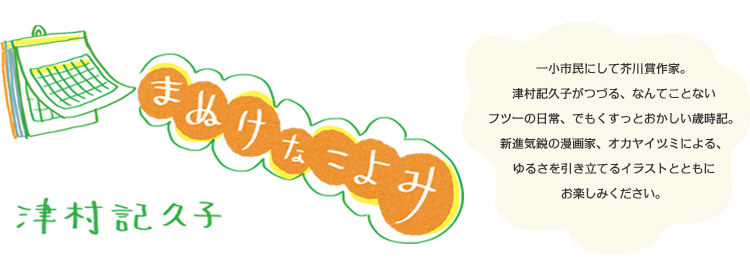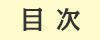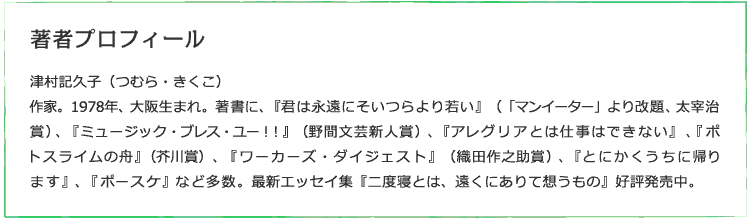五月病のただ中にいらっしゃる方もいることと思う。会社にも学校にも行っていない今、ゴールデンウィークが明けたら締め切りがあるし(ものすごくありがたいことなのだが)、また登校か、出勤か、という人々のつらさが本当によくわかるので、会社に行っていた頃と変わらず普通に憂鬱である。特に、今年は短かったなあと思う。何か抗議の文書のようなものがあれば、喜んで同意の署名をする。
五月病? 何それ? というぐらい、日常生活を愛せたらいいのだけれども、出勤はまだしも、登校が楽しかったという日々すらも遠く思える。五月病のなかった日々は存在するのか? たぶん、小学1年の一学期まではそうだったと思う。団地の集団登校仲間のしがらみがあったり、妙に細かくて暴力的な男子がけっこういた二つ目の小学校と比べて、小学1年の最初の4ヶ月だけを過ごした小学校には、いい思い出しかないのだった。
私服だったし、一学年が5クラスぐらいある大きい学校だった。諸手を挙げて、いい小学校だった、というよりは、悪い面を見つける時期になる前に離れてしまったと言うべきかもしれない。この連載の第一回に登場した、帰り道に路上の花を食べる友人と通っていたのもこの小学校である。彼女がそのへんの植え込みのつつじの花の蜜を吸っていたのも、5月のこの時期だった。彼女は驚くほどうまく蜜を吸っていたのだが、わたしは花の摘み方もわからなかったし、どれだけ教えてもらっても蜜が吸えるように摘めず苛立たせたりもしたので、しまいに彼女があらかじめ摘んでくれたもののおこぼれに与ったりしていた。1月生まれのわたしより、だいぶ早く生まれた人だったので、基本的にはおねえさんのような立場の人だった。今も反射的に、つつじがたくさん咲いているのを見かけると、彼女的には入れ食いだな、と思う。もちろん、わたしの同級生なので、だいぶいい年の女性になっているはずであり、どちらかというと、子供さんに花を食べないでと注意する立場のほうが妥当なわけであるけれども。
友人が花を食べたくなるぐらい、通学路に花が咲いている場所が多かったというのもあるのだが、他にも、学校の近くに丘のようなところがあって、野の花や野草が多数自生していた。タンポポやレンゲソウやシロツメクサといったメジャーどころはもちろん、ナズナ、カラスノエンドウ、オオイヌノフグリ、ハルジオン、ヒメジョオン、スズメノテッポウ......、と花や野草の名前がえんえんと出てくることに自分でも驚く。スズメノテッポウなんて、物心ついてから発音したことがないぞ。大阪の人に、円広志による「探偵! ナイトスクープ」の主題歌「ハートスランプふたりぼっち」を歌ってもらうと、生まれて初めて歌ったという人でも、自分でも不安になるようなところまで歌えてしまうという現象にも似ているような。いや似てないか。春の野草については、小学1年の一学期の、最初の理科の時間に学んだと記憶がある。人生でもっとも野の花が身近にあったのが、あの時期ではないのか。
5月のいい時期になると、ときどき、もう一回あの小学校に行きたいなあと思うことがある。ぼんやりと思うだけではなくて、おそらく、現時点でやりたいことの20位以内に入っているから、なんだかシビアな話である。友達と別れることになった、という悲しさもあるし、給食がおもしろかった。ゼラチンの入ったミックスと牛乳を混ぜて、ババロアみたいなものを作って食べたことを強烈に覚えているのだが、その後通った小学校で、そういったものが出てきた記憶はない。6人きょうだいの5人目の女の子と仲良くなったりもした。だから長年、4人姉妹の4番目の女の子と友人でも、そのきょうだいの中での立ち位置について、少しも珍しいと思ったことがなかったのかもしれない。
帰り道に花を食べる友人の正体も、ぜひ知りたかった。わたしの記憶の中の彼女は、永遠に小学1年で、前世はチョウかミツバチだったんじゃないかというほどの手練れだった。不意に断たれた物心がつく前の友情は、いつまでも美しく、そしてけっこう不思議だ。