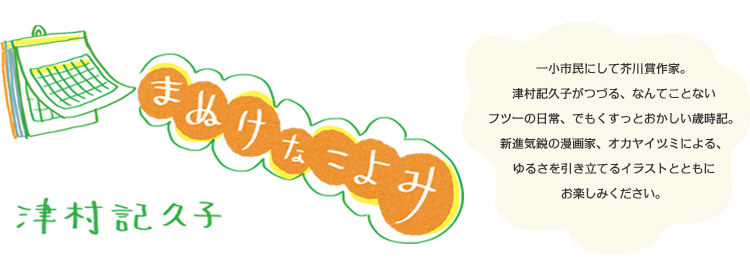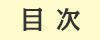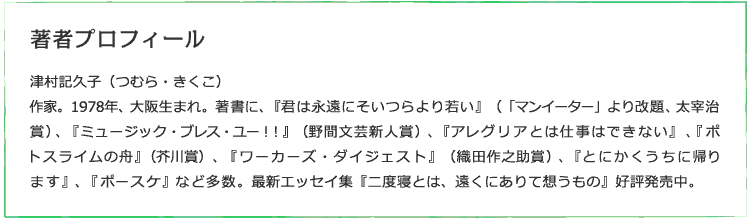この連載は、七十二候について書くというものなので、いつかこんな日が来るだろうと思っていたのだが、ちょっとびっくりするぐらい書くことに困った今回だった。いや、担当編集者さんは、いろいろとテーマを出してくださってとてもありがたい。紫陽花、新茶、電波の日、田植えなどをこのたび提案してくださったのに、わたしは、それぞれの主題に対して、「新茶......。紅茶ばっかり飲んでるんで考えたこともなかった」とか、「あじさいの花壇といえば、小学生のころに読んだ推理クイズの本で、夫が妻を殺した凶器のピストルを埋めたところだ......。土の中の鉄分で花の色が変わるのでそれでわかったのだ(ある作家の短編のオチだそうだ)」などと季節感もへったくれもないことばかり考えていた。
そうなのだ、季節感がないのだ。5月が6月に変わろうとするこの時期は。新年度の環境に対して、まだ馴染めないと言っていてギリギリセーフの5月から、梅雨入りには少し早いかもしれないという6月の初旬には、個人的にほとんど印象というものがない。4月から5月ならゴールデンウィークがあるし、6月から7月には暑さへの恐怖が押し寄せ、7月から8月なら絶望的に暑く、8月から9月には涼しさへの儚い期待があり、9月から10月にはいきなり涼しなったなもう冬やないかというめちゃくちゃな文句が出て、10月から11月は陽の落ちる早さに憂鬱を覚え、11月から12月なら有無を言わさず師走へ突入、12月から1月は普通に新年、1月から2月は寒さで無口になり、2月から3月はかすかな暖かさの兆しにやや頬を緩め、3月から4月には新年度の不安があり、と長々書いたが、それぞれの月の境目にはそれなりにいろいろある。しかし5月から6月。何もない。あえて言うなら、そろそろ梅雨か......ぐらいだ。まだ梅雨ではない。気候自体は過ごしやすいので、何も所感がなく暮らせていい季節といえばそうなのだが、そのぶんなのか、6月には祝日がない。新しい年度を迎えて、初めて土日以外の休みがなく、がっつりと動かなければならない月なのである。この年度の体制はいやなんだけど、と言っていてもどうにもならないので、諦めて順応することを視野に入れ始める月でもあると言える。空気は良くても、なんだかつらい季節だ。
学生さんで言うと、クラス内での立場が定まってくるのがこの時期だと思う。グループの移籍期限は、誰も口にはしないが、おそらく6月1日である。新年度のどたばたと、ゴールデンウィークによる人間関係の中断の後、現実を厳しく見つめて、自分の立ち位置と照らし合わせた結果、それまでのグループでOKならばそのまま、まずったなということならグループを異動ということになる。そういう意味では緊張の季節である。
あまり大きな声では言えないけれども、わたしも移籍を経験したことがある。理由はよく覚えていない。高校1年の時のことだった。おそらく、中学校までは小学校の時の人間関係の遺産でなんとかやっていたのだが、高校に入ってそれがリセットされてしまい、行き詰まったものと思われる。学校の人間関係で難しいのは、グループの移籍は、一学期の中途半端なこの時期の一度きりと決まっていそうなところである。二度三度も異動できるほど、一クラスの人数は多くない。高校3年までの一年というのは、非常に長く感じるもので、個人的な体感としては、社会人の一年の3倍はあるように思える。そんな長い時間を、一回のグループ異動しか認められない中で過ごさねばならないなんて、学校って厳しいところだな、と思う。大人数の、学校っぽい人間関係の会社も大変だと思うのだけれど、「振り込みのついでに外食に行く」などとこじつけて、昼休みに抜け出せることを考えると、学校はなかなか潰しがきかない。
5月と6月の境界は、そういった際(きわ)にある状況における、緊張をはらんだ凪(なぎ)なのではないかと思う。4月の狂騒も、5月の猶予も過ぎた。さあこれからが本番だ。ああ、だからいい思い出がないのだ、と思う。あじさいにも目がいかない。新茶を飲んでいる場合でもない。その年度の計を懸けた、本編の入り口なのだ。せめて祝日があって休めればいいのだけれど、6月の門番はなかなかに厳しい。