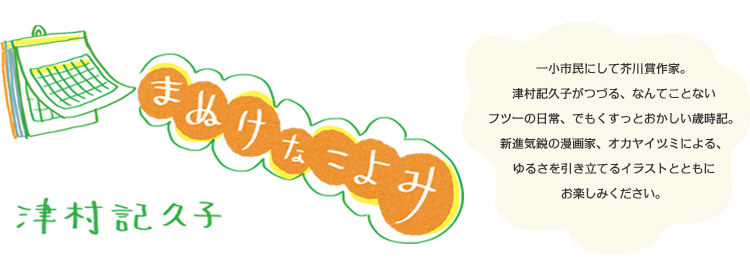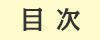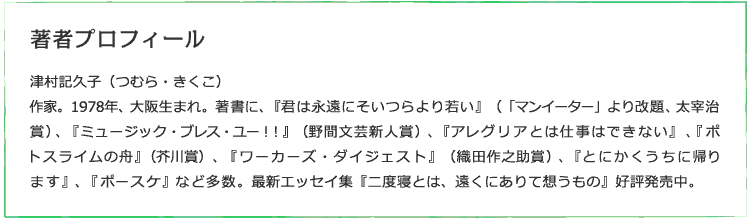見上げ系の娯楽は、花見、紅葉狩り、打ち上げ花火の三つが主だったところだと思うが、個人的にはまさしくその順番に難易度が上がっていく。桜は、とにかく見られる場所がたくさんあるし、期間も短いと言えば短いが、桜の種類によって咲く時期が違ったりするので幅がある。紅葉狩りは、そりゃ家の近くの木が枯れ始めるとなったらそれを観たらいいのだが、そうではなくて、もみじらしいもみじを観ようと思うと、意外と場所が限られる。紅葉狩りの名所である東福寺の通天橋で、見物客がお互いの写真を撮るためとかで滞留していたため進まないことに、「紅葉を観ろ」と激怒し、その写真の中にわざとちょいちょい入るという悪事をやらかしてしまったことは、紅葉狩りの季節のたびに誰かに打ち明けている。それでも、期間がある程度あって、然るべき場所に行けば見られるので、紅葉だって超難しいというわけではない。
問題は花火である。日にちが決まっている、夜にしか観られない、という2点で、花見と紅葉狩りをゆうにしのぐ大変さを獲得している。花火大会はしんどい。本当にしんどい。夜にしか観られず、人は押し寄せ、そして暑い。場所取りをする要領の良さもない。帰り道の混乱が怖い。もう何年も、花火を見に行ったりはしていない。嫌いなのではなくて、自分の根性では無理なのだ。わたしが花火を大手を振って見られるようになるには、花火が行われる川べりにアパートを借りるぐらいしか方法がないと思う。
わたしが大金持ちになったら、部屋に桜を植えて、毎週花火を打ち上げてもらうつもりなのだが、そういうレベルで打ち上げ花火は娯楽として遠く、高級なものなのである。どんなものすごい額の名画だって、とんでもないギャラを取るモデルさんだって、とにかくそこには在るし居る。でも花火は一瞬で消える。花火は、どんな精細な印刷でも、大きな画面でも、再現はできない。その日にそこへ行かないと観られない。そんな難しいものに積極的に関わることはできない。
「あさって花火大会あるらしいで、浴衣着てみんなで行こか」みたいな気軽さで花火に行く人たちからしたら、おまえは花火を難しく考えすぎなんじゃないか、とおっしゃる向きもあるかもしれないが、いやいや、花火職人は、いろいろなクリエイター職の中でも、もっとも聖職に近いものだと思うのだ。花火に関する、ドイツで作られたドキュメンタリーを観ると、花火は長年贅沢な芸術の代表格とされ、花火師は宮廷で寵愛を受けたりもしたという。ほらわたしの話に近くなってきた。中国で発明された花火は、ヨーロッパに渡り、イタリアで盛んになったらしく、アメリカで花火職人になった人々は、ほとんどイタリアからの移民だという。ドイツのハノーバーでは、世界花火コンテストが行われ、五か国がその技術を競い合う。そこに「あさって」とか「みんなで浴衣」感はない。どちらかというと、「チケットとれませんでした。3分で完売だったらしいです」という方に近い。
ドキュメンタリーでは、日本の花火についても取り上げられていた。日本の花火玉は、家内制手工業で独自に発達してきた非常に高価なものであり、日本の花火を作っている映像はめったにないのです、とナレーターもすこし自慢げであった。芯がいくつかあって、開いていく時に色が変化することが日本の花火の特徴であり、「菊」という、あの打ち上げ花火を代表するような、大きく広がって流れる花火は、日本でしか作られていないらしい。それを気軽に観ているのである、「あさって」「浴衣」層は。書いていてあまりに悔しいので、もう今年は覚悟を決めてどこかに観に行こうと思う。
花火といえば、手持ちの花火も、もう何年もやっていない。前回の七夕の笹もそうなのだが、手で持つ方にも仲間が要る。去年、近所の家でやっているところを見かけたのだが、思わず入れてくださいと言いそうになった。中学生の頃は、縁日の帰りに友達と花火をやるのが毎年の恒例だった。出店で、小遣いの限り花火を買って、それで遊び倒すのである。ある年、三歳ぐらいの知らない男の子が、我々の花火しまくりぶりに惹かれたのか、家族から離れて仲間に入ってきたことがあった。当初は機嫌よく花火を楽しんでいたのだが、ねずみ花火が男の子の足元に飛んで行ってしまい、ほとんどそれまでの花火の記憶がなくなるぐらい焦ったわたしは、持っていたファンタ(メロンだったと思う)を男の子に渡して、親御さんには言わないでくれと懇願した。今までの人生における、最初で最後の賄賂である。男の子は、べつに泣いていたとか怖がっていたということはなくてきょとんとしていたのだが、自分が火をつけたねずみ花火が、よその子の足もとにじゃれつく子犬のように跳ね回るのをなすすべもなく眺めていたあの恐怖は、今もありありと覚えている。