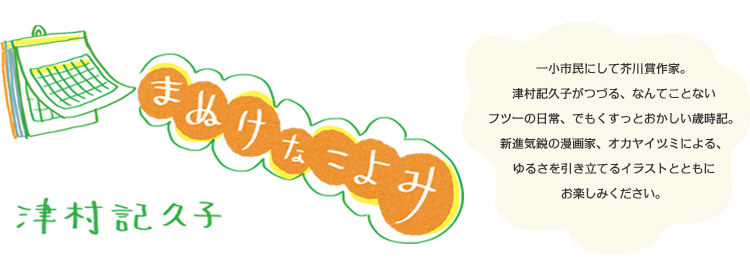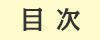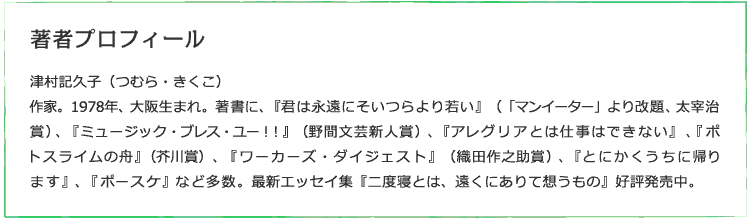わたしのお盆に対する感情は、おそらくあいまいである。他の勤め人の人たちが、お盆なので帰省するのよ、などと、忙しく仕事を片付けたり、両親や義両親に会うのが楽しみだ/めんどうだ、と話している時に、わたしはだいたい、遠い国のローカルなお祭りの話でも聞いているかのような、なんということのないえびす顔をして黙っている。実家に住んでいるわたしには、帰省も義両親も想像できないからである。
しかも、23歳から10年半勤めた会社には、お盆休みというものがなかった。世間でお盆と言われている時期の周辺は休んでいいけれども、有給休暇を使って各自で休んでね、ということになっていた。厳密にお盆には休む、というのではなく、仕事の調整さえできていれば、お盆の真っ最中だろうと前後のいつだろうと休んでも良い、という柔軟なシステムだったのだ......と言いつつ、本音では一斉に休みにしてくれよとずっと思っていた。業種の性格上、仕方がないことだったのかもしれないけれども、有給が減るのは普通につらかった。7月の終わりごろになると、会社全員の名前が書かれた予定表が貼り出されて、わたくしこことこことこことここをお休みにいたします、とマークをする。
10年半もそんなあいまいな状態だったので、お盆っていつやったっけ、と毎年のように思う。そういう人はけっこういるようで、「お盆」と検索ボックスにいれると、「お盆 いつ 2014」とか「お盆 いつまで」という候補がすぐに出てくる。2014て、毎年変動するのかよ、と不穏な空気を醸し出しているのだが、わたしの見たいくつかのサイトでは、8月13日から16日がお盆ということで見解の一致を見ていた。ややこしいのは、8月の方は旧盆ということになっていて、7月13日から16日が新盆であるとのことで、13日が迎え日、14日が中日、16日が送り日と決まっているらしい。15日について明記がなされていないのは、地域によって解釈が違うからだそうだ。長年、「お盆とは、サマーソニックが開催されるあたり」とクルクルパーな認識でいた自分をバチバチ殴りたい気がする。いや、冗談じゃなく、サマソニ後の3日間ぐらいが、わたしにとってのお盆休みだった。
実家に住んでいる上に、生まれ育った地域からほぼ動いていないという人間が、自分なりにそれと見做していたお盆は、今年もあづいなあ、雨降らんかなあ、と自宅にいて、『相棒』の再放送とかを観ているだけの期間だった。以前、文章を書く仕事をしていない頃は、趣味でひたすらサマソニの感想を書いていた。だいたい、2日で原稿用紙20枚ぐらい書いた。今はもはや、そんな力は残っていない。
お盆コードのない会社にいた上に、自分自身の認識も芯から間違っていたわたしが、明確に「お盆」を過ごしたのは、中学で塾に通っていた頃だけなんじゃないかと思う。塾は夏期講習があって、夏休みになっても毎日のように授業があるのだが、8月の10日から20日までは、休みであった。その期間はその期間で、教科ごとに一冊ずつ問題集をやるという宿題が出るので、完全に勉強から解放されるというわけではなかったけれども、とにかく「お盆休み」ではあった。
中学の塾通い以来なので、20年以上お盆についてまともに考えたことのないわたしだが、そういえば、8月の半ばに、いきなり地下鉄の駅に「土日のダイヤで運行しております」の貼り紙が貼り出されたりすることがあったな、と思い出す。あれを見ると、よし遅刻できる、とうなずいたものだった。なるたけのろのろ会社に行って、部長に、土日ダイヤだったんでぇ、と言い訳をするつもりだったのだが、なぜかいつも間に合っていて、土日ダイヤを引き合いに出したことはついぞなかった。
「土日ダイヤで運行しております」の電車は、とても空いていて、穏やかな空気が流れると同時に、こんな時にでも働いてはるんですか、というひんやりした共感が漂っていた。平日の満員電車の人々は、乗車時間の間だけはみんな敵意に満ちていたが、お盆の車内の人たちは、なんだか味方のように思えたのである。なので、ここで唐突に、お盆部を提案したいと思う。お盆に出勤した人を集めて、帰社後に花火をするのはどうか。おそらく優しくし合えるのではないか。書いていて泣きそうなのだが。