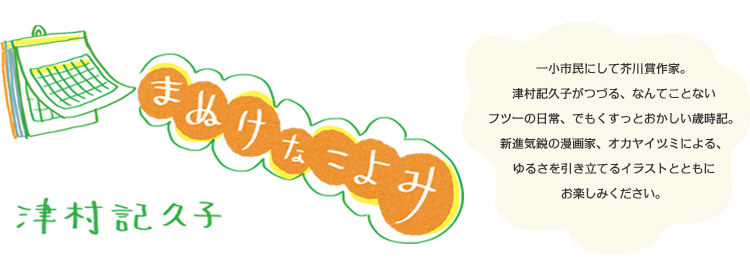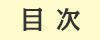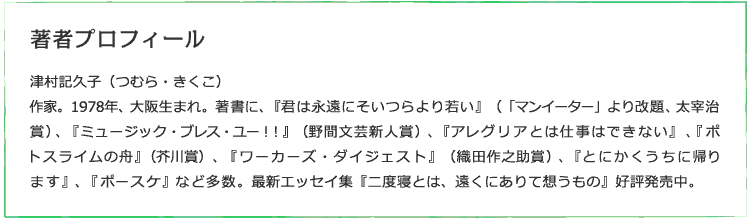内輪の話で申し訳ないのだが、今回のテーマ候補が、十五夜、秋の七草、さんま、ぶどう、萩、セキレイ、いわし雲、とすごく地味で縁のないことばかりになっていて、編集担当さんに心配されている。確かになあ。十五夜なんかやったことないし、秋の七草はお粥にして食べるわけでもないからよく知らないし、魚介類が苦手なのでさんまは食べられないし、ぶどうは好きだけどやっぱりなかなか食べないし、萩に至っては、なんのことだかもよくわからない(秋の七草の一種らしい)。
セキレイに関しては、おそらくうちの近くによく来ていて、早朝に鳴いているのだが、むしろ夕方のスズメの鳴き声のほうがすごい。えらいことになっているとすら言える。ある時間になると、窓を閉めていてもすさまじい鳴き声が聞こえてくるので、いったいどんなことになっているのか、空が火事にでもなっていっせいに逃げ惑っているのか、と窓を開けて確認すると、近所の電線やテレビのアンテナの上に、スズメがびっしりと並んでいて、鳴きまくっていた。電線から間違ってスズメが生えてきたかというぐらいの頭数を揃えていて、壮観といってもいい具合である。スズメって、ときどき曲がり角のマンホールに10匹ぐらい集まっている、かわいらしい野鳥ではなかったのか。しかし、夏から秋にかけての夕方のスズメは一味違う。町内中に反響するような勢いで、横一列に並んで鳴き倒すのである。夕方のスズメと比べたら、早朝のセキレイなんてかわいいもんである。
そういうわけで、いわし雲が残った。心もとないが、問いかけてみる。あなたはいわし雲をよく見るか? そうでもない、という答えが返ってきそうだが、回数はそんなにないものの、印象には残っていると思う。
会社員だった頃は、朝は会社の最寄り駅から東の方向に歩き、夕方は西に向かって帰っていっていた。これが何を意味するのか。夏場におけると日差しの地獄である。出勤時は、高くなり始めた太陽の直射日光が降り注ぎ、退勤時には、西日が襲い掛かる。文字通り、襲い掛かってくるのである。覆い被さると言ってもいい。帽子をかぶって出勤していたが、本当に朝も夕方も顔を上げられないのだ。眩しくて。まっすぐに前を見ることも難しい。それが、9月のある日、会社から出てふと、東に向かって歩くことがそんなに苦痛でないことに気が付くのである。あれ、なんだ、うつむかなくても大丈夫になったぞ。そして少しずつ頭を上に傾けてみる。そこにはときどき、夏には見かけなかった細かい筋がぶつ切りになった雲が貼り付いている。ああ積乱雲じゃないのか。いわし雲は、そういう小さな節目の瞬間に目にする雲である。
手持ちの小学館学習百科事典『天気と気象』によると、いわし雲はうろこ雲ともいい、正式には、巻積雲または絹積雲とも書くそうだ。どれもいい名前だと思う。その図鑑では、雲の10種の雲形が紹介されていて、たとえば、地面近くにできる積雲(わた雲、もっとも雲らしい雲)や乱層雲(雨雲)、縦方向に10キロメール以上も盛り上がることがあるという積乱雲(入道雲)、中ほどの高さにできる高積雲(ひつじ雲)、高層雲(おぼろ雲)などに対して、いわし雲は、巻雲または絹雲(すじ雲)、巻層雲または絹層雲(うす雲)のように、空のいちばん高い場所にできる雲とされている。
こう言われるとはたと、「もう秋だね。空が高くなってきた」というような、よく述べられているし自分もうっかり使ったこともあるかもしれないが、実は正確な実感がつかめていなかった物事の正体が見えてくるのである。なるほど、いわし雲は空の高いところにできるので、それを見上げると、相対的に空が高くなったように感じるというわけである。秋は、空が高くなるのではなく、雲が高いところにあるのだろう。「絹積雲」という名前は、とても美しいものを連想させるが、季節がそんな繊細さも繰り出すデリカシーをまとうのが秋なんだということなのかもしれない。人の生活に土足で踏み込む夏よさようなら。
ちなみに、「女心と秋の空」という物言いがあるけれども、昔はむしろ「男心と秋の空」という言葉のほうが主流だったそうだ。秋の空、そんなに変わるだろうか? という疑問も含めて、わたしには、男女に関係なく心変わりしやすい人とそうでない人がいるだけだと思える。心変わりしやすい人は、小学1年の時に買ってもらった『天気と気象』を30年間所持し続けていないだろう。渋い内容の図鑑だなと思うのだが、雲の名前が知りたくて選んだことを覚えている。考えごとの項目が少なかった子供にとって、二度と同じには見えない空の雲の名前を知ることは、一大事だったのだ。