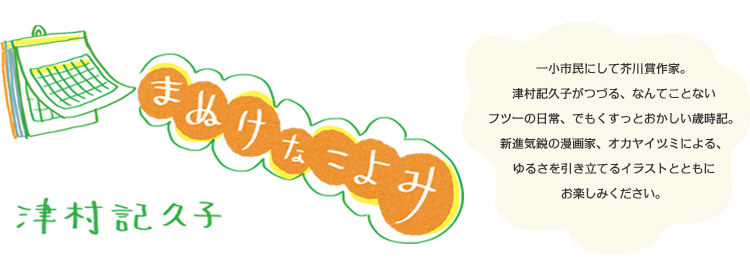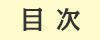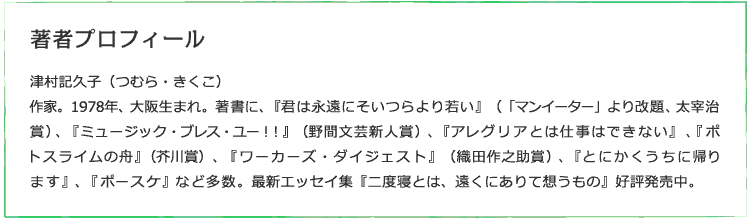ふとんにぐるぐる巻きになるのがとにかく好きだ。ちゃんと端っこから自分を巻いていく。そして頭の方のをちょいちょい丸め込んで、完全にふとんの中に入ってしまう。自分がふとんになったような気がする。もしくは、巻き寿司の具、もしくは、まるごとバナナのバナナになった気がしてくる。しかし、やはり決定的な「ふとんぐるぐる巻きの自分」のセルフイメージは、ミノムシかと思われる。わたしはふとんの暗闇の中で、「............」と口を開ける。一応生きてはいるのだが、微動だにしない。「............」。何もしない。何も考えない。幸せである。やがて外側から見た、わたし自身を丸めこんでしまったふとんを想像する。それこそが真の姿であるように思える。ふとんの中に包まれている自分こそが、完全体であるような気がしてくる。普段のわたしは、仮の存在に過ぎない。本当はわたしは、ミノムシなのである。
そういうわけで、人類の中では比較的、ミノムシを意識して生活している方だと思う。まあ、夏場はそんなふうにぐるぐる巻きにもなれないので、ミノムシ化は季節にもよるのだが、秋も深まり、そういう日々がまた訪れたというわけである。大変喜ばしい。エアコンの設定温度とか、そのわりに敷布団と接する背中が熱くなってきていやだとか、そんな余計なことは考えずに、ただ単純にぐるぐる巻きでいられる。秋は優しい季節だ。肌寒いぐらいにしておいてあげるから、好きな装いで防寒なさい。
ミノムシになるかならないかは別としても、好きなものはふとん、という人はたくさんいらっしゃると思う。なんといっても、ふとんは電源がいらない。かぶっていたらだんだんあたたかくなってきて、眠ることができる。様々な快適に関する指標、道具はあれども、その中でも最高の一品であろうと思われる。ふとんを好きな人のことを何と称すればいいんだろうか。フトナー。フトニシャン。フトニスト。なんでもいいのだが、世の中の七割ぐらいの人はフトニシャンなんじゃないだろうか。
仕事が終わって朝方に布団に入ると、幸せと安堵のあまり、なんだかわけがわからなくなってきて、ざまみろ的な気分になって、ヒヒヒヒなどと言い出す。会社員だった頃は、帰宅してカバンを下ろし、部屋着に着替えると同時に突っ伏し、「今日も帰ってきたよぅおおぉ」だとか「いつもありがとうございますぅう」などと訴え、しまいに、「ふーとーん、ふーとーん」と枕を叩いてふとんコールをしていた。どうかしているのだが、それがなんだというのだ。
そんなふとん教の狂信者と成り果てたわたしだが、子供の頃は、ふとんで寝ることが退屈だった。幼稚園でいちばん嫌いだったのは、昼寝の時間だ。「何もしない」ことが本当に苦痛で、隣の女の子にちょっかいをかけては嫌がられたり、いつまでも話をしようとして先生に怒られたりしていた。今でも、幼稚園や小学校低学年だった頃の自分が、どうやって眠くなっていたのかまったく思い出せない。眠くなる、という感覚があったのだろうか。今はこんなに、いつなんどきも眠いのに。
なので、本を読むための枕元の蛍光灯が、当時のわたしにはふとんよりも大事な存在だったのだが、いつまでも本を読んでいると、隣で寝ている親に蛍光灯のコードを抜かれるなどして消されてしまう。本もない。誰も話してくれない。わたしは、ふとんの中に取り残される。わたしは仕方なく、ふとんの中に潜って、ここは洞窟なのだ、だとか、ひたすら地べたの視点から部屋を眺めまわして、自分は虫だ、などと考えて暇をつぶした。
ミノムシになることは、その時に覚えたのだと思う。サナギというよりは、ミノムシ派だった。サナギの中身は液体だし、剥き出しで固まっているかのような緊張感があるのだが、ミノムシはその点、よそから拾ってきたいろんなものをくっつけてその中にこもるので、想像しやすかったのだろう。
「............」と口を開けるが、何も言わない。言わなくていい。家の中に別の世界があり、親の隣で私は、その人の子ではなく単なるミノムシになる。独立心というのでもない。ただ、あの自分をミノムシだと思うことにした暗闇の中には、子供の頃の王国があったのではないかと思う。今の自分が、それを持っているのか持っていないのかは、よくわからないが、安堵の種類の中でも最も純度の高い安堵であることは間違いない。