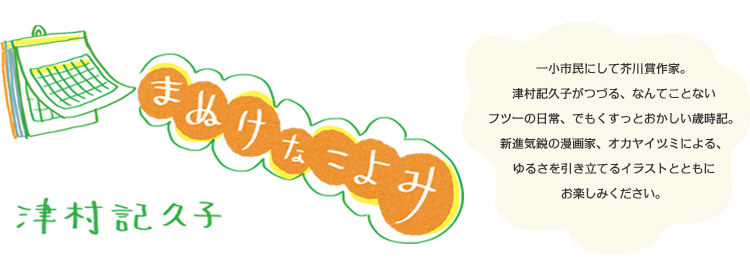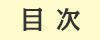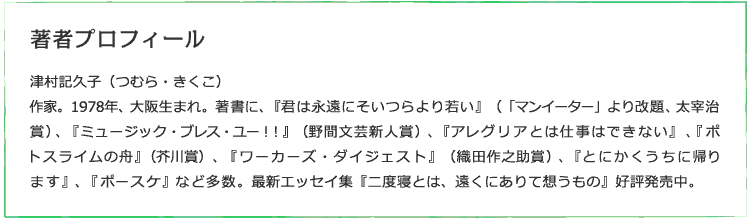国際バスク語の日というものがあるらしく、この欄の更新日に近いらしい。バスクという地域にわたしは行ったことはないし、縁もないのだけれども、世界史の中でも重要な人物を輩出していたりすることは知っている。シモン・ボリーバルやチェ・ゲバラ、フランシスコ・ザビエルはバスク人だという。わたしが中3の時に『パチンコ地獄』というライヴアルバムを耳にして以来、ずっと人生の要所要所で聴いているマノ・ネグラのフロントマン、マヌ・チャオの両親であるバスク人の父とガリシア人の母は、フランコ政権の際にフランスに亡命し、マヌはそこで生まれてマノ・ネグラを結成したそうだ。サッカー日本代表の監督であるハビエル・アギーレ氏も、バスク系のメキシコ人らしい。アスレティック・ビルバオという、バスク人だけのサッカークラブもある。バスク人しかいないはずなのに、リーガエスパニョーラの一部にいる強いチームである。単一の民族だけで、リーガの一部で通用するスポーツクラブを作ってしまう。スペインからフランスにまたがるバスク地域に住むバスク人は、270万人しかいないというのに。
かつて、エウスカルテル・エウスカディという、バスク人だけで結成されたサイクルロードレースのチームがあった。最大のエースであったサムエル・サンチェスが、バスク地方ではないアストゥリアス州の出身であったりとか、末期にはチームの事情があって、さまざまな国の選手が加入したりだとか、いろいろあったけれども、基本的には、アスレティック・ビルバオと同じコンセプトのチームであったと思う。エウスカルテル・エウスカディ(以下エウスカルテル)は、2013年、ヨーロッパの経済危機の煽りをくって、世界中のファンから惜しまれつつ解散した。バスクという言葉が出たのにかこつけて、わたしはこのチームにいたイゴール・アントンという選手の話をさせてほしいと思っている。まさか、この欄でこんな機会がめぐってくるとは思わなかった。いや、「バスク語」について書かなければならないので、べつにめぐってきてないといえばそうなのですが、アントンの話をさせてください。よろしくお願い致します。
イゴール・アントンは、スペインのビスカヤ県はガルダカオ出身のサイクルロードレースの選手である。1983年生まれ。山岳での登坂を得意とする、バスク人のクライマーである。一世を築くような選手ではないけれども、とても強い選手だと思う。エウスカルテル解散後は、スペインを拠点とするモビスター・チームに所属している。
2010年の年末に、わたしはイゴール・アントンを知った。会社の冬季休暇の間に録画をえんえんと見ていたブエルタ・ア・エスパーニャ(*1)で、第8・9、第11~13ステージまで総合リーダージャージ(*2)を着ていたのがアントンだった。しかしアントンは、第14ステージのあと残り6.5キロという地点で落車し、リタイアを余儀なくされ、血まみれの体で親指を立てながらチームカーに乗ってレースを去っていった。
次の年、2011年のジロ・デ・イタリア(*3)で、アントンは、ヨーロッパ最難関の山岳である、モンテ・ゾンコランを登る第14ステージで勝つ。そしてそのまま、前年のブエルタのリベンジかと思われたのだが、さっぱり調子が出ず失望していたところで、10年ぶりにブエルタが通過するエウスカルテスの地元ビルバオにおける第19ステージでなんとか勝利した。その後は、顕著な結果を出すというわけではないが、山岳アシスト(*4)として働きながら、たまに登りで閃きのようなものを見せつつ、エウスカルテル解散後の選手人生を送っている。
アントンのことは、実はよく知らないのである。活字になっているまとまった記事も一篇しか読んだことはないし、去年同僚のサンチェスと共に淡路島にやってくるというイベントがあったのだが、来日を知る前からの別件が入っていて行けなかった(これが前回言及したロハスフェスタである。因果なものだ)。
それでもアントンは、噛みついたり頭突きしたりダイブしたり本を出したりはしない中、わたしにある一定のインパクトを与え続けている。アントンについての記述、発言の中で、個人的に印象に残っているものを以下に記す。
「イゴールはすばらしい才能を持つクライマーだけど、集団内での駆け引きがものすごくヘタなんだ。だから集団の中では必ず誰かをつけてやらなくてはいけない。彼を守ってくれる選手をね」(ロベルト・ライセカ氏談 CICLISSIMO No.23 2011年5月号)
「......でも正直に言うと、これまで一度だって勝てると思ったことはなかったんだ。説明しづらいけど、ブエルタに5回、ツールに2回、ジロに1回出場してわかることは、これを勝つのは並大抵のことじゃないってこと。......ただ、どこかで自分が勝てるわけはないと思い込んでいても、自分の持っているもの全部を打ち込む、という決意でいつも闘っていたよ」(本人談 CICLISSIMO No.23 2011年5月号)
「(上りの強さに定評があるけど、特別な練習をしているの? という質問に対して)イエスでありノーだよ。まず、昔から上りが好きなんだ。それは自転車で峠を走るのはもちろんなんだけど、トレッキングとか山登り自体が好き。バスク地方の伝統として登山はすごく人気があるんだ。たくさんの山があるしね。ヒマラヤに登頂した有名な登山家でもバスク出身の人がいるんだよ。僕は山登りが好きということを表現する手段として、自転車を使っているだけという気持ちだね。本当に山が好きなのさ」(淡路島にて本人談 サイクルスポーツ.jp http://www.cyclesports.jp/articles/detail.php?id=381 2013年11月08日)
"El Giro ha sido muy duro, un infierno, pero también hemos encontrado algunos paraisos en el camino."
「ジロはとても厳しかった、地獄だったよ、けれどもまた、その道程で、僕らは何か天国のようなものにも出くわしたんだ」
(エウスカルテル・エウスカディ公式サイトより本人談。筆者がテキストして保存していたものより引用。現在、そのページはおそらく消滅)
どうなんだろうこの人物は。あえてコメントは差し控えたいと思う。というかできない。
スアレスやロッベンが好きだ。あんな化け物みたいな選手たちが大好きだ。でも、この、痛切なまでの人間らしさはなんなのだろう。アントンはきっといい小説を書くのではないかと思う。スポーツ選手が持つべき妄執のようなものをあっさりと手放していながら、ある地点で心の本質を貫くような。わたしが一生かかって書くような軽さと重さを、一瞬で書いてしまうのではないか。けれども、もう一度言っておくが、アントンはただのおもしろい人ではなくて、強い自転車の選手だ。そのことを思い返して、ちょっとはっとする。
競技が人生になっている選手はいくらもいる。しかしアントンは、生きていることの中に競技があるようなものを感じさせる。そして、その生きていることの様子からも、ことさらな濃密さは伝わってこない。しかし、ジロ・デ・イタリアの道のりで「何か天国のようなもの」に出くわしたと思う心を持っている。そういう人がどこかで生きているということを知るだけで、人生はくそったれなものだが、その興味深さゆえに生きる価値はあると思えやしないか。
それにしても、心とはいったいなんなのだろう。どんなはたらきをするのか。悲しむものか、喜ぶものか。悼むものか、勝ち誇るものか。わたしは、突き詰めると、人間の中の世界が通り抜けていく場所、そうして捕まえた光のようなものを記憶して攪拌し、反射する場所を心というのではないかと思う。言うなれば、中村一義が『1、2、3』で歌った「光景刻む心」が、バスク人のサイクルロードレーサーであるアントンの中にもあって、それが彼に「何か天国のようなもの」を見せたのである。わたしには、そういうことを知る体験が、心というものが他者の中にも存在するということを実感する端緒であるように思える。
*1 ブエルタ・ア・エスパーニャ:スペインで毎年9月に3週間かけて行われるレース。これとツール・ド・フランス、後述のジロ・デ・イタリアを併せて、三大グランツールと呼ばれる。
*2 総合リーダージャージ:ステージレースのあるステージが終わった時点で、それまでのすべてのステージのタイムを足し、最も短いタイムでゴールしている選手が総合リーダー。レース最終日でこの状態の選手が、そのレースの総合優勝者となる。総合リーダージャージは、彼らが着る特別なジャージのこと。ちなみに、ブエルタは赤のマイヨロホ、ジロはピンクのマリアローザ、ツール・ド・フランスは黄色のマイヨジョーヌ。
*3 ジロ・デ・イタリア:イタリアで毎年5月に3週間かけて行われるレース。
*4 アシスト:集団の中でチームのエースを守ったり、山岳でエースを牽引したりする役割の選手のこと。