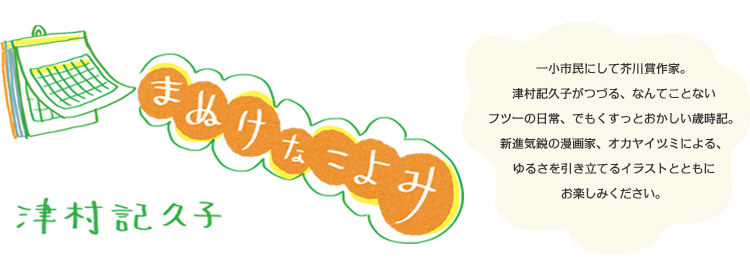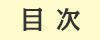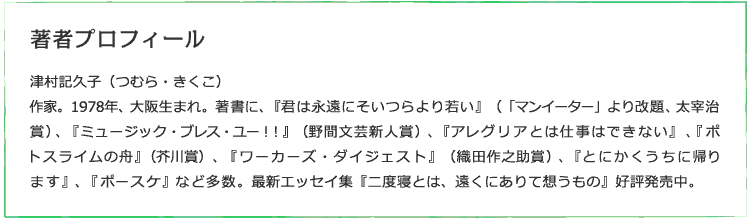かるたが好きなのだった。お正月で楽しみなことといえば、お年玉をもらうこと、出店に行くことの次にかるたをやることだった。親戚で集まって遊んだり、友達と新年に初めて会う時に、よくかるたをやった。わたしは年がら年中かるたをやりたかったのだが、さすがに夏場などは提案できず、正月にかるたが解禁になるのを心待ちにしていた。
いったい人は何歳までかるたを楽しく遊ぶのが妥当なのだろうか? たぶん、小学校高学年ぐらいから、かるたをやりたい、と言い出しにくくなったと思うのだが、36歳(もうすぐ37歳)の今、むらむらとかるたをやりたくなってきている。しかしまだ、誰にも言い出せないままだ。わたしの周りの人は、わたしと付き合ってくれるぐらいなわけで、さすがにみんな優しいため、おそるおそる打診したらやってくれると思うのだけれども、かるたは、札を読む人が1人、ゲームをする人が2人以上と最低でも3人必要なのである。で、3人以上の人とかるたができるような誰かの自宅で会う、という機会がなかなかない。もう、「かるたをやりたいのですが、いついつが空いていますか?」という話から始めないといけない。子供の時のように、正月付近に顔を合わせたのでなんとなくかるた、というわけにはいかないのだ。大人は忙しい。
仕方がないので、オンラインでかるたをやってみたのだが、それなりに楽しいのだけれども、実際に畳やカーペットの上でやっていた頃ほどは盛り上がらない。パソコン上で札を探してクリックする行為は、ぎろぎろ見回してべしっと叩くという身体性には届かないような気がするのである。あれはスポーツなんである、などと開き直るつもりは毛頭ないのだが、床を叩くというアクションと、札をとってやったという頭の気持ちよさが同居する、不思議な遊びがかるただった、と改めて思い出す。
かるたというゲーム自体も面白いのだけれど、かるたの内容も、わたしには重要なものだった。50通りのもの、という分量がうれしいのである。子供の手が届く範囲にあるもので、50通りのバリエーションを持つものはなかなかない。50着のお人形の服や、50色のクレヨンは、そりゃ持っていたら踊り狂うほどうれしいだろうけれども、現実的な数字ではない。トランプは53枚あるけれども、あちらは絵札以外はシンプルだ。しかしかるた。50通りの絵札と、それにまつわるストーリーがある。さらに言うなら、かるたにはいろいろな種類がある。ドラえもんかるたもあれば、恐竜かるたもある。同じシステムを共有しながら、世界観が違うのである。ドラえもんが得意な幼稚園児もいれば、恐竜が得意な小学2年生もいるだろう。かるたよ。フレキシブルな遊びよ。
いろいろなかるたを持っていたのだが、いちばん好きだったのは、五味太郎さんの『おみせやさんの おつかいかるた』である。五十音すべてに、五味さんの手によるいわゆる小売店が描かれており、町歩きの好きな人は絶対に眺めているだけで楽しい代物だと思う。かるたとしてだけではなく、好きなように札を並べて、商店街のようなものも作って遊んでいた。五味さんの独特のタッチと、そのお店の売り物を想起させる色遣いが、本当に素敵である。「のこぎり ほうちょう はものやさん」なら、黒を基調としたシャープな色、「らっきょう ぬかみそ つけものやさん」なら、ごはんのお供にしたいような味わい深いこげ茶の店内、「べーこん はむ そーせーじ にくやさん」なら、肉の赤みのような鮮やかな赤い屋根、と眺めていてうっとりする。わたしは、かるたのシステムで遊ぶという以上に、ケーキ屋だとか本屋だとかいったお気に入りの店を手元に集めることに執心していた。
『おみせやさんの おつかいかるた』は、弟が幼稚園でもらってきたものなのだが、あまりに好きだったので今も大事に持っている。わたしは実に30年弱、このかるたを所持していることになるのだ。正月にかるたをすることの難しさに気付く大人になっても。この原稿を書くために眺めながら、これをもとに小説が書けないかと考えたのだが、50の店がばらばらに展開し、ゲームを遊ぶ者の手の中で一つの世界を形作る柔軟さを再現することは不可能であるように思える。一組のかるたは、おそらく一つの宇宙なのだ。