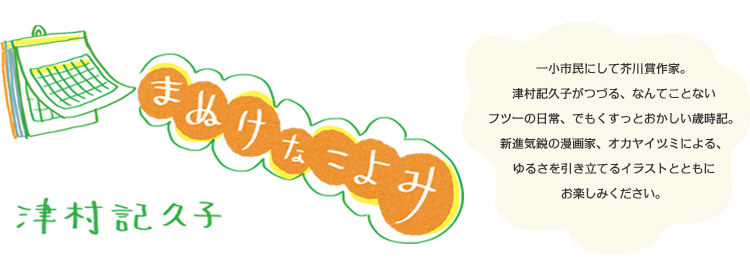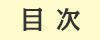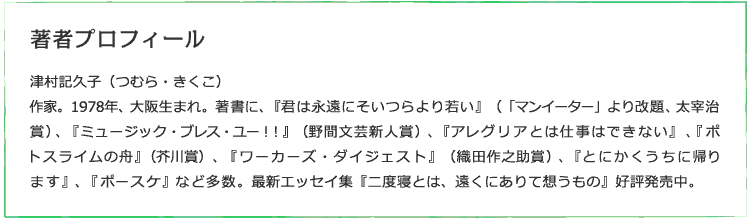この原稿を書くにあたってテーマを頂戴し、はじめて「骨正月」という言葉を目にしたのだった。骨と正月。なんとも言えない奇妙な、不穏な取り合わせの言葉である。しかしなんとなく、正月が終わってすべてが現実に戻っていく、あのむなしさと焦燥を言い当てている言葉でもあるような気がする。お正月を過ぎ、うれしさもお休みもはぎとられてしまったわたしは、まるで骨のようだわ......、冬の風が身に沁みる......、2月の建国記念の日のあたりまで、骨スーツを着てお正月が終わることの喪に服したいわ、というような意味で骨正月なのだろう、わかる、わかるわ、と勝手に想像して寒々しい気持ちになっていた。
しかしである。調べてみると、別名を二十日正月といい、正月用のブリを骨まで食べ尽くしてしまう時期が1月20日のあたりだということで、骨正月というそうだ。他に、棚正月、乞食正月(!)なる言い方もあるらしい。とにかく、正月のためのたくわえが、20日ぐらいになるとなくなるよね、というニュアンスがあるようだ。なので、本当にもうお正月はおしまいだよ! と言い聞かせてくるような言葉なのだが、最短で1月4日から出勤した経験がある者としては、意外と長いな正月、と思える。20日まで正月気分でいられるなら、べつに自分の家の棚を荒らしまわることなど造作ないし、最悪乞食ということでもいい。しかも昔は20日は物忌みの日として仕事を休んだらしい。いいなあ。
もう毎年この時期になるとこの欄で書いているのだが、1月1日は、初詣の帰り道から現実である。今年は、初詣から帰った正月当日の夜は、新年最初の締め切りのために本を読んでいた。2日は外での仕事だった。3日も4日も、仕事用の本を読んでいた。わたしに正月はあったのだろうか。大好きな大晦日は、さすがに一日仕事ではないことをして過ごしたので(部屋の掃除をし、年越しそばを食べたあと、風呂場で足湯をしながら私用のシューベルトについての本を読んでいた)、もうそれでよしとすべきなのか。こうまとめてみると、問題はわたしがすごく働いているということではなくて、わたしが年々本を読むのが遅くなっているということであるのがよくわかる。
何事にも後ろ向きなわたしは、もはや1月1日に初詣に行くために起床した瞬間から、これから正月は減っていくばかりだ、という悲しみに打ちひしがれるようになった。正月は「お正月......」と12月29日あたりから覗き込んでいるのに限る、と思う。そして大晦日の23時45分ぐらいに、その胸の高まりは頂点を迎える。ちなみに今年の大晦日は、生まれてはじめて外に出て、近所の神社に行った。ここ数年の年越しは、毎年のように家でクラッシュの「サンディニスタ!」を聴いていたのだが、一人で近所の小さな神社に行った。単独でというのがまた乙というか、周囲の人はみんな何人かで連れ立っていたので、これでいいのかという感じもする中、個人的にはとても楽しかった。初詣の列に並びながら、もう本当に2014年は苦しかったので、とにかく年が終わるっていうので少し泣いた。お詣りをし、獅子頭に頭を噛んでもらい、お屠蘇を注いでもらった。こんな冬の夜中に獅子頭を出してくれたり、お酒を注いでくれる氏子さんたちが本当にありがたくて、もうありえないぐらいへこへこした。狭い、けれどもちょうどいい大きさの境内から見上げる夜空がきれいであった。
だが、骨正月という言葉について考える限りでは、そこまで正月の足の早さを嘆くこともないのかもしれないと思えてくる。正月気分をこれまでより延長できるというわけではないのだろうけれども、1月20日にも、正月の余韻を感じていいという許しを与えられたような気がする。20日にもなると、たぶんもう、正月じゃないこととの折り合いがついているはずなので、その時に、「これで最後よ」と正月の残り物を差し出されたら、あれ、終わったと思っていたのに、とちょっと得した気分になるんじゃないだろうか。けっこういいんじゃないのか骨正月。仕事が終わったら、お茶を淹れて、お正月用に買ったおやつを、しみじみ食べながら少し休んだらどうだろう。